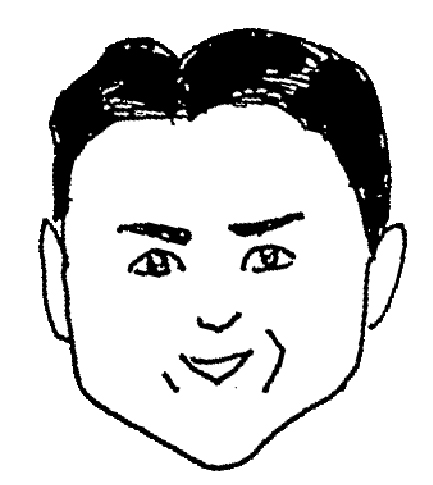学芸員の紹介
三重県総合博物館(MieMu)には、さまざまな分野を得意とする学芸員が在籍しています。言い換えれば”強烈な個性”を持つ専門家集団でもあります。
そんな学芸員のプロフィールをご紹介いたします。
館長
自然分野
人文分野
総合分野
守屋和幸
 |
専門分野動物遺伝育種学、特に松阪牛に代表される黒毛和種牛の育種・改良に関する研究を行ってきました。また、情報測器等を用いてフィールドから収集した多量のデータを用いた統計解析手法(生物統計学)についても研究しています。研究活動(1) フィールド分析法.共立出版.2021.(2) 廣岡博之. 守屋和幸.ラテン方格法の実験データに関する統計分析について.日本畜産学会報.91.371-374.2020. (3) 守屋和幸.廣岡博之.Rパッケージを用いた最小2乗分散分析と最小2乗平均値の算出.日本畜産学会報.89.1-16.2018. (4) 寺谷諒.守屋和幸.機械学習の手法を用いた自己保全管理農地の発生に関する要因分析と予測モデルの構築―京都府綾部市を対象地域として―.システム農学.33.137-147.2018. (5) 生物統計学.向井文雄編.共立出版.2016. MieMuのここがおすすめ!三重県の山、盆地、平地、磯の、自然と人とのかかわりを総合的に理解できる、自然科学分野と人文科学分野の内容を融合した基本展示がお勧めです。また、御師屋敷の模型は、細部まで忠実に再現されており、当時の様子をうかがい知ることができます。 |
自然分野
大島康宏
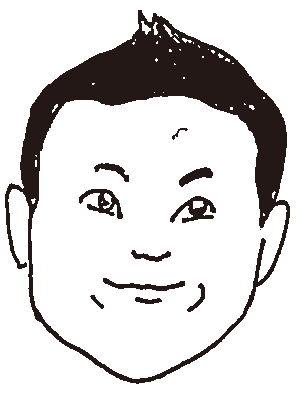 |
専門分野名前のない昆虫に名前をつけたり、昆虫の仲間分けをする「昆虫分類学」が専門で、特に世界中のイチモンジチョウの仲間を専門に研究しています。また、三重県を初め、紀伊半島や東海地方を取り巻く自然を理解するため、どのような昆虫類が生息しているか調査することが主な仕事です。研究活動<著書>(1) 矢田 脩 監修, 山内健生, 矢後勝也, 小田切顕一, 大島康宏, 植村好延, 千葉秀幸, 中臣謙太郎 著(2007) 新訂原色昆虫大圖鑑 I.北隆館. <論文> (2) 大島康宏 (2019) 昆虫学で「学ぶ」きっかけを -三重県総合博物館での取り組み-, Japanese Journal of Entomology (New Series), 22(3): 106-121. (3) WU Li-Wei, HIdeyuki CHIBA, David C. LEES, Yasuhiro OHSHIMA & Ming-Luen JENG (2019) Unravelling relationships among the shared stripes of sailors: Mitogenomic phylogeny of Limenitidini butterflies (Lepidoptera, Nymphalidae) focusing on the genera Athyma and Limenitis. Molecular Phylogenetics and Evolution, 130: 60-66. (4) Yasuhiro OHSHIMA(2008) The systematics of the tribe Limenitidini based on morphology (Lepidoptera; Nymphaidae). Graduate School of Social and Cultural Studies. Kyushu University, Fukuoka, Japan, 122pp + 60pls + 9tbs.(博士論文) <学会発表> (5) Yasuhiro OHSHIMA・Nana MORITA・Tomoko FUKUDA・ (2019.09.04) Insect Pinning Project in collaboration with Museum and University, International Symposium of 'Network of Natural History Museums' as a Tool for Promoting Research, Collection building, Education and Outreach: Case Studies from Asian Regions. Kyoto University Museum. P-9.
博物館をより多くの方に利用し、県民とともに成長するため、企業や団体、大学や学校、文化施設、県民の皆さんと一緒に、観察会や講座、調査・研究を行っています。また、行政等からの依頼を受け、専門的な視点から助言もしています。他にも、昆虫に関する様々な質問に対応したり、人材育成活動、ボランティアの方に協力を得ながら収蔵標本の整理・管理も行っています。
|
北村淳一
田村香里
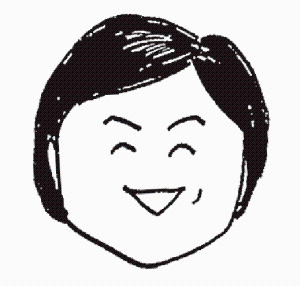 |
専門分野脊椎動物担当として、哺乳類や鳥類の骨格標本や毛皮標本の作成を行っています。盲学校や地域団体と連携し、製作した標本等を活用した「さわって学べるアウトリーチキット」の作成などにも取り組んでいます。
(1) 田村香里・佐野 明.2023.三重県中部におけるカヤネズミMicromys minutusの繁殖習性に関する若干の知見,三重県総合博物館研究紀要,9:1-4. |
中川良平
 |
専門分野古脊椎動物学が専門で、特に500万年前以降の哺乳類化石に興味を持っています。三重県に勤めるまで、ザイルやアルミラダーなどの探検装備を駆使し、沖縄の島々にある洞窟を数百ヶ所めぐり、化石や動物骨を探していました。
(1) Nakagawa, R., H. Taruno and Y. Kawamura,Pliocene Land Mammals of Japan, Fossil Mammals of Asia: Neogene Biostratigraphy and Chronology, Columbia University Press,334-350,2013.(国内の鮮新世哺乳類化石の研究) |
森田奈菜
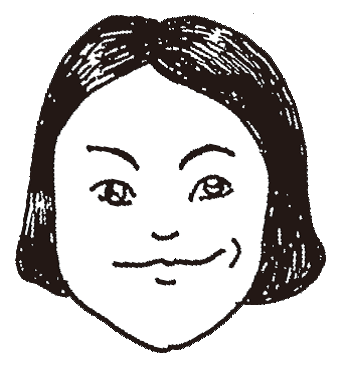 |
専門分野専門は植物です。大学では森林生態学を専攻し、樹幹に着生するコケ植物のすみ分けを研究しました。博物館では、三重の植物相の解明をめざして、どんな環境にどんな植物が生育しているか?を調べ、現在の環境を標本として残しています。
<書籍> |
人文分野
宇河雅之
 |
専門分野古代史・民俗(民具)学生時代は律令期の葬送儀礼について調べていました。特に持統太政天皇の火葬採用の理由とその背景は、現在も研究テーマとしています。 研究活動(1) 三重県総合博物館第20回企画展図録『おもちゃ大好き~郷土玩具とおもちゃの歴史~』(三重県総合博物館、2018)共著(2) 三重県総合博物館第14回企画展図録『植木等と昭和の時代』(三重県総合博物館、2017)共著 (3) 三重県総合博物館第11回企画展図録『伊勢志摩~常世の浪の重浪よする国へ、いざNOW!~』(三重県総合博物館、2016)共著 (4) 宇河雅之「第6節 斎宮の年中行事」『明和町史』斎宮編(明和町、平成17年) (5) 宇河雅之「伊勢国府の方格地割」『研究紀要』第6号(三重県埋蔵文化財センター、1997) 担当している仕事博物館で暮らす様々な資料がいつまでも健康でいられるよう、住まいである収蔵庫の環境に気を配っています。また、新しく博物館の収蔵庫に移住してくる仲間たちについても、健康状態はもちろん、その性格や“癖”にも気をつけてお付き合いしています。過去に担当した展覧会(1) 第20回企画展「おもちゃ大好き!~郷土玩具とおもちゃの歴史~」(2018年7月7日(土)~9月2日(水))(2) 第14回企画展「植木等と昭和の時代」(2017年1月21日(土)~3月20日(月・祝)) MieMuのここがおすすめ!やはり基本展示室です。各コーナーの担当が、県民のみなさんにお伝えしたい三重の魅力的な自然や歴史、そして文化を、「もうこれ以上コンパクトにできない」というくらいまで、削ぎ落した展示です。ぎゅっと凝縮した郷土三重をお楽しみください。 |
太田光俊
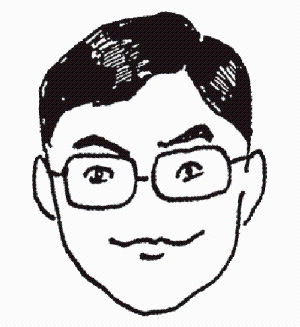 |
専門分野伊勢参りや藩校など、江戸時代の三重県の宗教・文化を中心に研究しています。また、あわせて一向一揆・本願寺や専修寺など、戦国・織豊期の宗教についても論考があります。
(1) 『三重県史通史編中世』(三重県、2020年)の第四章第四節「『作善日記』の世界」、第十章第二節「室町・戦国期の寺院と仏教文化」 |
門口実代
 |
専門分野専門は民俗学で、県内各地の人びとのくらしについて、地域でのフィールドワークを通して調べています。また、お雑煮や調味料をはじめとする食文化や、くらしの道具と絵本との関わりに関心を持っています。
(1) 「婚礼記録の継承―家における記録の保有状況を通して―」『史境』60、pp.71~88、2010年 |
小林 秀
 |
専門分野日本中世史が専門です。特に室町時代から戦国時代が得意です。最近では、参宮を支えた神宮御師に興味関心があります。研究活動(1) 「中世都市山田の形成とその特質~屋敷売券を手がかりに」『中世都市研究 都市をつなぐ』新人物往来社 2007(2) 「伊勢国司北畠氏の領域支配に一側面」『伊勢国司北畠氏の研究』吉川弘文館 2004 (3) 「発給文書にみる北畠氏の権力構造」『戦国期の権力と文書』高志書院 2004 (4) 「伊勢国司北畠氏の花押について」『三重県史研究』9号 三重県 1993 (5) 「中世後期における土器工人集団の一形態~伊勢国有爾郷を素材として」『研究紀要』1号 三重県埋蔵文化財センター 1992 担当している仕事館で収蔵する人文系資料の調査や整理をしています。また、実物図鑑の展示も担当しています。MieMuのここがおすすめ!最大の御師三日市大夫次郎邸の復元ジオラマです。神楽や、準備に忙しい台所の様子など、リアルに再現しています。 |
瀧川和也
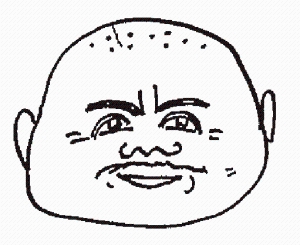 |
専門分野美術の歴史、特に日本の仏像が専門で、三重を中心にこれまで調査・研究を行ってきました。また、地獄・極楽の絵や地域の歴史などについても調べています。研究活動(1) 「食行身禄と富士講関係資料」(『美杉の石造物―八幡地区編―』2022)122-123(2) 「小天狗清蔵について―その活動と天正伊賀の乱後の復興」(『忍者学大全』東京大学出版会 2023)319-329 (3) 「三重の仏像 ―平安・鎌倉時代を中心に―」第51回東海地区浄土宗青年会研修会(2023年5月24日) (4) 「三重の円空」(『三重の古文化』第109号 三重郷土会 2024)18-30 担当している仕事主に博物館の展示事業や県庁他部局・他機関・企業との連携事業に関わる仕事をしています。あと、『みえんしす』に「ミエムのみっちゃん」を描いていましたが、最近ちょっとサボっています。過去に担当した展覧会(1) 第32回企画展「三重の円空」(2022年10月8日(土)~12月4日(日))(2) 第8回企画展「SUZUKA 夢と挑戦のステージ~ホンダのF1と鈴鹿サーキット~」(2015年9月19日(土)~11月15日(日))
館長をはじめMieMuで働く人たちは、私以外全員非常に個性的で、いわゆる「キャラが立った」人たちばかりです。博物館主催の講演会などに積極的に参加して、一度自分で確かめてみられてはいかがでしょうか。 |
福島幸絵
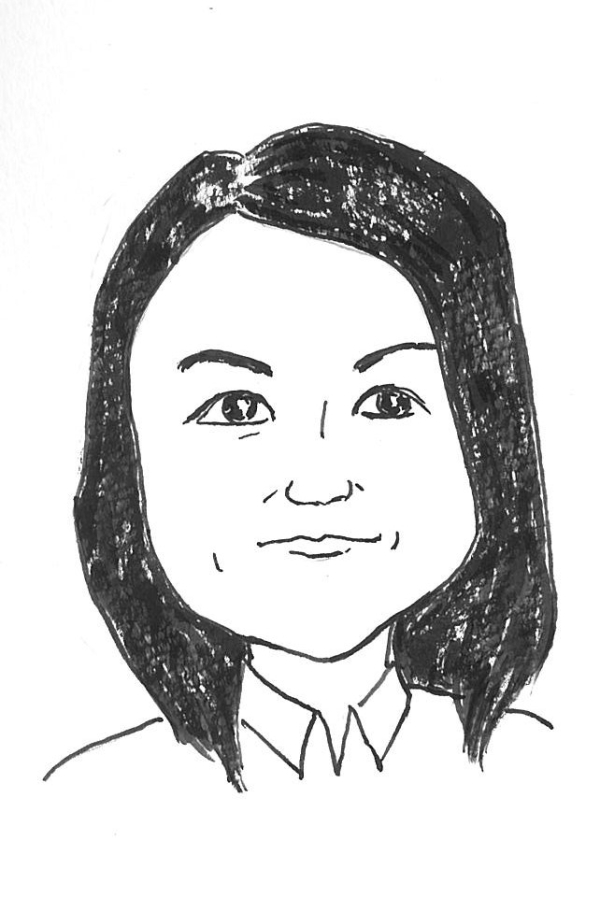 |
専門分野大学では日本文学を専攻していました。近代文学を学びましたが専門分野から少し離れていたので学び直し中です。これからMieMuにどのように貢献していけるか模索しています。担当している仕事寄贈された資料の状態や形状、内容などを調査し分類ごとに一点一点登録し収蔵していく作業補助をしています。歴史的に重要な資料を末長く管理保存していくことの大切さを感じています。過去に担当した展覧会(1) 三重の実物図鑑 特集展示「戦争と三重」(2024年7月20日(土)~8月25日(日))(2) 三重の実物図鑑 特集展示「戦争と三重」(2023年7月22日(土)~8月27日(日)) MieMuのここがおすすめ!とにかくいろんなものがあるところです。体験できるスペースや大きな御師屋敷のジオラマ、剥製や標本展示、古文書からさんちゃんまで。初めて来た人にも興味のあるものがきっと見つかる場所だと思います。 |
福田良彦
 |
専門分野専門分野は民俗で、三重県をフィールドに祭礼や民俗行事、諸職等様々な調査を行ってきました。近年はかんこ踊りやカンジョウナワ行事について調査を行い、現在は宮座の行事に関心をもっています。また、住民が主体となり、地域全体を博物館としてとらえるエコミュージアムにも関わってきました。 研究活動(1) 「四日市市諏訪神社祭礼鯨船行事の伝播~鈴鹿市長太地区四ツ谷垣内の鯨船部材をとおして~」『三重県総合博物館研究紀要10』 2024(2) 「春日神社の宮座 壬生野地区と春日神社の祭礼」『春日神社拝殿解体修理工事報告書』(宗教法人春日神社)2023 (3) 「市木木綿」『生活の中のデザイン松阪木綿(2)』(三重県伝統染織研究会)2019.2 (4) 「伊賀地域のカンジョウナワ行事~その分布と地域性~(一)(二)」『伊勢民俗44、45』(伊勢民俗学会)2015.9、2016.9 (5) 「保存と継承」「周辺地域の伝承・三重県」「陽夫多神社の願之山踊」ほか『伊賀のかんこ踊り総合調査報告書』(伊賀市伝統文化活性化事業実行委員会) 2013.3 担当している仕事民俗のほか、資料収蔵についても担当しています。過去に担当した展覧会(1) 移動展示「未来へ伝える伊賀の自然、歴史・文化」(2024年1月19日(金)~1月28日(日))(2) 第31回企画展「集まれ!三重のクジラとイルカたち」(2022年7月2日(土)~9月11日(日)) MieMuのここがおすすめ!まずはミエゾウの全身骨格復元標本を体感してください。三重の実物図鑑も沢山の実物を見ることができ、とても楽しめます。これらは全て無料ゾーン!基本展示室や企画展示室はもっと楽しめます。ぜひお越しください! |
星野利幸
 |
専門分野日本古代史(文献)が専門です。以前は平安時代の官人・官司制度を研究対象としていましたが、近年は三重の古代史、斎王制度や条里制度などを研究対象としています。2022年に開催した企画展「名所発見、再発見!」で取り上げた三重の名所についても関心があり、引き続き調べています。 研究活動(1) 多気町郷土資料館記念講演会「古代の丹生水銀をめぐって」2020年(2) 朝日町歴史博物館教養講座「古代伊勢のブランド品 伊勢水銀」2019年 (3) 古代寺院史研究会例会報告「古代の壱志郡-交通を中心に-」 2019年 (4) 『三重県史』通史編 原始・古代編(条里・伊勢水銀)2016年 (5) 「文杖についての覚書」『斎宮歴史博物館研究紀要25』 2016年 担当している仕事展示・交流事業課長として、主に課業務の総括が仕事です。2024年度は開館10周年記念事業も担当します。
(1) 第30回企画展「名所発見、再発見!~浮世絵でめぐる三重の魅力~」(2022年4月16日(土)~6月12日(日)) |
総合分野
稲垣玲弥
 |
専門分野博物館教育、とくに子どもを対象とした教育普及を専門にしています。子どもたちが博物館でどんなものに興味をもつかということに関心があります。あと脊椎動物もちょこっと(個人的には鳥が好きです)
(1) 稲垣玲弥.2023.三重県総合博物館ミュージアムフィールドおよび周辺ため池における鳥類相.三重県総合博物館研究紀要,9: 17-27. |
小掠光裕
 |
専門分野教育学を学んできました。博物館から様々なことを学んで、笑顔になる子どもたちをたくさんみたいです。担当している仕事遠足社会見学、修学旅行等で学校との連携を進めたり各団体の利用受け入れ管理をしたりしています。教育活動に関する取り組みを主に担当しています。MieMuのここがおすすめ!基本展示室です。三重県の多様な自然と歴史・文化が興味深く展示されていて「三重県のすごさ」がよくわかります。多くの人にぜひ、見ていただきたいです。 |
甲斐由香里
 |
専門分野保存科学担当学芸として、展示資料だけでなく博物館にいらっしゃる皆様にも適切な環境になるよう調整するほか、収蔵品の保存管理に関わる業務として文化財IPM業務、資料分析、文化財レスキューなど多岐にわたる業務に携わっています。研究活動(1) ミュージアムレポート 企画展示室のちょうどよい環境づくり Vol.1 みえんしす(三重県総合博物館情報誌),27号(2) ミュージアムレポート 企画展示室のちょうどよい環境づくり Vol.2.みえんしす(三重県総合博物館情報誌),36号 (3) 三重県総合博物館における地中熱を用いた空調管理の仕組み・運用(第45回文化財修復学会)2023.6 (4) 第36回企画展「パール 海の宝石、神秘の輝き」展覧会図録.三重県総合博物館, 津,112p (5) ミュージアムレポート ジュエリーを美しく輝かせるには~照明のひみつ~.みえんしす(三重県総合博物館情報誌),48号 担当している仕事専門分野に書いた内容以外にも、各企画展の展示照明を調整したり、博物館実習で資料保存について授業をしたり、そのほかにも三重県内の博物館美術館の学芸員さんから施設・展示環境についての相談対応もしています。過去に担当した展覧会(1) 開館10周年記念・第36回企画展「パール 海の宝石、神秘の輝き」(2024年4月20日(土)~6月16日(日))MieMuのここがおすすめ!3階にはいろいろな形のイスが置かれていますが、個人的には壁と一体型のイスとテーブルがおすすめです。 |
中村千恵
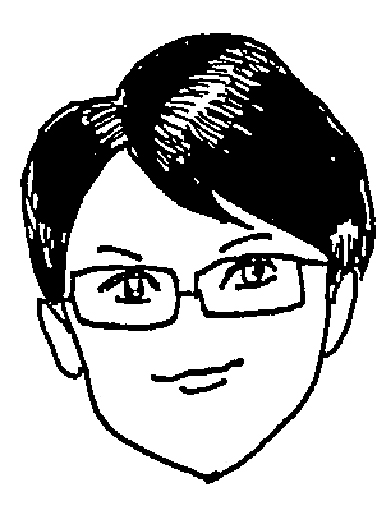 |
専門分野博物館学が専門で、その中でも特に博物館を活用した教育活動に興味があります。博物館を利用することで、利用者の人生にどのような影響を与えるのか、長期的な視点で調べたり考えたりしたいと思っています。研究活動(1) 中村千恵.2025.県立博物館における企業連携活動―三重県総合博物館10年の歩み―.國學院大學博物館學紀要,49:39-49(2) 中村千恵.2025.3.3.アウトリーチ―博物館と地域をつなぐ 連携の視点から.学芸員の現場で役立つ基礎と実践 博物館教育論 第2版.黒澤浩編著.講談社サイエンティフィク:142-151. (3) 中村千恵.2023.実践事例集「ユニバーサル・ミュージアム」な仲間たち16自分の好きな学び方で楽しもう.ユニバーサル・ミュージアムへのいざない 思考と実践のフィールドから.広瀬浩二郎編著.三元社:144-145. (4) 中村千恵・田村香里・稲垣玲弥 2022.三重県立盲学校と連携したさわって学ぶ学習プログラムの実践と教材開発.全科協NEWS,vol.52 No.4(通巻305号):6-7 (5) 中村千恵 2022.「お伊勢参り道中すごろく」のねらい~江戸時代の旅を体感する~.地域をつなぐ伊勢参り再発見プロジェクト 活動の記録.みえむプロジェクト実行委員会(令和3年度文化庁地域と共働した博物館創造活動支援事業) 担当している仕事広報担当として、メディアからの取材対応や、ホームページ・公式SNSの管理などをしています。博物館における広報は、博物館を活用した教育活動の一環だと考えて取り組んでいます。過去に担当した展覧会(1) 開館10周年・三重県総合文化センター開館30周年記念特別展・第39回企画展「金曜ロードショーとジブリ展」(2025年1月31日(金)~4月11日(金))(2) 第34回企画展・特別展「高畑勲展 日本のアニメーションに遺したもの」(2023年7月8日(土)~9月18日(月・祝)) MieMuのここがおすすめ!エントランスの吹き抜けにあるモビールはお見逃しなく!夫婦岩や熊野古道など、三重に関わるモチーフばかりで、見ているだけでもあちらこちらへ出かけたくなります。基本展示室を見れば、モチーフが全部何かわかるようになれるかも!? |