【移動美術館】 - 「かたち◆冒険」
会場=松阪市文化財センター
会期=2002年8月2日(金)~18日(金)
ごあいさつ
三重県立美術館では、松阪市におきまして、所蔵作品による2002年度移動美術館「かたち◆冒険」展を開催することになりました。
移動美術館は、三重県立美術館の最も重要な活動のひとつとして毎年開催されています。三重県立美術館にたびたび訪れることがむずかしい地域の方々には、美術館のコレクションを身近で鑑賞できる機会として、好評をいただいております。
今回の移動美術館は、20世紀のさまざまな「かたち」に注目した展示を試みました。20世紀の社会はこれまでになく激動の時代でしたが、美術の世界でも多様な表現がわずかな期間に目まぐるしく誕生し、流行しました。とくに、1910年代から次々と発表されるようになった抽象作品は、感覚的・直接的に私たち鑑賞するものに訴えかけ、表現としての「かたち」はますます豊かになったといえるでしょう。
日本においても、1920年代から30年代にかけて神原泰や村山知義、吉原治良らが感情的な抽象作品、あるいは構成主義的な抽象作品を発表しました。そして、戦後になると、フランスで生まれた、より感情的な要素を押し出したアンフォルメルの運動が1956年に開催された「世界 今日の美術展」で紹介され、その影響は地方にまで及びました。ほぼ同時期、アメリカでは「行為としての芸術」に重要性を見出したアクション・ペインティングが生まれ、日本では具体美術協会などがこれら双方の要素を取り入れつつ独自の活動を行い、世界からも注目されました。
今回の展示には抽象作品が数点含まれています。前述の具体美術協会で活躍した白髪一雄や元永定正は、リーダーであった吉原治良の「絶対に他人の真似をするな、いままでにないものをつくれ」という有名な言葉を実践してみせました。伊勢市に生まれた足代義郎も、1950年代から作風を大きく転換し、人物のかたちは簡略化して画面に構成され、60年代になると強烈な色彩と感情的な筆のタッチが加わり、人物の内奥に迫る表現となりました。一方、第二次大戦中からの後半生を三重県で過ごした岩中徳次郎はアクション・ペインティングの信条や元来の美術に永遠と流れつづけた手仕事感覚を否定する、幾何学的抽象の世界へと向かっています。
「抽象作品」というと、むずかしいものと最初から敬遠される方もいらっしゃるかもしれませんが、鑑賞する人に何かを伝えたいという点は具象作品と同じです。わたしたちは、それらの作品を無理にわかろうとするのではなく、作品のなかに登場する「かたち」などの面白さ、自由さを楽しむことから接してみるのもいいように思います。
最後になりましたが、2002年度松阪市での移動美術館開催にあたり、ご協力いただきました関係各位に厚くお礼申し上げます。
2002年8月
三重県立美術館
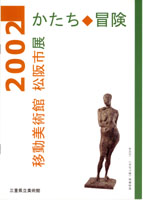
| 番号 | 作者 | 作品名 |
|---|---|---|
| 1 | 黒田清輝 | 薔薇の花 |
| 2 | 赤松麟作 | 白い扇 |
| 3 | 小川詮雄 | 漁村の夏 |
| 4 | 北川民次 | 海への道 |
| 5 | 中谷 泰 | 煤煙 |
| 6 | 中谷 泰 | 渇き |
| 7 | 中谷 泰 | 機織り |
| 8 | 三輪勇之助 | 昆虫採集にいった時 |
| 9 | 佐藤昌胤 | 伊勢湾台風 |
| 10 | 林 義明 | エビス島 |
| 11 | 片山義郎 | 女の頭部 |
| 12 | 足代義郎 | 女 |
| 13 | 足代義郎 | 木枯 |
| 14 | 柳原義達 | 黒人の女 |
| 15 | エッシャー | 秩序とカオス |
| 16 | 土嶋敏男 | 人と物(X) |
| 17 | 岩中徳次郎 | 港 |
| 18 | 岩中徳次郎 | Work-81-26-A |
| 19 | 菅井汲 | 愛人たち |
| 20 | 菅井汲 | 森の朝 |
| 21 | 平井憲廸 | 白い昼下がり |
| 22 | 白髪一雄 | 黄龍 |
| 23 | 元永定正 | 作品 |
| 24 | 麻生三郎 | 男の顔 |
| 25 | タピエス | ひび割れた黒と白い十字 |
| 26 | ミロ | 岩壁の軌跡 |
| 27 | 浅野弥衛 | 作品 |
| 28 | 浅野弥衛 | 作品 |
| 29 | 浅野弥衛 | 無題 |
| 30 | 向井良吉 | レクイエム |
