|
荒屋鋪 透 |
*( )内のno.は当館ほかで開催された「モランディ展」カタログ番号。 |
|
1990年冬、美術館連絡協議会の海外研修派遣でヨーロッパを訪れていた私は、フィレンツェでモランデイの版画展を観ることができた。1月27日から4月22日まで、ウフィツイ美術館の素描・版画室で開催されたエッチングによる展覧会である。展示された総計124点のなかには、珍しい5点の肖像画も含まれており、版画作品からモランディ芸術の秘密の一端をかいま見たようで楽しかった。まずモティーフの特定。油彩では崩れてしまう物の形体が、版画にはまだ鮮明に残されているのだ。例えば1924年の『静物』には、強い光りにつぶされたテーブルの上に、3個の物がシルエットになり置かれているが(fig.1.)、右の2個は一体何だろうか。それが雲形に切り取られた板と逆さに置かれた鍋だと判る版画がある(fig.2.)。この雲形の板は、1919年の形而上絵画の主要なモティーフ(no.9.)だが、鍋のほうは1936年(no.27.)と41年(no.37.)、48年(no.57.)、49年(no.60.)、55年(no.74.)の作品にも繰り返し登場してくる。モティーフが判明すること自体は、モランディ芸術を解釈するうえで重要なことではない。問題はその変容のプロセスを明確に知ることなのだ。そのためには、55年の『静物』に描かれた半円が鍋の一部だと知っておく必要がある。まるで写真のネガ・ポジが反転したような絵画。それが、この24年の『(籠・鍋・雲形の板のある)静物』である。もうひとつ不思議な作品がある。背後から強い光を当てたものか、もしくは夕暮時の次第に微かになる光のなかで描かれたのかは定かでないが、ある光の作用で物の形体が重なりあい、ひとつに融合されたのが29年の静物だ(no.19.)。美術評論家ジェームズ・ホールは、40年代のモランディの静物画に顕著な、物の上辺を同じ高さに揃え、花瓶の口を水差の口に重ねる形体の同化を、1935-36年に描かれたセザンヌ的風景画に由来すると解いたが(James HALL,“Rosso,Morandi,Manzoni(LONDON).”(EXH.REVIEWS),Burl.Mag.,Aug.,1989,P.577.)、この形体の同化はすでに1920年代に始まっていたのだ。重要な点は、その融合が光のなかで試されたことである。ホールは1910年代の風景画が、その筆致、光の処理において一見すると印象派風だが、その画肌は艶消しのフレスコ画のように感じられると指摘し、淡褐色の施された画面に注目している。確かに、褐色混じりの色彩はモランディ絵画を特徴づけている。そしてこの褐色の配合された画面では形体の同化が容易であったともいえるだろう。ではなぜ物と物とを同化・融合させるのか。形体相互の同化と同時に構図の単純化がある。例えば54年の静物(no.71.72.)に見られる一種儀式的な配置。57-58年の静物(no.77.)の「おばけ煙突」風構成といったもの。これらの工夫は一体何に起因するのか。1989年5月から1990年3月にかけて、ロンドン、ロカルノ、チュービンゲン、デュッセルドルフで開催されたモランディ展には、1点の奇妙な油彩が出品されている(fig.3.)。奇妙というより、構成が単純に図式化されているため、他の作品より説明が明快につくといったほうがよい。画面は左右相称となり、左半分の球と缶は茶褐色のテーブルと同化し、右半分の黄褐色の椀と瓶は、テーブルの上に鮮やかに浮かび上がる。直立する中央の缶と瓶、それを左右から見守るような球と椀。椀と球は互いに呼応し、次の瞬間には、球が椀のなかに飛び込んでいく。あるいは、すでに椀から球が飛び出したのか。前掲展評のなかでホールは、「こうした物と物との無言の親密性こそ、確かにモランディ芸術の原理なのだ。」と結論づけ、一見したところ、メタフィジカ(形而上絵画)を離れていると思われる作品さえも、メタフィジカを特徴づける、遊びの感覚を内包していると指摘する。ただ、この1920年代の静物画から強く感じるのは、やはり「光の分離」ではなかろうか。画面を上下に二分するテーブルの水平線によって、光はさらに複雑に錯綜する。物の影も見落としてはならないだろう。この光が実は、光学的に説明のつく光ではなく、なにか別の、それこそモランディの光としかいいようのないものだと判るのは、やはり版画作品に見られる光の処理においてである。例えば1930年の静物では、台かテーブルの上に乗る物たちは皆、暗い闇の中に消えているはずなのに、ひとつの瓶と貝殻、そしてポットの口の一部だけが白く抜き取られて光っている(fig.4.)。この画面では、一体どこから光が当たっているのか。かつて光と影の効果すなわち明暗法は、平面上に物を立体的に写し出す技術として考案された。アカデミックな技法として、それはeffet(光の効果)と呼ばれ、画家が人為的に創り出す、物の立体感を意味していた。それに真っ向から異議申し立てをしたのが印象派のグループである。印象派にとってeffetとは、外光に左右される光の動きとなった。この時から、画家にとって光とは永遠なるものではなく、移ろいやすい時間の連続として把握されてきたのである。印象派が何よりもまず風景画において、その光を創造したのと同様に、モランディもまた、風景画のなかに光の面を発見している(no.124-125.)。光が物の輪郭線を消し、形体相互の同化を図る。前掲した静物(fig.4.)において、白く抜き取られた部分が、ひとつの形体ではなく、貝殻とポットの一部からなる、まるでパイプのような別の物になっている事実は見逃せない。ここでは、光が形体を一端破壊した後に、再び別の形体に再構成させる手法がみられるのだ(fig.5.)。これが、モランディ芸術の秘密である。彼が繰り返し、同じ物たち、彼の身辺に常にある物を選んだ理由もここにある。それは、常に存在する形体こそが常に変化すると主張せんばかりの、堅固な意志に貫かれ、そのくせ柔軟な変容を遂げた物たちの神話なのである。 (あらやしき・とおる 学芸員) |

Fig.1 「静物」油彩 1924

Fig.2「ふたつのものと衣のある静物」 エッチング 1929
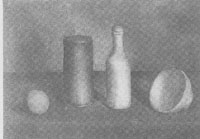
Fig.3「静物」油彩 1920

Fig.4「静物」エッチング 1930

Fig.5「コーヒーポットのあるたくさんの静物」エッチング 1933 |
美術館 > 刊行物 > HILL WIND > ひる・うぃんど(vol.21-30) > ひる・ういんど 第30号 モランディの光
ページID:000055551
