むすび
|
以上12点の作品に見られる総体的な印象を述べれば、抒情的で柔らかい線描の効果が、ときに抽象的な曲線を伴って、随所に活用されていることであろう。しかも、先行する石版画集「起源」あるいは「聖アントワヌの誘惑」第1集などの80年代までに制作された作品群において、しばしば見受けられたグロテスクな形象は影を潜めている。観る者を震憾させる異様に気味の悪い一つ目の怪物や、奇怪な顔をした大蛇の姿は、画面から残らず放逐され、たとえ蛇や悪魔が登場するにしても、それまでとは異なって、静穏で寂しげな姿に変貌させられている。本作品の〔4〕、〔6〕、〔12〕などの画面は、一種の理想主義的といえる清雅な印象さえ与えられているが、このことは主題が聖書から選ばれたという理由以上に、おそらく画家の内面に大きな変化が生じた結果と理解すべきであろう。実際、「聖ヨハネ黙示録」制作に至る10年間には、さまざまな出来事がルドンの生活に起伏を与えたようである。彼は1886年46歳のときに、生まれて間もない長男ジャンを病死させており、この事件は彼の精神に深い苦悩の傷跡を残した。だが3年後の1889年に次男アリが誕生して、この時期以後、彼の生活は徐々に晴朗なものへと向ってゆく。1894年には、デュラン=リュエル画廊で開催した大回顧展で成功を収め、画壇的地位を揺ぎないものにすると同時に、経済的余裕をも確保するに至る。また1897年にはルドンの「黒」の主要な源泉と解され、彼の脳裡に長らく寂し気なイメージを焼き付けていた故郷ペールルバードのルドン家所有地が、彼の意に反して売却されるという事件が起っている。ルドンはこの事件を契機にして新しい人生に踏み出そうと決意した。加えて人生の師と仰いでいた微生物学者クラヴォーの死(1890年)、それにルドンが真に胸襟を開いて友情を確かめ合った詩人ステファヌ・マラルメが、この石版画集刊行の前年(1898年)に死亡している。しかもこの間の1895年のはじめに、ルドンは大病をして困感の毎日を送ったという。代表作の一葉「死-わがイロニーは他のすべてを超越する」(1889年)で最高潮に達した「黒」の塊量の迫力ある表現力は、「聖ヨハネ黙示録」において確実に後退し、入れ替るように、直線と曲線を巧みに混在させた線的要素が増加する。この理由のひとつに、種々様々な陰影をもつ上記の人生体験が挙げられると解すべきであろうか。しかしこの石版画集に際立って認められた流れるような線的要素に関しては、先の分析で明白となったデューラーの直接的な影響が大であると思われる。後年ルドンはデューラーの銅版画「メランコリアⅠ」(1514年)に言及して、「変化に満ちた緊密な線。バッハの音楽の喜びを引き合いに出すのはどうかと思うが、私は似たところがあると感じる。中年期以後私はこのような線のフーガを常に感じていた」と語っている。最終場面の〔12〕を除いて、ルドンは、主題と細部にわたる形態モティーフの選択を、デューラーが主題あるいは副次的モティーフとして描出した情景からヒントを得て決定したようである。もっともデューラーでは、一画面中に幾つかの物語が組合わされて、時間的推移が読みとれる中世的な<絵物語>の形式にされた。それに対してルドンでは、各画面に共通して指摘できるように、物語の一場面は、映画のひとコマを切り取ったように選択され、しかも、引用された『黙示録』のテキストに忠実な単一の本質的主題のみの描出に全精力が費やされている。こうした画面構成の特徴は、いうまでもなく、未だ宗教的な物語の展開に強い執着をもつデューラー時代と、象徴主義の思潮を閲した19世紀末との芸術観の決定的な相違に起因するものであろぅ。いずれにしてもデューラーの影響の大きさは、彼が印した組合わせ文字(モノグラム) ルドンは1879年に書き記した日記の中で、絵画は文学作品の挿絵ではないことを強調し、「造形的な構図に隙間があると、必ず文学的観念が入り込む」と警告を発しながら、絵画が言葉では再現できない自律的な領域をもつことを、はっきりと語っている。だが、以上12点の作品を基本的に規定する重要な特質として、これらの諸場面がいずれも聖書の記述、とりわけルドンが主題として引用したテキストの言葉に、できる限り忠実に絵画化されていることであろう。特に〔1〕と〔11〕においては、画面の形象が『黙示録』のテキストの力に引きずられているようにも思われる。その上ルドン自身の言葉とは裏腹に、本石版画集の制作に当っては、ある種の観念的なものが作品制作を鼓舞しているのではなかろうか。前期の作品「夢の中で」や「起源」においては、決してある特定の観念や言葉が作品制作を主導してはおらず、いわば無意識の中から湧き上ってくる形象が、構図や形態モティーフにそのまま反映された。具体的に述べれば、紙に鉛筆で不明瞭な線や形を描いている間に、徐々に明確な形象が姿を現わしてくるというわけである。要するに前期の手法には一種の自動筆記法的な画像形成の跡を辿ることができた。しかも作品の題名は、抽象的な概念である場合も多く、画像と題名とは必ずしも密接に結びついてはいなかった。だが特に「聖ヨハネ黙示録」に至って、ルドンの制作手頓は大きく変化したように思われる。彼は単なる個人的な幻想に身を委ねるよりも、むしろ世界の意義を開示する『黙示録』のテキストの趣旨に忠実であろうとし、なし得る場合には、逐語的な文字通りの描写をさえ行っている。しかしこれはデューラーの場合も同様であるが、ユダヤ的な幻想に満ちた『黙示録』のテキストは、画家の強力な想像力の発動なしには、そのイメージを画像として結ぶことが適わぬものである。ルドンは多くの細部的な記述を省略しながらも、自己の想像力によって、テキストの本質的な意義を捉える幻想、あるいは『黙示録』の数々の象徴主義的図像とでもいうべきものを、次々に生み出していった。 純然たる聖書の主題が選ばれたことに関連して、既に〔2〕の画面について考察したように、ルドンはデューラー以外に、中世のカトリック教会の芸術に関心を抱いていた。彼がゴシック大聖堂をはじめとするキリスト教的主題に興味をもち、それらの形態モティーフを駆使して作品制作を始めるのは、主として1895年のイギリス旅行以後のことである。クラウス・ベルガーの指摘によると、1895年頃から1905年頃にかけての約10年ほどの間、ルドンは彼を取り巻くカトリック的雰囲気によって、重圧を感じていたという。確かに知人の画家モーリス・ドニは、キリスト教的宗教芸術の再興を声高に唱道していたし、親友の詩人フランシス・ジャムは、20世紀初頭に転向して、カトリック教会への忠誠を誓うことになる。また悲観主義的(ペシミスティック)な気分を漂わす奇作『さかしまに』(1884年)によって、ルドンの作品を一躍世に知らしめた、親友の小説家ジョリ=カルル・ユイスマンスは、1892年にトラピスト修道院へ馳せ向って参籠、以後『大聖堂』(1898年)などのカトリック教芸術の主題に基づく小説を発表し、カトリック教会の懐に抱かれた。さらにルドンの作品の収集家ガブリエル・フリゾーの回心と続く、取巻連の雪崩(なだれ)現象にも似たカトリック教への転向は、ベルガーのいうように、ルドンの内面にも少なからず動揺を与えたかも知れない。彼はこの時期に、「聖心のキリスト」(1895年)、「十字架上のキリスト」(1895-98年頃)、それに13世紀のゴシック大聖堂に取材した「ステンド・グラス」(1901年頃)などのパステル画、加えて、ゴシック様式の尖頭形アーチを画面に配置した一連の人物画といった、キリスト教、中でもカトリック的色彩を帯びた作品を集中的に制作している。こうした状況から推し量るところ、この石版画集を、単純に『黙示録』の幻覚的性格のみに関心を示した非宗教的作品と断定することはできない。とはいえルドンは、デューラーのような熱烈な信仰心を保持するには、あまりにも近代的かつ繊細な神経と知性の持ち主であったことはいうまでもない。またルドンが聖書的なものへと導かれるのも、神学的、教義的な理解に基づくというよりは、むしろ闇と光の幻想画家として、聖なる光と闇の弁証法を展開したレンプラントの、あるいはその逆であるゴヤの造形的表現の伝統との交わりそのものによってであったと思われる。 一方においてこの時期のルドンが、デューラーの大きな影響を受けていることは事実であるにしても、デューラーの作品への心酔だけから「黙示録」の主題を選んだと結論づけるのもあまりに皮相的であろう。そうした主張では、この時期、ルドンが聖書の主題に並々ならぬ興味を示した事実の説明にはならないからである。既にこの作品に関しては、聖書の記述に忠実であろうとする努力と、『黙示録』の本質的意義を開示する象徴主義的な画像を創出しようとする努力との、二つの点を指摘したが、それこそ他ならぬ絶対的なものに対してのく敬虔なる心情〉の為せるわざではなかったか。この意味からいっても、最終場面〔12〕の「聖ヨハネ」の主題は「敬虔」あるいは「信仰」と名づけられるべきであろう。彼はこの時期以後、仏陀やギリシア神話、また華麗で神秘的に輝く花の主題へと関心を移した。この事実を指してベルガーは、ルドンの宗教的危機は去ったと述べている。ベルガーの言説の真偽はともかくとして、結局、近代的感受性の持ち主であるルドンは、モーリス・ドニのような画家とは違って、カトリック信仰への明確な回心を行ぅことはなかった。ただ注意すべきことに、彼の立場は、有神論か無神論かといった単純な二者択一の問題に帰せられるのではないということである。ルドン研究家のクロッケンプリンクが語る「決して自己を立派に見せようとせず、何も征服しようとせず、他人を押しのけてその地位を奪おうとせず、ただ強く、真に自己自身であろうとした」芸術家オディロン・ルドンは、長い生涯のただ一時期心情的にカトリック教へ急接近して、自己の芸術作品を媒介とし、自己の芸術的感性において照らし出されるキリスト教的「信仰」そのものを表明したと思われる。「聖ヨハネ黙示録」連作石版画は、まさしくこの時期に位置しているのである。 |
 デューラー 「メランコリアⅠ」 1514年 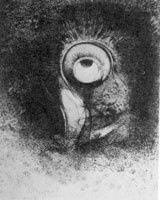 ルドン 「起源」より、-おそらく花の中には最初の視覚が試みられた。 1883年  ルドン 「聖心のキリスト」 1895年 |
主要参考文献
L'OEuvre graphique complet d'Odilon Redon. MM.Artz et Debois, La Haye,1913.
André Mellerio,Odilon Redon. Société pour l'étude de la gravure française. Paris, 1913.
(A reprint of the 1913 edition. Editor;A.Hyatt Mayor,Da Capo press, New York,1968)
André Mellerio, Odilon Redon,Peintre,Dessinateur et Graveur. Floury, Paris,1923.
Klaus Berger, Odilon Redon, Phantasie und Farbe. Verlag M.DuMont Schauberg,Köln,1964.
Alfred Werner,The Graphic Works of Odilon Redon. Dover,New York, 1969.
Richard Hobbs,Odilon Redon. New York Graphic Society, Boston, 1977.
Jean Selz,Odilon Redon. Crown Publishers,New York, 1978.
Rudolf Koella,Odilon Redon. Office du Livre,Fribourg,1983.
粟津則雄 『ルドン 生と死の幻想』美術出版社 1966年
A.G.クロッケンプリンク著 足立朗訳「オディロン・ルドン」 1973年(神奈川県立近代美術館主催『ルドン展』図録所収)
池辺一郎 『ルドン 夢の生涯』 読売新聞社 1977年
オディロン・ルドン著 池辺一郎訳 『ルドン 私自身に』 みすず書房 1983年
