不語似無憂
東 俊郎
|
湯原和夫の作品をかたることはやさしい。それは迷路ではなくもつとも単純な幾何学的なかたち,すなわち六面体の箱か円筒,あるいはそれと他のいくらかのかたちとの組合せにほぼかぎられているのだから。湯原の作品をかたることはむづかしい。それは迷路ではない。時間さえかければいつかはときほぐすことができる迷路とちがつて,ひとめで記憶されているこの単純性ゆえの,すべてが出入口ならかえつて出入口がみつからないという不可解がはりついているのだから。どんな饒舌もはねかえして傷ひとつつくことのない立方体の沈黙。 だから,というのもへんだがどこからはじめてもいいわけで,それなら記憶をさぐつてふれたものからささやかな一歩をふみだすことにしよう。まづそれは1982年神奈川県立近代美術館でひらかれた「湯原和夫展」のカタログに載ったとても印象ぶかい発言にかかわる。そのことばをいま引用すれば, 藝術とは,エレガントなものでなければならないと思う。(略)。おぞき苦闘の告白を作品に残しておくのが好きな人が多いけれど,それをあるレヴェルまで昇華された表現にまでもっていかなければ,作品にならないと思う。そういうレヴェルに到達してはじめて,呈示する段階になる。(*1) そういつたあとで湯原はさらに佐伯祐三とクラナッハを例としてこのエレガンスをめぐる理路を展開するわけだが,ようするにかれによればクラナッハはエレガントで佐伯はそうでないことになる。佐伯──パリ──詩情──エレガントという想定される紋切型へのこの一撃でこのことばはいつたん白紙にもどされ,エロスとはどうむすびつくのか当惑しても,湯原のいうエレガントの重點はむしろ作品の仕上に対する作者の態度にあるらしいくらいの見当はつく。苦労も努力も裏打ちされるもの。そして眼にみえるのは手品つかいが虚空からとりだす花束も同様にそこにすでにある作品だけ。 作品を追いつめていって,さわれなくなる。いままで荒っぽかったものが,ある時点で急にエレガントなものに変る。荒っぽくてもエレガントになる。(*2) けれどここでのこのことばは又べつの横顔をみせようとする。荒つぽさからエレガントへの脱皮,でなくて,荒つぽさそのままが同時にエレガントでもあるし,逆に,エレガントがエレガントに徹するならふつうそこにはないとみられる力にも欠けないということ。つまりそれは作品という名とほとんど同一でありうるので,だからかれの使用法にならえばロココの美術よりもアルタミラの壁画のほうがエレガントだという表現はなりたつ余地があるどころか,じつさい湯原自身にそうかんがえたがる傾向はじゆうぶんよみとれそうだ。 そしてそういう意味でかれのつくりあげた作品もまたエレガントというしかない感情をぼくらによびおこす。一,二,三と順に加算してゆく底の努力のはての自然としてそこにいたるべく汗と涙と血とをうつとうしげにかかえるわけでなく,それとは無縁のすずしさ,いつそ非情の顔つきで無から突如として姿をあらわしそこに立つそれら立体作品。いうまでもないけれど汗も涙も血も,それさえエレガンスに変形せずいない圧倒的な現前の感覚によつて,存在はするが眼にみえぬものなるだけである。 ようするにそういうつよい作用を宰領することのできるものといつたらまづあげられるのは知性の機能で,精神の刻印がおされていない単純はおよそありえない。知性への湯原のまなざし。そういえば札幌の藝術の森美術館におかれた湯原の作品は『1・9・8・5 知性沈下』と超されていて,その知性不在の現在への批判そのものがかれにおける知性の意味のおおきさを裏がえしにかたつているとみえる。感性とか感覚を第一とみる藝術理会ほどかれからとおいものはない。知的でなければすでにエレガントでない──それが湯原和夫の作品のつくられる場所にはたらく格率なのだ。ついでにいつておくと,日本美術に対するかれの点の辛さもたぶんここに起因する。 西欧では美の根本に知的なものをおくがi、、日本の美意識は純粋感情的なものであって知的なものからではない。(*3) |
(注) *1 「作家との対談から」,「湯原和夫展」図録,神奈川県立近代美術館,1982年 *2 同上 *3 「あなたにとつて〈空間〉とは」,『みづゑ』823号,1973年11月号 |
|
しかしいそいでつけくわえておくと,そういつたからといつて湯原和夫をこの国の明治以来にはじまる西洋志向の系譜の最後あたりにかきくわえるつもりはない。かれ自身その模倣につぐ模倣ではどうしてもこえることのできない限界と同時に,けつして普遍だけでできあがつてはいないヨオロッパの存在をその留学の地パリでしたたかにあじわつたはずであるが,それはそれとして湯原の言をまつまでもなく,西洋が西洋をおいつめたあげく西洋をかえつてみうしなつた趣さえする二十世紀の美術はマルセル・デュシャンあたりをさかいにしてその主知的な傾向をますますつよめ,まつたく新たな次元にふみこんでしまつた。いまとりあげたいプライマリ・ストラクチュアとかミニマル・アートがそのいい例だろうし,コンセプテュアル・アートももちろん無縁ではない。 湯原の仕事をその初期からよくみているひとをべつとして,数年の区切で管見する程度の興味しかないひとならプライマリ・ストラクチュアの一種とみてふしぎでないかもしれない。分類癖のつよいひとならなおさらそのあいだの小異をすてて大同につくだろう。しかし固有のあゆみをしめすという意味でオリジナルであるかれの作品はそういつた分類から逸脱する。そしてたとえば今回この図録にエッセイをよせているフランスの美術批評家オットー・ハーンとの出会などもこの逸脱なしにはありえなかつた。そのいきさつをここでてみじかに紹介するなら,1965年のビエンナーレ・ド・バリの展覧会場をまわつた後,さきごろのニューヨークでみてきたばかりのジャッドやロバート・モリスにそつくりの作品を日本人がもう出品しているという揶揄まじりの記事をオットー・ハーンがかいた,それがきつかけで,いつぽうその記事をよんだ湯原は指をくわえていられないとその訂正をもとめ,かたがた自作の展開を納得させるべく資料一束をかかえて会見にのぞんだのである。その結果はどうなつたか。しばらくのち,『ART INTERNATIONAL』に掲載されたオットー・ハーンの‘LETTRE DE PARIS…ET D’AMSTERDAM’にはその誤認をみとめたつぎのような箇所がある。 湯原のあゆみはドン・ジャッドのそれとはちがう。デビューのころの湯原は表現主義的な人体や顔をつくつていた。その顔がしだいに幾何 学的なかたちへと変化し,クロームメッキの鋼をつかつた直方体にたどりついた。たとえ結果的には各々の構造探求がおなじ地点にたつしたとしてもかれのあゆみはたしかにオリジナルである。 ここにあげたオットー・ハーンの理解のしかたについて湯原はいまもつて不満があるらしいときくけれど,とにかくミニマル・アートの模倣ではないオリジナリティはあきらかにされたわけだ。自分のものになつていない色はつかわないし又つかえない画家に似て,それを不器用とよぶなら不器用を善しとし器用をむしろ軽蔑するのが湯原の流儀だとすれば,そういつたひとがたやすく流行をおうはずもない。うたがいは納得がいくまで反芻する。それは又すつかり同化したと信ずるかたちについては,くりかえしつかつて飽きることがないということでもある。 かれの歩みはゆつくりしている。しかしこの漸進こそ発想のオリジナルに固執することのあかしでもある。引用したオットー・ハーンをよんだからでもないだろうが,そういえば,もつともあたらしい『意味の自由区No.1-88』のならんだ二枚の板なども,初期作品の壁である人物像ととおく呼応するものだといえば荒唐か,どうか。 かたちが単純であればあるほど,ものがものとしてそこにあるという実在のちからはつよまる。逆に,実在ということがもんだいなら,かたちも素材もできるかぎり単純化するのがものの道理だ。ものの出現──ものがものであるという自立的自同律的状態をかれはめざす。しかしそのとき,もののちからを混同すれば,素材に潜在する可能性のすべてをひきだしたところで作品の生命はとだえる。ところで湯原はけつしてそれを混同したりたやすく統一したりしていない。『作品No.5-67』をはじめとする金属の鏡面を利用した作品がいい例で,それによつて存在や空間や重力を宙吊りにしつつ虚とか無とかいう名でさす消滅の方向へもつてゆこうとするけれん味をふくんだ策をもてあそばず,あくまでも鏡面/ものに固執するのが湯原の湯原らしさであつて,物理の法則にさからつて同時に同一の場をしめるかにみえる映す鏡面と映される外界がそのためにハレーションをおこす,その危険は覚悟のうえで空をみたしてそこに存在するものへの信頼をくづさない。不完全な実在が役目をおわつたところから真の劇がはじまるといいたげなコンセプチュアル・アートの狙いとはまつたく異質だし,プライマリ・ストラクチュア,ミニマル・アートとかれの藝術とを劃する理由もここにみえかくれする。すこしべつのみかたをすると,愚直な排中律のかたい殻にまもられ無をそのことばどおり無 nothing としかみないそれらの即物性にくらべれば,湯原のほうがはるかに存在については柔軟でしかもどことなく形而上学的にみえてくる。かれはもののものであることの非情を一面ではたしかに強調している。彫刻とはなによりもまず存在してしまう,或はしなければならない造型の形式だろう。だからメティエに対する知識とか技術とかの要求がそうとうにつよいはずだし,かれの仕事の関心もそこに集注していそうにみえる。それにもかかわらず,かれのいうものはきけばきくほど精神の刻印を帯びてくるのもたしかである。つまり湯原のいうものは,実在のイデーにちかい。 しかし実在とかイデーとかいづれ空々漠々たることばにちがいない。そこにどう目鼻をつけるべきかとかんがえるうちに,ハイゼンベルクの自伝『部分と全体』にあつた挿話をひとつおもいだした。ハイゼンベルクは青年時代の一時期プラトンの『ティマイオス』に記述された物質の極小の部分についての理論に,荒唐無稽ととまどいながら異常な興味をかきたてられたらしい。不確定性原理とおなじように非常識で奇妙な原子についてのその理論をかれはつぎのようにかたつている。 |
 ①『三人像』1959年 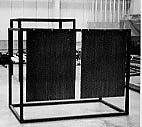 ②『意味の自由区NO.1-88』1988年 |
|
そこには物質の一番小さな部分は直角三角形から作られており,それが一対になって正三角形か正方形に集まったのち,立体幾何学の正多面体,すなわち,六面体,四面体,八面体および二十面体に組み立てられるということが主張されていた。そして,この四つの多面体が四つの元素,土,火,空気,水の基本単位とされていた。(*4) 土は六面体で火は四面体。それだけとれば狂ととなりあわせた詩人のほしいままな妄想に似る。それでも,それ以上かんがえつくせないまで徹底した思考の遠心力が宇宙にちらばせた星雲にたとえたい原始仏教のあれらの理論,あるいは思考が究極にはある厳密な文法の物をつくりあげることに還元されるヴィトゲンシュタインのそれとおなじように,そのみかけはふうがわりな非合理をふみやぶつたところで超合理のせかいを予感させるべくむこうからやつてくる迫力をかんじとらなければ,べつにハイゼンベルクもこんなふうにこだわりつづけなかつたはずだ。もつとも日常からとおく単純を宗とする数学的形式が他を圧した絶対的なリアリティをふるう領域がたしかに人間にはあるのだ,ということこそこの挿話の命でなければならない。すべてをかんがえるとはなにもかんがえないにほぼひとしい無にすれすれのところに接近するということ,だからそれをはねかえすにせよ含みこむにせよそれ自体で全体を再成できるちからが一方になくてはならず,なにがつよいといつて単純なかたちにまさるちからはない。かれの眼にはつねにその全体があつた。そしてその全体をひとつのかたちにおきかえた。ことばを探しあぐねて凡そことばというものが意味をうしなつたときはじめてことばが一つうかぶ,というようなことをヴァレリーがいつているが,そのときたつたひとつのことばはあらゆることをふくみ,すべてがそこにかえつてくる。 正六面体は土だという思考がうみだされるせかいの消息はまづこんなところで,それならばその延長線上に湯原のかたちもある。湯原はどこかにかいていなかつただろうか,「冷静な理性と燃えるような情念とに分析され冷酷に再編成される世界」(*5)のことを。これはヨオロッパのうみだした知の形式をとらえたことばとして,プラトン,ハイゼンベルクにはそのままあてはめられ,したがつて湯原の知のかたちを大観するにはいいとしても,ここでは「燃えるような情念」にいれるしかない湯原のその非ヨオロッパ的知/非知の部分をかたるにはやや適切を欠く。ここでハイゼンベルクとわかれてもつと自然に東洋の精神とかれはつながつている。 東洋の精神とよぶのはじつは不正確だが,それにはしばらく眼をつむつてその仮の名によつてぼくはかれにおける感性をかたりたいのだ。湯原は知性のひとというより直観のひとである。かれのいう知性をすこしかんがえれば非西洋的神秘主義といつてもいいバルザックのエネルギー=意志論にちかい響きがある,とは,これはむしろ作品そのものからくる印象で,その無機的で単純なかたちを非情とみるこちらの感情がはたらくとき,それと同量でヴェクトルは逆をむく非情ならざる感性がひとしくぼくらにはたらきかけてこないだろうか。それはかれの作品のかたちが肉体の一部の産物でなく知性をこえた全身がつかみとつたという意味での直観によるからである。 |
*4 ハイゼンベルク『部分と全体』p.12,山崎和夫訳,みすず書房,1974年 *5 「有機的空間というムダの展開」,『S-a』NO.2,1973年春 |
|
たとえば『1・9・8・5 知性沈下』という作品をまえにする。そこに現代の非知的な状況を風刺した知性をよむことは作者のねがうところであつても,それよりその格子のイメージが,今回の新作『意味の自由区No.2-88』『意味の自由区No.3-88』にもうけつがれて,いくぶん虚無の相貌をみせることから逆算して,そういえばかれがいつか葬儀場の死者を焼く爐のなかがきれいだつたぞといつたのを,ふと,これだつたかとおもいだすことのほうがおもしろい。鍵と鍵穴がきれいにあうその一瞬に感性を否定するかたちにゆたかな感情がみちる,といえばいいすぎか。湯原の直観の不壊のかたち。それならばとこちらの連想はさらにすすんで,太平洋戦争の末期に東京をおそつた空襲の夜に探照燈にてらされて飛ぶB29の編隊をこの感性はうつくしいとみることができたはずである。あるいは一瞬のうちに炭化してしまつた人の死骸も。けれど,人は死ななくなればもはや人でなくなるという死の側からの生の認識がはたらくなら,それはそれで人にむけたつよい感情のこもつた愛着のまなざしであることは可能で,そういうことのすべてが初期作品『横たわる人』にこめられているかもしれず,その『横たわる人』から『意味の自由区』まで,人間くさくなることはゆるさないそのエレガンスに人が人であるしるしはけつしてきえることがない。 |
 ③『1・9・8・5 知性沈下』1985年 |
|
自分の,でなく自分がその一部である母国語とよばれる言語でしか文学はできないとみきつたところで英国留学をきりあげて帰国したあとのこと,その吉田健一は銀座にあつた洒落た洋風のカフェー資生堂が好きでよくたちよつていた。べつの常連に横光利一がいて,あるとき吉田にここだとヨオロッパにいるみたいだといつたことを喋つて当然同意をえるはずとおもつたところ,いやここほど日本的なところはないといわれて愕然としたというはなしを,オットー・ハーンのエッセイの,原文では,Chez Yuhara,le cylindre,le cube sont des formes calmes qui renvoient à des notions qui évoquent la sérénité,la douceur,la puissance,la tranquillité.という箇所をよんでいてひさしぷりにおもいだした。一瞬虚をつかれたおもいをしたあとで,なるほどこれは吉田とおなじ眼のはたらきだと合點する。そとからの眼。 湯原の作品に非西洋をかぎとるのはオットー・ハーンにはどうであれ,ぼくらにはコロンブスの卵も同様の発見で,それまで日本人ばなれのした西欧に伍してじゅうぶんに西欧的,でなくともほとんどそれにひとしい普遍的な造型の言語とみえたものが裏がえされ,たとえ「いはばしる垂水のうへの早蕨のもえいづる春になりにけるかも」という万葉集の歌とまではいわなくても,それにつうずるかのように手のきれるように清新でしかも威圧することのない親しみぶかい顔があらわれておどろくが,一度かんじればもう,それは湯原の作品のすべてに姿をみせてきえることがない。 このことは大事なことだが,もつと大事なのは,日本からみて少々おかしくてもヨオロッパ人には日本とみえる要素をとりあげる誘惑を注意ぶかく斥けることはおろか,いわゆる個性さえおさえつけ,知性も感性もその構造は人間に共通だとする場所にたつて普遍であることをもとめた湯原の作品にかえつてこの,とりあえずは日本とよぶしかない一文明のまぎれようのない刻印があらわれたことではないか。それを一箇人では逃れることのできない風土の條件とみて,湯原の限界をかたろうとするのではない。むしろ,日本的ということにもし意味があるとするならこういうかたち以外での道はほとんどないといいたいのだ。 岡潔がすみれはすみれのように咲けばいいとかたり,鳥海青児は庭の片々たる雑草の可憐なうつくしさにおどろき,坂本繁二郎はフランスには自然がないといつた。かれらにこういわせた日本にむけての直観のはたらきは,チェスの名人のような知性の平面を垂直につらぬいてふかくひろいが,湯原にも又まぎれもなくつながつて,こうしたはたらきのもとに現成するかたちには色も匂いもともなわずにいない。かれは岡や鳥海や坂本とひとつにされることを迷惑がるだろうか。しかし湯原の仕事が国際的などというその実どこにも根のない嘘さむさをまぬがれるほど豊かならその豊かさの一斑どころではない大部分は,銀座の資生堂に日本をみるその視線によつてこそあきらかなので,そのことをはなれても湯原がヨオロッパで日本うまれであることをわすれたことはない。だいいち,仕事と生活を一体とみなさずにいたる求道者然とした造型の追求がいかにヨオロッパからとおい精神かを知つて,藝術家観がゆらいだことをかくしていないではないか。あるいはまた,北魏の仏像とか殷周青銅器にひかれた学生のころすでにそのどこがヨオロッパとちがうかを懸命にみながらかんがえたというのも,ここで参考にしてよい。 だからといつてただ性急にかれの作品に日本,でなくても東洋をさがすことは無駄である以上に湯原のきらう文学性におちいつて有害となることはいうまでもない。いかにもぷつきらぼうでとりつく島もないとみえるその無愛想にしばし耐えれば,きつと作品のほうから手をのばしてくれる深切なときがあり,その記憶を,なにはともあれとどめること。そのうちきえるべきはきえ残るべきは残る。それはみる人の能力その他をこえた作品のもつちからにみあつた過不足のない自然のかたちでもある。オットー・ハーンのいう「澄明,やさしさ,かくれた力の暗示,静寂」はそこまできてはじめて,しかしなつかしげにうかびあがることばだつた。 |
|
|
個が有機性および普遍的なものに転換される非個性的なもの,非人間的なもの,オリジナルでないものこそ現代的なものであるというような,我々の基本的,根源的なものを放棄したような論理は,まったく現代の機構の中の本質を見失なってしまったものというべきではないだろうか。(*6) |
*6 「人為的な空間と精神的公害」,『S-a』NO.3,1973年夏 |
|
こうかいたとき,湯原和夫の批判がむけられるのは前衛的な姿勢をみせながらそのじつ「安易な没個性,人間性の否定」にすぎないすべての美術であり,それら新奇な思想をこわだかに唱えるひとだつた。しかしこれはヨオロッパを中心にせかいをみた夢のいわば名残ではないか。その夢からさめてみれば,ヨオロッパ十九世紀の近代精神がけつして普遍的でなくその特殊を普遍とみなしてあやしまなかつた特殊な時代にすぎないと気づいたヨオロッパの知性がしだいにとなえはじめた非個性への主張としてならそれはそれなりの意味をもつが,だからといつて一般化しすぎて,せかいが共通に病むもんだいにすりかえられれば,薬も毒にかわるのが道理。ニーチェのアンチ・クリストがキリスト教の影がきえる地点でなお力をうしなわなければ,あとは滑稽で悲惨な劇がはじまる。 このコンテクストの糸をきられた凧のように個性と人間性の否定が砂漠のうえをとんでいるのが現代だとまでいうのかどうかはべつにして,ここでも湯原の直観を時代おくれというのはその藝に実も花もない。西洋においてもそうなら,まして神も個人も発明しなかつた日本ではなおさらではないかと,これは湯原の批評にくわえたぼくの補注だが,それはそれとして,たしかに近代という舟もろとも個性も人間性も判断停止の括弧にくくる性うへとどうやら大勢がかたむいて,こういうあたりまえのことにも力をこめなければそとに届かないことへの屈託が湯原にとりついている気配がこの引用をふくめた湯原のエッセイ全体に濃い。 ところで,『団』を制作した1960年代すでにギリシア美術を個人主義的なものとみなして認めず「ぼく自身は,個人主義を超えたうえで,個に還る普遍性をもった造型をさぐっていた」とは湯原自身のことばである。彼我てらしあわせれば,かれの個性尊重が素朴に個人ならなんでもいいという個人主義でなくて,もうすこしひねつたものであることがはつきりするだろう。 つまり個性ということについてもかれのかんがえは自前ならではの迂曲があり矛盾にちかい複雑があつて,ここでも西洋と東洋とがからみあつてはいたが,すくなくともその運動があたまだけにかたよらずに身体髪膚にまんべんなくゆきわたつて一箇の肉体をみたしていた。ここはオリジナルとはとかんがえるためにも重要なところである。独創。たとえばモーツァルトみたいにあらゆる影響をノンシャランとみえるほど無頓着にのみこむことが自由に,ひいては独創につながるというのはまだ不十分で,ありようは,そういう有機体への途上の雑多とも断片ともいえる混合体をみたす肉体の満潮をみはからつてあふれる上澄だけをとるときそこに部分でなくて全体がきつとあらわれ,この精神の一であることが独創とおなじ円を描く。 そしてそれなら,他の受容にかけてはけして柔軟でない否定がめだつ湯原もちがいはなく,その都度の全が全の性質にかけて無とも充実ともみえつつ現前しなければ作品とならないそのでかたは独創の結果でなくとも独創の條件であり,まちがいなくこれは湯原をおとづれている。気が利いたということではないエレガントについてすでにふれたが,おもいきつていうと湯原にとつてオリジナルでなければエレガントではないのだ。それならばエレガントかそうでないかは人間の生をめぐつてのエチカをふくむことになる。独創ならざる作品をかれがみとめない理由のひとつはたぶんこのへんにあるのだろう。 |
|
|
さてここで,現在都市改造をおこなつているパリのデファンス地区にランド・マークとして建築中の「テット・デファンス」のことにふれなければならなくなつた。デンマークの建築家スペッケルセンの設計による,これは門のかたちをしたビルディングである。きわめて独創的なかたちにおどろくが,湯原和夫にはすでに今回出品される『不快な門』『門』『黄金と黒色による彫刻』『開かれた形』といつた一連の門の造型があることを知るひとのためには,このふたつのかたちが単なる類似ですむのか気になるところだ。そのあいだの事情はこの図録にのつたオットー・ハーンのエッセイと,水沢勉の「都市計画と彫刻の教え」(*7)にややくわしい。複雑な構造をしたものならともかくシンプルきわまる形態をめぐる類似ゆえ,スペッケルセンのがオリジナルかどうかをいうことをむずかしくしているとしても,このことだけはいつていい。湯原の門のアイデアはすでに1969年国際鉄鋼彫刻シンポジウムの『無題 No.5-69』あたりからぼくらのまえに作品としてあつたということだ。 |
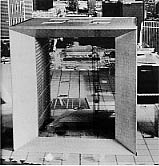 ④建築中の「テット・デファンス」 |
|
かつてプライマリ・ストラクチュアとのかたちの類似をいわれて抗議したことをわすれるかれではないはずで,だからこれもまたオリジナルかどうかは藝術にとつて死活のこととする,「非個性的なもの,非人間的なもの,オリジナルでないものこそ現代的」だというひとすべてにあてたメッセージとしてぼくはきく。和歌における本歌取にはじまり引用の織物としての謡曲とか,粉本主義のきわまつた江戸の絵画をへて現代にいたるぼくらの国の藝術はどうやら型から型へうけついで藝の洗煉にこころをうばわれ,あるいはパスティッシュに終始してオリジナリティをかえりみるひまもなかつた。模倣にかんして法外に寛容なこの海に湯原のオリジナル論は半島のようにつきだしている。そして西洋の知がみづからへの懐疑と反省とから救いか自殺かだれにもわからぬ行為をくりかえすこの時代はいつけん日本に有利なときのようにみえるかもしれない。このせかいの,というより以上のそれをうけとる日本の体温の変化にもかかわらず,おなじ熱で個性や人間性やオリジナルをかたりつづける湯原がエレガントからとおく無骨きわまりなくみえるとしたら,それはそつちのほうが危険だ。流行と不易は藝術の両輪とはいつてもおのずからの軽重はあるからで,流行は湯原の場合もその作品の時代性としてやがてふるびるがむしろそこから不易ははじまる,とは,いまこそかれのいうオリジナルがその作品のうえであきらかにされるということだろう。それがはつきりすればスペッケルセンのもんだいはちいさいことになる。 詩は常識に反してじつはなにごとも意味しないし展開もしない。ことばが純粋にことばにかえつてそれは禅のことばでいうと全機関同時現成とでもなるのか,かぎりのある無限である宇宙をまねた卵であることをめざす。いつたい彫刻もおなじことで,いうべきなにものをももたなくなるにつれて彫刻は彫刻にちかづく。ひとに感動をしいることばの拒否。つまりそとからはりつける意味を拒否して,自然にまかせておけば奇形をとるはずもないせかいへ推しだすちからをそのちからの線にそつてうけとめること。彫刻家とはそういうせかいをみたす存在たちの祝祭の司祭であり,その祭壇にまつられるべきそれをたとえばアランは尊厳MAJESTE(')とかたつたことがあつた。湯原をかんがえているあいだずつとこのアランの定義があたまにあつた,とは,かれの作品もまたひとつの卵だということか。表現をかたく拒否することがかえつて表現のただひとつの根拠となる,といつた風の。 鉄にはじまつて,その研磨された表面の魅力からアルミニウムをはじめとする鏡面,またそれとの対照をなす人造毛皮とか錆とか琺瑯とかのマチエールに注目してきた湯原の素材の探求からは,さらにガラスもふくめて,二十世紀後半のせかいがつくりだした現実によりそつて思考する彫刻家ならではのあゆみがとれるいつぽう,そのあゆみを展開というならその展開をになう素材はちがつてもそこからとりだされたイデーのかたちにかわりなく,いつもことばのてまえに凛乎とした姿でたつ。過去と未来を前後際断して。 かれの彫刻はぼくらのもののかたちを,さらにいえばものがそこにあることの,そことかあるということについて教えてくれる。この教えはどんな意味をもきびしく謝するゆえにかえつて応用ひろく,やがて気がつけば街路に工場に室内にとおよそ眼にふれるあらゆるところに湯原という固有名詞をもたぬ無題の湯原がある,という地点までぼくらをつれていくはずだ。そしてそれがたつた一瞬にすぎなくても,ありふれた日常を尊厳というしかない感覚でつつむのだ。存在の祝祭。そこにたちどまらなくてもいいので,単純なかたちの連鎖でつくられたせかいの相はそういうやわらかな眼にかぎりなくとびこんでくるだろう。 (ひがし・しゅんろう 三重県立美術館学藝員) |
|
