横山大観《夜桜》について
佐藤美貴
|
近代日本画の巨匠と称される横山大観の知名度は、同時代の他の画家たちと比して群を扱いて高い。「横山大観展」と銘打った展覧金は枚挙にいとまがなく、大観についての論評も多い。そしてその人気は、大観の死後四〇年以上たった今もなお衰えをみせず、大観の作品や生涯は、われわれを魅了してやまない。しかし、一方で、大観が岡倉天心指導のもと在野の美術団体、日本美術院で並々ならぬ苦労を重ねたことも広く知られるところである。東京美術学枚の卒業制作《村童観猿翁》で同学年中最高得点を得、さらにその後は模写事業への徒事、京都市美術工芸学枚教諭さらに東京美術学校助教授と順調なスタートをきりながらも、東京美術学校騒動の析に、天心とともに野に下り、朦朧体と嘲笑された没骨描法の研究に邁進した。従来日本画が重視してきた描線を捨て、色彩により光や空間を表現しようとする新しい描法は、その斬新さゆえにうけいれられず、日本美術院も窮地に立つことになる。ことに五浦時代は、その日の食事にも困るほどの貧窮ぶりであったという。このように苦しい在野の立場から、文展での活躍を経て日本画界の頂点へ。そして手にした絶大なる権力といまなおかわらぬ大衆性。これらの相反する要素があいまって、ある意味で大観をとらえ難き存在としていることは否めない。 |
|
|
このような波乱に満ちた大観の生涯をふり返るとき、すでに指摘されているように、一九三〇(昭和五)年にローマで開催された日本美術展(以下、ローマ展)は、実力は充分に認められながらも在野として活動していた大観が、日本画界の主流へと転じたひとつの契機になっている(註1)。ローマ展以降の大観は、一九三一年の帝室技芸員就任、一九三六年の帝展松田改組への全面的協力、一九三七年の文化勲章受賞、帝国芸術院会員、一九四三年の日本美術報国会会長就任、一九四六年の文部省主催第一回日本美術展覧会第一部審査員など一転して官を代表する日本美術界の巨匠へと転じる。このように在野の雄から華々しく官の中心的画家へと転じた大観については、その正当な評価が為されているとは言い難い状況である。ここでは、ローマ展、そして、そのローマ展の出品作で、幸いにも今回の展覧会での展示が叶った《夜桜》が、大観の画業においてどのような意味をもつのかを、先行する研究をもとにみてゆきたい。 |
(註1)大熊敏之「昭和期アカデミズム日本画の確立-一九二○~四○年代の横山大観」(「横山大観の時代 1920-40s」一九九七年 宮内庁三の丸尚蔵館 p.42) |
1.ローマ日本美術展
|
一九三〇(昭和五)年四月二六日から六月一日の間、ローマ、パラッツオ・ナッツィオナーレ・デッラ・エスポジッツィオーネ(Palazzo nazionale della Esposizione)で開催されたローマ展は、大倉喜七郎(1882-1963)が企画、全費用を負担した大規模な展覧会である。一九二八年、大倉がイタリア首相ムッソリー二に、大観が描いた《立葵》を寄贈したのを機に、ローマでの日本美術展開催が決定した。一九三〇年といえば、大倉が帝国ホテルの創業者である父喜八郎の後を継いでその経営にあたり、川奈ホテル、上高地帝国ホテルを準備中であった時期でもある。東京朝日新聞に掲載された「展覧会は明年三月ごろになるでしょうが、その頃は外人客がローマに殺到する時期で、そうした遊覧客に見てもらうことも一つの目的です(略)」という大倉のことばには、イタリアに日本美術を紹介することだけでなく、ローマを訪れている欧米人に日本美術を紹介し、最終的には美術を通じて海外から日本へひとびとを誘致しようという壮大な理想が秘められていたともいわれている。 一方で、実際の運営と出品作家の選択は大観に一任された。そして、過去に例がないほど大規模なこの海外展において、大倉と大観は、日本画を展示する展示室の在り方に特にこだわりをみせている。この点については、大観が『伊太利政府主催大倉男爵後援 羅馬開催日本美術展覧会に就て』一九三〇年八月)の中で、緒言に続く第一章で「其の内的動機とも申すべきものは、日本画を日本室らしい曾場に於て西洋人に鑑賞されて見たいといふことにありました、即ち、日本画を玩味するに必須なる條件としての、床の間や青畳等の設備、活け花の趣向さへ添へて、日本画の本領をば欧洲へ遺憾なく西洋人へ伝へたいといふ念願を發せられたのであります。」と真っ先にとりあげていることからも、この展覧会の特色のひとつであったことがうかがえる。大工監督六名、表装師二名などがイタリアに同行して会場設営にあたったことや、日本画をそれに適した環境に展示することの重要性など、かなりの頁を割いて力説しており、同書に掲載された展覧会会場の写真をみても、和の設えに徹している様子がうかがえる。ローマ展において、大観をはじめ日本を代表する画家たちの描いた日本画は、既存の西洋展示室内ではなく日本の伝統的な設えの中で異国のひとびとに紹介されたが、このような大規模な試みはもちろん過去に例のないことであった。 このように、展示環境にも日本を十二分に意識したローマ展に出品された大観の作品は、《寒牡丹》《暁靄》《雙龍双珠》《蜀葵》《梅花》《隼》《春の夜》《飛泉》《富士山》《山四趣》《夕顔》《百合花》《夜桜》《龍胆》の一五点。この出品点数は、帝国美術院の代表としてローマ展にのぞんだ川合玉堂の一〇点、竹内栖鳳の五点に比しても多い。さらに、イタリア全土の汽車内に掲げられたという「富士山」の描かれた展覧会ポスターも大観自らが手掛けており、これらの事実は、この展覧会に占める大観の存在の大きさのみならず、大観自身の意気込みも感じられ非常に興味深い。 |
 挿図1. Palazzo nazionale della Esposizione 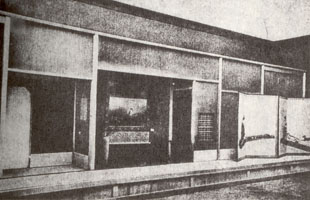 挿図2. ローマ展 展示室  挿図3. ローマ展 ポスター |
2.《夜桜》
|
大観が、熱意をもって臨んだローマ展に出品した作品の中の一点が、一九二九(昭和四)年に制作された《夜桜》である。ローマ展のために描かれた新作で、同年一一月一七日に日本美術院で内覧会をおこなっている。翌月一三日には、出品作の中殻優秀な作品三二点が宮中で展覧に供されたが、その中にはもちろん《夜桜》も含まれていた。 六曲-双という大画面に描かれた《夜桜》は、数多い大観作品のなかでも、華やかな装飾性と、群青、緑青、朱など濃彩や月に用いられた白金の使用による鮮やかさ、迫力という点において抜きん出ており、記念すべきローマ展の出品作であるだけでなく、大観の画業における代表作のひとつに数え得る。背後に連なる山々は墨で描かれており、篝火にうつしだされた山桜が鮮やかに映える。桜花はすべて観者を向いて開き、画面を-層華やかなものにしている。さらに山々に用いられた墨は、画面上部にわずかにのぞく夜空の群青と相俟って重厚な空気を生みだし、松に使用された緑青は、篝火の朱と大胆な色彩の対比をみせる。篝火からまっすぐにたちのぼる烟は、静かに散る花びらと対照的な動きをみせながらも、まっすぐに地面へと向かう花びら同様、この画面が風の動きのない静かな状況であることを暗示し、色彩の対比や画面構成とともに、大観の周到な計算を感じさせる。 |
|
|
ところで、この《夜桜》は、富田溪仙筆《祇園夜桜》(横山大観記念館蔵)から影響を受けているとしばしば指摘される。《祇園夜桜》は、一九二二(大正一一)年にクリーブランド美術館の要請で開催され、米国を巡回した日本美術院米国展覧会(以下、米国展)の出品作であり、京都祇園の枝垂れ桜が篝火の中から幻想的に浮かび上がる様子を描いている。縦四八.三センチメートル、横七一.〇センチメートルの絹地に、闇に包まれた山々、そして夜桜を取り囲む松が墨の微妙な調子をいかして描かれ、趣ある空間を生み出している。その閣の中に、《祇園夜桜》の主役でもある枝垂れ桜が朱色の篝火によりその優美な姿を浮かび上がらせている。この作品は、キャサリン・M・ボールが、「この展覧会で最も人気を呼んでいる作品の一つは富田溪仙の《祇園夜桜》であるが、画趣に富んだ詩的な作風に鑑みればもっともなことである。下方からの火明かりで陰影を帯びた淡紅色の桜が夜の闇に神秘的に浮き上がるのである(注2)。」と述べているとおり、当時も人気があった作品のひとつと考えていいだろう。そして、大観は、この《祇園夜桜》を非常に気に入り、のちに譲り受けている。長尾政憲氏「富田溪仙と大観-溪仙にあてた手紙からみて-」(『財団法人横山大観記念館館報No.1』)で紹介された大正一五年五月一九日付の溪仙に宛てた大観からの手紙には、《祇園夜桜》に触れた箇所があるので、以下に引用しておきたい。 「此度は御無理願上候処、早速御作品集御恵贈被下難有拝受仕候 |
 挿図4. 富田溪仙筆《祇園夜桜》 (註2)『日本美術院百年史 第五巻』(一九九五年 日本美術院百年史編集委員会)p.881/同p.1026に掲載されている原文は次の通り。 |
|
画題の桜については後に詳述するが、二人の画家がともに海外展において同様に夜桜をモティーフとしている事実は興味深い。しかし、同主題を扱っているとはいえ、溪仙の《祇園夜桜》と大観の《夜桜》には大きな逢いもある。 差違としてあげるまでもないことではあるが、まず第一に、画面形式の違いがある。《祇園夜桜》は、前述のとおり現在は軸装である。米国展出品当時は額装であったが、しかしこれは展覧会の規定であり、基本的には溪仙に画面形式を選択する余地はなかった(註3)。一方、大観の《夜桜》は六曲一双屏風である。《祇園夜桜》に刺激をうけながらも、画面形式において、大観は《祇園夜桜》を踏襲せず、六曲一双屏風という、力強さをより強調することのできる大きな画面を選んでいる。 続いて、溪仙と大観の夜桜は、その色彩においても大きな違いをみせる。《祇園夜桜》は、墨の濃淡を生かして夜の山々が表現されており、篝火や、その炎に照らされて仄かにうかびあがる桜により、幻想的な京の夜の情景が描き出されている。一方、大観の《夜桜》では、先にも触れたように、群青、緑青、朱など濃彩がもちいられており、溪仙のつくりだした幻想的な世界とは対照的に、鮮麗かつ重厚な世界をつくりだしている。 続いて、溪仙と大観の夜桜は、その色彩においても大きな違いをみせる。《祇園夜桜》は、墨の濃淡を生かして夜の山々が表現されており、篝火や、その炎に照らされて仄かにうかびあがる桜により、幻想的な京の夜の情景が描き出されている。一方、大観の《夜桜》では、先にも触れたように、群青、緑青、朱など濃彩がもちいられており、溪仙のつくりだした幻想的な世界とは対照的に、鮮麗かつ重厚な世界をつくりだしている。 最後に、もうひとつ特筆しておくべき差違は、桜の種類である。《祇園夜桜》に枝垂れ桜が描かれていることは既に述べた。溪仙のこの作品に限らず、祇園の桜といえば円山公園の「祇園枝垂れ」が有名である。祇園の初代枝垂れ桜は、江戸時代に八坂神社の境内から移植されており、その後、昭和24年に二代目枝垂れ桜が植えられているため、溪仙が《祇園夜桜》で描いた祇園枝垂れは初代の枝垂れ桜ということになろう。一方、大観の《夜桜》に描かれている桜は枝垂れ桜ではない。大観は《夜桜》を描くにあたって、頻繁に上野に通っている(註4)。たしかに上野の桜は染井吉野や里桜、山桜などが主であり、大観の描いた桜の種類が枝垂れ桜でないことと上野の桜とは無関係でないかもしれないが、「概して實感本位に立脚して視覚対照の効果に重きを置く洋画としては、行詰るのが当然の歸結ではなかろうかとも感じました。然るに日本画は、東洋精神の伝統に根ぎして時代とともに研鑽を進め、高く主観的理想から出發するものでありますから、描寫の根本が洋画と相反し、客観界を寫實的に説明するとちがひ、作者胸憶の世界を不可言的に如實に吐露するものでありますから、日本画の道たるや、實に窮まる所なき永遠の大道なのであります。」とも述べている大観のこと、やはり、意図的に枝垂れ桜から山桜へと変更しているとみるべきであろう(註5)。月夜に浮かぶ背後の山々や、《祇園夜桜》の影響力を考えてみても、大観が祇園の夜桜を意親していた可能性は非常に高い。それゆえに、「祇園=祇園枝垂れ」という-般的な常識を覆してまで山桜を描いたことの持つ意味は大きい。大観は、この作品において、上品ではかなげな美しさをもつ枝垂れ桜ではなく、力強さを感じさせる山桜を選択したのではないだろうか。画面の大きさ、配色のみならず、モティーフの選択においても、大観がある種の迫力を追求した可能性は決して低くないように思われる。 このように、山桜を選択した大観であるが、この桜というモティーフが、日本人にとって非常に思い入れの深いものであることは、ここで改めて繰り返すまでもないだろう。日本においては、桜花が描かれる絵画、工芸作品は極めて数が多い。しかし、それに反して万葉集で詠まれた歌は、梅が一一八首、桜が四三首、椿が九首と圧倒的に梅が多いのである。桜について、すでに「平安、鎌倉期に国粋主義の発展とともに多く描かれている(註6)」との指摘があるように、中国から伝わった梅の愛玩は、平安時代に入り、日本的な美意識が生まれるにしたがい桜へと移行し、次第に桜をモティーフとした作品が増えていく。 |
(註3)『日本美術院百年史 第五巻』(一九九五年 日本美術院百年史編集委員会)p.863 「大きさは尺四方物、尺八、尺二、ニ尺五寸の四種でみな額」 (註4)竹越真三夫「″夜桜″″紅葉″両屏風ご製作時のこと」(「財団法人 横山大観紀念館館報No.2 一九八四年 横山大観記念館)p.6「昭和四年の花どき、上野公園へ、夜桜の情趣観察に幾晩も出掛けられ、最初と中間の二回私も供をいたしました。五重の塔を囲んで咲いた山桜が、美しい印象を深く残しました。」 (註5)加藤類子「日本画と桜」においても、大観の《夜桜》について、「紅枝垂の優美さを、躊躇することなく山桜に変えている」と指摘されている。(『日本美術全集二二』 一九九二年 講談社 p.234) (註6)北村四郎『花鳥画の世界』の植物『花鳥画の世界 花鳥画資料集成』第一一巻 p.130 一九八三年 学習研究社 |
|
このように、桜というモティーフのもつ歴史的な意味を充分に意識し、大観は、ローマ展出品作のモティーフとして、伝統的、日本的な桜を選んだと考えられる。また、大観がこの論説を目にしていたかどうかはわからないが、「櫻花の画」(『繪画叢誌』一三五 明治三一年四月発行)と題した論文の中で、野口勝一が、已に櫻「本邦人花を以て天下第一の花となし之を誇り又本邦画を以て世界の希有の技となして之を貴ふ乃ち希有の技に因りて天下第一の花を画き而して其眞趣を得るに至らさるは是れ大なる?点といはさるへからす盖し其花に誇り其技を貴ふことを知て其花と技とを併せて宇内に誇揚する所以を思はさるに於ては二者分離して花の薦めに技の足らさるを嘆き技の薦めに花を顯はすを得去る惜しますんはあらす故に他の卉木禽獣等の如く櫻花を専修して形意兼ね盡くし櫻花の薦めに一法門を開くあらは畫史の薦めに好模範を垂るるのみならす之に因て名花の光彩を世界に耀かすを得へきならん乃之を勉むるは畫道の一進歩にあらすや」と述べている点も興味深い。 |
|
3.海外展への取り組み
|
ところで、大観が存命中にかかわった海外展は、もちろんローマ展だけにとどまらない。大観の画歴のもっとも早い段階での海外展とのかかわりは、一八九二(明治二五)年米国シカゴのコロンブス記念万国博覧会で、政府出展物「鳳凰殿」の室内装飾を、大観が在籍していた東京美術学枚で引き受け、これに大観が加わったというものである。また、一九〇〇(明治三三)年のパリ万国博覧会には、農商務省に買い上げられた《聴法》(焼失)が出品されている。さらに、麦田春草とともにインド、欧米視察に出かけた折に、各地で展覧会を開催し、好評を博したことはすでによく知られている通りである。また、先に溪仙の《祇園夜桜》に言及する析に触れた米国展に大観も出品しており、一九二九(昭和四)年にパリ開催の日本美術展に《生々流転》を出品、そして一九三〇(昭和五)年のローマ展以降もベルリン、ニューヨークなどの展覧会にかかわっている。 大観がかかわった海外展は少なくないが、当然の結果として、ときどきの日本画界における大観の位置により、大観の展覧会への対し方、展覧会の持つ意味合いは大きく異なっている。すなわち、まだ大観の画家としての評価が定まっていない時期に、美術学枚の一員として参加したコロンブス記念万国博覧会やその四年後のパリ万国博覧会。そして、インドや欧米各地で試みた、日本で受け入れられない自らの実力を海外で計り、加えて外遊の資金を得るための展覧会。さらに、日本国内においてその実力を認められた大観が、日本美術院あるいは日本を代表する画家として積極的にかかわった展覧会である。日本を代表する画家として海外展に臨む場合、日本あるいは日本画を誇示しようとする意識が多分に働く。ここでとりあげているローマ展はまぎれもなく第三のケースであり、もっともその特徴が顕著にあらわれた事例であるとさえいえよう。《夜桜》の主要モティーフである桜は、日本を強く意識させる。さらに枝垂れ桜ではなく山桜というモティーフの選択からも、海外に日本をしらしめようとする大観の意欲が垣間見える。つねに広く世界を見、自らも世界を舞台に活躍した師、岡倉天心同様に、海外とのかかわり方が、大観を考えていく隙のひとつのポイントとなるように思われる。 このように、日本画あるいは日本を強く意戟した《夜桜》に対しては、それゆえに厳しい批判もある。それは、《夜桜》という作品に向けられた批判であるという以上に、在野の立場で新しい日本画を目指し、日本美術院を率いて精力的な制作活動をおこなってきた大観が官の画家へと転じ、当時の国家体制への支援を惜しまなかったことに向けられた批判でもあろう。この点については、今後さらなる検討が必要である。しかし、それらのテーマを考えていく上でも、海外展、特に日本画壇の代表として積極的にかかわったローマ展における大観の在り方、その出品作《夜桜》は重要な位置を占める。《夜桜》は、大観の装飾的作品の集大成であると同時に、以降の大観作品にあらわれる特色を内包した、昭和期の大観を考えてゆく上で欠かすことのできない作品である。そして、昭和期の代表作と言っても過言ではない《夜桜》をもって臨んだローマ展を終えた大観はいう。「古へは、西で『世界の道は羅馬へ』でありましたが、これからは全地球に就いて『世界の美術は日本畫へ!』向ふのであります」(『伊太利政府主催大倉男爵後援 羅馬開催日本美術展覧曾に就て』)と。ローマ展を成功させた大観が手にしたものは、はかりしれない自信と栄誉であった。 (三重県立美術館学芸員) その他の参考文献 『昭和五年・ローマ開催日本美術展覧会の回想』一九八〇年 大倉文化財団大倉集古館 |
