上村松園の画業-近代絵画としての意義
毛利伊知郎
はじめに
|
上村松園は、近代日本を代表する女性日本画家としてつとにその名が知られ、生前から現在に至るまでに幾種類もの画集や評伝・研究書等が刊行されている。また、全国各地で頻繁に開催される個展会場は常に多くの人々で埋め尽くされるという。松園描くところの女性像・美人図は多くの人々から愛され続け、その近代美術史上の評価も既に定まった観があるといえる。 女性の社会的立場が今日とは比較にならなかった明治・大正期に、画家として自立を果たし、美術史上に名を残した松園の人生と、生きざまに眼を向けることも重要ではあるが、松園作品が近代絵画史に占める位置、作品自身の造形性・技法上の特質等についてはまだ考察すべき余地が残されていると考えられる。また、松園の作品が今も多くの人々の関心を集める背景について、私たち日本人の美意識や嗜好等と関連づけながら考えてみることも無駄ではないと思われる。 |
|
|
ところで、本展覧会では一つの試みとして松園の生涯を年代順に四つの時期に分けて展示構成を行っている。松園の画業を検討しようとすると、かつて原田平作氏が指摘したように、大きく二系列に分かれる松園作品の画題に着目する観点と作風の展開に着目する観点の二つの見方が考えられる(註1)。この画題選択の在り方と作風展開は相互に関連している部分があることから、六〇年に及ぶ松園の画業を時系列のみで整理することには危険も伴うのだが、上記の松園作品の展開について考える一つの手法として、このような展示構成を採用することとした。以下では、この展示構成にそって松園の画歴をたどるとともに制作の背景を見ながら、上村松園における「近代」とは何かについて検討してみたい。 |
註記 一.原田平作「上村松園の画風」『上村松園画集』一九八九年 京都新聞社 |
一.生い立ち・修業期
|
上村松園(本名・津禰)は、一八七五(明治八)年四月二三日、現在の京都市下京区四条通り御幸町西入に葉茶屋「ちきりや」を営む上村太兵衛、仲子夫妻の次女として生まれた。しかし、松園誕生前の二月に父は逝去していて、松園は誕生時から母一人で育てられることになる。 松園に近い世代の画家を見ると、松園は京都では西村五雲、木島櫻谷、伊藤小坡らより二歳年長、東京では川合玉堂・下村観山より二歳下、菱田春草より一歳下で、結城素明と同年令、平福百穂より二歳年長ということになる。 松園は幼い頃から絵ー特に人物を描くことを好み、また結髪や着物・帯など服飾にも強い関心を抱くようになったという。一八八七(明治二十)年、松園は小学校を中等科五級で中退して京都府画学校へ入学、親戚の反対にあいながらも母の理解に支えられて本格的に絵の道を進み始めた。 当時の画学校には、西洋画の西宗、南画の南宗、円山・四条派の東宗、狩野派・雪舟派の北宗の四科があり、松園は北宗科に属して画学校に通うかたわら、師鈴木松年の勧めもあって松年画塾にも通うこととなる。翌一八八八(明治二一)年には師松年から「松園」の雅号を与えられ、松年が画学校を辞したのに従って松園も退校して松年塾の塾生となった。 |
|
|
松園の展覧会への出品は同年の後素如雲社展への《美婦人図》が初出品とされる(註2)。一八九〇(明治二十三)年、第三回内国勧業博覧会に松園は《四季美人図》を出品して一等褒状を受け、この作品が英国王子コンノート公に買い上げられることとなる。当時、松園はまだ一五歳であったから、画家としては早熟で幸運なデビューだったというべきだろう。以後も毎年、日本美術協会美術展覧会、京都市美術工芸品展、新古美術品展覧会などに出品を重ね、一八九三(明治二十六)年にはシカゴ万博にも作品を出品している。そして、この年から松園は幸野楳嶺の画塾にも通い始めたが、一年半ほどで楳嶺が死去したことから、一八九五(明治二八)年からは楳嶺門下四天王の筆頭といわれた竹内栖鳳にも師事することとなる。 当時の松園は、栖鳳から写生の重要性を説かれて、熱心に写生や古画の模写を行っている。現存する古画の模写や縮図は、江戸中期以降大きな影響を与えていた円山応挙の作品を初めとする江戸時代諸派の絵画、平安期の絵巻物、室町水墨画、近世初期期風俗画などの他、染織品・櫛簪など広範囲に及んでいる。こうした古美術研究と並行して、松園は早くから有職故実研究に励む他、漢学塾にも通うなど、画嚢を肥やすことに精力を注いでいた。 明治二〇年代後半から三〇年代前半の松園画としては、デビュー作となった《四季美人図》の他、《清女●簾図》《義貞勾当内侍を視る》(明治二八年)など古典に題材を取った作品、当世風俗画的性格を持つ《人生の花》(明治三二年)などをあげることができる。 この時期の作品を見ていて気づくのは、作品の内容・表現が必ずしも一様ではなく、松園が試行を重ねていた様子を見てとることができる。《四季美人図》は、内国勧業博出品作以外にも複数の作品が描かれているが、それらは上方浮世絵の代表的画家西川祐信の肉筆画(挿図1)を連想させる画面構成と色感を示している。 また、《清女●簾図》(挿図2)《義貞勾当内侍を視る》(挿図3)等は、松園による歴史・古典文学研究の成果と見受けられる作品で、直接的には草薙奈津子氏が指摘したように竹内栖鳳の《富士川大勝図(平軍驚禽声逃走)》(挿図4)との関連と同時に師鈴木松年の影響をも窺わせる作品である(註3)。こうした細密描写と濃彩による歴史画は、その後はほとんど制作されなくなったが、修業期の松園の一面を知る上で重要な作品である。もちろん、《伊勢大輔》(昭和四年)、《雪月花》(昭和一二年)など古典文学に取材した作品は後年も描かれたが、こうした作品では建築や庭園など情景描写は省かれて、人物のみが大きく配される点、初期の歴史画とは大きな相違がある。 《人生の花》は、一九〇〇(明治三三)年の第九回日本絵画協会・第四回日本美術院連合共進会で銀牌を得た《花ざかり》の異作で、「華やかな婚礼の式場へのぞもうとする花嫁の恥ずかしい不安な顔と、附添う母親の責任感のつよく現れた緊張の瞬間をとらえた」(註4)作という。この作品については、二〇代半ばの松園が自身の青春の夢を込めて描いた作品と評されることが多いが、造形的には登場人物を画面に大きく配する点、背景を描かず余白を大きくとって人物を浮き立たせている点、着物の描写に見られるように大きな色面による表現を取り入れている点、髪飾りや帯・着物の文様、あるいは髪筋などを細密描写している点など、各所に後年の松園画にも通じる特徴を見出すことができる。この時期の作品中最も大幅であることも考慮すると、《花ざかり》《人生の花》が後の松園女性像の一つの原型であるといえるだろう。 ここで、この時期に描かれた所在不明の作品《一家団欒》(明治三〇年)(挿図5)にも言及しておこう。この作品は、文字通り家族団欒の様子が主題となっていて、想像をたくましくすれば、誕生前に父を亡くしていた松園の家庭団欒への憧れが込められた作品とも読むことができる。興味深いのは《花ざかり》《人生の花》とともに、この作品が同時代の家庭生活、人々の営みを主題としていることである。しかも、それは近世以降、好んで風俗画・美人画の主題として描かれた花見や紅葉狩などの遊楽ではない。近代日本のごく普通の家庭生活の一齣であったり、人生の転機となる出来事である。こうした作品が既に松園二〇代に描かれていることは重要で、ここにこそ近代を生きた上村松園という画家のものの見方、近代的な視覚が既に現れていると筆者には思われるのである。 ところで、明治三〇年代の松園画を見ていると、明治三五年以降に一つの変化が起こっているように見受けられる。それは、《よそほい》(明治三五年頃)、《姉妹三人》(明治三六年)、《遊女亀遊》(明治三七年)(挿図6)などに認められ、次の時期に継承、展開されていく表現の誕生である。 たとえば、《よそほい》は《人生の花》の一展開とも言える作品で、花嫁衣装の着付けを手伝う母親とその娘の様子を主題としている。この図では、着物や帯の文様の華やかな表現、動きを加えた人物のポーズと構成などに、《人生の花》にはなかった新しい試みを見ることができる。 また、《姉妹三人》では和本を見る三人の若い娘が重なって立ち、複数の人物をどのように表現するかに松園は腐心している。また、手前に立つ娘の着物に使われた明るいピンクは、後年の作品で多用される松園独自の清潔感のある色彩で、色彩画家上村松園の誕生を予感させるものである。 さらに、この時期の代表作の一つ《遊女亀遊》は、異国人男性に身をまかすことを潔しとせずに自害した遊女を題材にした作品。行灯や屏風、文箱等を配置することによって、この主題が持つ劇的な性格が強調されている。画中に描き込まれた水墨の山水図屏風は、松園による古画研究の成果であるとともに、色彩画家上村松園が水墨表現にも長けていたことを示している。しかし、この図でより興味深いのは亀遊の沈鬱な表情とポーズで、ここには人物画において登場人物が示す感情表現に対する松園の基本的な立場が見てとることができる。このような明治三〇年代後半に現れた人物表現の特質は、一九〇七(明治四〇)年以降の官展出品作に引き継がれ、完成度を高めていくことになる。 |
二.村田真知『上村松園書誌』一九九九年 美術年鑑社 
挿図1 西川祐信《詠歌美人図》18世紀 
挿図2 《清女●簾図》1895年 
挿図3 《義貞勾当内侍を視る》1895年 
挿図4 竹内栖鳳《富士川大勝図(平軍驚禽声逃走)》1894年 三.草薙奈津子「上村松園の画業」『上村松園回顧展図録』一九九六年 日本テレビ放送網株式会社 四.上村松園「作画について」『青眉抄』所収
|
二.明治末から大正期の画業
|
一九〇七(明治四〇)年に文部省美術展覧会が始まると、松園は第一回展に《長夜》を出品したのを皮切りに、《月影》(第二回)、《上苑賞秋》(第四回)、《蛍》(第七回、挿図7)、《舞仕度》(第八回)、《花がたみ》(第九回)、《月蝕の宵》(第十回)と出品を重ねた。しかも、松園の出品作は常に上位賞を受賞し、同世代の西山翠●、木島櫻谷らとともに、京都勢を代表する活躍を見せた。また、『生写朝顔話』に取材した代表作の一つ《娘深雪》(大正三年)(挿図8)もこの間に描かれ、大正中期には異色作《焔》(大正七年)が文展で発表されるなど、一九一〇年代を中心とする明治末から大正前期は松園の制作がいわば高揚期に入った時期であった。 そのことは、掛幅・額装の作品に加えて、屏風形式の作品も描かれるようになったことからも窺うことができる。三〇代に入り、画家としての経験が増し十分な体力もある時期で、こうした大画面作品への挑戦が行われるようになったと推察される。 第一回文展出品作《長夜》は上方浮世絵との関連が指摘される作品であるのに対し、翌年の《月影》(挿図9)は同時代の生活の一齣を題材とした作品というように画因は異なるが、これら二作品は情景描写的な内容、余白を活かした画面構成、変化に富む墨色など造形面では《遊女亀遊》と共通する点が少なくない。このように作風のみを吟味すると、明治三〇年代後半ー三七年頃に画風展開の一つの画期を置くのがより妥当かもしれない。しかし、官展という公的な大美術展への出品が、松園にとって大きな意義を持っていたことは疑いなく、そうした意味では一九〇七(明治四〇)年を転機の年と見ることもできるだろう。 ところで、この時期の松園画には主題と表現双方において模索の跡が認められる。そのことは古画研究ということに限っても顕著で、例えば西川祐信に代表される上方浮世絵風の《長・驕tの他、《彦根屏風》など近世初期風俗画研究の跡が濃厚な《虫の音》(明治四二年)、喜多川歌麿の美人画との関連が認められる《蛍》(大正二年)(挿図8)、円山四条派風の美人画を連想させる《吉野太夫》(明治四三年頃)(挿図10)等々、この時期の松園は近世初期から幕末期に至る広範な古美術研究に基づく作品を制作している。 また、主題については、《月影》《月蝕の宵》《舞支度》など同時代の生活や風俗を描写した作品の他、《吉野太夫》《娘深雪》など古典文学に取材した作品も描かれるなど振幅が認められる。 この時期から松園は能・謡曲に画題を求めるようになった。それは後年の画業においても重要な意義を持つ、新たな作画法の発見であった。その先駆けとなったのは《花がたみ》(大正四年)で、《焔》(大正七年)もこの系列に属する作品である。 《花がたみ》は凶女物の謡曲「花筐」から題材を得た作品で、継体天皇の前で凶人の舞を舞う照日前の姿が描かれている。物語性を持つ作品ということでは、《遊女亀遊》《娘深雪》に連なるものだが、松園は京都岩倉の精神病院を訪ね、実際に能面や舞妓の舞姿を写生するなどして制作を進めている。 そうした制作過程について松園は、「何事も見極めるー実地に見極めることが、もっとも大切なのではなかろうかと思う。まして、芸術上のことにおいては、単なる想像の上に立脚して、これを創りあげるということは危険であるように思うのである」(註5)と記しているが、こうした実証的な姿勢が松園にあることは、松園の絵画観を考える上で興味深い。 一方の《焔》は謡曲「葵上」に基づく作品で、光源氏の正妻葵上を襲う生霊となった六条御息所の姿が絵画化されている。激しい嫉妬から怨念を抱き生霊となった凄絶な女性の姿が描かれ、その激しい感情表現は数多い松園画の中で異彩を放っている。造形的には、長い黒髪が描くゆるやかな曲線とやや前屈みで振り返る身体の動勢、女性の視線の向きとが関連づけられて、六条御息所の存在は一際印象深いものとなっている。 《焔》については、一八世紀に京都で活躍した曾我蕭白の《美人図》(挿図11)との共通点が指摘されている(註6)。確かに、女性の嫉妬を表現した内容、手を口元に当てる姿勢、左手小指を立てるしぐさ等の図像などの他、衣装の文様が大きな存在感を持つ点も似通っている。直接的な影響関係を確認することは不可能だが、こうした《焔》と蕭白《美人図》との類似性は、上村松園という画家の背景が意外なほど大きく広いことを示しているといえるだろう。 また、この図では蜘蛛の巣と藤の文様が描かれた打掛が大きな役割を果たしている。この衣装は桃山期の服飾を参照して描いた旨を松園は記しているが、この蜘蛛の巣と藤の文様にアール・ヌーボー調的な雰囲気が感じられるといえば言い過ぎであろうか。 松園は一九一四(大正三)年頃から金剛巌に謡曲を習い始め、謡曲や仕舞をながく趣味としていたことから、能・謡曲に取材して作画することが多くなったと自ら記している(註7)。しかし、絵画と能・謡曲との関係を振り返って見れば、江戸時代以降能・謡曲に絵画作品の主題を求めることは決して特別のことではなかった。そうであれば、能・謡曲に取材した松園画は彼女の個人的関心だけで説明されるべきものというより、松園という画家が長い歴史を持つ京都の絵画史に連なる存在であったことを示す証左の一つでもあるといえるだろう。 ところで、文展開設に数年先立つ頃から、京都の美術界では新しい動きが起こりつつあった。一九〇二(明治三五)年、ヨーロッパ留学から帰国した直後の洋画家浅井忠が創立間もない京都高等工芸学校に赴任したのを契機に、一九〇六(明治三九)年には浅井を慕って教えを受けた千種掃雲らを中心とする青年日本画家たちが丙午画会を結成することになる。一九〇九(明治四二)年には田中喜作を中心とする無名会、その翌年以降も黒猫会、仮面会など青年画家たちの研究会がいくつも結成され、一九一八(大正七)年の国画創作協会結成に象徴されるように、個性を尊重する西洋近代の芸術観の強い影響を受けて新しい日本画を追究する運動が、批評家・青年画家たちの間で盛んに行われていた。 こうした京都での日本画革新運動に代表される美術界の新しい動向に対して、上村松園はどのような立場を取ったのだろうか。松園はこのことについて直接何も語っていないが、その生涯に死を意識するほどの悩みを抱いたことが幾度もあったという松園の回想と関連づけて、この時期松園は自らの制作に思い悩んだとする解釈もある(註8)。 しかし、何よりもこの時期の作品が示す振幅に松園の心の動きを見て取ることができないだろうか。また、《花がたみ》《焔》に見られる強い感情表現が、内面表現への傾斜を強めていた革新的な日本画の動向と無縁であったとは思えない。 これまでの発表された松園の評伝では、《焔》発表後の三年間官展へ出品しなかったことから松園はスランプに陥っていたとする見方と、松園自身の回想文を根拠に《焔》を完成させたことによって松園は不調から脱したとする二つの見方がある(註9)。どちらの説を採るかによって、《焔》に対する見方だけではなく、明治末から大正前期に至る画業の位置づけも変化することになる。 確かに、《焔》に続く官展への出品は一九二二(大正一一)年の《楊貴妃》まで三年の空白期があり、その間は他の展覧会への出品もほとんど無いことから、制作を十分行えない状況にあったことは間違いない。しかし、松園は官展への出品を見送った年が一度ならずあるので、官展不出品をもってスランプと即断する根拠は今のところない。 しかし、この間に松園が新しい領域を求めて思考を重ねていたことは、《楊貴妃》を見れば明らかだ。《焔》を描いた後に、松園は仏壇の襖絵として仏教的主題になる《天人》を制作した他、《梅下佳人》《楚蓮香》などいわゆる唐美人図風の作品を描くなど作域を広げていた。 この《楊貴妃》も、そうした唐美人図の系統に属するが、ここには《焔》とは対照的に明るく華やかな女性像が登場し、《花がたみ》《焔》に顕著であった内面感情の表出は影を潜めている。帝展で《楊貴妃》が特に高い評価を得ることはなかったが、文展時代とは異なる新しい表現が確立されていることは明らかで、三年後の帝展出品画《待月》もあわせ見れば、この頃に松園が新しい画境を開きつつあったということができるだろう。 また、この図で興味深いのは楊貴妃を乳房を露わにした姿に描いている点である。松園は二〇代半ばに《夕》(挿図12)など裸婦を描いたことがあった。これら初期の裸婦像については、第三の師竹内栖鳳の実証主義的な姿勢の影響から生まれたものと見る説があるが、《楊貴妃》の薄衣を通して見える肉体の表現や線描、明るい色感は、初期の裸体表現のそれとは明らかに異なっている。確証はないが、《楊貴妃》誕生に際しては村上華岳ら若い世代の画家たちが発表していた裸婦像の存在が意識されていたのかもしれない(挿図13)。 |

挿図7 《蛍》1913年 
挿図8 《娘深雪》1914年 
挿図9 《月影》1908年 
挿図10 《吉野太夫》1910年頃 五.上村松園「花筐と岩倉村」『青眉抄』所収 
挿図11 曾我蕭白《美人図》18世紀 六.このことについては、伊藤紫織「曾我蕭白「美人(?)図」考」(『曾我蕭白展図録』一九九八年 朝日新聞社)が最も詳しい。 七.上村松園「謡曲と画題」「簡潔の美」『青眉抄』所収、上村松園「謡曲仕舞など」「無表情の表情」『青眉抄拾遺』所収などにも松園の能・謡曲に対する考え方が記されている。 八.関千代『上村松園 近代の美術 一二』一九七二年 至文堂 
挿図12 《夕》1900年 
挿図13 村上華岳《裸婦》1920年 九.《焔》の後にスランプに入ったと見る代表的な説は、内山武夫「評伝」『上村松園画集』一九八九年 京都新聞社。また、《焔》によってスランプから脱したとする説は、加藤類子『虹を見る 松園とその時代』一九九一年 京都新聞社。 |
三.円熟・完成期
|
《楊貴妃》発表後は、宮内省御用画、御大典御用画など皇室関係の制作が目立つようになり、帝展への出品は一九二六(大正一五)年に《待月》を出品した後は、一九三四(昭和九)年まで不出品が続くこととなる。おそらく、依頼画が多かったことに加え、嗣子松篁の結婚、最愛の母仲子の体調不良、孫・淳(淳之)の誕生など公私にわたって多くの出来事があったことも官展不出品の一原因かもしれない。しかし、五〇代を迎えた松園の画境は確実に新たな段階に入っていた。そのことは、松園五〇歳代後半から六〇歳代にかけて制作された《春秋》(昭和五年)、《虹を見る》(昭和七年)(挿図14)《序の舞》(昭和一一年)、《草紙洗小町》(昭和一二年)(挿図15)《砧》(昭和一三年)(挿図16)などを見れば明らかで、六〇年に及ぶ画業の中でこの時期を松園芸術の完成期、画業の円熟期と見ることに異議はないだろう。 この時期の松園画は、画中人物の大きな存在感、堂々とした人物表現を最大の特質としている。そして、そうした表現を支えているのは、独自の明るい色感と色面の効果的な使用、人物を浮き上がらせる余白を活かした画面構成、無駄のない線描、能・謡曲など伝統的な主題と近代的な人間観とが融合した松園独自の人物描写などである。 二曲一双の大作《春秋》と《虹を見る》は、それぞれ徳川家と岩崎家からの依頼画で、松園画中最も大画面の作品である。《春秋》は、向かって左隻に蝶々を見やる二人の若い娘、右隻に萩が咲く庭に縁台を出して涼を取る年増女性を配して、季節の春秋に加えて、人生の春秋の意も含んだ趣向が取られている。また、《虹を見る》では、向かって左隻に床几に腰掛けた若い娘、右隻に幼児を抱いた若い母親を配し、彼女たちの視線の先ー右隻の端に虹を淡彩で描き出している。 季節感の表出、余白による大気の表現、立像と座像を対比的に扱う画面構成、横長の大画面が数少ないモチーフだけで構成されている点など、両作品には共通点を数多く見出すことができる。しかも、これら二作品に登場する女性は、整理された無駄のない線描と透明感のある明るい色彩で描かれているが、それは松園の女性表現が完成の域に達したことを示しているといってもよいだろう。 ところで、《虹を見る》に描き込まれた母子像のモチーフは、松園にとって格別の意味を持つものであった。松園はその初期から母子像を多く描いていたが、一九三四(昭和九)年の帝展に出品された《母子》は、それまでの母子像の集大成ともいえる作品であった。母仲子の深い愛情を受け画家としての地位を確立した松園であったから、《母子》発表の八か月前に最愛の母を失っていたことは、《母子》成立と大きな関係があるだろう。 そうした時期に描かれただけに、この作品は母に対する松園の追慕の念と関連して語られることが多い。しかし、そうした松園の人生における意味だけではなく、作品自体が示す内容においても、《母子》は《春秋》《虹を見る》に登場した女性表現が縦長の画面形式で試みられて成功をおさめた作品ということができるだろう。 《母子》と関連して松園自身は、「明治初期頃の京の町の中京辺の御寮人というような風俗で母子の情趣を描いて見たいと思いました」(註10)、「私の制作のうち「母性」を扱ったものがかなりあるが、どれもこれも、母への追慕から描いたものばかりである」(註11)、「あの頃への思い出を描いたものであるが、いわば、わたくしひとりの胸の奥に残された懐かしい思い出」(註12)と記しているが、女手一つで自分を支えてくれた母仲子への追想と、江戸時代の面影がまだ残っていた青春時代の京都市中の庶民生活への郷愁は、松園にとって重要な画因として終生変わることがなかった。 昭和一〇年代に入ると、能・謡曲から題材を得た大作が連続して生み出された。《序の舞》(昭和一一年)、《草紙洗小町》(昭和一二年)、《砧》(昭和一三年)である。これら三作品が、能・謡曲に画題を求めている点、無地の背景に人物が大きく描かれている点などは、一九一八(大正七)年の《焔》から展開したことを示しているかもしれない。 しかし、抑制された感情表現によって人物の存在感を強調することに成功している点、背景を無地として衣装等に明るい色面を大きく配して色彩効果を最大限に利用している点等を見れば、大正末・昭和初期に完成した松園女性像の一つの頂点がこれら三作品にあるということができるだろう。ここにはカラリスト松園の面目躍如たるものがある。また、美しい色彩の陰に隠れがちだが、この時期の松園画に見られる無駄がなく伸びやかな線描が果たす役割も無視することができないだろう。 |
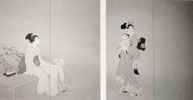
挿図14 《虹を見る》1932年 
挿図15 《草紙洗小町》1937年 
挿図16 《砧》1938年 一〇.「作者のことば 帝展名作選集(一)」『読売新聞』昭和九年一〇月一六日 一一.上村松園「母への追慕」『青眉抄』所収 一二.上村松園「四条通附近」『青眉抄』所収 |
四.晩年の画業
|
還暦を過ぎた昭和一〇年代は、美術界における松園の地位は既に揺るぎなく、制作面でも最も実り多い時期であった。その頃日本はアジア各地へ進出し、戦争に向かって突き進んでいた。社会状勢も次第に抑圧的・禁欲的な傾向を強くしていったが、そうした中で松園の制作にも変化が現れる。 それは、《夕暮》(昭和一六年)や《晴日》(昭和一六年)、《晩秋》(昭和一八年)など働く女性を主題とし、生活感を強く漂わせた作品が描かれるようになったことである。 これらの作では、裁縫、障子貼り、伸子張など女性の家事労働が主題とされているが、そこには政治や社会状勢がどのように変化しようとも変わることなく続けられる女性たちの日々の営みに対する画家のこまやかな視線を見てとることができるだろう。 《夕暮》には、日が傾いても針仕事を続ける女性が明かり障子を開けて針に糸を通す様子が描かれ、褐色系の色彩で統一された画面には針山の朱が彩りを添えている。松園自ら記しているように亡き母への追想が込められていることはいうまでもない。注目されるのは、大きく取った余白の巧みな配置、あるいは開かれた明かり障子の桟や縁・敷居の直線と女性の身体が示す柔らかな曲線との対比によって、画面に奥行きと一種リズム感が生まれていることである。こうした特徴は、二年後の《晩秋》、あるいは本画が焼失した《晴日》にも指摘することができる。 しかし、これらの作品が高く評価されるのは造形性もさることながら、誰もが共感を覚える、庶民のひたむきな生活感情が率直に画面から伝わってくるからであろう。昭和一〇年代前半の《序の舞》《草紙洗小町》のモニュメンタルという形容がふさわしい堂々たる人物表現とは異なる、やさしく清潔感ただよう近代的市民感覚にあふれた女性像を《夕暮》や《晩秋》で松園は確立したのである。 こうした作品が描かれるにあたっては、松園が戦時下という当時の社会状勢を配慮したという指摘もある。もちろん、松園のみならず戦時下で画家がどのようなスタンスを取ったかは慎重に検討しなければならない大きな課題だが、そうした議論とは別に純粋に造形的な面では松園がこれらの作品で新しい画境を開いたことは間違いない。 落ち着いた色調と整った線描、余白を活かした巧みな画面構成、あるいは同時代の社会と人間に対する画家の強い関心ー一種の近代的感覚などを根拠に、これらを松園画の一つの頂点とする見方もある。 松園作品の主題について、かつて京都の美術批評家神崎憲一は「徳川風俗」「謡曲もの」「明治初年の追憶作」の三種に分類した(註13)。四季の移ろいや時世粧を主題とする美人画・風俗画の類、神崎のいう「徳川風俗」ものを松園は依頼に応じて最も数多く制作した。美人画の近代化という点で、それらの作品が持つ意義は決して小さくない(註14)。 しかし、近代画家上村松園の真の姿は、むしろ堂々たる人物表現を確立した《序の舞》に代表される昭和一〇年代の「謡曲もの」と、人間に対する近代的な視覚を示す《夕暮》など晩年の「明治初年の追憶作」に現れていると見るのが適当だろう。 上村松園は、平安京以来の長い歴史を持つ古都京都と切っても切れない存在であった。しかし、太平洋戦争が激しさを増す中一九四五(昭和二〇)年二月には住み慣れた京都から奈良郊外の子息松篁の画室唳禽荘に疎開することとなる。松園は戦争後も京都に戻らずに奈良にとどまって、一九四八(昭和二八)年には女性として初の文化勲章を受章したが、一九四九(昭和二四)年八月に七四歳で画道三昧の生涯に幕を下ろした。 六十年に及ぶ上村松園の画業は、古都京都に生まれ育った一人の女性が画家として自立していった波乱に満ちた人生、あるいは近世以降の歴史を持ついわゆる美人画を女性が描いたことなどに力点を置いて語られることが多い。 しかし、いうまでもなく上村松園の作品が持つ真の意義は作者が女性であることにのみ由来するのではない。明治期の《人生の花》《長夜》《月影》、大正期の《娘深雪》《花がたみ》《焔》、昭和一〇年代前半の《序の舞》《草紙洗小町》《砧》、晩年の《夕暮》《晴日》《晩秋》など各時期の作品に、近代日本の画家誰もが直面した絵画の根源的な問題に対する松園独自の優れた解答が提示されていること、これこそが近代を生きた画家上村松園の真価であり、同時にその作品が多くの人々の共感を呼ぶ理由でもあるといえるだろう。 二.村田真知『上村松園書誌』一九九九年 美術年鑑社 |
一三.神崎憲一「随筆上村松園鈔」『美之國』一七巻七号 一九四一年七月 一四.近世から近代に至る美人画の展開、「美人画」の定義等については『特別展 美人画の誕生』図録(一九九七年 山種美術館)に詳しい。 |


