江戸後期の空間構成-江漢から北斎へ
山口泰弘
|
江戸時代の文化は,宝暦明和安永頃を境として大きく様相を転じる。文化の担い手が武士や富裕な商人から次第に庶民に移っていくのがちょうどこの時期である。この傾向は貴族や町衆の築いた伝統の余脈を継ぐ京都よりも開幕以来ようやく150年を経たばかりの新興の都市江戸で一層顕著に現れ,加速度的な勢いでやがて京都を凌ぐにまでに至る。江戸の庶民,いわゆる江戸者の嗜好を楽しませるために作られた浮世絵版画が江戸絵と称して京都でもてはやされたり,圧倒的に優位を誇っていた京都の出版物がこの期を境に江戸の書肆に駆逐されたり,この現象は挙げるにいとまがないほどである。 この庶民文化は,庶民の生活,信仰,亨楽などとのかかわりのなかで,生きた行動を伴う活動的で消費的な文化である。新吉原や歌舞伎などいわゆる悪所での遊び,四季の花見,寺社詣でに吸引される人口は膨大な数にのぼった。たとえば,江の島弁才天の開帳は,江戸時代しばしば行われているが,斉藤月岑の『武江年表』にはこれに参集する江戸庶民の有様が幾度となく特記されている。この江の島人気をあてこんで,旅行案内記の類がおびただしいほど出版されたし,江の島詣でに題材を採った浮世絵も少なくない。葛飾北斎の「富嶽三十六景」や歌川広重の「東海道五十三次」などもこのような熱烈な富士信仰熱や旅行熱から生まれた江戸庶民からの要請と無関係では生まれなかったものである。 この庶民文化は,宝暦明和安永のころ,江戸という一己の大都市に萌し,文化文政天保のころに盛時を迎え,やがて幕末明治に至って終息する近世社会における都市文化であった。 この稿では,上記のような時代の一区画に沿って消長した画面形式のひとつについて特に司馬江漢の「相州鎌倉七里浜図」(図11)と葛飾北斎の「富嶽三十六景・神奈川沖浪裏」(図18-Ⅰ),それに先後する作品を取り上げ,私見を述べることにしたい。 日本には平安時代以来,風景を描くための素材としてのひとつに和歌に詠まれた地すなわち名所(などころ)を描く習慣があった。しかし,司馬江漢が「相州鎌倉七里浜図」に描く江の島は,特に名所に取り上げられることもなく,中世以前では「一遍上人絵伝」のように説話を語る背景のひとつとして描かれていたにすぎない。江の島が画題として盛んに描かれ出すのは,江戸に開府されて以来,それも江戸近郊の霊場・行楽地として江戸庶民のあいだで脚光を浴びるようになった江戸時代後半をそれほど遡ることではない。 |
|
|
司馬江漢は「相州鎌倉七里浜図」を,江戸時代もなかばを過ぎた寛政8年(1796)に描き,絵馬として芝の愛宕神社に奉納している。この時期江漢は,油彩で日本風景を集中的に描き,絵馬として全国の寺社に奉納した。この作品はそのなかのひとつで,当時たいへんな評判を得たものである。同種の作画の依頼が殺到したのだろう,ヴァリエーションと思われる七里浜図が少なからず現存している。(挿図1)は窪俊満の描いた狂歌摺物の挿図である。図中,外題を平仮名で横書きして筆記体のアルファベットに見立てる趣向が加えられているが,これは葛飾北斎の「おしおくりはとうつうせんのづ」などにみられる趣向と同趣のものである。「さうしうえのしま七里かはまのづ」と読めるが,この画中画は江漢の「相州鎌倉七里浜図」あるいはそのヴァリエーションの図柄をそっくり移している。江漢の一連の江の島図が評判をさらっていたことを裏書きするといえよう。では,この評判は何に由来するのだろう。 寛政12年に出された画会引札によると,「是よりさき江漢先生西洋をゐして。江戸ハ愛宕。京ハ祀園の社内ノ大坂ハ生玉薬師堂ニ掛く是ハ,人々面り観るところ也。然ども,氏風ハ外の者と違ひ工ニ工をかく。且又彩る処の物。彩丹,青緑ハ皆重き西土の産にして工からきぶ多く。」とあり,また,この作品が屏風に改装されて後,文化8年(1811)に大田南畝は,「昔掲城南愛宕廟 今帰郭北青山堂 泰西画法描江島 縮得姻波七里長」と題賛を加えている。“西洋“西土の産”“泰西画法”という言葉に留意すると,この作品は,西洋画法で描かれたところに新奇さがあり,そこに衆目が集まったのだと考えることができる。 西洋画法を取り入れた作品は江漢を遡るはるか以前にはじまっている。16世紀中頃,キリスト教伝来とともにはじまった南蛮美術は,日本で西洋画法を取り入れた最初であったが,度重なる禁教と鎖国によってもなく潰えてしまった。ふたたび西洋の影響が現れはじめるのは,享保年間,将軍吉宗の命によってキリスト教に関係しない洋書に限って輸入が緩和されて以降になる。西洋画法にすぐさま反応したのは浮世絵師で,東洋画にはない遠近法の生み出す魔術的な立体効果は,浮絵と呼ばれ,その新趣向がもてはやされた。しかし,浮絵は視覚的な奇工を楽しむ,一種の玩具絵として民間に受容されたにとどまり,既存の絵画観からは,蔑視の対象とならざるをえなかった。これが本画の伝統のなかに注入されるには,さらに時日を必要とする。 この動きは,明和安永期になってようやく地表に現れてくる。円山応挙の作品は桃山時代の障壁画や狩野派の伝統あるいは明清画など様々な水脈がひとつとなって形成された大きな流れといえるが,応挙は若いころ京都の玩具屋で眼鏡絵を作っていたといわれ,これが後年,応挙の画風形成にとってなくてはならない重要な水脈のひとつになった。 同じ頃江戸では,平賀源内を中心とする文化サークルが形成され,最も先鋭的な文人学者が輩出した。源内が本草学・博物学・戯作に多彩な活動を展開したことに誘われて,ここに集まった人々も多士済々であった。杉田玄白のような蘭方医,大田南畝・平秩東作・手柄岡持のような戯作者・狂歌師,戯作蘭学いずれにも才幹を揮った森島中良,画家では宋紫石などを挙げることができるだろう。司馬江漢もはやくから参加していたひとりである。江戸で最初に西洋画法を本格的に本画に取り入れたのは小田野直武や佐竹曙山ら秋田蘭画と呼ばれる一派で,曙山は秋田藩主,直武はその家臣である。直武は郷里秋田角館で源内に知遇を得,その直後江戸に出て源内宅に寄寓していた。秋田蘭画の様式形成の思想的背景には,源内あるいは源内のもとに集まる文人たちの思想が反映されているとみることができる。 たとえば,今回出品される直武の「日本風景図」(図10)をみてみよう。 この作品は,金沢八景,江の島という実景にもとづいて描かれてはいるが,景観構成に山水画的な原理が強く残してあるために,一見それとわからない。まるで,実景をそれとわからないように山水画に偽装させているかのような観を呈しているのである。単なる山水画であることに疑問を抱かせる景物は左幅なら二重橋,右幅なら旅姿の町人しかない。しかし,これらの景物は逆に,実景描写であることを探る手掛りともなる。この作品はこうした思考の操作を楽しむことを趣向に描かれているのである。また,個々の景物には,リアリティーが求められている。しかし,全体として必ずしもリアリティーを問うものではない。つまり,個々のリアリティーは,思考の操作を誘う趣向の材料としての必要から求められた,近代的感覚からはいささか瑣末なリアリティーとしかいえないのである。これは,当時の戯作類に極めて特徴的に現れている特質で,近代の文学観からは否定の材料にしかならないものである。直武の「鷹図」では,極めて謹直に描かれた鷹のとまる木に鷹の糞がそれとなく画かれ,戯作者がするある種のうがちに似た,卑俗な笑いを誘う。鷹が謹直であればあるほど,糞にリアリティーがあればあるほど対比効果のつくりだす笑いは大きい。こうした,趣向を絵画思考の発想源とする姿勢は,源内サロンにおける当時の最も先鋭的な人々との接触から生まれ,そのなかでの共通理解に支えられていたものだったと考えることができるのである。 秋田蘭画の場合,西洋からの直接の影響もさるものの,中国を介して受入された西洋の影響も勘案しなければならない。「日本風景図」にみられる近景を極端に拡大し水面をはさんで遠景を低く配する構図は,秋田蘭画の基本的な構図のひとつであるが,これは中国で清朝の前半にヨーロッパ人宣教師の指導を受けて起こり宮廷で調度して使われ,乾隆帝の時代にはヨーロッパ向けの輸出品としても作られたきわめて精巧なガラス絵の構図法に共通点を求めることのできるものである。 |
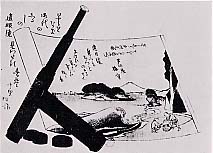
(挿図1 )窪俊満 |
|
直武は,江戸風景や東海道の道中風景を描いた眼鏡絵を残しているが,「富嶽図」(挿図2)は,眼鏡絵制作を通して学んだ視覚を本画に取り入れた例で,「日本風景図」の構図とは異なる。東海道黄瀬川から富士山を望む風景が描かれているが,江漢の「相州鎌倉七里浜図」を先取りする構図がみられることに注意してよかろう。橋のたもとから右岸が画面奥へとおおきくカーブし,その最奥に富士山を配する構図は,海岸線を画面右からカーブしながら延ばし,奥に江の島さらに富士山を配する「相州鎌倉七里浜図」に受け継がれ,江漢によって影響力が広汎になる。「富嶽図」は安永6年(1777)頃に描かれたと考えられるが,この種の構図としては初発的なものである。 「富嶽図」が墨彩色で描かれているのに対して「相州鎌倉七里浜図」は油彩で描かれている点で両者のマティエール上の懸隔は大きい。しかし,風景を見たまま自然に画布上に再現できる,西洋画の構図法の魔力は直武ともども江漢も捉えて離さなかったようだ。次の葛飾北斎になるとこの魔力はそれだけでは力を発揮しえなくなる。 |

(挿図2)小田野直武 |
|
「相州鎌倉七里浜図」には富士山が江の島の左側に描かれているが,実際にはこのようにみえる場所はない。江漢は「相州鎌倉七里浜図」において,視点から富士山に及ぶ空間を実際以上に大きいものに表現したいために絵画的操作を行ったのだと解釈されている。寛政9年(1797)に蔦屋重三郎から狂歌画本『柳の糸』が上梓されている。北斎は,堤等琳,鳥文斎栄之らとともに挿絵を一図描いている(挿図3)。ここには七里が浜から江の島さらに富士山を望む風景が旅風俗の背景として描かれ,富士山は「相州鎌倉七里浜図」と同じく江の島の左側に配されている。寛政9年というと「相州鎌倉七里浜図」が発表された翌年にあたり,この作品の評判がまだなまなましかった時分である。偶然の符合というよりは,当時江漢に対して強烈なライバル意識を燃やしていたといわれる北斎,あるいは時好を取り入れるのに敏感だった書肆の意志がここに働いた結果のパロディ,ということができよう。 しかし,江漢の表現しようとした見たままの自然な遠近感はこの画面でははやくも解体の兆しをみせている。かわってここでは,近景の大波と富士山・江の島の遠景とがつくりだす対比関係が一見のどかな風景に一抹の緊張感をひそませている。同時に大波は,人物を飲み込む一歩手前まで成長している。この波は「おしくくりはとうつうせんのづ」や「賀奈川沖本杢之図」を通して成長を続け,「富嶽三十六景・神奈川沖浪裏」で富士山とのあいだにはるかに劇的な緊張をつくりだすに至るのである。 「おしおくりはとうつうせんのづ」は窪俊満の「江の島図と遠眼鏡」の画中画と同じように外題を横書きでくずしてアルファベット風のサインに見立てる趣向になっている。これは当時新奇の眼で迎えられた銅版画を十分意識してのことと思われる。しかし,波はぼってりと重く,波頭の線は硬く形式的であり,北斎がまだ成長期にあったことをものがたる。 明和4年(1767)に河村岷雪の『百富士』が刊行されている。編中たとえば,「橋下の富士」と題される図は,画面いっぱいに橋桁を拡大し橋脚のあいだから遠くの富士を覗く,という構図で描かれている。この編には,俳諧の付合にも似た機知的な感覚で富士と景物を取り合わせた図がいくつも載っているが,北斎の場合,こうした先蹤作品をも十分顧慮し,西洋画法にまで網を拡げて捉えた成果が,「富嶽三十六景」となって結実したのである。 北斎が西洋画法に求めて得たものは,江漢の場合ほど直接的なものからは抜け去って,もっと日本的な装飾感覚と複雑に撚り合わせることによって自然を単純化し,幻想と劇的緊張あるいは造型の理知的な論理といったものに組み換え,転化変容する術を編み出したことにあるだろう。直武が伝統様式の中に折衷的に取り入れ江漢が自身の主様式とした西洋画法は,北斎に至って日本的な美意識のなかに消化されたのである。 |

(挿図3)葛飾北斎 |
| 「富嶽三十六景」の奇抜な構図はまた,追従作品を生み出している。歌川国芳の「高祖御一代略図」は,日蓮上人の事跡を十枚に描いたもので,天保2年(1831)の日蓮五百五十年忌をあてこんで刊行されたとされている。そのなかの「文永入年鎌倉山ケ崎雨祈」では,荒海に斜めに突き出る大岩の上で日蓮が祈る情景が描かれているが,「富嶽三十六景・甲州石班沢」をそっくり左右ひっくりかえすとこの構図ができあがる。「佐州流刑角田波題目」(挿図4)は佐渡に流される途上,荒波にのまれそうになるところを題目の霊験によって危うく助かるという日蓮の事跡譚の一コマを描いたものである。日蓮の乗る小舟をいましものみこもうとする大波,波間にはるかに覗く遠山は,明らかに「富嶽三十六景・神奈川沖浪裏」を敷き写したものにほかならない。しかし,大波のスリル感溢れる瞬時性や富士山とのあいだにつくりだす劇的な緊張の糸は,ここに至ってはやくもぷっつりと切れてしまっているようにも見れる。 (三重県立美術館学芸員) |
 (挿図4)歌川国芳 「高祖御一代図 左洲流刑角田波題目」 |
