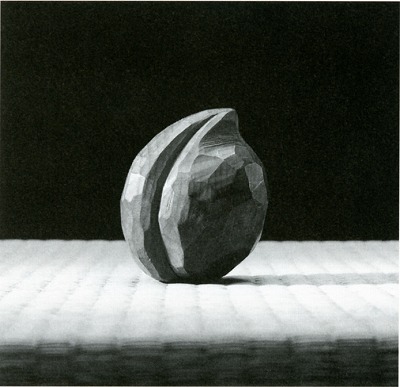多様性の時代
毛利伊知郎
|
時代が大正から昭和に変わる頃から、日本の彫刻界は新たな様相を示し始めた。本章はあわせて6名の作家によって構成されるが、彼らの共通点のひとつは、作家によって軽重の差はあっても木彫と塑造の双方を手がけたことである。 技法・素材、形式などを異にする塑造と木彫では、作家の意識も自ずと異なってくる。日本では、歴史的に木を素材とした彫刻が圧倒的に多かったことから、近代以降の木彫はこうした伝統との関連で語られることが多い。実際、佐藤朝山、新海竹蔵、平櫛田中らのように、仏師、人形師、宮彫師に師事してから木彫に転じた作家も少なくない。 一方、明治時代に導入された西洋式塑造制作は、欧米を模範とした日本の近代化と深く結びついていた。塑造を手がけた作家たちの脳裏には、常にヨーロッパがあった。そういう意味では、前章で紹介したオーギエスト・ロダンへの憧憬と作家の個性重視という動きも、ヨーロッパヘ目を向けることなしに生まれることはなかった。 しかし、大正後期から昭和前期にかけて活動した作家たちの作品や言説などを検討してみると、「木彫=伝統的世界」、「塑造=西洋的世界」という単純な構図は成り立たないことがわかる。作家たちは、江戸時代以前の造形と西洋の造形双方を視野に入れ、生い立ちや資質、あるいは個性に従いながら自己の造形世界を形成していった。その結果、作家ひとりひとり、あるいは作品ひとつひとつのなかに日本東洋的世界と西洋的世界とが共存し、多様な造形が生み出されることになった。それが、本章を「多様性の時代」と名づけた理由のひとつである。 |
東洋と西洋のはざまで
新しい造形感覚
木彫芸術の新たな展開
|
経済的に恵まれることなく早逝する作家が多かったなかで、石井鶴三、平櫛田中、新海竹蔵らは第二次大戦後も活動を展開した。 平櫛田中は、大正初期に日本芙術院の研究所で裸婦像制作の修練を積んだ体験をもち、大正末年・昭和初期頃までの作品ではその経験を基に着衣の下にある身体の抑揚や動勢の表現を強く指向していた。 しかし、1931~32〈昭和6~7)年頃から変化が現れる。そして、1934(昭和9〉年の《浅野長勲公寿像》、1937〈昭和12)年の《慶典読書奉仕》などの肖像作品を見ると、肉体表現への意識はかなり稀薄化している。 伝統的な寄木造と彩色技法研究に基づいて制作されたといわれるこれらの肖像彫刻は、濃密な彩色の効果もあいまってきわめて写実的な表現を示しでいる。リアリティを追究するために、鎌倉時代から室町時代にかけての頂相彫刻に先行例が見出される実際の顎髭を植える技法が採用されることもあった。 平櫛は20代半ばの頃、京都や奈良に滞在して古仏を研究したのを皮切りに、その後も古仏に関心を寄せ続け、仏教的主題の作品を数多く制作した。しかし、1935(昭和10)年前後以降の寄木造彩色仕上げになる作品を見る限り、平櫛の古彫刻に対する関心は『白樺』同人や和辻哲郎に代表される明治後期以降の知識人たちが古仏に対しで示した関心とは異質のものと思わざるをえない。 こうした古仏に対する関心の両者の相違は、同時に日本近代における彫刻芸術に対する認識の差でもあった。平櫛の長期にわたる制作活動は、ある時期には西洋近代芸術を指向し、また別の時期には前近代的な造形世界を指向していた。こうした振幅は、平櫛だけでなく日本彫刻の「近代」全般に通じる特質のひとつであったといえるだろう。 寄木造彩色仕上げの技法によって制作されたリアルな肖像彫刻の解釈と歴史上の位置づけについては、現時点では種々議論のあるところだろう。しかし、日本近代彫刻の全体像を構築するためには、こうした問題の検討が重要ではないかと筆者は考えている。 山形の仏師の家に生まれ、新海竹太郎を伯父にもつ新海竹或は、世代的には橋本平八と同年齢である。彼は大正期に再興日本美術院に属しで木彫を中心に出発したが、戦後は木彫のほかに塑造や乾漆造の作品も制作して、伝統的な主題と表現を基盤に、イタリア現代彫刻との関連をも窺わせるような独自の彫刻世界を捷示した。こうした新海の展開は、早逝した橋本平八の造形世界を見る際にも示唆するところがあるように思われる。 以上のように検討してみると、昭和前期の在野系作家たちの作品には、大正期のそれとは異なる傾向をはっきりと見てとることができる。それは、明治末から大正期にかけて熱烈に紹介されたロダンの彫刻思想を冷静に研究し、それを日本に根づかせようとする動きと呼応していたし、同時代西洋の芸術思想に対するより広範で深い知識、前近代以来の造形への共感が背景にあった。 木彫の技術によって新しい表現を見出した高村光太郎、素材自体の霊性に着目した橋本平八、卓抜な木彫技術を駆使してさまざまな試みを行った佐藤朝山、一種の土着性あるいは社会性を感じさせる主題を採用した石井鶴三、古彫刻の彩色技法に目を向けて迫真的な写実表現を目指した平櫛田中など、作家たちはそれぞれの立場で日本固有の近代的な彫刻表現を目指しでいたのである。 (もうり・いちろう/三重県立美術館) 参考文献 『20世紀日本美術再見Ⅲ 1930年代』(図録) 三重県立美術館、 1999年 『〈彫刻〉と〈工芸〉:近代日本の技と美』(図録) 静岡県立美術館、2004年 |