伊孚九と池大雅周辺
山口泰弘
伊孚九(いふきゆう)の名は、沈南蘋(しんなんびん)とともに江戸後期の画壇に多大な影響を及ぼした来舶清人画人としてひろく知られている。この小論では、池大雅の周囲にいて伊孚九画に強い関心を抱いていた韓天寿(1727-95)・青木夙夜(しゅく)(?-1802)・悟心元明(ごしんげんみょう)(1711‐1780)らに焦点を当てて、伊孚九画の受容について考えてみたいと思う。
伊孚九は中国江蘇省呉県付近山塘の人で、馬を主に商う貿易商として1720年(享保5)に初めて長崎に来港し、以後数度にわたって来日した。余技として南宗画風の山水画をよくした。
専門画家でもなく士夫でもなく一商賈にすぎない伊孚九であったが、桑山玉洲が『絵事鄙言』(寛政11年刊)で宋の黄休に倣って「逸品を以て神妙能の三品の上に置」(『益州名画録』)いたうえで、「(唐宋元の名家とは)同年の談には非ざれども、今眼下に指ときは、近世長崎に來遊せし伊孚九など、舶來清人中の逸格なるべし。本朝にては大雅堂一人なり。長崎に來れる清人の中にて賞すべき者は伊孚九が山水」とその山水画を高く評価したほか、『近世名家書畫談三編』でも「伊孚九ハ工拙ヲ以テ不可言」としながらも「尤モ風致ヲ存シテ逸ニ類シ、筆墨ノ閑雅ナル、獨自ラ樂ム者ニシテ、頗ル高踏ノ風アリ。」と、彼の閑雅な画風を南宗画に相応しいものとして賞している。
また、「是ニ於テ沈南蘋、伊孚九ナドノ此ノ土二來リシハ南北宗ニ功アルコト多シ、豈天道近世ノ畫法ヲ開キタルカ」(森島長志『槃ハクザ話』「漢畫監裁」)と指摘されるように、伊孚九は北宗画の鼻祖としての沈南蘋とともに最上位に置かれる存在であった。
伊孚九の画蹟は、鶴田武良氏の調査では、図版などによってのみ知られるものも含むと、71点に及んでいる(鶴田武良「伊孚九と李用雲」『美術研究』315号 昭和55年)。
|
なかでも現在、伊孚九の代表作としてよく知られるのが、「離合山水図」(重要文化財・挿図a)である。この作品は、三重県松阪市の長谷川家の所蔵で、『四碧斎画話』に野呂介右は、松坂のある人が15金で入手したが、後に窮乏して12金で売ろうとしたところ、豪商長谷川家がそれを惜しんで30金で買い求めた、という佳話を載せている。 長谷川家には別に青木夙夜の手になる模本(挿図b)があり、何かの時には門外不出の原本の代わりにこれを出品するのが常であったという。この模本は、三村竹清が「伊勢だより」に書くところでは、「朱にて印まで善く写し」たものであるが、「画は常の夙夜にも似て、いと拙かりき」ものであるという。図版で比較するかぎり、きわめて忠実な写しであることがわかる。 夙夜については、その生年をはじめ事歴であきらかになることはきわめてすくないが、師大雅が真葛ヶ原の草堂で亡くなったあと、天明7年(1787年)の春ころ、他の弟子たちとともに謀って双林寺の境内に大雅堂を建て、初代の堂守りとしてここに住み、師の遺品を管理したり、大雅の画を鑑定したりしながら、十余年を過ごしたという。その有様は田能村竹田(たのむらちくでん)によると「杜門不出、傭書自糊、草樹不除、階庭不掃、殆十餘年、翳然輿世間隔、人罕見其面也」(『山中人饒舌』)と、大雅堂に籠もって世俗と隔絶する生活であった。 |
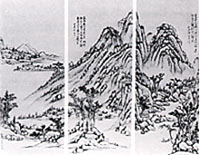
挿図a 伊孚九「離合山水図」 
挿図b 青木夙夜摸「伊孚九・離合山水図」 |
夙夜は韓天寿の死後、これを悼んで青木氏の菩提所通妙寺に塚を建てるが、その碑銘「酔晋斎古紙■(もう)銘序」の細合半斎の撰文に「距今三十九年丁丑予遊東都初見大年及従弟夙夜相得驩甚」とあることから、天寿と夙夜とが従兄弟であったことが明らかになる。大雅と夙夜の師弟関係がどのような経緯からいつごろ生まれたかはわからないが、大雅と親しい従兄を介して始まった可能性は高い。
今展出品作に夙夜が董其昌(とうきしょう)の筆意に倣って描いた「蘭亭曲水図」(図44)があるが、これには韓天寿が蘭亭手記の序を書き、大雅が七言絶句を題しており、かれら三人の文雅の親しい交遊をあとづけることができる。天寿の款記には宝暦11年(1761)の年紀があり、大雅が39歳、天寿が35歳の年の作であることがわかる。夙夜の生年はわからないが、天寿の従弟ということであれば、このとき30歳前後か、それを下回る青年時の作ということになり、夙夜の若描きとして貴重な作品である。
夙夜には、特異な、しかし看過できない一面があった。それは大雅の模作者としての一面であるが、大雅の有名な「富士十二景図」(八月・十二月にあたる二幅、図23・24)とそれに対応する夙夜の模本(図45・46)はその例証といえるものである。出品されている夙夜の模本はともに絹本だが、そのほかにも紙本のものなど含めて複数の模本があったとみられる。おおぶりでのびやかな大雅に較べると、どれも繊細で巧緻であるが少し小さくまとまった観のある画面作りで、そこに追従者が陥りがちな矮小化をみないわけにはいかない。
夙夜からみれば従兄にあたる韓天寿は、大雅とは、高芙蓉(こうふよう)と三人で連れ立って白山・立山を経て富士山を巡り、これを記念して三人おのおのが「三岳道者」を号したという気の置けない友人どうしであった。京都に生まれ、通称を青木精三郎(のちに中川長四郎)といった。京都在住芸術家名鑑ともいうべき『平安人物志』明和五年版には書家の部に大雅・芙蓉とともにその名が載る。のちに親戚関係にあった松坂の中川家を継ぐことになるが、同家は江戸にも店をもつ豪商であったから、天寿は、大雅にとってよき友であると同時によき後援者でもあったわけである。
天寿のいる松坂中町の中川邸とは木戸を挟んだ地続きに継松寺という寺があった。大雅の伊勢訪遊は、天寿というよき理解者に誘われて、しばしにおよんだとみられるが、あまりの長逗留にいたたまれなくなった大雅が時折、ここに逃げ込んではほとぼりを冷ましたという。同寺には大雅が寝起きした部屋がいまでもあり、現存作品は今展に展示しているが、かつては膨大な量にのぼったらしい。
当時の住持を無倪(むげい)といったが、彼は詩文に深い関心を示したばかりか、天寿とは「断金の交わり」(『松阪文芸史』)があり、天寿の収集した晋唐の墨帖出版を実現するために巨費を投じたという。また、大雅の代表作として名高い高野山の遍照光院の襖絵は、彼の推挙によって大雅が描くことになったという。
この寺は、松坂の市街でも中心に位置し、まわりには豪商たちの邸宅が軒を並べていたほか、参宮街道にもほど近いこともあって、旅人の画人文人たちがここに旅装を解くこともしばしばであった。こうした環境と無倪の熱意が、自然にこの寺を刺戟的で先鋭的な文芸サロンに成長させた。
今回出品されている鶴亭(かくてい)の「芭蕉図}(図39)は、現在まくりになっているが、もとは継松寺の書院の床を飾っていたものである。「墨菊図」(図42)も同寺にあって鶴亭が描いたものである。
鶴亭は、黄檗憎で長崎聖福寺第四世岳宗の法嗣であったが、長崎で南蘋派の熊斐に学んだ画家でもあり、一時大坂に住み、後に万福寺の塔頭紫雲院に住んで南蘋派を上方に広めた画人として位置づけれられている。
鶴亭と大稚との風雅の交友は、すでに人見少華によって論じられており(『南画鑑賞』1-1)、悟心元明とは、悟心の詩集『一雨余稿』に鶴亭に贈った送別の詩があることや、鶴亭の「石菖図」に悟心が加賛していることなどから、交渉の跡がたどれる。また、韓天寿との交遊をものがたるものとしては「天産奇葩図」(図43)が松阪市内の旧家に所蔵されている。これは鶴亭の画に韓天寿が著賛したもので、ふたりの交遊が当地で行われたことを示すものである。鶴亭も継松寺サロンを賑わせたひとりとして欠かすことのできない存在であったのである。
さて、書家としての天寿はそれに相応しい評価が下されていたが、画人としての天寿となると、『近世逸人画史』が、「韓天壽〔喜多村民書入に、明和五人物志に、韓天壽字大年號醉普、了頓辻子、中川長四郎〕木孔恭と同じく畫をたしなむ、さして稱すべきものにもあらず、小景の山水を作る、偶四君子などあり、伊孚九を模擬す、最風致あり。」というように、かならずしも高い評価を与えられているわけではない。しかし、着目を要するのは、「伊孚九を模擬」した山水に限ってはそれなりの風致が認められている点である。
現在天寿の作として知られている山水画の多くは、『近世逸人画史』の評にあったようにたしなんだ程度のもので、たしかに専門画家の熟練には程遠いものがあるが、「小景の山水を作る」と同書がいうように、比較的閑疏な山水の小景が多く、またその多くに伊孚九に倣ったことを明記しており、明記されていない場合も伊孚九の様式下にあることが明らかなものが多い。松下英麿氏のみるところでは、大雅には意外に伊孚九の直接的な影響は少なく、むしろその周辺画人、たとえば野呂介石などに比較的影響の跡が大きいというが、傾倒の深さという点ではむしろ、天寿がその最右翼に置かれるべきかもしれない。
伊孚九の名を広めるにあたって『韓大年縮■(も)・伊孚九・池大雅山水画譜』の上梓が預かった役割は小さくない。享和3年(1801)の出版であるが、この書は『伊孚九画譜 乾』『池大雅画譜 坤』の二冊からなり、乾冊の巻首に中野素堂撰大窪詩仏書の序があり、上梓に至った経緯が明らかとなる。
天寿が素堂に語ったところによると、かねて自分は伊孚九、大雅の画に傾倒し、それらを縮摸して画譜を作り、学画の指針にしたいと考えていたが、たまたまその稿本を見た木村兼葭堂(けんかどう)が喜んで持ち去ってしまった、という。そのうちに天寿も亡くなってしまい、かといって兼葭堂も大阪にいるのでおいそれとみることもできず、素堂もじれったい思いでいたところ、享和2年の春に、江戸滞留中の素堂を中沢景山が訪ねてきて、思いがけず、天寿の稿本を示していうには、これを兼葭堂から譲り受けたので、今度刊行したい、ついては序文を書いてくれ、と頼まれた。このように素堂は語っている。続く景山の序によると、天寿は明和4年(1767)9月、大坂の「客舎」で伊孚九の山水43図を縮摸した、という。その翌年にはやはり大坂の「寓舎」で大雅を縮摸している。
この画譜は結局、伊孚九と大雅を併載するかたちで上梓されることになったが、これには、当時大雅を取り巻いていたひとびとに共通の思いが込められているように思われる。大雅の弟子であり論画家として知られる桑山玉洲は、『繪事鄙言』のなかで画の格を論じて次のようにいう。「南齋の謝赫古畫品録を著し始て是を論定す、唐の朱景玄また名畫録を著して其品第を分つに、神品妙品能品逸品の四つを以てす。續て宋の黄休または益州名畫録を選むに、逸品を以て神妙能の三品の上に置たり。此逸格と云ふは、尋常の畫法を脱略したる清奇幽妙の格なり、唐にては王洽、張志和、宋の米元章父子、元の黄子久、倪雲林、高彦敬などの類ひなり。同年の談には非ざれども、今眼下に指ときは、近世長崎に來遊せし伊孚九など、舶來清人中の逸格なるべし。本朝にては大雅堂一人なり。」。玉洲には、おそらく、「舶來清人」中最も尊敬を集めていた伊孚九と大雅とを「逸格」という最高位に併置して、師大雅をある種神格化しようとする意図のようなものが働いていたと思われる。伊孚九と大雅を併載した、この画譜の意図も大雅周辺のこうした基本思想が底に流れていたのではないだろうか。
天寿の狙いは没後ようやくかなえられたわけだが、同書が江戸時代後期の画譜および南画流行の時勢に適って絵画教科書としてひろく受け入れられたことは十分に考えられる。そしてそれが伊孚九の画名をいっそう高めることとなったことも想像に難くない。
|
天寿の伊孚九への関心を示すものは、この画譜だけではく、実作品をみても枚挙に暇がないほどである。「倣伊孚九山水図」(図26)は、その一例として今回出品しているものである。画面左上に賛文が置かれ、そこには伊孚九の落款があるが、印章は捺されていない。代わりに右下に天寿の落款印章が置かれている。伊孚九自賛の画の完全な模写とみてまちがいない。出品作品ではないが、伊孚九の原本を賛文落款まで含めて完全に模写したもので、原本と摸本とを比較できる作品もある(原本=挿図c、摸本=挿図d)。落款の位置や細部、画面の縦横比が双方で微妙に異なることを考えると、天寿自身が素堂に語ったように一旦縮摸してそれをふたたび原寸大に還元するという操作を経た結果かもしれない。 ところで、大雅の周囲にいた他の人同様、悟心元明も伊孚九に心酔するひとりとして忘れるわけにはいかない。 悟心は、正徳3(1713)年伊勢松坂中町に生まれた。無倪の継松寺、天寿の中川家とは同じ町内生れということになる。後の交渉の遠因として、この地縁も無視できない。11歳で出家、やがて江戸に出て服部南郭に学び、延享元年(1744)に京都金戒光明寺門前に一雨庵を構えている。このころ売茶翁などとも親しく交遊しているが、宝暦5年(1755)に伊勢多気郡相可村法泉寺の第6代住持に請われ、伊勢に赴くが、宝暦9年(1759)には法泉寺を辞し、ふたたび一雨庵に帰っている。その後宝暦13年(1763)に近江の正瑞寺住持となったが、安永2年(1773)には同寺を退き、帰郷して松坂に近い中万の浄光庵に隠棲した。売茶翁(ばいさおう)のほか、大典・六如・木村兼葭堂・宮崎■(きん)圃・鶴亭・高芙蓉など当代の文人と親交があった。 田能村竹田は、木村兼葭堂を訪ねたときたまたま大雅の瀟湘八景画帖をみる機会を得ている。「己丑六月十一日、兼葭主人寄示大雅翁畫帖三、其一爲瀟湘八景、毎景用古人法、悟心師爲書其詩、卷首高芙蓉作意在瀟湘四簒字、蓋池翁盛年用意之作、悟心芙蓉二人書亦佳、紙墨新鮮、満幅猶濕、亦一快観也。」(『屠赤瑣瑣録』)とあるように、それは、巻主に高芙蓉の篆字があり、大雅の描く八景のひとつひとつに悟心が賛詩を加えたものであり、いずれもすばらしいできばえであったという。 また、森島長志が『槃はくざ話』で、大雅の妻玉瀾について語った項で、「因こ説ク、玉瀾ハ大雅ノ室ニシテ亦山水ヲ以テ顯レタリ、悟心師モ趙松雪ノ衛夫人アルガ如シト賞セラレシモサアルベキ事ナリ』と悟心の言に触れていることや、悟心が宝暦9年(1759)に玉瀾の「梅嵓帰隠図」に題していることなどからみて、大雅とは夫妻ともども親しく付き合う間柄であったようである。また、大雅が若いころよく使った「雨笠烟蓑」(白文円印)は悟心が贈ったもので、大雅が親しく兄事していたことをうかがわせる。また、悟心の詩集『一雨余稿』には「送池貨成之東都」「贈池貸成遊勢州伝古曲」と題された大雅への送別があり、文雅の交遊が偲ばれる。 |

挿図c 伊孚九「山水図」 
挿図d 韓天寿摸「伊孚九・山水図」 |
ふたりの親しい交遊を作品のうえで示しているのが、今展出品の「山水図」(図25)である。人里はなれた山間の亭で、あたりの山水の風光を楽しむひとりの脱俗の高士が描かれている。樹木をつくるやや濃い目の墨と思い切った白抜きのコントラストが明るい日差しに照り輝く光景を描き出している。この図上方にあるのがほかならぬ悟心が認めた賛で、奇しくもふたりの交友を偲ばせる。この作品は、円山応挙の後援者・コレクターとして『近世絵画史』(藤岡作太郎)のあげる松坂の小津家の旧蔵であった。
本来黄檗僧であり専門画家ではなかった悟心元明は、詩書あるいは篆刻には長じていたが、絵画作品ということになるとその数は決して多くない。「倣伊孚九山水図」(図34)は、少ない遺例中のひとつであるが、伊孚九に倣ったことを明記しているのみならず、作風の点でもあきらかに伊孚九傾倒を示すものとして貴重である。
もう一度「山水図」(挿図c、d)へもどってみたいが、この作品は天寿の伊孚九傾倒を知る重要な作例であったことはすでに記した。同時に悟心の伊孚九傾倒の深さを明かにする証左としても忘れることができない作品である。天寿がこの伊孚九画を摸写したのは宝暦9年12月23日、33歳の年の暮れであったが、賛文には次のような記述がある。「法泉厳師所蔵伊■(しん)野十二幀其六幅閣葉亭持此六幅山水悟心和尚所■(も)傍両写乙卯十二月廿三日醉晋」。法泉厳師は、黄檗僧で、伊勢国多気郡相可村天照山法泉寺の第二世衝天元統(1666-1730)、やがて法泉第六世を継ぐ悟心にとっては法嗣を授けられた師であった。伊■(しん)野は伊孚九。この幅は、賛文に従うと、もともと衝天元統所蔵であった伊孚九画12幅のうち6幅を閣葉亭なる人物が所蔵しており、これを悟心が模したものをさらに天寿が模したうちのひとつであったことがわかる。図の右上端に「第一幀」と書き入れがあるのは、第二幀、第三幀以下第六幀の存在を暗示する。
しかしこの伝摸経路は、ある意味で伊孚九画の江戸時代後期画壇への普及の仕方を象徴するものといえるだろう。黄檗宗のなかの閉ざされた好尚が、黄檗と交渉をもつ一部の先鋭的な文人のあいだに新しい刺激剤として注入され、やがて拡散していく、多くの明清文化の日本への移植普及の仕方である。鶴田武良氏が指摘するように、伊孚九に対する崇敬の気持が、実は『韓大年縮■(も)・伊孚九・池大雅山水画譜』の上梓を契機として文人画壇全般に一気に広がったとすれば、大雅周辺の伊孚九傾倒が、まだその段階では、極めて限られた仲間内の範囲の好尚でしかなかったことになる。しかしだからこそ、時代を先読みした彼らの先鋭的な動きは見逃すことができない。
(やまぐち・やすひろ 三重県立美術館主任学芸員)
