|
いつもながら君側の移動パターンにはあきれるよ 坂田靖子、「浸透圧Ⅲ」、『闇夜の本2』
|

ジョアン・カルデイス 会場風景
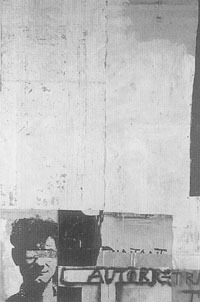
ホセ・サンレオーン 「網膜上のマンハッタン」 1066年(cat.,no,28)
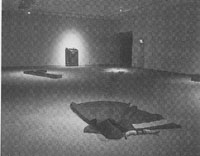
アンヘレス・マルコ 会場風景

アンヘレス・マルコ 「高速道路」 1987年(cat,no,17)

カルメン・カルボ 「集成」 1990年(cat.no.1)
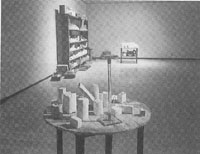
カルメン・カルボ 会場風景 (cat,no,2,3:第4室)

カルメン・カルボ「中心で」(部分) |
|
ラモーン・デ・ソトの展示は、インスタレーションを構成する各パーツの、展示空間に対する小ささ・背の低さにもかかわらず、空間全体をみたすある種の緊張感を感じさせずにいなかった。その意味で、床にそって水平にひろがるという見かけにもかかわらず、あるいはだからこそ、表現自体は、床と天井にはさまれた垂直の空間において現われたものと見なすことができるかもしれない。これは、階段、橋、アーチといった、宙に浮き、かつ移動の中継経路であることによって空間を連絡する各パーツの形や、鋼を主とするその硬質な質感、落とされた照明とともに、背の低さ自体がその上にひろがるからっぽの空間を意識させる点、展示室の壁と平行に、あるいは対角線上に、アーチならアーチ、橋なら橋ごとは等間隔に配されている点、すなわち、与えられた空間の構造に即した布置によってもたらされたのだろう。東西の二元論はそこで東と呼ばれるものがふくむ複数性を抑圧してしまうがゆえにいかなる意味でも妥当とは見なしがたく、またソト自身93年には京都のさる寺院で展示したことはおくとして、とりわけ柱廊だか飛び梁を連想させるアーチの列にあきらかなように、天と地を截然と区別する、垂直感の強い建築空間をこそ、ソトの作品はその出自としているのではないだろうか。 ふりかえって今回の<移動>展展では、ナバッロとサンレオーンにおける都市、カルボの作業場やテーブル、墓地、マルコなら高速道路や歩道といった経路など、広い意味での建築物との関係を出発点とするものが少なくない。就中、蝟集と散在、垂直にのびるパーツのあるなしによって一見その表情は対照的であるにしても、ソトとともにナバッロのインスタレーションもまた、部分部分でのパーツの配列の規則性、壁ないし対角線に即した布置という点で共通している。さらに、いささか附会の気味を覚悟でいえば、カルデイスのドローイングは、クラフト紙にグラファイトを擦りこむ中から凹凸のある線だけでイメージを浮かびあがらせるというフロッタージュ、またそれを額にぴったり留めず、ひらひら浮かすということをもって、厚みを有した壁に、また同時にその前にかけられた壁掛けに呼応するともいえようし、何よりも人体ないし女性の身体をそのモティーフとするナバローンの作品ですら、それぞれは正しく垂直水平に配されているというところだけとれば、たとえばエル・リシツキーの<プロウンルーム>と比較することも不可能ではない。 もっとも、ただ骨組みの共通点をあげて足れりとするのでは、ナバローンの作品が批判しようとしているであろう、他者を客体化してその全体性・多層性を抑圧する視線の専制をなぞることにしかなるまい。彼女の作品の場合、垂直・水平の布置は、立つ・寝るという生活上の態勢を喚起するとともに、包みこむように丸められたビロードの状態によってもたらされる、外と内の区別および関係を強調することとなっている。ビロードの厚みと、いったんは外にむかって発散しようとする紅色は、包みこまれたその内部を呼びださずにはおらず、それに応じて綿や糸がはみだすのだ。はみだすのはさらに、そうした物の形をとるとはかぎらない。ビロードの筒の内側がからっぼの場合もまた、からっぼであるということ自体が、垂直・水平の布置に対する余剰としてはみだすのではないか。そしてはみだしたものは、糸屑であれ空虚であれ、定まった形をもってはおらず、そうした形なきものを召喚するために、逆に、建築に応じる規則的な布置が要請された。 この点では、ナバッロの『敷地Ⅰ』において、奥の壁にたてかけられたパーツ群も相似た位置を占めているといえそかもしれない。主要な部分でもすでに、手前から見て塔状のパーツがならぶところより奥にいくと、それまでの規則的な配列が崩れた部分を見出すことができるが、壁のパーツ群はさらに、主要部分が基本的には床の上に一つ一つ配されているのに対し、床ならぬ壁とも接点をもつため重力以外の因子がはたらくこと、およびその配置の不規則さによって、主要部分全体を相対化してしまうのだ。壁のパーツはまた、たてかけられていることゆえ、床におかれたパーツと尺度を異にする。これは主要部分での塔状のパーツと集合をなす小パーツとの落差に呼応し、作品全体から安定を奪いさることだろう。 たえず可能態の深淵に滑りおちようとする、作品全体を壁に留めるピンででもあるかのようなパーツ群のこうした役割は、マルコの『高速道路』および『歩道』で、床や壁に放りだされた余りの軸棒にも認められる。ナバッロの『敷地Ⅰ』がいつなりとその配置を変化しうる可動性を感じさせるように、マルコの経路もまた、現在の姿はかりそめの組みあわせにすぎない。他方、経路という点ではソトの階段や橋、アーチにも通じるが、マルコの場合、ソトのように経路は連絡した空間に解消されることなく、段差や内側への油ないしアスファルトの塗布がしめすように、経路自体がさまざまな錯綜と制動、遮蔽と切断を内包しており、また『裏』のたるんだゴムのトンネルもふくめ、経路といってもすんなり通過させてくれるとはかぎらない。『裏』のトンネルの鉄粋が、透視法によって投影されたものであるかのようにひしゃげた平行四辺形であり、展覧会初日におこなわれたパフォーマンス『補われた同一性 運命の秋に移動し、再生すること』から死と再生の過程を読みとれるとすれば、マルコにおける<通行>とは、異なる次元間でのそれなのかもしれない。ただし、マルコの作品がはらむさまざまな隠喩は、きわめて無愛想な形態と、それが容器状をなすことでつねに交換可能な空虚を容れている点によることを忘れないでおこう。 容器が内と外との境界をなすように、器の鉄とその内側に塗られた油やアスファルトは、そこを何かが通過しようとしても、速度をたがえさせる層と化する。同様に、カルデイスとサンレオーンの平面も、決して厚みのない幾何学的な二次元ではない。いささか単純化すれば、カルデイスにおいて層は(ソトの<テーブル>と同様に)平面の内部からひきだされるのに対し、サンレオーンでは、外部から侵入した複数の因子の邂逅そして葛藤として成立している。 カルデイスの場合、クラフト紙に施されるグラファイトのひろがりは、即物的には紙の上にのっているわけだが、同時に、黒というひきさがる色の性 格および紙に加えられた圧力ゆえ、紙の内奥に沈もうとする。しかしこれは、視覚的なイリュージョンにかぎられたものではなく、グラファイトとクラフト紙の質感によって、触覚的な感触をも伝えずにいない。この触覚性はさらに、グラファイトを塗った部分と紙の地のまま残された部分とを、画面上で分割された不連続な区画にとどめず、一つの、しかし多層をはらむ面の変化した相と感じさせることになる。イメージをつむぎだす凹凸のある線も、グラファイトと紙が形成するこうした厚みの内に包みこまれているのであり、量塊をともなう形態を型どるというより、こちらは厚みのない影の輪郭にすぎない。そしてこの厚みを閉ざしてしまわないために、紙はぴったりとは額に留められなかったのだろう。 こうしたカルデイスのドローイングを、平面に対する彫刻という試みであるとともに、近世西欧的な意味での絵、英語ならペインティング――塗るもの、すなわちヴァン・エイクらネーデルランド絵画から基本的には一九世紀 なかばまでの、透明・半透明・不透明な塗膜の層の重なりからなるそれに対する、素材の物質性に即した再検討と見なすことができるかもしれず、とすれば対するにサンレオーンは、単一の表面上に不連続な筆触を併置していく印象派以降の画面づくりに応じているといっては、これも附会の感を免れないだろうか。松浦寿夫が幾度か語ったように、印象派における筆触分割が、「画面の単一性/筆触の多数性という矛盾」を開いてしまったとすれば(松浦、「現在の記憶、迅速な手」、『ユリイカ』、1993.11、P.162;また同、「デッサン ボードレールの徴のもとに」、『武蔵野美術』、no.106、1997.17、など)、ここでも、全体性を保った画面を作りあげることはあらかじめ断念されていたのだろう、テント用のシートや大小の尺度を異にする写真は、画面の枠の外のさまざまな場所、さまざまな時間から仮に寄せ集められたものでしかない。それらが接触した境界が大まかには画面の縦横と平行に整えられ、沈んだ色のものが選ばれている点のみが、かりそめの邂逅を保証する。しかし邂逅はあくまで仮のものでしかなく、ナバッロの都市同様、いつなりとばらばらにほどけてしまってもおかしくあるまい。こうした様相はまた、支持体の自明性に対する問い直しという点で、一方でタピエスらスペインのアンフォルメル、他方シュポール/シュルファスにもつながっている。 記憶を担った物たちを集めることで作品を成立させるという点は、カルボにも通じるところだろう。ただ、くすんだ調子で統一されているとはいえ、かなりなまの状態の物がそのままもち来たらされ、だからつねに分解しそうなサンレオーンに対し、カルポはその多くを、石膏やセメント、漆喰でかためてしまっている。しかもその内かなりは、紙の箱だか袋のようなからっぼの器に石膏などを注いだものだ。物の以前の状態とのへだたりはいっそう大きくなり、石膏等の漂白したような白っぽさとあいまって、目の前にあるのは、かつてあった何かの痕跡でしかなく、そのかぎりで、時間の流れから脱したかのような充足した表情をたたえている。しかしまた、痕跡は痕跡なりに、現前からのずれをはらむとすれば、そこで決して、エントロピーが極大になってしまったわけではあるまい。 他方、サンレオーンにおける演繹的な分割にあたるのは、墓地に想をえたという床の上の配置、静物をのせるテーブル、作業場の棚などの枠どりだ。宙に浮いたテーブルがしめすように、これらの装置は、公的な中立性を装う美術館の展示室という制度化された空間を一気に無効にしようとするのではなく、作品内部にもう一度物を置くための台をおり重ねることで、展示という形式を宙吊りにし、もって相対化しようとしているように思われる。これは床に配した場合も同様で、照明とあいまって、舞台上の演者たちのように暗転とともに姿を消しそうだ。その際はたらきかけるのは、さまざまな度合いで漂白された物の集積である。テーブルや棚は展示室から出されてもおかしくはないかもしれない、しかし物たちは、外であれ内であれ、単なる棚なりテーブルであれ宙吊りにされた展示の入れ子であれ、石膏などでかためられているがゆえに即座に崩壊しきることもかなわず、白っぽい、つまり光の封印ゆえ廃物にもオブジェにもなりきれず、居心地悪げなささやきをつぶやきつづけるのではないだろうか。 (いしざきかつもと・学芸員) |
美術館 > 刊行物 > HILL WIND > ひる・うぃんど(vol.61-70) > 展の会場を移動し終わっても迷子でありつづけるためのガイド
ページID:000055687
