|
荒屋鋪 透 頽廃した状況というものは、なにも世紀末にのみ起きる訳ではない。ただ世紀末には、人々をその状態に対して寛容にさせる、不思議な力があるのではないか。もっとも、その時代に生きる者全てが頽廃の恩恵に浴せる訳ではなく、それは文学作品のみならず絵画にも必然的に反映されている。例えば、グスタフ・クリムトの描く『愛』(1895年)と、ほぼ同時代に制作されたマクス・シュワビンスキーの『霊魂の融合』(1896年)──プラハ国立美術館コレクション「ヨーロッパ絵画の500年」展に出品──の間には同じ男女の抱擁が描かれながらも、深刻な溝が横切っているに違いないのだ。1987年7月東京、銀座セゾン劇場における、アルトゥール・シュニッツラー作『輪舞』(台本・演出=木村光一/訳=高橋健二)を観ながら、そんなことを考えていた。『輪舞』は、10場の村話劇という副題のとおり、19世紀末ウィーンを舞台に、様々な階層の10人の男女が、それぞれ身分違いの二人の相手と関係をもつ過程を、各場面二人の登場人物の対話を中心に描いた戯曲である。第二次世界大戦後、二度フランスで映画化されているので、銀幕のラブシーンに心ときめかせた方も多いであろう。銀座セゾン劇場の公演で、演出家の木村光一は役者のセリフ回しを少し速め、場面展開に弾みを付けることで、歯切れのよい舞台を創り上げた。美術を担当した朝倉摂の素晴らしい舞台装置が、その演出を助けている。 原作者シュニッツラーは、高名な咽喉科医を父に持ち、自らもウィーン大学医学部に学んだため、早くから同時代の医師フロイトの精神分析学に興味を持ち、分離派の画家クリムトにも多大の影響を与えた自然主義の作家。「人間の行動の原動力は意識下の性欲衝動(リビドー)にある」というフロイトの学説を、巧みに登場人物のセリフと動作に採り入れて構成させた作品のひとつがこの『輪舞』である。シュニッツラーのみならず、ホフマンスタール、バールといった「若きウィーン派」の作家は印象主義者ともいわれるが、それは彼らが常に移ろいやすい存在に憑かれていたことに起因している。世紀転換期の1900年前後に、文学カフェに集った「若きウィーン派」の作家たちは、世の儚なさを憂い、その象徴としての「死」の概念に囚われていた。近代社会が産み出した変わりやすく、神経質な都市環境と人間関係。そこに衰退の兆しを見て取った耽美主義の作家たちは、寧ろ滅びゆくものの中に生命の本来の姿を感じていたのではなかろうか。『輪舞』の最終場面で、伯爵が娼婦の寝顔に自分の最も大切な女のそれを見い出す箇所は、大変印象的である。「だが、本当に眠りという奴は──兄弟分の、つまり、死の神と同じように、みんな同じように見せるもんだなあ……」(『輪舞』中村政雄訳 岩波文庫) ところで私達は、この末期ハプスブルグ帝国の首都ウィーンに、同じ様に帝国の没落の兆しを感じながらも、そこに新たな力の源を探りだした知識人のいたことを忘れてはならないだろう。彼の名はマクス・ドヴォルシャック。ウィーン大学の美術史教授である。40代後半で急逝したこの学匠の研究は、死後出版された論文集『精神史としての美術史』に集約されている様に、一つの時代の美術と他の精神文化、例えば文学や音楽、演劇との間には共通の問題が横たわっているという前提の上に成されていた。彼の研究には学問の専門分化を拒む姿勢が見られ、芸術作品に、自然科学に屈することのない、独自の価値基準を確立させたいという理想があったが、その理想が生まれる背景には、彼の実人生における二つの事実が隠されている。ひとつは、ドヴォルシャツクがウィーンに住むチェコ人であったことで、師ヴィクホフの愛弟子として、大学の教壇にたった時の苦い経験は、終生彼の脳裏から離れなかった。一部の民族派ドイツ人学生から、彼はただチェコ人であるというだけの理由から侮辱されたのである。あとひとつは、言うまでもなく第一次世界大戦によるオーストリア・ハンガリー帝国の崩壊と、チェコ民族の独立である。ドヴォルシャックの父は、プラハに近いエルベ河畔のラウトニッツ城の文書係であったが、この敬虔なカトリック信者の父親から彼は、ボヘミアの改革派カトリックが唱えた、部分に対する全体の優位という思想を学んだ。自然科学の打ち出す短絡的で楽観的な自然主義を、精神主義としての理想主義から批判するドヴォルシャツクの立場は、まさに、部分すなわち個々の対象の経験的な分析に頼る自然主義と真っ向から対立し、前工業社会への郷愁、中世の再来の懇願へと向かうのである。皮肉なことに、ドヴォルシャックのこの全体を見渡した理想主義は、実は、全体が混沌としていた帝国の首都ウィーンの耽美的知識人と共通した土壌で培われたものでもあった。 ドヴォルシャツクがまだウィーン大学の学生であり、シュニッツラーが『輪舞』を発表した1900年、プラハ出身の詩人ライナー・マリア・リルケは祖国の画家エミル・オルリクを紹介する一文を、ウィーンの『ヴェル・ザクルム』誌に発表している。オルリクはクリムトらの分離派の芸術運動に参加した画家であるが、版画家としても知られ、わが国とも縁のある芸術家である。リルケがオルリク論を発表した年、オルリクは日本を訪問している。彼の版画は雑誌『明星』の挿絵にもなった。ところで、このリルケのオルリク論には、新たな芸術の指標を求めて世界中を旅したコスモポリタン、オルリクに託して、詩人リルケ自身のコスモポリタニズムが表明されている点が興味深い。リルケは、祖国を持たぬプラハの芸術家が、その芸術の独自性を主張するには、自らの背負った風土を自己の表現へと収斂させ、そこから生まれた様式に風土の特異性を強調するか、もしくは、自らを育んだ土地から離れ、他の異なる文化を学び、不安定な自己同一性を克服しながら、自己の風土について思い巡らす方法しかないと考えた。勿論後者は、リルケ自身が選択したコスモポリタニズムである。異郷における他者の発見によって、真のコスモポリタンは強い意志のもとに自己の芸術と、なによりも自己を確立してゆく。 その自己同一化を成し得た芸術家は、まだ見ぬ祖国と精神的に結ばれるのである。彼の『われらを結合させる魂』という詩などは、その詩を含んだ『オルフォイスヘのソネット』を書き上げてから、数年後に世を去ったリルケの生涯を思い描く時、痛々しいまでに詩人の魂の叫びを聞く思いがするのである。今回のプラハ国立美術館コレクション展に出品されている、マクス・シュワビンスキーの『霊魂の融合』という絵画作品なども、まだ祖国を持たなかった世紀転換期前後のプラハの芸術家の熱い思いの託された作品であるといえるだろう。青年は画家自身であるが、白い衣の女は、伝説の王妃リブシェにも見えてくるではないか。
(あらやしきとおる・学芸員) |

グスタフ・クリムト作 『愛』1895年
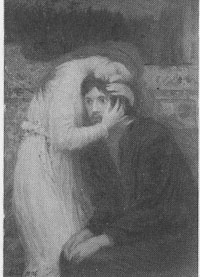
マクス・シュワビンスキー作 『霊魂の融合』1896年
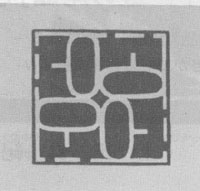
エミル・オルリクのモノグラム 1902年

雑誌『明星』に掲載された エミル・オルリクの蔵書票1900年
|
美術館 > 刊行物 > HILL WIND > ひる・うぃんど(vol.11-20) > ひる・うぃんど(vol.20) 世紀末プラハ ─プラハ国立美術館コレクション ヨーロッパ絵画の500年展にちなんで─ 荒屋鋪 透
ページID:000055486
