|
昭和48年、85歳の長寿を全うしてこの世を去った石井鶴三は、彫刻家として近代彫刻史に確固たる地歩を固めた一人の作家であっただけでなく、油彩画・水彩画・版画などにも優作を遺し、「いつか挿絵が本職のように見られるようになった」(註・1)と記しているように、挿絵を描いた作家としてもよく知られている。多芸であった石井鶴三の作品と文集から窺える人柄は、生来の江戸っ子であったことを象徴するかのように、何より先ず誠実で、最前を早くしきる強い探求心を忘れることのなく、まっすぐに道を歩んだ一人の人物であったろう。石井鶴三美術館のある上田市において、生誕99年を記念した「石井鶴三先生を偲ぶ会」が昭和61年に開催されているが、その記念講演で中川一政は、「90歳まで生きる」と話しながら5年早く亡くなった以外には全く嘘をつかない人で、鶴三ほど「堅固な思想を持って物事に対した人ってのはいない」と述べていることからも窺える。 ところが戦後の東京美術学校教授時代のエピソードとして、石井鶴三の教室は、雑巾掛けから始まり、制作者と対象のモデルとの間を横切ることを許さなかったという。また鶴三から怒られる一方で頑固一徹のイメージを多くの卒業生は抱き、鶴三に免職を求める動きまであり、それで鶴三を奇人と呼ぶ人もいるが、制作に対する厳しい心情の表れであり、自己の生き方への確信がそういう行動に反映したと考えるべきであろう。 小山正太郎の不同社で油彩画とデッサンを学び、彫刻は加藤景雲に習った後、東京美術学校彫刻科を卒業、大正2年同校研究科を修了し、翌年佐藤朝山と知り合ったことを契機に日本美術院で研究に励み、大正5年には第3回院展に『佐藤朝山像』などを出品して日本美術院同人に推され、同年第3回二科展に水彩画『行路病者』『井戸を掘る』を出品して二科賞を受け、同時期に彫刻、絵画の両分野において活躍を始めている。 明治・大正・昭和の時代を通じ、石井鶴三が描いた挿絵は挿絵の歴史を刷新し、以後の展開に大さな影響を与えているが、鶴三が初めて挿絵を手がけたのは、大正7年、田村松魚の『歩んで来た道』という自伝的小説からであった。これはやまと新聞に連載されているが、当時は挿絵が毎日入るのではなく数日おきであったらしい。兄であった洋画家・石井柏亭が実在する風景や人物を担当し、鶴三が想像による描写を受持っていた。この頃には挿絵はそれほど重視されることもなく、いわば小説の飾りのようなもので、文章の内容からかけ離れた挿絵も多く存在していた。しかし、鶴三は松魚宅を終始往来して小説が発表される以前に粗筋を聞き、「小説の本文を読んで、そのなかから感じとったところをモチーフするという挿絵の常道とはちがった、一種の変態であったが、おもしくはあった」(註・2)と述懐しているように、伝統的な挿絵の風潮に甘んじることなく、この時期既に鶴三は自分勝手に描くことはしていない。 その後「婦人公論」に掲載された上司小剣の小説『森の中の家』の挿絵を主筆嶋中雄作のなかだちで描き、大正9年の頃、時事新報に連載された上司小剣の新聞小説『花道』の挿絵を担当しているが、鶴三が以前の挿絵と全く異なるものとして反響を呼び賞賛を集めたのは、大正10年2目20日から7目9日までの間、東京朝日新聞で連載された上司小剣原作『東京』の愛慾編であった。『東都』は男女の愛をテーマとした現代小説で、今回の『石井鶴三展』に総数138点のなかから5点が出品されている。背景を人物と調和させることに細やかな神経を通わせながら、鶴三は卓抜な素描力を駆使し、コンテを用いた光と影の調子によって、登場人物の心情を巧みに形象化し、鶴三の心髄をみせている。「日比谷の夕」と題された挿図・1は、今まさに夕闇の中で車が出発しようとしている情景のなかで別れを惜しむ男女を描いたもので、従来の型にはまった浮世絵の系統の風俗画・美人画の挿絵を否定し、小説と挿絵は「義太夫と三味線との関係」であるとし、「所謂新聞小説と芸術上の創作との調和混一」(註・3)が必要であると平素から考えていた鶴三は、この確信に基づき『東京』愛慾編挿絵の準備を始めたと記している。「挿絵の使命に就て文中にこれあるによって先ず紙面の美的効果をたすけ、進んでは画によって本文の及ばざるところを補い以て本文のひき立て役となることであり、本文の読者をしては一層の興趣あらしめることになる」(註・4)と述べた鶴三の心配りがこれらの作品に満ちている。 画期的であった『東京』の挿絵も、鶴三が考えたほどの効果は出なかった。「新聞雑誌の用紙製版印刷のわるいのは困ります。折角骨を折って描いたものが半分位しか効果があがらぬことがしばしばです。(略)といっていい加減な仕事の出来ないのが画家の心です。」(註・5)はその反省であり、粗悪な用紙製版印刷をうまく使いこなして、逆に効果を得ようと鶴三は腐心し、その成果が発揮されたのが中里介山原作の『大菩薩峠』であった。 鶴三が手がけたのは現代小説であり、時代小説を依頼されても断わっていた鶴三であるが、断わりきれず、「とにかくひきうけて全く泥縄勉強で幕末時代の世相風俗などを調べ、画をかいて見ることにし」(註・6)たという。大正14年1月から昭和3年8日の間に大阪毎日新聞と東京日日新聞の両紙に掲載きれ、無明・多生・流転・みちりや・鈴慕・Oceanの巻から成る『大菩薩峠』の挿絵では、かつてこっそりと日本画を学んだ画技を生かし、毛筆による1本の線に持てる力のすべてを投入して描く方法を試みている。「たんだ一本の線でかかなくてはいけない」(註・7)は、論語にある「君子は和して同せず小人は同じて和せず」という言葉とともに、不同社の小山正太郎から学んだもので、生涯を通じた鶴三の信条となっている。 この『大菩薩峠』には、小説家・中里介山と鶴三との間にちょっとした事件が発生している。発端は大正14年12月に「大菩薩峠原画展」が開催されたときに始まり、同9年7月に『大菩薩峠』のなかから442図を選んで『石井鶴三挿絵集第一巻』を出版しているが、その準備段階のとき、小説に基づいて挿絵を描いている以上、挿絵の著作権も原作者である自分にあるとする中里介山と、それに反論する鶴三との間に論争が起こり、上司小剣が著作権帰属と名誉毀損信用毀損について告訴するという事態となったが、結果は鶴三の勝訴となり、この事件は挿絵への関心を高める機会となり、また挿絵の位置を明確に示す契機となった。また『大菩薩峠』の挿絵は、『南国太平記』『松五郎鴉』『松のや露八』『宮本武蔵』などこれ以後に展開する鶴三の挿絵の方向を明確に示している。 今回の生誕100年記念を記念した「石井鶴三展」には彫刻82点、油彩画39点、水彩画22点、屏風2点、小説挿絵から85点(5件)、素描10点版画22点(18件)計266点(182件)が出品され、これらの作品から石井鶴三芸術のほぼ全貌を窺うことがでさるが、作品の主題は派手なところは全くなく、彫刻、油彩画、水彩画、版画、そして挿絵のどれを見ても、強烈に惹かれるといった性質のものではない。しかし主題に添って誠実に表現する石井鶴三の作品には深く沁みるような魅力に満ちている。 (もりもとたかし 学芸員) |
註・1 「挿絵の思い出」『日本文学の歴史』月報(12) 角川書店 昭和43年 註・2 「挿絵の思い出」『日本文学の歴史』月報(12) 角川書店 昭和43年 註・3 「『東京』を書くに就いて」東京朝日新聞 大正10年2月18日 註・4 「挿絵の話」JOAKより放送 昭和11年4月 註・5 「さしえ画家として」中央美術 大正12年7月 註・6 「挿絵の思い出」『日本文学の歴史』月報(12) 角川書店 昭和43年 註・7 朝日新聞 昭和42年12月14日 「たんだ1本の線」は「たった一本の線」のこと。

『東京』 愛欲篇 挿絵10 1921年(大正10)年

『大菩薩峠』無明の巻 挿絵17 1925年(大正14)年
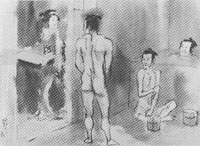
『松のや露八』 挿絵 1934年(昭和9)年
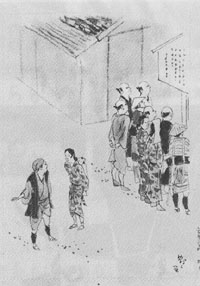
『宮本武蔵』 挿絵 1938年(昭和13)年頃
|
美術館 > 刊行物 > HILL WIND > ひる・うぃんど(vol.11-20) > ひる・ういんど 第19号 石井 鶴三──その人と挿絵──
ページID:000055479
