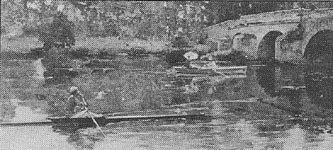グレー=シュル=ロワンと明治のピクチャレスク
荒屋鋪 透
|
一、 セピア色の風景 「・・・。大分寒くなった。もう秋ですね、浜の方は靄(もや)でセピア色になった。いゝ景色だ。・・・」 夏目漱石は、『坊ちゃん』(明治三十九年四月『ホトトギス』掲載)のなかで、教頭の赤シャツと画学の教師野だいこに、こんなやりとりをさせている。この一節は、近代日本文学に初めて、「セピア色の靄」がかかった瞬間かもしれない。季節は秋。四国の中学に赴任早々の坊っちゃんは、バッタ事件の直後、ふたりに誘われて釣りに出掛ける。赤シャツは、島に生えた、まっすぐな幹の上が傘のように開いた松を見て、その島をターナー島と名付けたりする。エピソードの多いこの小説のなかで、唯一、見晴らしのよい場面である。漱石は赤シャツの太鼓持ち、野だいこを意図的に画学の教師として登場させ、ふたりの会話を絵画的にしている。そして、情景をセピア色に染めることで、ピクチャレスクな雰囲気を強調するのだ。この手法は、近代日本文学はともかく、十八世紀の英国では常套句に属している。いわゆるピクチャレスクの美学である。平岡敏夫氏は『坊っちやん』に、四国の中学を舞台にして漱石のロンドン留学体験を描いたものではないかという仮設を設定し、明治三十四年二月二十日付の書簡(ロンドン留学中の漱石から鏡子夫人宛)と、坊っちゃんが清を回想する場面に共通する「手紙はなにか事ある時にのみ出すもの」という表現、鏡子夫人と清(キヨ)の名前の類似、ダンゴ事件やバッタ事件という小説のエピソードが、やはり不愉快であったロンドン体験に重ねられ、鏡子夫人にとってのロンドンは、清の四国と同様の距離を持つとして、『坊っちやん』の主題は、「東京に残してきた、ただひとりの愛する女性存在を思う、異国の孤立した男の物語」であり、そう見ることによって初めて『坊っちやん』という作品は、その根底に神経衰弱を孕んだ、日露戦争後の日本および日本人批判の文学として読むことが出来ると結論づけている(『文学』、一九八九年九月号)。その漱石が小説のなかで、風景が重要な役割を負う場面において、英国流のピクチャレスクな修辞法を駆使しても不思議ではないだろう。『野分』明治四十年一月)においても、漱石は「セピア」という語を用いているが、それは夕暮れの景色の形容である。 時計はもう四時過ぎである。深い碧(みどり)の上へ薄いセピアを流した空のなかに、はっきりせぬ鳶(とび)が一羽舞っている。 夕暮れをセピアで表現した作家は、漱石が初めてではない。すでに明治三十四年、小諸の島崎藤村は、『落梅集』に収めた「雲」のなかで、夕暮れに消えかかる雲の変化を以下のように表現する。 雲緑は茶褐色、もしくは洋画に用ふる「セピア」の色彩に似たりき、・・・ ジョン・ラスキンの雲の観察に興味を覚えた藤村は、彼の写生文に絵画的手法を応用しようと試みた。藤村の小諸の友人には、丸山健作(晩霞)がいたが、晩霞のパレットにもセピア色の絵具があったのだろうか。明治三十七年七月、片山富文館と武田交盛館から発行された織田一磨の『水彩書法』には、第四章の「水彩画絵具」にセピア色が紹介され、同書には「黄色の葉の間より見ゆる所の枝は『セピア』を用ふべく、・・・」などと用例まで示されている。セピア色は、どうも当時大流行の水彩画から借用された語であるらしい。そして、その色は水彩画がやはり盛んであった英国のピクチャレスクに由来している。ピクチャレスクとは、十八世紀に英国を中心に起こった一種の芸術運動である。自然界や文学など諸芸術を、絵画の規範に則って「絵のようなもの(ピクチャレスク)」として観る、趣味の伝播であったともいえるだろう。文学者や芸術家は、ピクチャレスクな風景を求めて、こぞって旅に出掛けた。その旅の必携となった小道具に「クロード・グラス」という鏡がある。クロード・グラスは、広大な風景を手元に小さく映し出す凸面の鏡で、表面が淡いセピア色に施されている。そのため、別名グレイ・グラスともいい、一般的な銀の鏡とは異なり、そこに映るものの細部までは見えにくい。全体の形と明暗のみが強調される映像なのである。マルコム・アンドリューズ著『ピクチャレスク を訪ねて』(一九八九年)▼1によると、その時代の知識人の多くは、スケッチブックと日記帳、そしてクロード・グラスという「ニック・ナック(楽しい旅の小物)」を携帯して、ピクチャレスクな旅行を楽しんだようである。旅先は、ワイ河渓谷、北ウエールズ、湖沼地方、ハイランド。夏目漱石も留学を終えて帰国する二か月前、明治三十五年の十月に、ハイランドつまり英国スコットランド北部の山岳地方に旅行している。その時の想い出を綴った作品が『永日小品』のなかに収められている。「昔」という一文である。 ピトロクリの谷は秋の真下にある。十月の日が、眠に入(い)る野と林を暖かい色に染めた中に、人は寝たり起きたりしてゐる。十月の日は静かな谷の空気を空の半途(はんと)で包(くる)んで、ぢかには地にも落ちて来ぬ。と云って、山向へ逃げても行かぬ。風のない村の上に、いつでも落ち附いて、凝(じっ)と動かずに霞(かす)んでゐる。其の間に野と林の色が次第に変って来る。酸(す)いものがいつの間にか甘くなる様に、谷全体に時代が附く。ピトロクリの谷は、此の時百年の昔し、二百年の昔にかへって安々と寂びて仕舞ふ。人は世に熟(う)れた顔を揃へて、山の背を渡る雲を見る。其の雲は或時は白くなり、或時は灰色になる。折々は薄い底から山の地を透かせて見せる。いつ見ても古い雲の心地がする。 漱石はロンドンでは決して見ることのなかった、空を見上げた。雲が山の背を渡っていく。のどかな景色てある。ここで漱石の目に映じた一九〇二年十月、英国ハイランドの風景は、一八八四年十月、森鴎外がベルリンで見上げた都市の光景とは、全く異質なものだ。漱石は、目の前に広がる現実を絵画を見る時のように眺め、日常的な目よりも優れた趣味を獲得している。都市の統一性よりも、自然の多様性、不規則性を重視した趣味。この自由なスケッチ風の現実描写こそピクチャレスクなのである。「(ピクチャレスク)は、自然のなかに、目で観ることの出来る様々な特徴を知る手段を、初めて与えてくれた。その手段は、既に画家たちがかねてから目で識別していた特徴を知るための目の教育によっている。(美術・建築・文学など)それぞれの芸術様式は、その(ピクチャレスクな時代)後に到来するロマン主義時代に到達する以前に、絵画作品を模倣するという段階を通過したのである」と明快に解説するのは、『ピクチャレスク』(一九二七年の著作)のクリストフアー・ハッシーである。ハッシーの解くピクチャレスクな絵画には、ターナーの水彩『ティンターン僧院の内部』(一七九四年)が含まれていたに違いない。ターナーは一八〇五年から一八一〇年にかけて、ウォルトンとウィンザーの間にあるテームズ河とワイ河の風景スケッチを多数制作している。英国南イングランドのなだらかな丘陵地帯、牧場や小麦畠の続く丘を観ながら西へ汽車で旅し、ブリストル市からフェリーでセヴァン河を渡ると、対岸は標高数百メートルの低い山々の続くウェールズ地方である。この山なみを縫うようにして流れるワイ河とその両岸の風景は、十八世紀の「ピクチャレスク」な景観を代表した眺めであった。ウィリアム・ギルピンというピクチャレスク運動の推進者は、一七七〇年代にワイ河を旅行し『ワイ河紀行―主としてピクチャレスク美をめぐって』(一七八二年)を著している。またトマス・ウェイトリーは、ワイ河渓谷のティンターン僧院を訪ねた紀行文において、廃墟の抜け落ちた屋根、アイヴィ(蔦)のまつわりついた壁、芝草に覆われた地面という荒廃したイメージこそ美しいと記す。ターナーが描いた廃墟の僧院はまさにピクチャレスクな光景であったのだ。ワーズワースもまた一七九三年、ターナーの水彩が描かれた時期、妹ドロシーを伴い、この地を訪れている。そして五年後に再訪して『一七九八年七月十三日、旅の途次ワイ河の辺を再訪し、ティンターン僧院の数マイル上流にてよめる歌』(川崎寿彦訳)を発表している(ピクチャレスクな旅とティンターン僧院については、川崎寿彦氏の『森のイングランド』(一九八七年、平凡社)と、『ロマン主義に向けて』(一九八八年、名古屋大学出版会)に収められた同氏の諭考「ティンターン僧院の風景」を参考にさせて頂いた。また展覧会カタログ『ウィリアム・ワーズワースと英国ロマン主義の時代展』(一九八七年、米国ラトガーズ大学他)Exh.Cat.,Wiliam Wordsworth and Age of English Romanticism,1987/キース・トマス著、山内昶監訳『人間と自然界』(一九八九年、法政大学出版局)を参照した)。十二世紀にシトー修道会の僧院として創設されたティンターン寺は、十三世紀に拡充されて再建された大建築物だが、十六世紀のへンリー八世による僧院解体政策により廃墟となった。この種の廃址は、十六世紀から十七世紀には全て取り壊されたが、グロスタシアの僻遠にあるティンターン僧院は破壊を免れた。領主の貴族ボーファト家の所領の一角に永い間、ひっそりと佇んでいたのである。ワーズワースの友人の美学者プライスは、「ピクチャレスク、それは荒々 しさ、複雑さ、不規則性を特色とする小規模な風景で、鋭い対照(コントラスト)と多様な色彩に満ちたもの」と定義している。ワーズワースが甥クリストファに宛てた書簡、「私達はセヴァン河をフェリーで渡り、さらに十マイル(約十六キロ)歩いてティンターン僧院に到着した。ワイ河沿いの大変美しい廃墟だ」。 自然のなかに佇む廃墟のイメージ。十八世紀英国のワイ河渓谷に建つティンターン僧院の図像は、一九世紀後半のパリに再び登場することになるのだが、漱石がスコットランド旅行に出向く一年ほど前、やはり欧州を訪問していたひとりの日本人画家が次のような手紙を家族に宛て、投函している。 日本の景色ハ世界絶生ならんと心ニほこり居候処 所々をあるいて見ると趣ハかわれど夫れ夫れの特色ありて及バさる所も勝る所もありて優劣を分ち難く候 佛国の地方中々面白き所ありて空気の異なる間色の美なる日本ニてハ見得られぬ異観を呈して両題ニ入り候 来月よりハ二ケ月斗り田舎ニ引込んで秋の景色を写さんとす。▼2 「西洋画研究ノ為満二年間佛國留學」を命ぜられた画家、浅井忠の書簡である。文中にある、「彿國の地方」または「田舎」とは、パリ近郊の村グレー=シュル=ロワン。浅井はフランス滞在中、四度グレーを訪れセピア色の風景画をものしている(図版1)。浅井のグレーの橋(図版2)は、ピクチャレスクな水彩画とされたジョン・セル・コットマン John S.COTMAN(1782-1842)の『水道橋』(一八〇四年頃)(図版3)に似ていなくもない─風景に橋を挿入する趣向は英国ピクチャレスク絵画に頻繁に登場する─が水道橋の見事な大きさを誇示する目的で描かれたコットマンの水彩に対して、浅井の橋はロワン河と背景の森に挟まれて、風景に溶け混んでいる。連続する半円の石橋のアーチも、その間から奥の風景が覗くコットマンの水道橋の威嚇するようなアーチとは異なり、静かな風景のアクセントに過ぎない。ここには英国流ではなく、バルビゾン派的なピクチャレスク(そう呼んでよいのであれば)な風景が描かれている。やはりグレーを愛した画家コローの『グレー=シュル=ロワンの眺め』(一八五〇年~六〇年頃)(図版4)を見てみよう。橋は、やはり風景に引用された、時間・歴史を暗示する部分である。コローのグレー滞在は、一八六三年。同じ年に綴られたゴンクール兄弟の日記、八月四日。 夕刻の七時。空は薄青色で、まるで土耳古玉が溶けこんだかの様に殆ど緑に近い青い色である!その空の上を、ふはふはと、切れぎれになった小さな雲の魂りが、ひと所に掃き寄せられ、落日の中に漂ってゐる湯気と同じ位なごやかな紫色を帯びて、ゆったりと、調子の好い緩やかな足取で動いて行く、そして、此の雲の頂きは、薔薇色の陽の光りをうけた、氷河の高い所の様に薔薇色てある。(中略)私の傍の、古びた橋の一番手前の橋弧の下には、ゆったりと水を飲んでゐる赤褐色の牝牛の身体が半分丈け橋弧の蔭になった拱門(アルク)から見えてゐた、そして、やがて水を飲み終ると、牝牛は白い鼻面を上げ、糸の様に口から水をたらしながら、凝っとこちらを眺めた。▼3 ゴンクールの日記は、一八六三年七月二十四日から始まっている。十七世紀オランダの風景画やバルビゾン派の絵画を想起させる、牛のいる小川の情景。 グレー=シュル=ロワンは、パリ・リヨン駅から近郊線(バンリュー)に乗り(所要時間約五十分)、モレー(MORET)で乗り換え、二つ目の駅ブーロン・マルロット・グレー(BOURRON-MARLOTTE-GREZ)下車、徒歩約五十分の村である。明治四十一年(一九〇八年)、二十八歳の児島虎次郎は日記に以下のように記す。 六月十日(水)晴・「午前九時湯浅一郎氏に送られ、リヨン停車場よりグレ・シュル・ロアン村に向う。汽車は一時間と四十分程。プーロン停車場に下車、ホテル・シュヴィヨンに投宿。午後此の宿に滞在中の斉藤豊作君と近郊を散歩す。花は終りたれども緑鮮かにして心地よく、野には美人草、矢車など一面に咲き盛りたり。ホテルの裏に一寸したる清き河あり、舟を浮べて上流を上る。古びたる石橋のかかれるは面白し。此の地に滞在するは二週間ほどの予定なれども、宿は至極物静かにして閑雅なり。感想探うして筆取るによし。土地の気風は質朴にして親切なり。出来るだけ長く泊りたし。制作もやって見たし。こんな所で描けば絵は機枚でも出来ると思う。夕食後、満月のスケッチに趣く。 此の宿には二十年ほど以前に黒田清輝先生、久米桂一郎先生が長く滞在あり、其の後和田英作氏、浅井忠氏なども写生旁々滞宿されし由なり」。▼4 児島虎次郎のグレー滞在は、明治四十一年(一九〇八年)六月十日から翌年の七月まで。グレー滞在期の作品『風景』(図版5)は、十九世紀末にやはりこの地を訪れた欧米の画家と共通したピクチャレスクな雰囲気に満ちている。児島の日記に登場する日本人画家、黒田清輝のグレー滞在については、既に芳賀徹氏の『グレーの哀歓─黒田清輝の場合』(『絵画の領分─近代日本比較文化史研究』、昭和五十九年、朝日新開社)という詳細な論考があるし、同氏も引用している平川祐弘氏の研究「黒田清輝のモデル、マリア」(『文学界』昭和五十六年五月号)に詳しいが、グレーという村の芸術家コロニーに集う画家が皆若かったこともあり、ここでのロマンスは枚挙にいとまがない。例えば、スウェーデンの画家カール・ラーションは、将来の妻カーリン(図版6)と出会っている。彼女もまた画学生としてパリに留学中であった。ラーションのグレー滞在は一八八二年から八五年。ふたりはグレーで婚約し、祖国で式を挙げてから再びグレーで制作を続けている。八四年には娘のスザンヌが生まれた。ラーションの友人で『赤い部屋』の作者、劇作家のヨハン・アウグスト・ストリンドベリ(図版7)とシリ・フォン・エッセン(一八八三年グレー滞在)、『宝島』の作者ロバート・ルイス・スティーヴンソンは、芳賀氏も報告されているように、シュヴィヨン館で未来の妻オズボーン夫人と出会う。そしてドイツから留学していた女性、画学生イェルカ・ローゼンに、一八九七年のグレーで出会う作曲家フレデリック・ディーリアス。 |
▼1 Malcolm ANDREWS, The Search for the Pictureaque:Landscape Aesthetics and Tandscape Aesthetics and Tpurrism in Britain, Univ.Press, California. ▼2 浅井忠、明治三十四年八月二十一日付浅井家皆々宛書簡より、(『浅井忠画集』京都新聞社、昭和六十一年、三七五頁。) |
|
二、グレー=シュル=ロワン 作曲家フレデリック・ディーリアス(一八六二-一九三四)に 『二つの水彩画』という曲がある。もともと歌詞のない無伴奏混声合唱曲として作曲されたが、一九三八年に弟子のエリック・フェンビー(一九〇六- )が弦楽合奏用に編曲した小品。原曲の題名は『水の上の夏の夜を歌わん』(一九一七年)といい、ある夏の宵、河で舟遊びを楽しんだ作曲家自身の思い出に曲想を得ている。フォーレの『シチリアーノ』シャブリエの小品を思わせるモティーフがゆったりと流れ、微妙に半音階的に動く旋律が牧歌的な情景を想起させる美しい曲である。この作品が生まれた場所は、ディーリアスがその後半生を過ごしたパリ近郊の村グレー=シュル=ロワンである。舟遊びをした河とはつまりロワン河。現在も作曲家の旧邸の庭のまえをロワン河が静かに流れているそうである。英国近代を代表する作曲家のひとりディーリアスの両親は、ドイツ人である。彼はライブツィヒ音楽院で学んだ後、一八八八年以降、裕福な伯父の援助を得てパリ効外に住み、九七年にドイツ人の女流画家イェルカ・ローゼンと結婚。九九年にグレー=シュル=ロワンに家を購入し定住した。第一次世界大戦中、ドイツ軍の砲撃がグレーを脅かした時にロンドンへ避難した以外、生涯その地で暮らした。ディーリアスは英国国籍の作曲家だが、ドイツ人の家族を持ちフランスに移り住んだ国際人である。ノルウェーでは、やはりライブツィヒ音楽院に学んだグリーグと会い、強く影響を受けている。北欧の国民音楽を代表する作曲家グリーグが晩年住んだ村ベルゲンに近いトロルドハウゲンが、ディーリアスにとってはグレー=シュル=ロワンであった訳だが、ひとりの繊細な作曲家を牽き付けたその村はどのような所だったのか。 後にバルビゾン派と印象派の後継者、外光派の画家を育てることになるこの村を初めて紹介したのはゴンクール兄弟である。一八六三年七月二四日の日記には以下のような記述が見られる。 七月二十四日。─フォンテエヌブロオの近傍、グレッツ(筆者註 グレー)。 吾々は今、画家達の泊る、鄙びた宿屋に居る一日三法半の宿料、漆喰で白く塗った部屋に泊り、羽蒲団に臥し、地酒を飲み、オムレツをふんだんに食べる。しかも、居酒屋の亭主達はにこやかな顔をし、緩やかに流れる小川の奇麗な水には游いでゐる魚の姿が見え、─そして森がすぐ傍だ。(大西克和訳) ゴンクール兄弟は、賄い付き一日三フラン五十の農家の民宿に滞在したようだ。その家には果樹園(リンゴ畠)があり、歩いてすぐの所に河が流れている。河には小舟が浮かび、村人が釣糸を垂れている。廃墟も見える。一八六三年の夏のことだ。滞在は二十日間ほどであった。同じ年にグレーを訪門した画家にカミーユ・コローがいる。一八七五年にパリ国立美術学校で開催された、「コロー遺作展」に出品の『グレー=シュル=ロワン』は美術評論家フィリップ・ビュルティ所蔵と記載されているようだが、この時期の作品と考えられる。 グレー=シュル=ロワンは、フォンテーヌブローの森の端に位置し、ブーロン=マルロットから五キロメートルのところにある村。GREZ-SUR-LOING の綴字は、画家によって異なる。つまり彼らの回想に登場するグレーは、Gres,Gres,Gretzと様々なのだ。このようにグレーは、特にフランスを訪れた外国人画家を魅了した土地だが、彼らは農村に暮らしながら制作に励むバルビゾン派的習慣、戸外で風景を描く印象派的制作法をそこで学んだ。そこには絵画的モティーフが豊富にあった。川辺のポプラと柳、ロワン河に掛かる石の橋、廃墟の城館、中世の教会。田舎の宿シュヴィヨン館では、川辺に食卓が整えられ、制作に疲れた画家は水泳や舟遊びに興じている。グレーがボヘミアン芸術家を最も牽き付けたのは一八七〇年から八○年代で、英国・アメリカ・北欧の画家、また留学生を受け入れるアカデミー・ジュリアンの生徒が訪れている。フランスでは世紀末のアンデパンダンたち、ジャクソン・ド・ラ・シュヴルーズやカロリュス=デュラン。またグレーで忘れてはいけない画家ジュール・バスティアン=ルパージュ。英国では、グラスゴー派の印象主義者たち(グラスゴー・ボーイズ)、もしくはアイルランド印象派の画家フランク・オマエラFrank O’MEARA(1853-1888)、ウィリアム・ストット William STOTT (1857-1900)、ジョン・レィヴァリJohn LAVERY(1856-1941)ロデリック・オコナーRoderic O’CONOR(1860-1940)、トーマス・ダウhomasM.DOW(1848-1919)、ウィリアム・ケネディーWiliam KENNEDY(1859-1918)、ロバート・スティーブンソンRobert A.M.STEVENSON(1847-1900)、ジェームズ・パターソン James PATTERSON(1854-?)、アレクサンダー・ロッシュ(ロッチ)Alexander ROCHE(1863-1921)らで、ホイスラーの影響下にある、またはピュヴィス・ド・シャヴァンヌに私淑した画家たちである。北欧、スカンディナヴィア諸国の画家には、スウェーデンのブルーノ・リリェフォスBruno LILJEFORS (1860-1939)、カール・ヌードストローム Karl NORDSTROM(1855-1923)、カール・ラーションCarl LARSSON(1853-1919)、アンデシュ・ソーンAnders ZORN(1860-1920)、ノルウェーのクリスティアン・クローグ、Chistan KROHG(1865-1925)カナダ人のジェームズ・ウィルソン・モリスJames W.MORRICE(1865-1924)、米国人ウィリアム・グラッケンズWiliam GLACKENS(1870-1938)、ロバート・ヘンライRobert HENRI(1865-1929)、バージ・ハリスンBirge HRRIOSON(1854-1929)、アーネスト・ローソンErnestLAWSON(1873-1939)などが、このコロニーの主要なメンバーであろうか。滞在期間はそれぞれ異なっている。勿論その中には、黒田清輝・久米桂一郎・浅井忠など日本人画家も名を連ねている。 グレーは、バルビゾンに比べて小規模なコロニーであるが、外国人留学生を中心とする若人の集団という様相を呈していた。コロニーであるため、むろんアカデミーのような教師はいなかったが、ジャン=シャルル・カザン、レオン・オーギュスタン・レルミット、ジュール・バスティアン=ルパージュという影響力の強い何人かの画家がいた。 一八七〇年代を代表するコロニーは、やはり英国の芸術家たちであろう。前掲した画家ロバート・アラン・モーブレイ・スティーブンソンの伯父は『宝島』の作者として知られている小説家ロバート・ルイス・スティーブンソンだが、彼は一八七五年頃グレーを訪れ次のように懐想している。 それは可愛らしく、とても物悲しげな平野の村である。沢山のアーチを持ち蚊帳吊草をぎっしりと詰め込んだ低い橋があり、広い牧草地には白や黄色の未(ヒツジ)草が咲き誇っている。無数のポプラと柳の木々。それらの上を、悲哀とゆっくりとした時の流れを含んだ大気が覆っている。▼5 また米国人画家バージ・ハリソンの回想。 そのコロニーの中心はアングロ・サクソンで、メンバーの大半は英国人か米国人だが、若干のフランス人、スカンディナヴィア人もいて国際色豊かであった。時折、スペイン人やイタリア人が訪れて南欧色を添えた。この地を構成する人間は、芸術家とモデル、といっても「避暑客」もしくは絵画や彫刻を学ぶ学生、音楽や演劇を学ぶ学生たちである。▼6 一八七〇年代にグレーを訪れた英国人画家は、ヘンリー・エンフィールドHenry ENFIELD(1849-1911以後)、ヘンリー・ディトモールド Henry E.DETMOLD(1854-1902以後)、アーサー・ヘセルタイン Arthur HESELTINE(1855-1930)、ウィリアム・ローWiliam H.LOW(1853-1932)、そしてロバート・スティーブンソン、フランク・オマエラである。北欧の画家がフランスを訪れるのは、一八六六年にデュッセルドルフを発ってパリへ向かったスウェーデン人アルフレド・ヴァールベりを端緒にしているが、七〇年代にパリを訪問しコローの影響を受けるカール・フレードリク・ヒル、一八八七年にブルターニュに旅行しブレハ(ブレア)島で制作をするエーンスト・ヨセフソン、アラン・エステルリンドといった画家がグレーを訪れたかどうかは定かでない。北欧の芸術家のコロニーが脚光を浴びるのは八○年代に入ってからのことだ。 八○年代の英国人画家を代表するのはロデリック・オコナーとジョン・レイヴァリである。オコナーは一般にアイルランドの表現主義、もしくはフォーヴィスムの画家として知られている。彼はアイルランド系のいかなる画家よりも長くフランスに滞在し、制作の拠点とした。ダブリンの市立美術学校から、当時名門とされていたアントワープ美術学校に留学し、一八八六年から八八年頃パリを訪れている。当初カロリエス=デュランに師事し肖像画をサロンに出品。八六年もしくは八七年、つまりパリ到者直後にはグレーを訪問して外光派絵画の洗礼を受けた。オコナーにグレー行きを勧めたのはジョン・レイヴァリだが、カロリュス=デュランの生徒たちは十年以上もの間、グレーを絵画修業の場にしていたようである。オコナーとレイヴァリはそこで、七〇年代から制作を続けているヘセルタインと出会った。またオコナーは、ロワン河近郊で印象派の画家シスレーと会った可能性もある。彼のグレー滞在時期が明確に判るのは、ローランというホテルに宿泊していた八九年。この年サロンに出品し、他に三点の作品をサロン・デ・ザンデパンダンに展示、グレーでの成果を披露している。九〇年に宿をボ=セジュール(シュヴィヨン夫人はオテル・セーヌ・エ・マルヌを経営し、ローラン夫人がオテル・ボ=セジュールを営んでいたという)に移し、再びアンデパンダン展に十点を出品。彼はアンデパンダン展でポン=タヴェン派の画家と会い、強く影響を受ける。九〇年代以降は、アンデパンダン展を中心に活動している。オコナーはまた一八八六年にブルターニュでゴーギャンと会っている。オコナーのフランスでの経歴を辿ることで分かるのは、印象主義者と後期印象派が活発な美術運動をしていた時期、フランス国内の反応はともかく、パリに留学していた異国の若い学生たちは、その運動に敏感に反応して積極的に印象派の画家に接し、ナイーヴにその技法・様式・生活態度までをも吸収していた事実である。印象派を取り巻く、これらの留学生は国際的な印象主義の伝播に貢献するが、それが外光派と呼ばれる画家の一面である。ただ、外光派には印象派が決別したレアリズムから逃れられない、もうひとつの面がある。この外光派の抱える自然主義の一面こそ、グレーの芸術家コロニーと密接な関係をもっている。オコナーにグレーを紹介したジョン・レイヴァリがパリに向かうのは一八八一年のことだが、彼がパリでまず感銘を受けるのは、リュクサンブール美術館に展示してあったブーグローの『悲しみの聖母』(一八七七年)である。レイヴァリは早速、作者に師事するためにアカデミー・ジュリアンに登録する。この辺の事情は、同じくリュクサンブール美術館のラファエル・コランの『花月(フロレアル)』(一八八六年)に感動した若き日の黒田清輝が、コランの指導するアカデミー・コラロッシに入学する経緯と全く同じ。留意すべき点は二点。すなわち、いずれもリュクサンブール美術館の展示作品を見て感激している点、そして外国人留学生を受け入れるアカデミー・ジュリアンやコラロッシといった私立のアトリエ(美術学校)に、その作者を訪ねて入学している点である。レイヴァリはアカデミー・ジュリアンで、ブーグローとフルリーの教室に入った。彼と同時期にアカデミー・ジュリアンに学んだ画家には、アイルランド人へンリー・ジョーンズ・サディアス Henry J.THADDEUS(1859-1929)、グラスゴー派のロッシュやケネディー、オマエラそして、モーパッサンとの文通で知られたマサー・バシュキルツェフ Marie BASHKIRTSEFF(1869-1884)がいる。レイヴァリはオマエラが滞在していたホテル、ザクセンという地名をづけたジャコブ街のオテル・サクスに宿泊。スコットランド人ロッシュやトーマス・ダウ、パターソン、ケネディー、ストットと交際し、リュクサンブールに近いカフェでルパージュやシャヴァンヌについての議論を戦わせている。シャヴァンヌの厳粛な寓意画に見られる象徴主義とルパージュの田園風俗画の自然主義が、この時代の絵画に一種の教派分裂を引き起こしていた。レイヴァリは一八七六年頃から風景画の制作を試みていたが、パリでは肖像画を勉強するつもりだったようだ。ブーグローに師事したという選択も歴史画や肖像画の研鑚を積む意志の現れであろう。彼はまたアカデミー・コラロッシにも通った。友人のジェイコム・フッドJacomb HOOD は以下のように回想する。 私はよく彼(レイヴァリ)を、モデルを廃業したコラロッシという男の経営するアトリエで見掛けた。そのアトリエは週単位で授業料を支払う所で、ヌードや着衣のモデルがいた。我々の仲間の多くは、午後そこで着衣のモデルから制作したものだが、皆に混じってレイヴァリは、その着衣習作に偽りの背景を施す習慣を身に付けた。そしてそれを完成作に仕上げて、グラスゴーの画商たちに売り捌いた。▼7 だが先に述べたような外光派の画家たちとの交友によって、そして一八八三年、サロンに出品されたシャヴァンヌの作品『夢』を見たことで、レイヴァリは新たな選択を迫られた。彼は一八八三年の夏、初めてグレーを訪れたと思われる。グレーのフェルナンド・サドレ女史 Fernande SADLER(『シュヴィヨン館とグレー=シュル=ロワンの芸術家たち』(一九三一年)の著者)に宛てた手紙。 私は、ウジェーヌ・ヴァイユEugene VAILに勧められてグレーを知りました。二人はアカデミー・ジュリアンの同窓で、私は週末を過ごすためグレーに行こうと決めたのです。そして九か月間、そこに留まりました。私が訪れた最初の芸術家村(コロニー)です。パリでの辛い仕事を終えた後に、グレーという地と住民の新鮮さ、美しさが私の心を強く捉えたので、パリとは絶縁し、ヌードを描くことを中断して、バスティアン=ルパージュやカザン(シャルル・カザン)の影響を受けた風景画を描くことになったのです。私には、パリに嫌悪感を感じれば感じる程、外光派的な生活が好みに合っているように思われました。油絵の材料を調達せねばならない時も、早朝の汽車に乗れば日帰り出来たのです。現在ではそれも一変し、田舎から街には急いで戻ることが可能です。地方との連絡は短時間です。ロバート・ルイス・ステイーブンソンは、その頃ちょうどグレーを去ったところでした。彼の友人フランク・オマエラ、オールダムのストット(註 ウィリアム・ストットの別称、一般に英国ではこう呼ばれていた)、ハリソンらは、彼の魅力的な人柄について多くの話を聞かせてくれました。貴方の手紙は、私がほとんど忘れていた名前を思い出させてくれます。スウェーデンと米国の一団は英国より強力でした。カール・ラーションは恐らく最も興味深いスウェーデン人でしょうし、米国人ハリソン、英国人ストット、アイルランド人オマエラは、グレーで過ごした最後のいくつかの季節に出会った人物のなかで、最も私に影響を与えた画家です。カザン─彼は義理の兄弟アルトゥール・エセルティーヌに会うためにグレーを訪れたのですが─を除いては、フランス人画家と会うことはありませんでした。▼8 この手紙にあるように、レイヴァリは一八八三年に初めてグレーを訪れた際には、数週間を過ごし帰国後再び訪問した一八八四年、九か月間滞在したものと思われる。宿泊先はオテル・シュヴョン。グレーでは、オマエラ、ストット、ハリソン、ウィリアム・パトリック・ホワイトWiliam P.WHYTE(1882-1905に活躍)らと合流した。レイヴァリはグレー滞在時代を「生涯で最良の日々」と回想する。 私のフランスにおける最良の日々は、パリ郊外グレー=シュル=ロワンの芸術家村(コロニー)で過ごした月日だ。そこは費用の掛からぬ気持ちのよい場所で、画家のみならず時には作家や・・・音楽家まで逃避してくる。▼9 レイヴァリの外光主義の作品は、ロワン河に掛かる橋を描いた一連の油彩に代表されている。彼は「グレーを訪れる画家は皆、作品の輪郭もしくは形態にそれ(グレーの橋)を採り入れるに違いない」と断言している。レイヴァリは、一八八三年から一九〇四年まで、合計十回以上、その橋を描いた。『グレーの橋』(図版8)と題された作品への画家自身のコメント。 私は特に河の絵を描いた。そこには、ひとりの男が小舟から、むこうのボートの幸せそうな二人の少女に向かって、手でキスを贈る光景が描かれている。はじめ『ゆきずりの挨拶』という題名をつけたが、何人かの画家がこの題名を類似の主題に使っていることを知り、私の作品は『グレーの橋』となった。▼10 オールダムのストット作『水浴』に触発されて、レイヴァリは河で夏の日を楽しむ人々の絵を構想した。小舟の男、パラソルをさし落ち着いた服装に身をつつむ女たち、そして橋、河の水に反映する風景。画家はすばやい筆さばきで、水面を瑞々しく描写する。ロワン河は次第に馴染み深いものとなり、後年レイヴァリはテームズ河に主題を移した。歓びに満ちた情景、陽光の処理、背景の木々のきらめき、それらは印象主義的である。同時期のグレーを描いた作品をもう一点。印象派的に処理され、構成的な画面をもつ『グレーのメイン・ストリート』(図版9)。伝統的な約束に従って画家自身を描いた作品かと言うと、そうではなくモデルはウィリアム・ラウダン Wiliam M.LOUDAN(1868-1925)。そして、グレーの橋を主題にした二作めの作品『桜の木のしたで』(図版10)、これはもともと『ロワン河のほとりで─午後の歓談』(一八八四年)と題されていたもの。レイヴァリの外光派絵画を代表する一点である。画面には桜の木のしたで男を待つ二人の少女と、その出会いの情景が描かれている。男は竿で小舟を操る。恐らく画家は、シュヴィヨン館の使用人をモデルに使い庭でポーズさせたに違いない。風景のなかへの人物の挿入は大胆で、筆致は奔放で変化に富む。その技法は前作『グレーの橋』同様、印象主義的であるが、木々の緑に若干灰色の色調と土の色が重なり、自然主義的な人物構成なども外光派の特徴をよく表している。人物・橋と水辺・草と樹の準備習作があり、いずれも自由な筆致のスケッチだが、この作品が綿密な構想のもとに組立てられたことが分かる。仕上げは習作に基づき、細部を整えてアトリエで完成されいる。小舟の男が、まるでマネの描く人物のように平面的な省略法で処理されているのに対して、一輪車に腰掛ける少女は綿密に描かれている。バスティアン=ルパージュを想起させる灰色の色調と、細部に拘るラファエル前派風の人物。表の批評実はこれらの特徴に批判的であった。「春を表現した作品なのだろうが、正直いって喜びや輝きが感じられない春の絵だ。」という厳しい意見も聞かれた。「注意深く描かれているが、冷たく風通しの悪い作品」という批評もある。この時期、レイヴァリに影響えお与えた画家はオマエラやストツトだが、写真のように緻密に描かれた画面、部分的に滲んだテクスチュアを施した灰色の色調を、彼はバスティアン=ルパージュから学んだ。柵囲いの所で男が少女に出会うという構想はルパージュの『村の恋人たち』から着想を得た。このルパージュの作品はレイヴァリが『桜の木のしたで』を制作する前年のサロンに出品されている。粗末な服装の少女が腕を伸ばしているポーズも、ルパージュの『ジャンヌ・ダルク』を想起させる。ルパージュが得意とした、人物の動作のある瞬間を捉える方法もレイヴァリは吸収したようだ。レイヴァリはルパージュに会っており、その時ルパージュは動きの一瞬を捉えるように画家に助言したと言われている。ただレイヴァリの作品にはルパージュの好んだ主題、農民に見られるレアリスムは感じられない。むしろ静かな雰囲気の漂う背景に、有閑階級の女性の佇む詩的な情景が彼の主要な関心事なのである。その好例が、やはり『グレーの橋』(図版11)と題された、こちらは批評家にも好評であった作品。グレーの橋をモティーフにした作品になかで比較的初期に属する前掲の作品(ふたつのボートがすれ違う構図の作品)に比べて、逸話を慎重に回避したものになっている。画面には、より印象派的な効果を狙い自由で力強い筆致が見られる。一八九〇年代のモネの作品にあるような、光と陰影の効果。レイヴァリは、快適な空気、静けさといったものの感覚を、エドワード調の優雅な雰囲気に包みながら、巧みに描き分けている。パラソルを持つ女性が河に反映する部分、明るく照らし出された水面が創る色のアクセント。同時代の美術雑誌『ザ・マガジン・オブ・アート』誌には以下のような批評が掲載された。「この作品の技術上の完成度は、実際注目に値する。澄んだ水の熟達した自由な描写。ボートに乗るご婦人が手に持つ白いパラソルの輝きを置いたキャンヴァスも、同様に賞讃の価値がある」。▼11 |
▼5 Exh.Cat.,The Irish Impressionists :Irish Artists in France and Belgium,1850-1914.1984,The National Gallery of Ireland,p.31.
(『アイルランド印象派展』カタログ、三一頁。本稿の多くの部分は、ジュリアン・キャンベル氏Dr.Julian Campbellに負っている。) ▼7 Kenneth McConkey, SirJohn Lavery R.A.1856-1941,Exh.Cat.,Uister Museum,Belfast,1985.p.10からの引用。
▼8 前掲『アイルランド印象派展』カタログ、六六~六七頁。 ▼11 Kenneth McConkey, SirJohn Lavery R.A.1856-1941,Exh.Cat.,R.a.1856 1941,Exh.Cat.,Uister Museum,Belfast,1985.p.58からの引用。 |
|
三、パリ 一八八九年-万国博覧会と外光派絵画 『パリ 一八八九年-万国博覧会におけるアメリカの芸術家』と題された展覧会が、一九八九年九月から一九九〇年七月まで米国を巡回した。フランス革命二百年を記念する催しが各地で開かれた一九八九年、九月二十九日から十二月十七日までヴァージニア州のノーフォークにあるクライスラー博物館で始まった同展は、一九九〇年二月一日から四月十五日には、ペンシルベニア州フィラデルフィアのペンシルベニア美術アカデミーで、五月六日から七月十五日には、テネシー州メンフィスのメンフィス・ブルックス美術館で開催された。タイトルにあるように、同展は革命百年を記念したパリ万国博覧会に出品された米国の画家の作品を追跡して、同時代のフランス美術から影響されたアメリカ合衆国の芸術の様相を多面的に辿るという企画である。世紀末のフランスとアメリカの親密な関係を、時間と空間を越えて蘇えらせるには、確かに万国博覧会という場の設定は極めて有効な手段に思われる。フランス政府が諸外国に、革命百年の万博への参加を呼び掛けた際、他の国々の躊躇をよそに合衆国はいちはやく、その招待に応じている。そして美術部門に限定してみても、出品点数は一八九作家、三三六点と多く、絵画は九〇点、六七作家である。『パリ 一八八九年』展には、合衆国内外にあって暫く陽の目を見ることのなかった油彩が展示されているが、自然主義的な色相が濃厚でアカデミックなそれらの作品類は、万博以来全く観衆の前に現れなかったものも含まれているようである。同展はペンシルベニア美術アカデミーの主催で開催され、カタログには以下五名の研究者による論文が掲載されている。主催のペンシルベニア美術アカデミーからは、ゲスト・キューレーターのアネット・ブラウグランドが「舞台裏では―アメリカ絵画の組織」という論題で、美術部門が組織される過程を明確にして、合衆国の文化行政に見られる複雑な戦術を明らかにしている。またパリ国立美術学校や私設アトリエで指導するフランス人画家からの影響を具体的に提示するのは、「国際的な傾向―アメリカ芸術の来たるべき世代」を執筆したニューヨーク市立大学教授のバーバラ・ワインバーグである。同展企画のチーフを務めるワシントン、ナショナル・ギャラリーのドッジ・トンプソンは、「パリ万国博覧会散歩―一八八九年パリ万博におけるアメリカ絵画のハイライト」で、展示計画を記号論理学的な立場から解析し、その美学的反響に関心を寄せ、カリフォルニア大学ロスアンゼルス分校教授のアルバート・ボイムは、「チョコレートのヴィーナス、『腐った』豚肉、酸っぱいワイン、そして料金表―万博のフランス・アメリカ風シチュー」という凝った論題の論考において、後の仏米関係に影響を及ばしたこの万博を、社会学的、政治学的な立場から分析している。ヴァージニア大学建築学教授のリチャード・ガイ・ウィルソンは、エッフェル塔に代表される万博の建築物が米国に与えた衝撃を例証している。 この展覧会には、十九世紀・魔ゥら今世紀初頭にかけて活躍した米国の画家のみならず、彼らに影響を与えたフランスの画家の作品が展示されているが、そのなかには、ジュール・バスティアン=ルパージュやレオン・ボナ、ウィリアム・プーグロー、ギュスターヴ・プーランジェ、ジュール・ブルトン、アレクサンドル・カバネル、カロリュス=デュラン、ジャン=レオン・ジェローム、シヤルル・グレール、ジュール=ジョセフ・ルフェーヴル、アルフレッド=フィリップ・ロールらの名前が含まれている。こうした世紀末のサロン画家の名前を列挙する際、彼らの傾向と留学生との関係の微妙な相違点を明確にする事が肝要である。彼らのある者はアカデミシャンであり、パリ国立美術学校の教授であり、アカデミー・ジュリアンやコラロッシという外国人留学生を入学させる私立美術学校(アトリエ)の教師であるが故に、単に技術指導という側面からのみ、絶えず引き合いに出される画家である。しかし、そうではない画家も何人かいる。ひとつは、万国博覧会のような建築・デザイン・装飾美術と密接に関連したところで仕事をした、歴史画家たち。彼らは博覧会建造物の装飾壁画を担当し、ある者は美術総監督の任を負っていた。留学生の憧れの的であるが、建築の施工主や国家、時には大衆の趣味にあわせてキッチュに堕落する画家もいた。そしてもうひとつ、サロン絵画を特徴づけていた外光派絵画の担い手と折衷様式の象徴主義者たちである。外光派絵画を代表するのは、自然主義の画家ジュール・バスティアン=ルパージュ、折衷様式の象徴主義者を代表するのは、寓意的歴史画家ピエール・ピュヴィス・ド・シャヴァンヌである。シャヴァンヌは留学時代の黒田清輝がコランの紹介により『朝妝』を持って面会した画家であり、藤島武二の模写でも知られているが、大正五年八月号の『美術新報』には特集が組まれ、大正十五年に斉藤与里の評伝が刊行されている。一方バスティアン=ルパージュについての日本での紹介は少ない。しかし、グレーで制作を続けた留学生にとって、ルパージュは最も重要な画家であったのだ。ブルトン、ジャン=シャルル・カザン、レオン・オーギュスタン・レルミット、アルフレッド=フィリップ・ロールそしてポール・アルベール・ベナールというフランス外光派の画家のなかでも、ルパージュは同時代の回想に最も頻繁に名前の挙げられる人物だ。彼はアトリエの教師をしていた訳ではないのだが、その作品は英国・アイルランド・米国など、一八八○年代を通じて諸外国の若い芸術家たちに、アカデミーの教師以上の影響を与えた。その芸術家コロニーは、ブルターニュ、グレー、スコットランドなど広範囲に及んでいる。ルパージュは恐らく一八七八(七九?)年から八二年頃ロンドンを訪れ、自作の展覧会を開催している。一八八三年のコンカルノー滞在は、ブルターニュ地方の若い芸術家を結集させ外光派に向かわせる牽引力となったに違いない。ルパージュは一八七七年の『干し草』で成功を納めたが、そこには、牧場に横たわる男女が細部に配慮された写実的な表現で描かれている。「絵画全体の色調は、明るい灰色・緑となること」を望んだ画家に相応しい、微妙な色彩。外光派絵画の代表的な作品である。彼の農民画で他に重要な作品は、『十月の季節』(一八七九年)、『乞食』(一八八一年)、『ジャック老爺(樵)』(一八八二年)、『村の恋人たち』(一八八三年)などで、前章で述べたように、これらは若い留学生、レイヴァリ、オマエラらに影響を与えた。①主題の選択。②彩色、例えば背景の細部を入念に描き、色彩を曇らせたり部分的にぼかしたりする油彩技法。③人物の姿勢や仕草。④特異な対象を小道具として挿入するといった、ルパージュ絵画の諸特徴を彼らは吸収した。「美は厳粛な真実てあり、右も左もなく中庸こそ正しい。」とは画家自身の言葉だが、実際ジュスト=ミリュー(折衷主義)の芸術家は、急進的なモダニズムと伝統を墨守するアカデミスムの間を行く中間的な立場を選択した。キャンヴァスの表面から絵筆の痕跡を排除した、光沢あるアカデミックな完成作を拒否したとはいえ、人物は常に背景と親密な関係に置かれている。印象主義の破壊的ともいえる筆致や大気の表現を応用しながら、一方で注意深く素描(油彩スケッチを含めた)による準備段階を怠らない姿勢。外光派の画家バスティアン=ルパージュは、まさにジュスト=ミリューの画家の持つ多様な側面を備えた芸術家であった。①ミレーやブルトンの農民画に見られるレアリスム。②クールベ風の記録性(ドキュメントとしての歴史画)。③カメラなど光学機器に対する、同時代的な関心。④ラファエル前派風の細部を誇張した表現などである。彼は、絵画の小道具に付随する意味の重要性を等閑視せず、衣服の細部に到るまで緻密に描写し、花々を入念に挿入させ、背景に咲く草花さえも丹念に描き分けた。フランス農民を登場させたルパージュ絵画の源泉のひとつには、ラファエル前派が挙げられるだろう。ジャンヌ・ダルクの亡霊を描いた作品は、ジョン・エヴァレット・ミレーの『アリエル(エアリアル)に誘惑されるフェルナンド』に想いを得ているに違いない。例えば主人公の特徴的な広い額など。また『干し草』に見られる、地面にべったりと腰を下ろす姿勢、そして高い水平線はもちろん同じミレーの『盲目の少女』に呼応している。アーチボルド・ハートリックArshibald S.HARTRICK (1864-1950)は、ルパージュについて以下のような証言をしている。 三十六歳という、芸術家にとっては不吉な年齢でのバスティアン=ルパージュの死、加えて、最近パリで開催された没後の回顧展、それらはヨーロッパのほとんど全ての若い画家に深い影響を及ぼした。あらゆる国々で、前途有望な若者の大半が彼の作品を素直に手本にした。戸外で見たままの自然を精密に再現するという、窮極的な理想をもち、芸術家の制作中に、その効果が損なわれることのないように、全ては灰色の光のなかで斑点のように彩色される。こうした昼間の大気との取り組み方に対して、ボン=タヴェン派の若人たちの多くは、その巨匠(バスティアン=ルパージュ)を模倣することに、幾分無益な反抗を行った。▼12 一八八九年と一九〇〇年の万国博覧会は、フランス第三共和政の孕む、科学技術に対する楽観的な進歩主義を象徴していた。ミリアム・レヴィンが『十九世紀末フランスに虫ける共和政体の美術と思想』(一九八六年)(註 Miriam R.LEVIN,Republican Art and Ideology in Late Nineteenth-Century France,U.M.I.1986.)でいみじくも述べているように、パリ万博の象徴となった建築物エッフェル塔(図版12)は、ルネサンスやバロック建築に見られる観者と建物の関係を断ち、作為的な三次元空間に誘うための建築固有の連続性を排除して、あたかもビザンチンのイコンのように、天界に向けられた窓として永遠の中空に浮かぶのである。それは孤立したひとつのオブジェであり、遠くにありながら近距離にあるよう目に映るオブジェとなった。科学技術は建築に匿名性を与えたのだ。この時代に登場したふたりの画家、シャヴァンヌとバスティアン=ルパージュが、その楽観主義に真っ向から異議申し立てを行った芸術家であった事実は、非常に興味深い。そして、その時代にパリを訪れた留学生がパリのアトリエ(アカデミズム)に幻滅し、グレーという祖国の田園に類似した場に逃避したのもまた事実であった。技術を学ぶ学生が芸術に目覚めた場所。それが、グレー=シュル=ロワンである。浅井忠の『グレーの洗濯場』(図版13)は、カール・ラーションの『ロワン河のほとりで』(図版14)と同様、国際的な外光主義のコンテクストに照らした時、新鮮な驚きを再び観る者に与えるに違いない。カール・ラーション画集の編者は以下のように、グレー時代を評価している。「カール・ラーションの生涯における決定的な転機は、社会的にも芸術家としても、グレー=シュル=ロワンという小さな村で起こった。そこで彼は非常に素朴なモティーフの水彩画を描いた。例えば、かぼちゃの苗床やキャベツ畑、そして野良着の老人や老婆である」。▼13 この村を訪れた芸術家たちの記憶から、シュヴィヨン館(図版15)が消え去ることはなかったであろう。グレーは、外光派の絵画に観られる束の間の輝き、懐かしい光景として、それぞれの芸術家によって定着されたのである。 |
▼12 前掲『アイルランド印象派展』カタログ、九二頁。 ▼13 Gorel Cavalli-Bjorkman,Bo Lindwall,(English Translation by Allan Lake Rice,Ph.D.),The World of Carl Larsson,1982,SanDiego,CA.,U.S.A.,p.12  (図15)カール・ラーション『シュヴィヨン館』一八八四年 挿絵 |