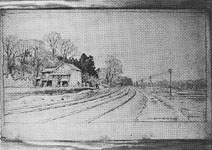主題としての駅
──鹿子木孟郎「津の停車場」をめぐって
荒屋鋪透
|
一、 鹿子木孟郎(かのこぎ・たけしろう)の描いた『津の停車場』は、個人的な想い出の託された一枚の習作に過ぎないが、その絵の中には、日本が本格的な近代化を押し進めた明治三十年代の「現実」が奇しくも定着されることになった。この備前池田藩士の末裔は、西欧の文化に対して旺盛な知識欲を持つ明治期の青年らしく、パリで油絵を学びたいという大望を内に秘めながらも、旅費を工面し外国語を修得するために、まず堅実に三重県津市の尋常中学校に就職している。長兄の勤めていたという縁で津の中学に勤務することになった画家は、その中学の校長から英語の手解きを受けている。鹿子木孟郎の生涯において津への赴任は結果的に、官費留学など望むべくもない一地方教員が、西欧に旅立つための布石のひとつとなるのだが、いま少し視野を広げてみると、洋画家を志す岡山県出身の青年が三重県に赴任したことと、津で新婚生活を過ごした図画教員が新妻を写生した場所は「駅舎」であったという事実の背景には、日清戦争と日露戦争の間にある「臥薪嘗胆」の近代日本の姿が見え隠れしている。 当時、明治日本は日清戦争で軍事的には勝利を得ていたものの、ドイツ、フランス、ロシアの三国干渉にあい、旅順、大連という軍事的要衝を抱えた遼東半島の還付を強いられた。明治政府はこの時期初めて、帝国主義時代の厳しい国際社会の現実を思い知らされたのである。この三国干渉を契機にして日本国内では「富国強兵」、「臥薪嘗胆」という言葉と共に、近い将来の対露戦に備えて、日本社会を帝国主義的に再編成するため、戦後経営の四つの基本方針が固まっていく。即ち軍備拡張、殖産興業、教育改革、植民地領有である。軍備拡張には慎重な立場をとっていた財界においても、金融資本を中心にして資本主義の論理と帝国主義体制の確立を抱き合わせて論じる傾向が強固になり、明治三十年代に入り、従来は鉄道株として投機の対象にしか考えなかった鉄道を国有化させようという、鉄道国有論も論議されるようになった。後に、日露講和条約が批准された年の明治三十八年、西園寺首相は閣議に「鉄道国有の要旨概要」を提出し、以下の様な提言を添えて鉄道国有法の即時成立を促している。 鉄道ノ国有統一ハ戦後経営ノ急務ニシテ、其ノ断行ハ実ニ財政経済軍事等諸問題ノ乱麻ヲ断ツノ快刀タリ・・・▼1 この言葉は資本主義揺藍期の明治日本にとって、いかに鉄道政策がその要であるのかを率直に語っている。日本の近代化は何よりもまず鉄道建設によって実現されてゆくのである。 『津の停車場』を描いた本人は意識していなかったのであろうが、その習作は日本近代洋画史上、「駅舎」もしくは「鉄道」を主題に採った最初期の作例のひとつとなった。というよりもむしろ、数少ない作品の一点であるといえよう。三代広重の『横浜海岸鉄道蒸気車図』(明治六年頃)や、芳圀の『京坂名所図絵・大阪梅田ステンション気車之図』(明治十八年)(図1)といった、文明開花風俗の浮世絵を除くと、明治三十三年、鹿子木孟郎の後任として津に赴任した赤松麟作(あかまつ・りんさく)の『夜汽車』(明治三十四年)(図2)や、第三回文部省美術展覧会(以下は文展と略す)において三等賞を受賞した、高村真夫(たかむら・まさお)の『停車場の夜』(明治四十二年)(図3)、同じく第三回文展に出品され、来日中のバーナード・リーチに激賞された、山脇信徳(やまわき・しんとく)の『停車場の朝』(明治四十二年)といった作例は知られてはいるものの、明治から大正、昭和前期にかけての日本近代洋画において、駅や鉄道が画題として登場することは極めて稀なのである。もっとも、これは近代日本についてばかりいえることではない。当時、日本の洋画家が留学してみたいと憧れ、また美術の国であると憧景していたが故に、いろいろな点を手本にしていたフランスにおいてさえも、事情は似たり寄ったりであった。十九世紀後半のフランス絵画においても、鉄道や駅という主題は珍しい部類に属する。というよりも珍しいが故に、いくつかの駅舎の連作を描いたモネのみならず、サロン画家でさえも、その主題の意外性を狙って、駅を採り上げたのであろう。(図4・5)確かに、印象主義の画家たちは、自分たちの身の周りに起こりつつあった現実を、積極的に画面に定着させていた。モネが一八七七年にパリのサン・ラザール駅構内で描いた一連の作品(図6)は、「駅舎」を主題にした代表的な作品であろう。駅舎を主題に採り画面を構成する場合、画家はその駅舎を強烈に意識させるものを観者に提示しようとする。さすがにマネは汽車の車体を描くことなしに、その巨大な鉄の固まりが吐き出す蒸気や煙と、軌道に設けられた鉄柵を構図の中に組み込むことだけで、鉄道駅の雰囲気を存分に味わせてくれていたが、(図7)モネもサン・ラザール駅連作を制作するにあたって、明らかにこの印象派の先駆者の作品を意識していたに違いない。駅舎を強く主張する媒体、それは剥き出しの鉄骨である。十九世紀後半の都市には、鉄道駅のみならず、いろいろな空間を鉄骨が支え始めていたのである。カイユボットが『ヨーロッパ橋』(一八七一年)(図8)の構図の中に、大胆に鉄骨の架橋を挿入した際にも、画家は、その形の効果を狙っていたに違いない。明治三十年代の日本の空間の中に鉄骨が組み込まれたのも、鉄道という媒体が生活の中に入り込んできた後のことである。鹿子木孟郎の小品でも、黒い剥き出しの鉄骨が絵の中心を横切っている。この時代、多くの女たちはまだ髪を髷に結った和服の婦人を挟む様にして、画面の三分の一を占めている。 |
▼1廣岡治哉編『近代日本交通史』昭和六十二年四月 法政大学出版局 七〇頁 |
|
二、 鹿子木孟郎は明治三十一年三重県津市で、駅の架橋の上に一人後ろ姿の女が佇む、一点の油彩を描いた。絵の中の女は髪を髷に結い、地味な灰色をした羽織の身八つ口から長着の緋の袖を覗かせた処は、何処かいじらしく、右を向いた態の首を、少し振り返る様にして左に傾けながら、遠くを眺めやる仕草などは、とても可愛いらしくさえ感じられる。彼女の視線は、軌道が水平線に消える辺りに注がれている。あっさり彩色されていながら、丁寧に描かれた人物に比べると、風景は至極大雑把に扱われており、その事から、このオイル・スケッチ風の絵が、注文によるものではなく、画家の私的な生活を記録したものであるだろうことが推測される。昭和九年十一月、鹿子木孟郎画伯還暦記念会 画集編碁委員より上梓された『不倒山人 鹿子木孟郎画集』(以下は『還暦記念画集』と略す。)には、新婚時代の画家の妻を描いた作品が二点載っている。一点は水彩で、手拭を被り襷がけに素足という、勇ましい格好の画家の妻、春子が箒とはたきを携えて襖に凭れているところ。左手を襖に掛け、右足を爪先立ちにして重心を左足に移した気楽な姿勢の微笑ましい作となっている。(図9)そして、あと一点の油彩が件の後ろ姿の婦人像である。『還暦記念画集』では、二点とも題名は「春子」となっている。僅かばかりの月給の半分を郷里岡山の家族に送り、一家を背負って立つ身であるとはいえ、月俸参拾圓の図画教諭として、鹿子木孟郎は津で平穏な日々を過していた様である。彼が結婚して未だ、間もない頃に描いたと思われる、駅の架橋に佇む後ろ姿の婦人像の題名は、『還暦記念画集』によると「春子」である。ただ、本作品を家族の肖像としてだけではなく、駅という主題の内包しているいくつかの問題について考察する本稿においては、あえて『津の停車場』という題名を小品に付け話を進めたい。 本作品は暫く、カンヴァスの四隅を画鋲でとめて、木の板に張られ保存されてきたが板には以下の様に墨書されている。 明治三十一年三重県津市停車場ニ於テ (図10) 鹿子木孟郎がアメリカを経て、パリに留学したのは、明治三十四年秋の事であるからこの油彩は、彼が初めてヨーロッパの土を踏む三年程前に描かれていた。西洋の都市とその建築、広場と建物を飾る彫刻や絵画という、いわば芸術家にとっての西洋の現実を、実際には観てはいない青年がものした作品にしては、驚く程新鮮な感覚で構図が決められている。絵から人物をそっくり抜いてしまうと、画面は、空の部分の幅でまず五等分されている事が分かる。この中に更に女を加えてみると、今度は縦に、鉄道のレールが水平線に消える地点と、やはり、ぎりぎりいっぱい水平線に掛かる、女の髷の中心線までに丁度三等分されている。勿論、線遠近法の消失点は、軌道の終点なのだが、描かれた女の着物がもりあがっている部分、つまり御太鼓の帯によつて羽織りにできた起伏の頂点が、まさに絵の横軸になっている事も見逃せない。この時代のスケッチ帳には、恐らく春子をモデルにしたであろう後ろ向きの婦人が描かれている。(図11)画家は彼女を二度後ろ姿で描いている訳だが、『津の停車場』においては、春子が後ろ向きであることと、その視線が背景の消失点辺りに注がれていることによって、この絵を見る者の視線を自ずと架橋の鉄骨、鉄道の軌道、汽車や倉庫といった点景を越して、人物の前面に広がる空間へと向かわせている。 後に、浅井忠の後任として関西美術院長となり、京都と大阪に、私立の画塾「アカデミー鹿子木」を創立して、多くの後進を育てた、関西洋画界の重鎮も、この時末だ、旧制中学校の教員に過ぎなかった。鹿子木は、明治二十九年九月より同三十二年五月まで、三重県尋常中学校(現在の三重県立津高等学校)に勤務している。当時の職員一覧表には、 職名「助教諭」、資格「東京市立不同社卒業」、「図画」、貴族「岡山県士族」、氏名「鹿子木孟郎」、就任年月「二九・九」▼2 後に鹿子木孟郎は、昭和十年十一月一日に三重県立津中学校で催された、同校の「新校舎落成 創立五十五周年記念」行事の一貫であった記念講演会において、以下の様な講演を行い津時代の想い出を語っている。その講演会記録は、昭和十一年一月発行の同校の『校友会雑誌』第七十四号に掲載された。この記録は、津時代の鹿子木孟郎を知る上で、非常に重要なものであると思われるので、ここにその一部を引用し、本稿末に全文を資料として添付したい。 その時居た津と、今の津とを考へ合せると感慨無量なるものがります。一度、大正九年頃、一寸伊勢神宮に参りました時に、二・三時間汽車を降りて、阿漕浦の方まで行った事が有りましたが、暇が無かったから本校へは立ち寄りませんでした。それから津に参ったのは今日が始めてゞす。大正九年以来十五年目になります。 私が本校の職を退いて以来三十九年になります。私は色々な意味に於いて特に本校と関係が深いのであります。私の来る前に、私の兄が本校に奉職して、舎監を二年程勤めて居ましたが、病気になりました。その時私は東京に勉強して居りましたが、その見舞に一度参りまして、次いでこの津で兄の葬式を出すことになつたのであります。それから東京に帰ってゐますと山崎校長から急に来いと言ふことで、来て見ると、こゝの先生をやらぬかといふ話。遂にお世話になつたのであります。・・・中略・・・ 本校は明治十三年の創立で、私は本校創立十五周年記念式には兄の関係で参列することが出来たのでありました。私の居ります間の校長先生は山崎先生、久田先生、秋山先生でした。 先程パーレーの万国史といふのがお話に上りましたが、実を云うふと私は貧乏士族の子弟で、、 高等小学校を卒業するとすぐ、学資が無いから親から自分で資を得て卒業しろと云はれました。小学校に於て僅かの語学・僅かの漢簿・英語・地理を学んだゝけであります。さういふ訳で中等教育を受けてゐない自分は、この津にゐる間に何とかして無教育を取り返さうと思って、図画を教へる合間々々に、秋山校長にパーレーの万国史を学んだのであります。私はどうせ絵をやる以上は外国語の力が出来たら是非一度フランスに行きたいと思つてゐました。 三十二年に本校を辞し、埼玉県の浦和師範に奉職致しました。之は東京に近かつたからです。 文中パーレーの万国史とあるのは、Peter PARLEYのUNIVERSAL HISTORYのことである。同じ「創立五十五周年記念」で演説した同校卒業生の文学博士、紀平正美の講演からも分かるように、(前掲誌 七七頁~八二頁)明治三十年頃までの中学校の教科書はパーレーの万国史やモレーの地理学、ロストーの化学というように、まだ翻訳されていない英書に限られていたのである。生徒は全ての学問を英語によって学び教師もまた英書を基に指導に当たった。当時の中学校は非常に高い水準の西洋の学問を教授していた。鹿子木孟郎もまた図画を生徒に教える傍ら、自らも山崎旨重校長より英語を学んだ。 三重県尋常中学校での鹿子木の前任者は、藤島武二である。津時代の藤島武二については、陰里鐵郎氏が『没後四十周年記念 藤島武二展』カタログにおける論文「藤島武二 その生涯と芸術 前半期の藤島武二」(昭和五十八年四月)の中で、詳しく述べられているように、三重県尋常中学校の、図画助教諭 藤島武二に対する待遇は、悪いものではなかったらしく、月俸二拾三圓という額も、助教諭では二番目に高いものであったという。こうした図画教師の招請と優遇措置の背景には、明治二十七年に、第二次伊藤内閣の文部大臣となった井上毅が行った教育改革に伴う、三重県尋常中学校の学科課程の改訂と人事面における移動があった事は無視出来ない。この教育課程の改訂によって、明治二十八年から実地されたいた入学試験には、明治二十七年九月施行の文部省令第二十四号によって、新たに理科、図画、体操そして体格検査が増科されたのである。ところで『津市文教史要』(津市教育会編 昭和十三年五月)には、三重県尋常中学校は明治十三年に開設され、幾度か学則と校名を変えて今日に至ったことが記録されている。鹿子木孟郎が勤務していた明治三十年前後にも、教育課程の改訂と校名の変更がおこなわれた。 本市に於ける中等教育機関の発達を見るに、明治十二年の通常県会に於ける議決に基づき、翌十三年一月旧津藩有造館内に開設せられたる津中学校を似てその嚆矢とす。爾来学則の改正等により、校名に於いても、教育内容に於いても、数度の変革を経て、以て今日に至れり。即ち明治十九年には新町古河に校舎を新築して移り、翌二十年三月には三重県尋常中学校と改称し、三十二年三月三重県第一尋常中学校、同年四月三重県第一中学校、三十四年五月三重県立第一中学校と逐次改称し、大正八年八月に至り三重県立津中学校と称することゝなれり。又生徒数の逐年増加するに伴ひ、校舎の狭隘を告げたるため、市内新町大字刑部(おしかべ)に新校舎を建設し、その成るに及び手て昭和九年四月を以て移転せり。即ち現校舎なり。▼4 藤島武二と同じく山崎旨重校長に招致された、鹿子木孟郎の助教諭としての月俸は二拾五圓であった。 明治二十八年(二十九年の誤り 筆者註)三重県の山崎旨重校長に撰れて津中学校に転任し月俸二十五圓を給せられる久田督 秋山正儀(正義の誤り 筆者註)両校長に暦用せられて中学校教諭に登用せられ月俸三十圓を受くるに至り妻を迎へ一家を津市になせり時に余が年二十四歳 と鹿子木孟郎の自叙略伝『回顧五十年』(大正十三年六月)に記されている。彼は三重県尋常中学校に助教諭から教諭に昇進して、月俸三拾圓を与えられ、津で同郷の人、春と結婚している。明治三十年十一月十三日に撮影された、結婚当時の初々しい二人を写した写真が残っているが、裏面には墨で 明治丗年拾一月十三日写 ・・・前略・・・ほかには、現在藤島家に残されている二葉の写真があり、そのいずれも写真舗・佐藤三八製、津市地頭領町と台紙にあり、その1枚は明治26年撮影となっている。1枚は横向きの肖像、いま1枚は展示場を背景とした9人の群像写真で、背景が実景か書き割りかは不明である。(陰里鐵郎「藤島武二・その生涯と芸術前半の藤島武二」) さてここで、『津の停車場』を描いた画家の生立ちを概観して、津に至るまでのその修業時代の足跡を辿ってみたい。 |
|
|
三、 鹿子木孟郎は、明治七年(一八七四)十一月九日、備前の国、岡山県岡山市東田町に生まれた。父は池田藩士 宇治長守、母は志奈といった。孟郎は満七歳の頃、伯父の家を継ぎ鹿子木を姓としている。この辺の事情について『回顧五十年』には以下の様に記されている。 余八歳の時父商業に失敗して資産を失し恩兄は直ちに小学校教員となり薄給家を支ふるの止むなきに至れり余はこの時余が伯父の家の正に断絶せんとするを相続して鹿子木姓を冒せり▼5 明治十九年、岡山高等小学校を卒業した孟郎は、長兄宇治益次郎の尽力により、明治二十一年、画家を志して岡山師範学校の図画教師であった、松原三五郎の画塾「天彩学舎」に入学している。満十四歳の春である。天彩学舎時代の作品では、水彩の『野菜』などが残されているが、いずれも画家の早熟な才能を示す実例となっている。身近にあるものをモティーフにした、これらの習作類からは、確実な写実の技巧と共に、この年代の少年にしては稀な程、おおらかな写生の精神が伺える。(図12) 明治二十三年三月、師の松原三五郎が大阪に転任したため、鹿子木は東京に遊学することを決心した。東京では『裁判医学雑誌』を出版していたという雑誌社に勤務しながら、画業に励んでいたが、脚気病にかかりやむなく帰郷している。二十三年四月から僅か三箇月の東京生活であった。しかし郷里で静養した後の明治二十三年十月、友野晋の推薦を受けて、彼は岡山中学校予備校の図画教員となっている。この頃、自宅に洋画研究所を開き、就学を希望する者の指導を行ったりした。後に自ら京都と大阪に開設した「アカデミー鹿子木」画塾の構想は、既にこの時期に芽生えていたのであろうか。 明治二十四年十月、鹿子木は肖像画家として初めての旅行をしている。行く先は岡山県内、香川県、徳島県であった。この旅行に先立ち、明治二十四年秋に岡山中学予備校の職を辞している。未だ十七歳の孟郎が年長者に見える様にと、両親は彼に山高帽子に黒紋附きの羽織という出で立ちをさせたという。肖像画家と称して歩いたこの旅行の目的は、絵画の研鑽ともう一つ、描いた肖像画を売り東京に遊学する資金をつくることにあった。実際郷里を出発した時、懐中には六拾銭しかなかったという。津山では竹林源之助、讃岐では瀧豊三郎宅に泊まり、徳島から大阪を経て十八歳の秋に帰郷した。再び東京に遊学するためである。この時家族は私財を抛って孟郎に応援した。既に当時東京にいた長兄宇治益次郎の周旋から、河上謹一、杉浦重剛の知遇を得て、明治二十五年十一月から二十八年六月まで、小山正太郎の指導する「不同舎」に学んだ。この不同舎時代に鹿子木孟郎は、東京とその近郊の景色と風俗を描いた、多くの素描作品を残しているが、それらの習作は、不同舎の教授法を知るためのみならず、当時の画家の意外な程広い行動範囲や、明治二十年代の東京の姿を知る上で、非常に貴重な資料となっている。(図13) 不同舎在学中に二十歳になったので、彼は文部省の洋画科検定試験を受け首席で合格している。文部省中等教員図画科免許状を得たのは、明治二十八年四月である。この間、孟郎は長兄宇治益次郎を亡くしている。前掲した講演録にあるように益次郎は津で逝去した。家族の誰よりも孟郎を愛し、画家になることを勧め、経済的にも援助してくれた兄の死は大きな打撃であった。彼は兄に代わって一家の大黒柱となった。明治二十八年六月、杉浦重剛の紹介で滋賀県彦根中学校に助教諭として勤務したのも、岡山に残された家族に送金するためである。滋賀県の図画教員の月俸は拾七圓。彼はうち拾圓を郷里岡山の両親に毎月送金している。英語を教授してもらうことの出来る校長のもとで働くこと、そしてより良い待遇を求めたからであろうか、鹿子木孟郎は明治二十九年の夏、長兄益次郎の上司でもあった山崎旨重校長の招きに応じて、三重県津市に赴任することになった。 |
▼5 鹿子木孟郎『自叙略伝回顧五十年』大正十三年六月 |
|
四、 滋賀県彦根から三重県の津に来るには、彦根から草津までを東海道に乗り、草津から亀山を関西経由して津に至るのである。明治二十九年の夏に、鹿子木孟郎もまたこの様にして津に来たのであろうか。あるいは、四国の旅路を徒歩でこなした健脚の彼にしてみれば、彦根から津への旅路くらいは歩いてきたのかもしれない。ともあれ、東海道線(新橋-神戸間)が全通したのは明治二十二年(一八八九)七月一日のことであり、既に同二十一年、三重県四日市浜田に設立されていた関西鉄道株式会社が、難工事であった揖斐川鉄橋の架設に成功したのは明治二十八年で、この鉄橋の完成によって草津─名古屋間は鉄道で結ばれていた。関西鉄道は、後に参宮線となった亀山─阿漕間を明治二十四年八月二十日に開通させていたので、鹿子木孟郎は無事上記の行程で、彦根から津に鉄道を利用して赴任することも可能だった訳である。 日本の鉄道史上、明治三十年前後の時期は、明治二十年前後の官設鉄道による幹線に対して、民営鉄道による支線の建設が積極的に進められた、謂わゆる「第二次鉄道建設時代」にあたっている。三重県でも明治二十一年十二月に創立された、参宮鉄道株式会社が、阿漕─宮川間を明治二十六年十二月三十一日に、宮川─山田間を同三十年十一月十一日に開通させた。(『三重県史』昭和三十九年三月 三四七頁)関西鉄道や参宮鉄道といった民営鉄道業は、日清戦争後の好況期に銀行業、紡績業と共に資本家の投資の対象となったのである。関西鉄道と参宮鉄道の最大株主は三菱財閥であった。もっとも三菱にとっては、三重県の両鉄道への投資は、単に配当目当ての株式所有であったのに対し、山陽、九州、筑豊の各鉄道の支配は、「財閥化への道を歩み始めた三菱の石炭業の経営と密接な関連のもとに行われたものであった。」(廣岡治哉編『近代日本交通史』昭和六十二年四月 法政大学出版局 六四頁)つまり、近代日本の経済構造の変容に決定的な役割を果たした鉄道網が、全国規模で整備されてゆくのは明治三十年代のことなのである。この時期日本は、封建的経済を支えていた陸路、海路の交通網と訣別して、全く新しい交通機関である「鉄道」を経験することになった。ここで注意しておかねばならない事は、産業、経済の変革には奇与した鉄道に対して、その鉄道が敷設されることになった地方の人々は、必ずしも当初から鉄道を歓迎したわけではないという事実である。三重県の場合でも、津や松阪などでは参宮客の素通りを恐れての反対運動があった。(『県政百年記念画報』三重県 昭和五十一年四月 九六頁)そして、鉄道という現実が自然の中に挿入されることによって、人々は「自然」を新たな目で見詰めるようになるのである。 ひとつには、鉄道敷設工事によって造られた「人工的な景色」というものがある。鹿子木孟郎の『津の停車場』もそれを表現したものであろう。既に一八七六年(明治九)九月二日号の『イラストレイテッド・ロンドン・ニュース』には以下の様な日本通信と共に、「大阪・神戸問の日本の新鉄道近辺の光景」という挿絵が掲載されている。(図14) ・・・前略・・・大阪という大商業都市は、・・・中略・・・今では昨(明治八)年五月に開業した鉄道によって神戸の港とされている。この線路はさらに琵琶湖沿岸を通って、西海岸の敦賀に近い地点まで北上する予定になっている・・・中略・・・三つのトンネルがあるが、そのひとつは芦屋川の下をくぐるもので・・・中略・・・日本における煉瓦製造及び組立工事のうちでもっとも立派なものだ、と称賛されている。(中略)神戸から武庫川に至る間では、土地の干拓や人工灌漑が行われたが、そのため二〇八カ所の溝橋(カルヴァート)が必要になり、軌道一マイル当たり三〇カ所もこれを敷設した。最後のトンネルを過ぎると、線路はまったく趣を異にする田舎にはいる。山々は京都に向かって北東方向に広がっており、ある深い切通しのところから、線路は低く横たわる稲田を貫く堰堤に向かって進む。▼6 あとひとつは、鉄道の敷設によって眺めることの出来るようになった「省みられる事のなかった自然」である。いや、改めて眺められるようになった自然とでも言うべきだろうか。つまり画家や文学者が鉄道を利用して十九世紀的な「観光旅行」を試み、その体験を紀行文学や写生文、水彩画などに定着させたところの「自然」である。車窓からの景色も、汽車が導いてくれる田園も然りである。フランスでは早くもミレーやコローが、一八四〇年代までには開通していた鉄道を利用して、田園風景の本格的制作に取り掛かり、謂わゆるバルビゾン派と呼ばれるに至る。美術史のみならず、「自然と芸術作品」との係わりは、十九世紀後半の文芸学上最も重要な課題のひとつになった。勿論、近代科学の出現する以前にも「自然と芸術作品」との営為は存在していた。しかし近代科学が、それ以前には想像のつかない程に自然環境を変貌させた十九世紀にあっては、この問題は多角的な議論の対象となり始めたのである。例えば自然主義文学運動の場合、その尖鋒となったフランスでは一八五八年、イポリート・テーヌがバルザックをナチュラリストと呼び、エミール・ゾラが小説『テレーズ・ラカン』(一八六七年)の序文において自然主義を提唱して以来、この用語は科学的精神に基づく実証主義を文芸学上代弁してきた。ゾラは続いてその膨大な長編小説群『ルーゴン・マカール叢書』のなかで、ある遺伝的因子を持つ動物を一定の環境の下に置いた場合、ほとんど間違いなく予想された行動パターンをとるという、実験医学の成果を人間世界の表現に応用した。この自然主義を更に、近代化学によって拘束された環境における精神の自由という、十九世紀から二十世紀にかけての文芸学の窮極の目的に発展させたのは、何人かの北欧の劇作家たちである。彼らが扱うのは主に最下層の人間群像であり、遺伝因子は具体的に精神異常や分裂病として記録され、ロマン主義的な色合いの濃い北欧神話を「夢」といった象徴主義的なテーマとして挿入させながら、現代の真のヒーローである「アンチ・ヒーロー」を舞台の全面に登場させた。ストリンドベリは一八八八年の『令嬢ジュリー』序文のなかで、ひとりのアンチ・ヒーローをひとつの近代的性格にまで凝縮させた。 少なくとも、前の時代よりは急激でヒステリックな、この過渡期に生きる近代的性格として、私の描いた人物は動揺的であり、分裂的であり、古きものと新しきものとの混成物である。その上、近代的観念が、新聞紙や談話を通じて、田舎に生活する層にまで滲透していることも、けっして不思議ではないと思う。・・・中略・・・ジュリー嬢は一個の近代的性格である。▼7 日本の近代文学の場合、自然主義ないし写実主義を近代文学の確立に貢献した文学運動の本流として概観することは、今日では寧ろ皮相な選択であるかもしれない。何故ならば日本近代文学には、西洋文学史を縦貫している古典主義とロマン主義の伝統が欠落しており、明治浪漫主義にしてもその全体像は、翻訳文学に基づく象徴主義の散文を始めとして、日本古典を採り入れた王朝趣味の詩歌、耽美的な官能小説など、まさに同時代の世紀末文芸を反映した様相を呈していたからである。既に昭和二年、日夏耿之介は「自然主義的なる詩歌の発生」という一文のなかで、 自然主義時代には主唱者にも攻撃者にも双方に矛盾があった。・・・中略・・・その中で興味のあるは、森鴎外、上田敏、夏目漱石三人のこの派に対する態度であった。・・・中略・・・反自然主義的態度に出た鴎外が、自然主義的なる詩歌の始祖であったのは皮肉である。▼8 と自然主義の多義性を指摘している。ともあれ今ここでは、この時代の自然主義論争の展開には目を向けずに、一般に自然主義的なものであるとされる作品に共通する自然の扱い方に注目すべきなのかもしれない。例えば国木田独歩の『武蔵野』(明治三十一年)や徳富蘆花の『自然と人生』(明治三十三年)、島崎藤村の『千曲川のスケッチ』(明治三十三年~)には、東京という都会において挫折を経験した失意の主人公が、その空虚な生活から離脱し、東京の郊外や地方に漂泊しながら、自然との遭遇、対峙、対話を通して知らぬ間に自己を再発見してゆく過程が克明に記録されている。作者は風景を描写することで人間の内面を表現している。前述した文学作品が皆明治三十年代に著されたのは単なる偶然ではない。明治三十年代には文学者が地方に逃れる手段が整っていたのである。即ち鉄道と駅である。駅舎は文字通り、人生再出発の場となった。 確かに、『自然主義文学の背景』のなかで瀬沼茂樹が「日本の自然主義が二十世紀の初め十年間の運動であったということは、注意されなければならぬ。」と指摘したのは慧眼である。二十世紀の初め十年間とは、凡そ明治三十年代を指す。小杉天外が『はつ姿』(一九〇〇年)において「写実主義宣言」を表し、島崎藤村の『破戒』(一九〇六年)や田山花袋の『蒲團』(一九〇七年)がその写実(自然)主義を鮮やかに実践して、正宗白鳥の『何處へ』(一九〇八年)と岩野泡鳴の『耽溺』(一九〇九年)へと引き継がれ、最盛期を迎えた観のあった自然主義も、はや明治四十二(一九〇九年)には、『スバル』の創刊や前年に創立された「パンの会」の反自然主義に脅かされることになった。森鴎外、夏目漱石の文壇における活動が活発になるのも明治四十年代のことである。 では明治三十年代の自然主義の萌芽、開化、成熟の背景には、いかなる明治日本の知的状況があったのであろうか。瀬沼茂樹は前著のなかで、フランス民法ではなくドイツ民法を規範にした、旧民法の前近代的家族主義が規定した当時の「家」の在り方について触れ、明治憲法と教育勅語と共に、帝国主義に貢献した旧民法の功罪と文学への影響を論じているが、(瀬沼茂樹『近代日本文学の構造 一 明治の文学』集英社 昭和三十八年三月 二〇一~二〇八頁)美術史の同時代を知るものには、石井柏亭が『日本絵画三代志』(昭和十七年)のなかで述べた、以下の指摘を無視する訳にはゆくまい。 文学の写実主義、自然主義と美術の方のそれ等とを比較して見るのも面白いことであるが、・・・中略・・・ゾラやフローベールやモーパスサンなどの影響は早く藤村の短篇(例へば「明星」に於ける「藁草履」など)や、小杉天外の「はつ姿」などにもあらはれて居るだろうが、黒田の齎したやうな写実主義、見たまゝの自然を作為なしに其のまゝに写すやうなことは二十年代の文学には無かったのではないか。無論美術と文学とでは領域が違ふから其の比較も困難ではあるが、西洋美術の新潮を全面的に入れて其の目で日本の自然を見直したと云ふことに於ては、洋画の新派が文学よりも一歩を先んじたと云へるかと思ふ。▼9 明治二十六年夏の黒田清輝の帰国は、続く世代の芸術家にとって、明らかにひとつの分水嶺となった。「外光主義」的なものの見方、換言すれば二十世紀的な芸術家の「自然」への態度、姿勢を黒田は齎したといえる。それは彼がフランスから移入した最も重要な収穫物である。土方定一は『島崎藤村の「水彩画家」に関連して』という一文のなかで、黒田に続く世代、白馬会に集った外光派の風景画家のなかから、とくに三宅克己を採り上げて、明治三十年代の自然主義作家と外光主義画家との共通の地平を論じている。この辺りの岡題は新帰朝者三宅克己と、やはり同時代のフランスに留学して帰国した鹿子木孟郎との有名な「水彩画論争」や、自然主義と外光主義との関連といった点を絡めて、明治期の文学・芸術を考察する上で極めて興味深い論争の森を形成する地点なのだが、本稿では土方氏の指摘を引用するにとどめ、筆者の今後の課題にしたい。 歴史画のうちに内容、形式とも窒息しつつあった明治二十年前後のわが国洋画と対立的位置にある三宅克己のバルビゾン的情熱と、硯友社文学と対立している『千曲川スケッチ』の島崎藤村のうちに上述したような共通の同時代人としての外光への歓喜をみることができる。▼10 もっとも、主題としての「駅」を論じている本稿では、ここで極めて重要なことを補足しておかねばならない。駅舎は自然を再確認させ地方を再確認させる端緒となったが、都市を変貌させ都会の生活を変化させた張本人でもあったのである。それをうまく語るには、しばし明治日本から離れて、鉄道が人々の前に登場した当時のロンドンを旅せねばなるまい。 |
|
|
五、 ロンドン大学のロイヤル・ハロウェイ・カレッジに、『鉄道の駅』と題した絵が所蔵されている。ロンドンの英国西部への玄関ロパディントン駅構内の一八六〇年代の情景を描いた油彩で、作者はウィリアム・パウエル・フリス(一八一九~一九〇九 )彼は十九世紀中頃に活躍した英国の肖像画家で、中産階級の風俗を詳細に記録した作品から、十九世紀のホガースとも言われた。後にトーマス・ハロウェイが購入し、ロンドン大学に寄贈されることになるこの絵が一八六二年、ルイス・ヴィクトール・フラトーの画廊に飾られた時、フリスのホガースとも並び称される地位は定まったかに見えた。作品は好評を博し、版画に起こされ雑誌ににも掲載されたのだった。絵には、パディントン駅舎の鉄骨屋根を、画面を上下に二分する水平線の上部に巧みに組み込んだ構図内に、今まさに出発しようとしている列車を前に、プラットホームで別れを惜しむいくつかの家族が、まるで芝居の一場面を見るように描かれている。(図15)右端には、この絵で最も劇的な光景となっている、二人の私服警官に逮捕状を突き付けられた男がいる。彼は今まさに汽車に飛乗り、地方へ高飛びするつもりであったようだ。画家は駅構内のこれらの群衆の中に、自らの肖像を描き入れることも忘れなかった。画面中央の親子がフリス一家である。母親はこれから学校にあがる幼い息子に接吻し、父親であるフリスは、その子の兄の肩に手をやっている。フリスの代表作『鉄道の駅』は、原画をもとにした版画作品によって、しばしば鉄道の歴史を記述した書物に挿絵として使われているのだが、ブルジョワジーの人間喜劇を、恰も十八世紀の歴史画家ジェイムズ・バリーの「荘厳様式」宜しく、群像画にまとめたこの絵が、続く十九世紀後半の美術作品に固有ないくつかの問題を予言していることは、当のフリスさえ気付かなかったのではなかろうか。フリスには、ロイヤル・アカデミーの展覧会を訪れた若きオスカー・ワイルドを描いた作品があるが、アカデミー会員であったこの画家には、小説家や俳優など多くの友人がいた。彼の『鉄道の駅』が内包している問題について語る前に、その友人の一人に今登場してもらうことになる。 チャールズ・ディケンズが愛人の女優エレン・ターナンとフランス旅行に出発した駅の様子は、凡そフリスの絵に描かれた光景と似たり寄ったりであったろう。がしかし、帰国の模様はかなり違っていたのである。一八六五年六月九日、二人を乗せた帰宅途中の列車が大事故を起こし、多数の死傷者を出したからである。幸いディケンズらは事無きを得たが、この事件から受けた衝撃は、終生ディケンズを苦しめることになる。翌一八六六年、彼は、自分の主宰する週刊雑誌「オール・ザ・イヤー・ラウンド」のクリスマス特集号に、『信号手』という短編を発表した。怪奇小説とも推理小説のようにも思える、この不思議な短編は、話者である「私」が鉄道で働く信号手を訪ねるところから始まる。「鉄道という偉大な仕事に新たに閑心を抱くようになった」という「私」は、トンネルの信号燈を監視する男の異様な態度と、不気味な職場にまず驚かされた。 彼の職場は私がそれまで見たことのないような、淋しい陰気な場所だった。両側はじとじとと水のしたたるごつごつした岩の壁で、目に見えるものは狭い空だけだった。一方を見渡すとこの大きな牢獄がカーブを描いて通じており、もう一方はもっと近いところ、陰気な赤い信号燈と、もっと陰気な黒いトンネルの入口で終っていた。トンネルの入口のどっしりした構えには、どこか野蛮で、陰惨で、人を寄せつけぬところがあった。ほとんど日光も射さないので、気持ちの悪い土くさい湿気たにおいがし、切り通しにそって冷たい風が吹き抜けるので、まるであの世に来たみたいな気持ちがした。▼11 他人を威嚇する様でいて、しかも怯えた眼差しの信号手に、なんとか話の糸口を見付けた「私」は、その男の異様な態度が、彼の性格や境遇に原因するものではなく、彼の奇怪な体験即ち、信号燈の下に幽霊がでると、トンネル付近で必ず事故が起こるという予感から来る恐怖心によっていることを知る。この物語の結末は、信号手の事故死という一種のどんでんがえしの形をとっている。「私」との会話から、幻覚と幻聴に納得した男が、同じ叫び声を、しかし今度は実際に危険を知らせる叫び声を、聞こうとしなかったために事故に遇うという落ちである。ディケンズの『信号手』は、現実と非現実が奇妙に交錯した世界を巧みに小説化した佳作であるが、この短編に書かれた十九世紀中頃の社会にとって、文明の利器を強烈に主張する鉄道というものが、未だその社会に完全には馴染んでいない状況を、人々の心の動きを適して語っている点が興味深い。作者の体験に基づく凄惨な場面が、時に読者の好奇心を煽ってはいるものの、その筋書の背景には、次第に近代化してゆく都市とそこに棲息し始めた全く新しいタイプの労働者の出現があり、それらに対するディケンズの鋭い観察眼は、この小品を単なる怪奇小説や推理小説にはしていない。 一九八三年まてケンブリッジ大学で教鞭をとっていたレイモンド・ウィリアムズは、その著書『田舎と都会』(一九七三年)において、「鉄道」が象徴している新しい複雑な社会─極端に目まぐるしく、喧騒と雑踏渦巻く社会─の中で、近代人に特有の本能─すなわち一体自分が何者であり、自分を取り囲む環境とどのように閑係しているのかという疑問─が喚起する、社会の無秩序とその無秩序な社会を無視し続ける人々を直視した上でなおディケンズは、さらに観察を進め、結局のところもっとも重大な意義を持つものを見い出す。すなわち、変化の無秩序ではなく、そこから生まれでようとしている新種の秩序を見出すのである。▼12 とディケンズの『ドンビー父子』(一八四六年)を引用しながら、彼の鉄道観に肯定的な見解を下している。 鉄道は「生命を養う血液」であり、同時に「勝ち誇った怪物、死神」である。そしてこんなふうにこの力が持っている二つの要素─生への、また死への力、解体への、また秩序と偽りの秩序への力─をこのようなかたちで劇化することによって、ディケンズは彼の新しい社会的、経済的緒力がはらんでいる現実の矛盾に対応しているのである。ディケンズの関心は、常に、相次ぐ先例のない変化と、原型をとどめないほど変ってしまった風景のなかで、人間的な感覚と人間らしい優しさを生かしておくことにあったのである。▼13 『ドンビー父子商会のいきさつ』の執筆から『信号手』の出版までは、およそ二十年の歳月が経過しており、その間ディケンズの鉄道への感慨は、明らかに一八六五年の事故との遭遇以来、ある変化を見せ、それは二つの作品にそれぞれ例のニュアンスを与えているようである。 ところで近代日本文学の中で、とりわけディケンズから影響を受けた作家に徳富蘆花がいる。蘆花の長編自伝小説『おもひ出の記』(明治三十三年)は、ディケンズの 『デイヴィツド・コッパフィ-ルド』 (一八四九~五〇)をモデルにして執筆されている。蘆花の代表作『不如帰』(明治三十三年)もまた、近代文学のベストセラーとして新派劇の十八番に挙げられているが、いくづかの場面において鉄道と駅舎を巧みに用いて、登場人物の微妙な感情の動きを表現し情景の展開を計っている点はディケンズと同様の手法である。例えば、伊香保温泉に逗留していた武男と浪子を訪ねた千々岩の帰京の場面を、蘆花は巧みに千々岩の性格描写に当てている。 午後三時高崎上り列車の中等室のかたすみに、人なきを幸い、靴ばきのまま腰掛けの上に足さしのばして、巻莨をふかしつつ、新開を読みおるは千々岩安彦なり。▼14 また浪子の父片岡中将が、赤坂氷川町の自宅の書斎で読む書物は「西比利亜(シベリア)鉄道の現状」であったという設定も、この時代の状況を知る者には大変興味深いのである。モデル小説と言われた、この『不如帰』の登場人物のひとり片岡中将のモデルは、大山巌大将である。当時、軍首脳部の最大の閑心事は、蘆花の説くまでもなく、帝政ロシアの東方経略であり、既にロシアは、満州鉄道敷設権の取得や、遼東半島の還付に伴う軍事的要衝、旅順、大連の租借、シベリア鉄道の開通によって、着々と驥足を伸ばしていたのである。蘆花はそうした明治三十年代の緊迫した国際情勢を決して見逃さず、その背景にあった近代文明の持つ高度なテクノロジーであるところの「鉄道」を、文学作品の素材として最大限利用していたのである。 ともあれここでは、ディケンズの主題の醸成について論じるよりも、同時代の社会の様相が、文学作品としての小説における「鉄道」という主題を、いかに成立させたのかという点と、芸術作品としての絵画においては「鉄道」や「駅」という主題が、いかなる社会的状況のもとで生成されてゆくのかという点について、また更に、鉄道や駅を容認した社会が人々の感性をその根底から覆させて、芸術家が新たな主題を模索してゆく様を、鉄道や駅が実際にはどのように社会の中に組み込まれたのかを観察してゆきながら、考察をすすめてみたい。鉄道は既にそれが誕生した時から、更には年を経るに従って、都市の外観のみならず、その性格さえも変えていったのである。 |
|
|
六、 近年著された最も刺激的な歴史書のひとつである、ヴォルフガング・シベルブシュの『鉄道旅行の歴史―十九世紀における空間と時間の工業化』(一九七七年)には、十九世紀における鉄道と人間との軋轢、そして共存への過程が詳細に記録されている。確かにまだ著しく中世の面影を宿していたヨーロッパの都市の十九世紀における変様ぶり、都市空間の閉鎖性の瓦解、都市面積の拡大、特殊地域の成立(住宅、商業、工業地区、市民階級、無産階級地区など)は、産業革命全般の、特に鉄道による輸送革命の結果である。▼15 ということは、シベルブシュのみならず多くの社会学者一致した見解であろうが、十九世紀初期の鉄道の機能を端的に述べた、共通表現(トポス)である「時間と空間の抹殺」を、鉄道の出現によって変貌した都市に住む人間の心性研究(マンタリテ)にまで適用させた著者の姿勢は、この書物に独創性を与えている。心性の研究は、シベルブシュが前掲書でむしろ意図した中心的課題であるとも思われ、時間と空間が鉄道によって工業化されてゆく環境の中で、人間が翻弄される様子を著者は生々と描き出してゆく。この方法は、代二次世界大戦後の歴史学の新しい傾向であり、一九六〇年代、七〇年代を通じて、最も尖鋭的な発言を試みてきた『アナール』誌を中心とする歴史学研究に依拠したものであることは間違いなく、十九世紀という限定された領域を扱っているにもかかわらず、福井憲彦氏が『「新しい歴史学」とは何か』(昭和六十二年四月 日本エディタースクール出版部)の中で、『アナール』誌を中心に論陣を張った研究者たちの視座を整理した様に、『鉄道旅行の歴史』にもまた「歴史認識における長期的な時間の枠組の重視」と「歴史における空間の多層性への認識」がみられ、鉄道の誕生と発達を、単に政治学や経済学の文脈の中でのみとらえるのではなく、鉄道と鉄道の時代に生きた人間の在り様との間の関係にまでメスをいれた方法は、大変魅力的でさえある。逆に言えば、政治や思想と同様ないしはそれ以上に、時間と空間のあり方が著しく変化した十九世紀を解析する場合、中心的な視点を「鉄道」に据えることは、的を射た方法であるといえよう。 鉄道を、人間の心性研究に組み込む場合、まず念頭に置かなければならないのは、もともと人々は、鉄道を街外れに造ったという事実である。既に鉄道が日常化した存在になっている現代の都市においては、駅は都市の市街地の中心部にあるが、一八四〇年代のヨーロッパ諸都市の地図を広げてみると、駅はいずれも現在では旧市街地と呼ばれている地区の外れにあることが分かる。しかし鉄道の敷設と駅の誕生によって、旧市街地の周辺に拡張された新市街が形成され、更にそれらを取り囲む様にして周辺地帯が成長してゆく。ヨーロッパ諸都市の発展過程は、このように説明できる。もっとも著しく中世の面影を残していた、十九世紀初頭のヨーロッパ諸都市の姿を、あるひとつの理想郷と見立てた場合は、鉄道には、街に新たに建てられた建築物の稠密化を招いたこと、そして繁華な街の中心部と、荒涼たる外郭地区としての郊外と言う、都市内部における地域の性格付けを決定したという、二つの間接的ではあるが、見逃すことの出来ない重大な責任がある。また為政者が、こういった鉄道の都市構造への影響力に着目し、大規模な都市計画に応用することを考え、時の商工業資本が、その政府の立案に同調すると、鉄道は逆に、都市改造の要という積極的な役割を負った。オスマン男爵によるパリ大改造に果した駅の役割がそれである。苛酷なまでに徹底的であり、権力主義的色彩の濃い組織的なパリの整備(レギュラリザシオン)。狭い街路(リュ)に革命分子がバリケードを築かぬ様、建物の密集した貧民街を一掃し、道幅を広げ並木通り(アヴニュ)や大通り(ブールヴァール)を設計したのは、なにもルイ・ナポレオン指揮下の第二帝政期の軍隊を行進させるためばかりではなかった。カーネギー・メロン大学のハワード・サールマンが、『パリ大改造―オースンの業績』(一九七一年)の中て評価している様に、パリ改造計画はまず第一に、街路綱を整えて商業交易を盛んにすることを目的としていたのである。 ナポレオン三世とオースマンによって描かれた新しいパリは、何にもまして第二帝政そのものが象徴している政治的利益に役立つ都市でなければならず、また経済的自由主義と政治的保守主義を結びづけている社会の特質が、為政者にはできるだけ多く見てとれるような、そんな都市でなければならなかった。▼16 シベルブシュもまた前掲書の中で と述べ、急成長した都市問題に対する解決策として、十九世紀で最も影響力が大きかった、このセーヌ県知事、ジョルジュ・ユジェーヌ・オスマンが為し遂げた事業の経済的側面を強調している。ともあれ美術史の上では、このブールヴァールの出現によってブルヴァルディエ―即ちパリのマドレーヌ寺院からレピュブリック広場に至る大通り(グラン・ブールヴァール)に面して並ぶカフェや劇場に遊ぶ紳士淑女たち―の風俗を描いた画家マネやドガが登場することになる。オスマン男爵はまた、ストラスブール大通りの整備で、東駅を起点にしてパリ市街中心部へ向かう、鉄道路線の延長としての街路を生み出した。第二帝政期に実行された、このパリ大改造計画の理論上の指針には、鉄道路線の発想、とりわけ二点間を結ぶ最短距離は直線によって得られるという、交通技術上の理由があった。 オスマンの作りだした街路は交通のためのものである。その点で、この街路が破壊した中世の道路とは違う。中世の道路の機能は、交通のためというよりは、むしろ近隣の生活を見るためのものであった。また同様にその点で、バロック時代のアヴニュやブールヴァールとも違う。バロック時代の大通りの直線性と幅とは、交通機能というよりは、むしろ権力を見せつける機能を果たしていた。▼18 少なくとも十九世紀後半のパリに関する限り、その街の風景を決定したのは、鉄道が規定した、人々の都市に対する概念の変化であったとも言えよう。シベルブシュは更に、鉄道による時間の短縮が空間の収縮の形を取り、フランスの各都市が互いに近づき、そしてパリに接近するという空想に至った、サン・シモン主義の経済学者コンスタンチン・ペクールの主張を引用して、社会史のみならず文芸学も見逃すことの出来ない解釈を加えている。 フランスの地方都市がパリ市街に移動するという考えの伝えるところは、鉄道の速度による空間事情の変化は、実は空間収縮という単一現象ではなく、空間収縮と空間拡大という二重の現象であるということだ。▼19 美術史学が無視し得ないのは、この鉄道による空間の再編成、再構成という点である。観光旅行が普及し一般化することによって、地方は孤立性という価値を剥奪され、ワーズワースが一八四四年、鉄道に対する湖沼地帯の擁護のために「地方の主要な要素は、その美しさと閑居と辺辺鄙さというその性格にある。」と書いた地方の属性さえも危機に晒されるのである。ナポレオン三世の側近には、何人かのサン・シモン主義の経済学者がいたが、彼らが主張した、結集した労働者の力と先端的な科学に裏付けられた、合理的な産業本位の中央集権的な社会の確立と、そういったフーリエやサン・シモン主義で理論武装した、政府や大資本家の進歩主義的理想主義とは全く反対の立場に立つことになるのは、誰よりもまず同時代の前衛的な芸術家であった。いや寧ろ、流派や国籍、ジャンルを問わず、広く十九世紀の芸術家一般に共通する特性とは、科学によって近代化された現実から乖離して、失われた楽園を、少なくとも自らの作品の中には、奪還しようと試みたことではないだろうか。都会を離れて、自然の森のなかに、束の間の安らぎを求めたバビルゾン派の画家も、日常的な対象や現実的な主題を回避して、時間を遡り広大な空間を周遊しながら、神秘的な中世趣味や異国趣味に閉じ籠もった象徴主義の画家達にしても、何れも、現実世界が当時の先端科学によって、何もかも解き明かされてしまうかに映った、窮極の事態に対して、芸術家の側から異議申し立てをした点で一致していたのである。もっとも現実世界の中で、唯一箇所だけ都会であり田園である部分が生まれた事をここでは忘れてはならないだろう。それは駅である。駅こそは一本のレールによって都会の起点となり、田園の終点ともなった。駅舎の構造はその二つの機能を象徴している。 大都市の終着駅は・・・中略・・・鉄とガラスでできた純工業的な目的構造ではなく、建物全体が奇妙な二つの部分からなっているのが特徴である。 こうした構造をもつ駅舎は一八五〇年頃、ロンドンに現れ始めた。勿論その模範となった建築物は、一八五一年のロンドン万国博覧会に登場した「水晶宮」である。剥き出しの鉄骨とガラスによる建築に先鞭をつけたこのモニュメントは、建築史上輝かしい一頁を飾っている。シベルブシュは、アルフレート・ゴットホルト・マイヤーがまとめた「水晶宮」の特徴を前掲書で紹介している。マイヤーは、建築史上「水晶宮」が成し遂げたいくつかの価値転換を大きく四つに分け、まずそれが建物とし可能な限り、力と嵩をなくしたこと、壁を除いたことで、空間の境目が取り払われたこと、ガラスの使用で光量を最大にすることができ、光と影が逆転したこと、鉄骨を主体とした線の組織により、建築物に固有の閉鎖性を解消させたことを挙げているが、この「水晶宮」は、実は絵画史の上でも、大変重要な役割を果たすことになった。一八五一年のロンドン万国博覧会におけるロタール・ブーハーの報告書は、「水晶宮」に一歩踏み込んだ人間が感じる、奇妙な印象を率直に語っているのだが、それは既に、光と影の扱いを重要な課題とした「印象派」の絵画を予見している様な口調なのである。引用が少し長くなるが、非常に興味深い発言だと思われるので、シベルブシュが引用したものを、再びここに書きだしてみる。 われわれの目には、左右均斉の線が作りだす細かな網目細工が見える。だが、目から網目までの距離と、その網目の大きさとを判定するための拠りどころがどこにもないのだ。側壁は、一目でそれを捉えることができないほどに、どれもあまりに遠く隔たっている。そして向こうの壁を捉えられずに、目は果くしない見通しのなかをさまよい続け、見通しの果ては、青い空の中に溶けこんでいる。頭上の天井の骨組みは、高さ百フィートなのか千フィートなのか、また天井は平らなのか、それともかまばこ状に幾重にも続いているのか、われわれにはわからない。なぜならば、視神経が受けた剌戟を理解する上で精神の助けとなる、あの陰影が全くないのだから。目を真上の天井から再びゆっくりと天井に沿って下ろしてゆくと、青ペンキの塗ってある穴のある梁と梁の間の空間は広いが、次第に梁は近づきあい、やがて重なりあい、その後は光り輝く光線に遮られて、ついには遙か彼方の背景に溶けこんでしまい、その背景では、すべて形あるもの、線すらもが消えてしまい、残るのは色だけとなる。▼21 駅舎のなかで、水晶宮の構造をもつ建築物は、構内ホールすなわち、引き込み線の鉄道の軌道とプラットホームを格納した形の部分である。反対に都市の街路に面して、石造建築の入口ホールが建っている。初期の駅舎は、入口ホールと待合室、構内ホールが各々独立性を保ちながら機能し、乗降客の流れもまた、この駅舎の構造に添っていたのである。一八六〇年代に入り、駅に新たにコンコース(駅中央ホール)というものが誕生するまで、鉄道の駅では今日の空港と同様に、切符を持つ旅客は、汽車が到着するまで待合室におり、汽車が着いて出発の準備の完了した時、初めて旅客は待合室からミッドウェイ(横断道路)を通って、汽車の発着する構内ホールに入るのである。ところが一八六〇年代頃に、駅舎の水門ともなっていた、待合室およびミッドウェイが取り払われ、その場にいる客が、汽車に乗る客かどうかは問わない、広々とした通過ホールすなはち、コンコースが創られた。コンコースは人々に出会いの場を提供することになった。人と人との出逢い場を提供することになった。人と人の出逢いのみならず、従来列車の発車寸前にのみ構内ホールを見ていた人に、時間を与えゆっくり「水晶宮」の構造を持つ建築物を観察する機会を与えた。そして、汽車の車体や煙、音を掛けて体験させたのである。 |
▼15 ヴォルフガング・シベルブシュ著 加藤二郎訳『鉄道旅行の歴史――十九世紀における空間と時間の工業化 』昭和五十七年 法政大学出版局 二二〇頁 |
|
七、 一九〇〇年のパリ万国博覧会に際して、この華の都に新しい名所が生まれている。それは、セーヌ河を狭んでルーヴル宮殿と向かい合った駅舎、オルセ駅である。この駅のコンコースは凝りに凝ったものであった。(図16)設計者はヴィクトール・ラルー。駅舎は、パリ─オルレアン鉄道の駅とホテルの複合施設として設計された。現在のオルセ美術館は、このオルセ駅の美しい内装を生かして設計されている。(図17)昨年(一九八六年)十二月、パリに開館したオルセ美術館は、十九世紀後半から今世紀初頭にかけての美術史を再検許する、いわば討究のコンコースとなった観がある。本年に入り各国の美術専門誌は、主筆もしくは論説委員による、オルセに閑する論評を巻頭に掲載したが、既に昨年の『ルヴュ・ド・ラール』誌は十九世紀美術史の特集を組み、ジャン・ビアロストッキを始めとする研究者の興味深い諭考と共に、オルセ開館に至る経緯を報告した、ジャック・チュイリエの論説を所載している。オルセ美術館の大改装は、一九七九年のコンペティションで選ばれたバルドン、コルボック、フィリポンの建築チームと、特に内装の展示空間の設計を任されたゲ・アレンティによって、地下の鉄道路線跡に高さ三〇メートル、五一二〇平方メートルの空間の建設が進められた。このアレンティの内装デザインに批判的であった評論家もいた。しかし、内部装飾の中心的モティーフはエジプトの神殿建築にあるが、これは十九世紀がナポレオンと共に始まったことを考慮するならば納得がいく、と評したアポロ誌のデニス・サットンのように好意的に評価した論評もあった。何れにしても我々にとって興味深いのは、この美術館が駅舎を改造したものであるということで、十九世紀がまさに鉄道の時代であった事を考え合わせると、この組み合わせは極めて象徴的であるといえる。 旧駅舎を美術館に造り替えるという構想は、議論の余地なく素晴らしいことである。何故なら、そこは到着と出発の場所であるから。つまり私達はオルセ美術館で新しい領域の調査研究にも着手できるし、また私達の見解を恐らく今後も損なわれる事のない結論へと引き戻してもくれよう。何れの場合にせよ、この美術館は私達にその時代(十九世紀)の美術の再考を迫ってくる。▼22 オルセ美術館の展示領域は一八四八年の二月革命から開始される。十九世紀後半の美術への普仏戦争とパリ・コミューンの影響を配慮し、第二帝政時代以降の活発な博覧会、美術館、展覧会活動を積極的に評価した区分である。ミッシェル・ラクロットとフランソワーズ・カシャンをはじめとする美術史家サイドの学芸スタッフに加えて、社会学者のマドレーヌ・ルベリューの参画がこの分類を展示概念に展開させた。『バーリントン・マガジン』誌に「オルセ見開録」を寄せたジョン・ハウスは、 私は概観した状況を多少詳細に渡り説明してきたが、それは(この美術館の)視覚上の有様が、明らかに展示計画の あらゆる点を強調しながら、巧みに仕組まれた目論みとなっているからであった。▼23 とその展示の意図する所を見逃していない。確かにオルセのコンセプトの一つは、十九世紀を左翼と右翼、教会と都市、異なる美学といったもの二項対立の時代であるかの様に規定し、例えばセザンヌの絵画の革新とマルクス主義を並列して論じる様に、美術運動を革命によって括っていく立場を明示している。デニス・サットンが批判する様に、それは一つの解釈に過ぎないのであろうが、先の印象派美術館、ジュ・ド・ポームでは解決され得なかったであろう新たな美術史上の諸問題を、オルセは視覚的な演出によって端的に討究してゆく。アカデミー系の絵画と印象派などアヴァンギャルドの作品が並置され、ドガとモロー、ホイッスラーとカロリュス・デュランとマネを同時代的な視点で捕らえ直す契機を与えてくれる。またオルセは同時代の諸外国の芸術家の作品も決して見逃していない。それは国境を越えた芸術の影響関係を考察する上で重要であり、またパリという街の果たした役割の大きさを再認識するためにも不可欠である。そしてパリの近代化と同時進行していた芸術における反=近代という主張を解析する際にもまた、この広義の文化史的展示は極めて有効であるといえよう。一面において反=近代の先方の先鋒ともなった印象主義は積極的に田園風景を題材にしたが、一九八四年にロサンゼルス、シカゴ、パリを巡回して開催された『印象主義とフランス風景画』展のカタログにおいて、リチャード・ブレッテルがそのブリリアントな論考において解く様に、印象主義もまたあらかじめ用意されていた近代という前提のもとで独自の「印象」を構築させていったともいえるのである。▼24 ハーバード大学のT・Jクラークもまた、印象主義の風景画に見られる近代人の自然との接し方の特異性を強調している。 私が予てから主張してきた様に、印象派絵画に顕著な主題のひとつは風景画であり、それ故、画家の風景への取り組み方がどれ程諭人や詩人と類似していたのかという点を問いただすことは、あながち的外れともいえまい。私たちは詳細に、その見景がパリ─その特徴を付言している工業化への「道」と、「新しい社会階層(ヌーヴェル・クッシュ・ソシャル)」の自然との接し方という─に関係する兆候を彼らがいかに取り扱ったのかを知ろうとすることも出来よう。▼25 わたしはもう一度ここで、アーノルド・ハウザーの印象主義の定義に立ち帰るべきかも知れない。ハウザーによれば印象派の画家たちは、遠いものと近いものとの一致、一番身近にあって日頃接しているものの異和感、世間から永久に切り離されているという疎外感を感じながら、その感覚を表現形式にまで収斂させることの出来た芸術家であるという。そして希薄になった遠近感、日常と非日常との接点の喪失、現実世界における孤立感という問題は、高度な都市文明が出現した産業革命以後の西欧社会に固有の問題であったといえる。そして近代文明の象徴ともいえる鉄道は、人々が身体て憶えていた距離と時間との関係を壊し、自然と人間との関係、別な言い方をすると人々のものの見方をも変化させていったのである。十九世紀後半にフランスの印象派は、この移ろいやすい自然を、それまで美術学校の教育において中心的な課程であった、絵画で対象を彫塑的に捕らえるためには必要である明暗法から離れて、光と形ではなく、光と色との関係に着目していったのである。またルネサンス以降、西洋美術の空間構成の本流であった遠近法からも離れた印象主義の画家たちは、具体的な構図の手本として、東洋美術とくに日本の「浮世絵」に関心を奇せ、例えばその俯瞰構図などを用いて、独自な作品を産み出したことはよく知られている。遠近法的秩序の中では考えられない、大胆な部分の強調、角度を変えてみた自然描写といった手法を彼らは称揚した。そうした技法で描かれた作品は、日本趣味(ジャポニズム)によるものという評価を得ている。ここで大変興味深いのは、同時代の日本美術にジャポニズムの影響を受けたと思われる作品、つまりジャポニズムの逆輸入がみられるもののあることである。鹿子木孟郎の『津の停車場』は、あるいは逆輸入されたジャポニズムの初期の作例のひとつであるかもしれない。人物を中心から大胆に切る架橋の鉄骨、後ろ姿の婦人像がその特徴であるともいえよう。風景や人物など、描かれる対象を意外なもので画面上、切断する手法は、歌川広重の『東京名所 両国之宵月』などの例を引き合いに出さずとも、浮世絵の常套句であるが、『津の停車場』の架橋の鉄骨も、人物と風景を画面で二分している。そして、本作品のうち最も特徴的である、後ろ姿の婦人像は、やはり、菱川師宣の『見返り美人』、懐月堂安度の『立美人』を典型とした、後ろ姿の婦人図であり、後ろ姿を描くことで、髷の形や着物の美しさを強調したという作者の意図は、「両面摺」という技法によって『難波屋おきた』の艶やかさを表現してみせた喜多川歌麿と同様のものであったに違いあるまい。(図18)もっとも、西洋絵画のなかにも例えば、プーシェの素描『若き農婦』(図19)やフラゴナールの素描『背を向けて立つ若い娘』(図20)といった先例があり、いずれも対象の移ろいやすい一瞬を素描で表現した傑作であることを忘れてはならない。これらの素描の持つ絵画の私的な性格は、そのまま鹿子木孟郎の『津の停車場』のもつ私的な性格につながっている。 【付記】・・・ ※本稿作成にあたり、多くの書物を参考にさせて頂きましたが、直接の引用をしなかったために、諭旨の多くを負っていながら記載できなかったものに、東京都立大学人文学部教授、小池滋氏の著書『ディケンズ19世紀信号手』(昭和五十四年二月 冬樹社、『英国鉄道物語』(一九七九年十月 晶文社)、『ディケンズとともに』(一九八三年二月 晶文社)があります。 |
|
【付録資料】・・・
演題「思ひ出を語る」
講師 鹿子木孟郎(客員)
只今御紹介を蒙りましたが多少誤が御座います。第一に名が違って居ります。第二に奉職した時が異なって居ります。私が津に来たのは明治二十九年の暑中休暇で御座いました。時の校長は五代の山崎旨重御座んして、私はそれから足掛け四年この地に居まして明治三十二年の卒業式が済むと直ぐ他所に参りました。
その時居た津と、今の津を考へ合わせると感無量なるものがあります。一度、大正九年頃、一寸伊勢神宮に参りました時に、二・三時間汽車を降りて、阿漕浦の方まで行ったことが有りましたが、暇が無かつたから本校へは立ち寄りませんでした。それから津に参つたのは今日が始めてゞす。大正九年以来十五年目になります。
私が本校の職を退いて以来三十九年になります。私は色々な意味に於いて特に本校と関係が深いのであります。私の来る前に、私の兄が本校に奉職して、舎監を二年程勤めて居ましたが、病気になりました。その時私は東京に勉強して居りましたが、その見舞に一度参りまして、次いでこの津で兄の葬式を出すことになつたのであります。それから東京に帰つてゐます山崎校長から急に来いと言ふことで、来て見ると、こゝの先生をやらぬかといふ話。遂に御世話になつたのであります。 先刻講演された芝田さんがその頃生徒であつたといふことは、今日初めて聞いた訳です。何しろ私は今此処に居られる諸君の先生方が、まだお生まれにならぬ前に本校を去つた訳ですから、随分古いものであります。私は今六十二歳です。昨年有堀校長などが発起人になつて、私の還暦祝賀会を開いて下さいましたが、私は何時かはこの中学の一堂に会して、諸君に私の話を聞いて頂く事を祈つてゐたのであります。
今日こゝに諸君と親しくお目にかゝつてお話出来るのは非常に光栄と存じます。
本校は明治十三年の創立で、私は本校創立十五周年記念式には兄の関係で参列することが出来たのでありました。私の居ります間の校長先生は山崎先生、久田先生、秋山先生でした。
先程パーレーの万国史といふのがお話に上りましたが、実を云ふと私は貧乏士族の子弟で、高等小学校を卒業するとすぐ、学資が無いから親から自分で資を得て卒業しろと云はれました。小学校に於いて僅かの語学・僅かの漢籍・英語・地理を学んだゝけであります。さういふ訳で中等教育を受けてゐない自分は、この津にゐる間に何とかして無教育を取り返さうと思って、図画を教へる合間々々に、秋山校長にパーレーの万国史を学んだのであります。私はどうせ絵をやす以上は外国語の力が出来たら是非一度フランスに行きたいと思ってゐいました。
三十二年に本校を辞し、埼玉県の浦和師範に・Eしました。之は東京に近かつたからです。こゝに一年間奉職しましたが、その間図画を教へるひまに、有名なイーストレーキ氏の塾に入って英語を揉んで貰ひました。かうしてどうやら英語が語れるやうになりましたから、明治三十三年の秋に学校を辞職し、外国へ渡航したのであります。十一月中旬に日本を出てアメリカに行き、三ケ月位ゐてイギリスへ行きました。それからフランスへ参りました。それからフランスへ参りました。これが私のパリー留学の第一回でござんした。パリーで三重県の方に逢ふこともありまして、豈図らんや花のパリーの街頭で、本中学の事もあつたのであります。
日本に帰つたのは明治三十七年で、日露戦争の始まりかけでした。そこで私の帰る船は、どんな目のとつゝかまるやら分らず、ロンドン出発の際船体を塗りかへたり、英国旗を立てたりして、ジプラルタルから地中海・ボーサイドと云ふ風にやって来まして、スエズ運河までやつて来ますと、日本の日進・春日が廻航して来るのに会ひました。その真中に私の乗つてゐる稲葉丸が加はつて碇泊したのでありますが、その時の心強さは今以つて忘れません。その当時、日・露間に間もなく戦争が爆発するだらうと云ふことは、何処でも云はれてゐました。それからセイロン島・シンガポールとやつて来て香港に入りますと、いよいよ日・露開戦の報が入つて来ました。それから日本へ大急ぎで帰つて来たと云ふやうな次第でございます。
次に私は日・露戦争終了後間もない、三十九年十二月の末頃、更に再びフランスに留学致しました。二ケ年間あちらに居りまして、帰りはシベリヤを通過して来ました。当時はシベリヤ廻りをする人は極めて少かつたのでありますが、私は何だか行つて見たいと思ひましたから通つて来た訳です。この第二回の留学から帰りました頃から、京都の陳川同窓会と云ふ会の御通知を受けて、出席するやうになつたのだと記憶してゐます。誠に気持のよい会で、何時も出来るだけ出席させて貰つてゐます。今後も出席して若い人々と会つて大いに若返りたいと思ってゐます。
更にその後三回目のフランス留学を致しました。欧州大戦が大正三年から七年までありましたが、私はその大正四年から七年まで、丁度戦争中に留学をしてゐた訳です。この時もドイツの潜水艦があちらこちらに散らばつてゐて恐しい時でした。その為に私の船はスエズ運河を通らずにアフリカを迂回して、喜望岬を右手に見、ジブラルタル海峡を通つて地中海に入り、それからマルセイユに真直に入りました。これが大正五年二月でした。磯谷先輩は大戦前にフランスに参られたとの事ですが、それでは丁度私と入代り位ではなかつたかと思ひます。かくて私は大正六年の暮に帰って来ましたが、今度はフランスからスペインのタソー(?)と云ふ所に出て、アメリカへ渡つてニューヨ-クに着き、そこから大陸を横断して、それから太平洋を横断しました。これが大正七年春でした。それからずつと京都に居ります。大正九年に津に遊んだのは前に言つた通りです。大正十四年に満州に参りました。
これは明治天皇の御聖徳記念絵画館の壁画に、奉天入城の絵を画けと云ふことで、その実施を見る為に参つたのであります。例の大山元帥を先頭に、我が軍が列を正して堂々入城する光景を描くのであります。所が生憎私は途中から少々胃腸をこわして、下痢をして仕方がありません。勇気を振って奉天に到着しましたが、腹が迚も痛いので、直ちに満鉄病院に飛ひ込んで参りました。そして胃腸科の方のお医者に会ひたいと思つて名刺を出しました。が、始めはどんな待遇をされるかと内々心配してゐますと案外に優待を受けました。そして部長さんが出て来て、何かかう面会人とでも思はれた様子であります。実はこれこれでと容態を話すと、会ひに来て下さつたのではないのですかと云はれます。よく見るとこの部長さん、何でも見憶えがある。誰だつたかなあと思つてゐますと、向こふから話されました。それに依りますと「私は、先生、三重津中の卒業生です。先生にお世話になつたことがあります。」と云ふ訳。此の病院は院長初め各部長皆三重県の出身者でありました。そんな訳で大変気持ちよく待遇されましたので、病院を出る頃は気持がすっかりよくなつて居りました。そしてその晩はその部長さん初め、その病院に勤めてゐる五・六人の先生方に招待にされまして、大いに御馳走になつてしまひました。それといふのも私が三重津中に居つたお蔭であります。各地に於て津中出身の方は、随分重要な地位を得てゐられる方が多くて、意外な所で私は愉快を興へられる事が多いのであります。諸君も将来、これ等の先輩の方に劣らぬ立派な人となって、今教へて頂いて居られる先生方を、諸君の先輩の方々が私を遇するやうに、或はお招きしたり、御馳走したりして差上げられたならば、諸先生も亦私と同様非常に喜ばれることゝ思ひます。ですから諸君は一層努力して偉い人となられる様に衷心から希望致します。
ではこれで失礼致します。(在文責筆記者)
※三重県立津中学校校友会編『校友会雑誌』第七十四号 昭和十一年一月 八二~八六頁