現在・これからの展覧会・行事
※ 日程や催事名等は、やむをえない事情により変更となる場合があります※ 掲載の情報は 令和8年2月21日(土曜)17時現在 の計画です
※ ご利用の際は、最新の情報をご確認ください。
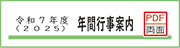 |
|
展覧会
冬季企画展「天地(あめつち)の神を祈りて-伊勢神宮、そして斎宮-」 
チラシは こちら
| 開催期間 | 令和8年1月31日(土曜)から3月8日(日曜)まで ※会期中展示替えを行います。 前期:1月31日(土曜)から2月15日(日曜)まで 後期:2月17日(火曜)から3月 8日(日曜)まで |
| 休館日 | 2月2日(月曜)・9日(月曜)・16日(月曜)・24日(火曜) 3月2日(月曜) |
| 場所 | 斎宮歴史博物館 特別展示室 |
| 開館時間 | 9時30分から17時まで(ただし入館は16時30分まで) |
| 展示内容 | 古代から中世にかけて、天皇の代わりに伊勢神宮に祈りを捧げるために遣わされた皇女・斎王。斎王は、年に三度、伊勢神宮での祭祀に参列するほか、斎宮で祈りを捧げる日々を過ごしたと考えられています。 伊勢神宮は、国家の安寧のために天照大神を奉斎し、神への祈りの形は、今も行われている日々の諸行事や、20年に一度の式年遷宮からうかがうことができます。 この展示では、古墳時代の祭祀に使用した石製模造品や神への祈りを形にしてあらわした宝物に着目し、関連した考古遺物などから、伊勢神宮と斎宮の深いつながりをたどります。 |
| 観覧料 | 一般:500円(400円)、大学生:400円(320円)、高校生以下:無料 常設展の観覧には別途観覧料が必要です(共通券あり) ※( )内は団体料金(20名以上) |
| 展示資料 点数 |
97件 570点 |
| 主な 展示資料 |
【三重県指定有形文化財】坂本1号墳出土 金銅装頭椎大刀 古墳時代 明和町教育委員会蔵 【松阪市指定有形文化財】佐久米大塚山古墳出土 鏡・勾玉 古墳時代 松阪市佐久米町自治会蔵、松阪市文化財センター保管 伊勢市塚山古墳出土 長方形鏡板付轡・飾金具・鉸具 飛鳥時代 東京国立博物館蔵 【重要文化財】斎宮跡出土 金銅製馬具 飛鳥時代 斎宮歴史博物館蔵 津市薬師谷14号墳出土 三輪玉・水晶原石 古墳時代 津市埋蔵文化財センター蔵 奈良県植山古墳出土 三輪玉・金銅製歩揺付飾金具 古墳時代 橿原市蔵 大阪府今城塚古墳出土 大刀形埴輪 古墳時代 高槻市立今城塚古代歴史館蔵 皇大神宮境内出土 勾玉・臼玉 古墳時代 東京国立博物館蔵 松浦武四郎旧蔵資料 馬角第五(石製模造品・勾玉類) 古墳時代 静嘉堂文庫美術館蔵 神路山発見 臼玉・有孔円板 古墳時代 國學院大學博物館蔵 【重要文化財】『日本書紀』巻第五・第六 南北朝時代・永和3(1377)年 熱田神宮蔵 【重要文化財】伊勢神島祭祀遺物 古墳時代から平安時代 八代神社蔵 皇大神宮御造営奉曳図 明治21(1888)年 神宮文庫蔵 |
| 主催 | 斎宮歴史博物館 |
| 助成 | 令和7年度 日本博2.0を契機とする文化資源コンテンツ創成事業 地域ゆかりの文化資産を活用した展覧会支援事業(文化資源活用事業費補助金) |
講座・イベント
冬季企画展「天地(あめつち)の神を祈りて-伊勢神宮、そして斎宮-」
記念講演会 第2回「考古学が語る多気、度会、そして伊勢神宮」  |
|
| 講師 | 穂積 裕昌さん 三重県埋蔵文化財センター 所長 |
| 日時 | 3月1日(日曜)13時30分から15時まで ※受付・開場は13時から |
| 会場 | 斎宮歴史博物館 講堂 |
| 定員 | 募集受付は終了しました |
| 参加費 | 無料 |
| 募集期間 | 募集受付は終了しました |
| 申込方法 | 募集受付は終了しました |
展示解説会  |
|
| 日時 | 2月14日(土曜) 13時30分から1時間程度 終了しました 2月28日(土曜) 13時30分から1時間程度 |
| 会場 | 斎宮歴史博物館 特別展示室 |
| 参加方法 | 事前申込不要 当日の企画展観覧券が必要 |
※左右にフリックすると表がスライドします。*Flick left and right and the table slides.
