2007年9月3日
斎宮跡第152次発掘調査ニュース
いつのまにか秋の気配
早いもので、この7月9日から着手した第152次調査も、台風で出鼻をくじかれたり、お盆の休みがあったり、あるいは連日猛暑日が続いたりといろいろありましたが、全体の面積の3分の1強を占める「中央区」約1,100㎡の調査をほぼ終えました。
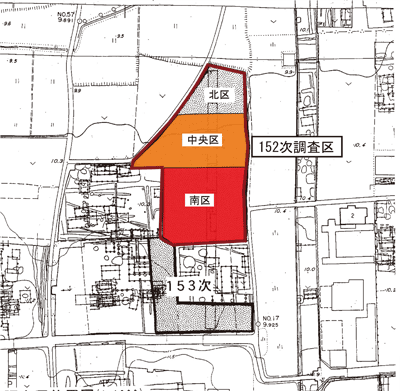
第152次調査区の配置図
「中央区」の調査結果の詳細については、遺構も遺物も整理・検討が進んでいませんが、次の略図で示したように東の端付近で平安時代前期(9世紀頃)のやや大型の柱穴をもつ掘立柱建物が、中央から西部に平安時代後期から末期(10~12世紀頃)の掘立柱建物や溝・土坑が多数見つかっています。この時期のものでは、まだ建物としてのまとまりが整理できていない小型の柱穴が多数見つかっていますので、遺構の実測を行い精密な図面が出来上がれば、かなりの数の建物が確認できると思います。
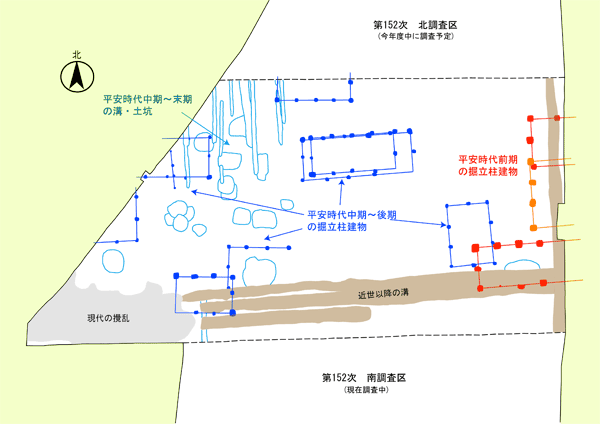
第152次調査「中央区」の遺構略図
一方、「中央区」での出土遺物は予想外に少ないものでした。土器などが捨てられない場所だったのか、土器を含んだ土が後世に削り取られてしまったせいなのか今のところよくわかりません。ただ11世紀頃のものとみられる白磁片など高級品とみられるものも少量見つかっています。また柱穴の中に小型の皿が意図的に埋められたとみられるものもありました。
「中央区」に引き続き、「南区」の調査に入っていますが、遺構の上の畑の土を取り除いている間にも9世紀頃の土器などが出土しています。「南区」は「中央区」に増して遺構・遺物の発見が期待されている箇所です。周辺の調査の結果から、史跡を東西に貫通する幅約9mの「奈良古道」の遺構も確認できるはずです。「南区」の調査は10月上旬頃まで行う予定です。

南区表土掘削状況
暑い暑いと思っていた今年の夏も、残暑はありますが秋へと季節が移っているようです。発掘調査現場のまわりでも、気がつくとカヤツリグサやエノコログサの穂が垂れ、コオロギなどが鳴き始めています。毎日外にいると、季節というものは決して緩やかに移ろうばかりではなく、「秋きぬと目にはさやかに見えねども 風の音にぞ驚かれぬる」(藤原敏行)と、あっという間に変わっていく季節にハッと気づかされることもあるのだなあと感じています。発掘調査のご見学をされるにも一番いい季節になってきたようです。

発掘調査現場に秋の声
(O)
