アケボノゾウ(Stegodon aurorae)全身骨格標本
| 資料名 | 学名 Stegodon aurorae (Matsumoto 1918) 和名 アケボノゾウ |
資料番号 | Fo0001466 |
|---|---|---|---|
| 分類 | ほ乳綱 長鼻目 ステゴドン科 ステゴドン属 |
産地 | 滋賀県犬上郡多賀町四手 古琵琶湖層群蒲生累層四手部層 |
| 原標本 | 多賀町立博物館 | ||
| 時代 | 新生代第三紀鮮新世(およそ180万年前) | 寸法 | 全長 5m 幅 1.2m 高 2.1m 重量 250kg |
| 解説 | 明治15(1882)年、河芸郡明村(かわげぐんあきらむら・現在の津市芸濃町林)で、三重県最初のゾウ化石が見つかっています。この化石は、後に「ミエゾウ」と呼ばれるものの臼歯のついた左下あごの骨でした。 この最初のゾウ化石発見からおよそ70年後の昭和29(1954)年、員弁郡藤原町(いなべぐんふじわらちょう・現在のいなべ市藤原町)で、ほぼ1頭分の骨化石が発見されました。これは、「アケボノゾウ」と呼ばれる化石ゾウのもので、「上之山田標本」としてゾウ化石研究の貴重な基準のひとつとされています。この発見の後、県内では、いなべ市員弁町(旧員弁郡員弁町)や四日市市、鈴鹿市、亀山市(旧亀山市)、伊賀市(旧阿山郡伊賀町・阿山郡大山田村)でゾウ化石が発見されています。多くは、「ミエゾウ」の化石ですが、いなべ市員弁町と四日市市、鈴鹿市で発見されたものは、「アケボノゾウ」の化石でした。 アケボノゾウは、およそ200万年から150万年前に生息していたゾウの仲間で、現在のゾウに似た姿をしています。胴長短足で、長く湾曲したキバ(専門的には「切歯(せっし)」といいます。)を持っています。いなべ市藤原町で発見された化石のキバは、1.37mもの長さがありました。 「ステゴドン」というグループに分類される「アケボノゾウ」は、肩までの高さがおよそ2mで、「ステゴドン」の中でも小型のグループに分類されています。 当館では、この「アケボノゾウ」の全身骨格標本(レプリカ)を展示しています。この骨格標本は、滋賀県犬上郡多賀町(いぬかみぐんたがちょう)で発見された「多賀標本」と呼ばれるもののレプリカです。(FK) |
||
|
|
|||
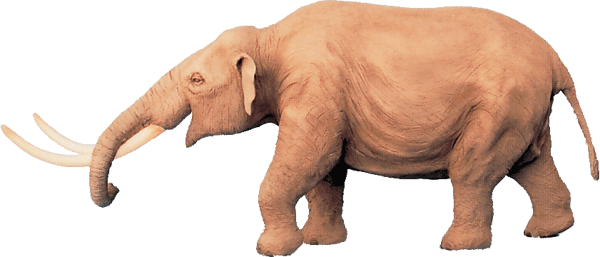 アケボノゾウ(復元) |
|||
| 関連ページ |  |
ミエゾウ(Stegodon miensis)の臼歯 | |
 |
ミエゾウ(Stegodon miensis)の臼歯(その2) | ||
| ミエゾウ(Stegodon miensis)の切歯(キバ) | |||
 |
コウガゾウ全身骨格標本(レプリカ) | ||


