トキソウ(Pogonia japonica Reichb. fil.)
| 和 名 | トキソウ |  |
|
|---|---|---|---|
| 学 名 | Pogonia japonica Reichb. fil. | ||
| 資料番号 | MPMP 13847 | ||
| 分 類 | 種子植物門 単子葉植物綱 ラン科 トキソウ属 |
||
| 採集日 | 1934年 | ||
| 採集地 | 三重県上野市(現・伊賀市) | ||
| 資料形態 | さく葉標本 | トキソウ(鈴鹿市) | |
| 解 説 | 植物の名前はネジバナやニガキのように、形や色、においや味などからつけられたものや、これらのイメージを伝えるために、他の生きものの名前がつけられているものがあります。サギソウ、カラスノエンドウ、スズメノテッポウ、イヌノフグリ、ネコノメソウ、ウシハコベ、サルスベリ、ヘビイチゴなど例をあげればきりがありません。今回紹介するトキソウもその一つです。 トキソウは日あたりのよい湿地でみられるラン科の多年草です。春になると土の中をのびる根茎から高さ10~30cmの茎を上方へ伸ばし、茎の中ほどに肉厚でしっかりとした線状長楕円形の葉を一枚つけます。そして、初夏になると茎の先端に淡い紅色の花を一輪咲かせます。北海道から九州まで分布していますが、四国、九州ではまれにみられる程度です。トキソウの仲間に山地や丘陵の日あたりのよい草地に生育するヤマトキソウがありますが、トキソウと比べ開花してもほとんど花弁が開かないことや、唇弁が側花弁(花弁の名称については下記のランの花の模式図参照)より短いことなどで区別されます。 トキソウのように湿地環境に生育する同じラン科のサギソウが、花の形や色が空に羽ばたく鳥類のシラサギ(白鷺)の姿に似ていることから名づけられたのに対して、トキソウは花の色が淡い紅色で鳥類のトキ(朱鷺)の羽の色に似ていることから名づけられました。トキは、江戸時代までは日本各地の水田などでエサを探す姿がみられ、身近な鳥でした。そのため、トキの体色である淡い紅色は朱鷺色(ときいろ)として、かつては誰もがイメージできる日本の伝統色の一つでした。しかし、日本産のトキは、近代以降激減し、ついに新潟県佐渡島の佐渡トキ保護センターで保護飼育されていた最後の個体が平成15年に死亡したことで絶滅しました。現在は同センターで中国産のトキの飼育・繁殖が試みられています。そのため、淡い紅色をさす朱鷺色も、トキの羽の色とのつながりが実感できない状況になろうとしています。最近では、トキソウは個人的な園芸や、販売目的の大量採取によって減少し、三重県内の多くの湿地から姿を消しています。トキのように絶滅させないためにも、大切に見守ってゆきたいものです。(M) |
 トキソウ 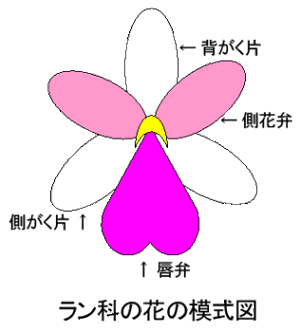 |
|
 |
 |
||
| トキソウの花 | (参考)ヤマトキソウの花 | ||
