斉王のみち歴史街道活性化協議会・会員一覧
地図上の青色の文字をクリックすると各会員のホームページへ進めます。
会員一覧の会員名からでも進めます。
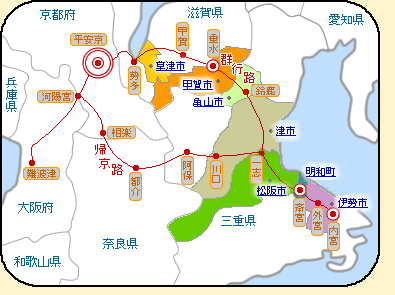 |
| 「斎王」とは、天皇が即位するごとに、天照大神の御杖代として伊勢に派遣された未婚の内親王もしくは女王のこと。この斎王制度の歴史は大変古く、飛鳥時代の天武天皇の頃にはすでに確立されていました。以降、南北朝時代の後醍醐天皇の頃までおよそ660年もの間続き、64人の斎王が任命されました。 斎王は、“ト定”という占い(亀の甲羅を用いひびの入り方から占ったと考えられています)により、選定されました。 選ばれた斎王は、まず宮中の“初斎院”という所に入ります。そこで斎戒沐浴の生活を送り幾度も禊を繰り返しながら、神にお仕えするにふさわしい、より清浄な身へと近づいてゆき、その後京外の“野宮”においてさらに厳しい潔斎の日々を送ります。 こうした生活を経て、ト定からおよそ3年後、斎王は伊勢へと赴くのです。別れの儀式を終えた斎王は、輿に乗り五泊六日をかけて伊勢の斎宮に向かいます。伊勢で斎王に仕える斎宮寮の官人や女官ら、500人余を数える人々が随行したこの大規模な斎王赴任の旅を「斎王群行」といい、壮大厳粛にして華やかな行事でした。斎宮までの長い道程の間には、勢多、甲賀、垂水、鈴鹿、壱志の5カ所の頓宮が設けられました。頓宮とは、斎王群行が宿泊するために造られた宿舎のことで、群行が行われる度に新たに建てられ、群行が終わるとすぐに壊されました。 斎王の一行が向かう斎宮とは、斎王の御所と事務などを行う役所(斎宮寮)を総称したものです。 幻想的で雅やかな斎王の世界。その奥深さに一度触れれば、きっと誰もが魅せられるでしょう。 |
|---|
斎王のみち歴史街道活性化協議会会員一覧
京都府
- 斎宮行事保存会
※野宮神社のページに斎王の紹介ページがございます。
滋賀県
三重県
- 亀山市
- 津市
- 松阪市
- 明和町王朝ロマンのまち
- 斎王まつり実行委員会
- 財団法人国史跡斎宮跡保存協会
- 三重県立斎宮歴史博物館斎宮の歴史、文学、考古学を展示
- 伊勢市はじまりのまち伊勢
- 伊勢商工会議所
- 伊賀町ランプの会
お問い合わせ先:〒514-8570 津市広明町13 三重県環境生活部文化振興課(電話 059-224-2233)
All Rights Reserved,Copyright(C)2008.Mie Prefecture