むかしむかし、秋も終わりに近いある日のこと、伊勢から海岸沿(ぞ)いを熊野に向かう街道(かいどう)の山道を、錦(にしき)の里を目指(めざ)してかいだりそうに歩く、二人連(ふたりづ)れがおったそうな。
質素な身なりながらもどことなく気品(きひん)の漂(ただよ)うお姫様(ひめさん)と、ほんのちょっとの身の回りの物を入れた小さな挟箱(はさみばこ)を担(かつ)いだ供(とも)の爺(じい)さんやった。
新桑(さらっか)を出てから一時半(いっときはん)ほど歩きづめで、ようよう錦の芦浜(あしはま)が見下(みお)ろせる山のてっぺんあたりにたどり着き、錦への下(くだ)り坂(ざか)にさしかかった途端(とたん)、姫がその場につくなりこんでしもた。
「姫! どうなされた! お気を確かに。もう、錦の里は近(ちこ)こうございます」
爺さんの呼びかけに、
「爺、私はもう歩けません」
こいだけ言うのがやっとやった。
|
|
|
錦(にしき)
現在の紀勢町 錦。
かいだりそうに
疲(つか)れた様子で。
ほんのちょっとの
ほんの少しの
挟箱(はさみばこ)
昔、旅行などの際に衣類などを入れて従者(じゅうしゃ)に担がせた箱。
新桑(さらっか)
南島町西部にある集落「新桑竈」。錦に隣接する。
歩きづめで
休みなく歩き続けて
一時半・四半時(いっときはん・しはんとき)
昔の時間の呼称。現在の時間に換算(かんさん)すると、一時半は約3時間、四半時は約30分。
つくなりこんでしもた
倒れ込んでしまった
|
|

|
|
ひとばあ木陰(かげろ)で休んでも、姫の塩梅(あんばい)は悪(わり)なるばっかやった。
「水を…」
そいだけ言うと、姫は眼(めえ)を塞(ふさ)いでしもた。
先を急ぐあまり、下(した)で谷水(たにみず)を汲(く)むのを忘(わす)れ、腰の竹筒(たけづつ)には一滴(いってき)の水さか無いことに気(き)いのついた爺さんは、姫をその場に残して、急(きゅう)な山道を水汲(みずく)みに転(まく)れ下(お)りてったそうな。
|

|
|
こいだけ
これだけ
ひとばあ
暫くの間・少しの距離(きょり)
塩梅
具合
悪(わり)なるばっかやった
悪くなる一方だった
そいだけ
それだけ
水さか
水さえ
転(まく)れ下(お)りてった
転げるように下って行った
|
|
四半時(しはんとき)もたって、爺さんが水を満たした竹筒を抱(だか)えて戻(もど)った時には、姫はすでに息絶(いきた)え、短い秋の陽(ひ)は辺(あた)りを黄金色(こがねいろ)に染(そ)め始めとったということや。
爺さんは、主人(あるじ)を失った悲しさと、最後までお守りできんだ後悔(こうかい)で、ひとばあ立ちすくんどったが、やがてそこにお姫様(ひめさん)の亡骸(なきがら)を鄭重(ていちょう)に葬(ほうむ)り、その後、山道をひとばあ下(くだ)った辺(あた)しで切腹して主人の後を追(お)うたということや。
こんなことがあってから、錦の人々(ひとら)は姫と供(とも)に爺(じい)やのために二つの塚(つか)を作り、この山を「姫越山(ひめごやま)」と呼(よ)ぶようになった、ということや。
今でも姫越山を通って錦から新桑(さらっか)に越(こ)える山道の脇には二つの塚(つか)が残っとる。
山頂(てっぺん)に近(ちっか)い塚を「姫塚(ひめづか)」、ちょっと錦の方へ下(さが)った所(とこ)にある塚を「爺塚(じじづか)」というて、水場(みずば)のないこの山に登る時は、必ず水をいっぱい持(も)てって、二つの塚に進(しん)ぜとるということや。

|
|
|
姫越山(ひめごやま)
紀勢町錦と南島町新桑竃との間にある山。標高502・9メートル。
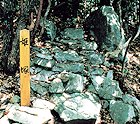
姫越山の姫塚

爺塚
いっぱい持てって
たくさん持って行って
進ぜとる
お供えする
|
|
|
|
|

