むかし、京の都の名高い一休和尚(いっきゅうおしょう)が東海道を旅しとったんやそうや。
そのころ、関(せき)の宿場(しゅくば)に地蔵(じぞう)さんが立っとったんやけど、往来のちりによごれて見苦しなってしもたもんで、里の者らが集まってきれいに洗(あら)い清(きよ)めたんやて。ついでに破れとったお堂も直して、お坊(ぼう)さんが通りかかったら、開眼供養(かいげんくよう)をしてもらおうと待ちかまえとったんやに。そこへたまたま通りかかったのが、一休和尚やったんさ。
里の者はさっそく、
「旅の坊さん、地蔵さんの開眼供養をしてもらえんかいな」
とたのむと、一休和尚は、
「ああ、よかろう」
と心やすく引き受けてくれた。そやけど、地蔵さんに向かって経(きょう)を読むでもなく、
「釈迦(しゃか)はすぎ、弥勒(みろく)はいまだ出(い)でぬ間の かかるうき世に 目あかしめ地蔵」
と妙(みょう)な歌をよんでな。そのうえ、衣のすそをまくって立小便して去ってしもたんやに。
|
|
|
一休和尚
室町中期の禅僧(ぜんそう)。自由な禅(ぜん)のあり方を主張。詩・狂歌・書画に通じ、数々の奇行でも知られている。
開眼供養
新しくできた仏像を供養して、眼(め)を入れ、仏の霊を入れる儀式。
現在の関のまちなみ

|
|
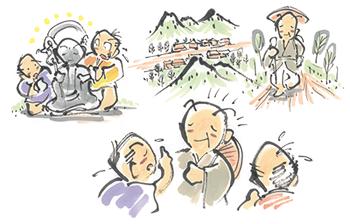
|
|
あっという間のできごとやったんで、里の者らはポカンとしとったんやけど、われに返るとかんかんに怒(おこ)ってな。
「とんでもないインチキ坊主(ぼうず)にたのんでしもたわ」
「あんなうすぎたない坊主にたのんだのがまちがいやった」
「もういっぺん開眼供養をやり直そや」
ということで、ちがうお坊さんにあらためてたのんだんやて。
今度のお坊さんは、身なりもりっぱでな。九条のけさを身にまとい、高座に上って鉦(かね)を打ちならしたり、水晶(すいしょう)の数珠(じゅず)をおしもんだりしながら、むずかしいお経を長いことよんでくれてな。そしておごそかに、
「ここにお集まりの善男善女(ぜんなんぜんにょ)は、功徳(くどく)により病苦(びょうく)をまぬがれ、田畑(でんばた)は穂(ほ)に穂が重なり、天災地変(てんさいちへん)も火難水難(かなんすいなん)も無縁(むえん)となろう。ましてこの関の地蔵のご本尊(ほんぞん)は将軍地蔵(しょうぐんじぞう)じゃから、たとえ大敵や強盗(ごうとう)が現(あら)われても、家のなかまで押(お)し入ることは金輪際(こんりんざい)ない」
と、回向(えこう)の鉦を鳴らしながら告げてな、ありがたさに涙(なみだ)をこぼさん者はおらんだん。感激(かんげき)した一同が心をこめてお坊さんをもてなしたんは、いうまでもないことや。
|
|
|
九条のけさ
けさの中で最も位が高いもの
天災地変
自然がもたらすさまざまな災害や異変(いへん)のこと
火難水難
火による災害、水による災害
将軍地蔵
祈ると戦(いくさ)に勝つという地蔵
回向
法要などの最後に、その功徳(くどく)を他におよぼしたいと願ってとなえる回向文
|
|
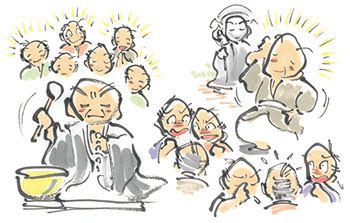
|
|
|
ところがその晩(ばん)、在所の者に地蔵さんがとりついてな、高熱を出し、うわ言のように、「せっかく名僧(めいそう)の供養によって目を開いたのに、どうしてつまらぬ供養のやり直しなどして迷わすのか。元のようにして返せ」
と口走ってな。これを聞いた者はたまげたのなんの。さっそく主だった者が集まって相談し、一休和尚を追いかけて呼(よ)び戻(もど)そうということになったんさ。
使いの者らが、やっと桑名の宿で追いつくことができ、かようかようしかじかと、地蔵がのりうつった様子を伝えると、一休和尚は、
「いまさら関まで引き返すことはできんゆえ、この下帯を持ち帰って地蔵さんの首にかけ、わたしが唱えた歌を三べん唱えるように」
と教えたんやて。使いの者は半信半疑(はんしんはんぎ)で和尚の下帯を持ち帰り、言われたとおりにすると、あっという間にのりうつった人の熱は引いて、もとの元気な姿(すがた)に戻ったんやて。関の地蔵さんが今も麻(あさ)の布きれを首にまいとるのは、こんな由来があったんやに。 |
|
|
関の地蔵
奈良東大寺の修行僧行基(しゅぎょうそうぎょうき)が天平(てんぴょう)13年(741)に造り安置したと言われている。これを享徳(きょうとく)元年(1452)、改めて開眼供養されたのが一休禅師だった
 |
|


|
|
地蔵院
 |
|

