伊勢の国は永井(ながい)の里、井手(いで)のお宮のあたりには、不思議な葦(あし)が生えてるそうな。どんな葦でも、葉は両側にようけついとるわな。ところが、ここの葦だけは、誰かがもぎ取っていったように、片側(かたがわ)にしか葉がついておらんのやと。どう考えても不思議な話じゃの。
実はな、この葦にはこんな話がつたわっとるんよ。
むかしむかし、このあたりは一面の沼地じゃったそうな。いつも澄んだ湧(わ)き水が出ておってな、葦や水草が生いしげり、虫や小魚たちの住み心地のいいところじゃったそうな。
春になれば、水辺には白い花も咲き、秋になれば、赤く染(そ)まった木が水に映(うつ)って、それはそれは、きれいじゃった。
村の人たちは、野良仕事(のらしごと)の合い間にここへやってきては一服することも、しばしばじゃったそうな。
「ここへ来ると、なんかしらんが心がやすまるな」
「そうやな。いつ来ても退屈(たいくつ)することがないわなぁ」
時々訪れる旅の人も、なぜか心をひかれて、ここで疲れた足を休めたということじゃ。
春、夏、秋と過ぎ、やがて寒い冬がやってくると、さすがにこの辺りには、人影(ひとかげ)もなくなってしまい、夜になると、沼はシーンと静まりかえって、村は深い深い眠(ねむ)りに包(つつ)まれていったということじゃ。
北の空に北斗星(ほくとせい)がさえざえと輝(かがや)く、そんな夜がいく晩(ばん)も過ぎたころ、村の人たちが心待ちにしている夜が訪れるんじゃ。
物音ひとつしない静かな夜ふけになると、毎年、どこからともなく不思議な物音が聞こえてくるんじゃと。それは、北の空、遠くのほうから聞こえてくるんじゃが、初めのうちは、耳をそば立てんと聞こえんようなかすかな音なんよ。それが大きくなってくると、初めて鳥の群れの声だとわかるんじゃ。
北の国から食べ物を求めて、広い海を渡ってこの土地へやってくるんよ。
|
|
|
永井
菰野町永井
井手のお宮
井手神社

|
|
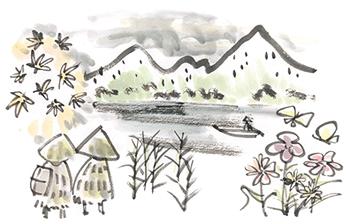
|
|
雁(かり)たちは、長い旅を終えて、やっとめざす沼にたどり着くと、ひときわ高い喜びの声をあげて、水の上を踊(おど)るように泳ぎまわるんじゃ。
村の人たちの中には、鳴き声に目をさます人もおって、
「今年もまた、雁がやってきたな。ぼちぼち正月の支度(したく)にでもかかろうかな」
などと言いながら、また深い眠りにつつまれていったということじゃ。雁が、村の人たちに季節の訪(おとず)れを教えてくれたんじゃな。
村の人たちにあたたかく見守られながら、ひと冬を過ごし、やがて遠くに見える山の雪が溶け出すころになると、生まれた国へ帰ってゆく時がやってくるんじゃ。
雁たちは、帰りの道のりがとてもとても心配じゃった。
どこまで行っても、暗い暗い、そして広い広い海。果てしない旅が待っているんじゃからな。長い旅の途中、羽根(はね)を休める場所はどこにもないので、力つきた仲間が吸(す)い込(こ)まれるように、暗い海に落ちていったそうな。それを見ても、雁たちは、どうすることもできなかったんじゃ。
|
|
|
|

|
|
|
ある年のこと、もうそろそろ北の国へ帰るころ、雁たちは井手のお宮の神様に、みんなでお願いをしたそうな。
「どうか、この沼に生えている葦の葉を私どもに一枚(まい)ずつください」
「それは、どうしてじゃ?」
「北の国へ帰る途中、疲れたら葦の葉を海に浮(う)かべて、その上で羽根を休めたいのです」
「うん、よかろう。そういうことなら、一枚ずつあげよう。ただし、葦の葉を全部とってはならん。枯(か)らしてはならんからな。片側(かたがわ)の葉だけは残しておくように。いいな」
こうして、願(ねが)いは聞きとどけられて、雁たちは、葦の葉を一枚ずつくわえて、飛び立って行ったということじゃ。そして、海の上に葦の葉を浮かべ、つばさを休める雁たちの姿が、いくつもいくつも波間(なみま)にただよっていたそうな。
くる年も、くる年も、雁たちは、そのようにして、北の国へ旅立っていったと。やがて、雁たちがやって来なくなってからも、井手のお宮に生える葦の葉は、片方なかったそうな。
美濃(みの)の国の須賀(すが)という里にも、片葉の葦があるそうな。それも、やっぱり、お宮のそばに生えているということじゃ。水の神さまの思(おぼ)し召(め)しなんかもしれんのう。
今も、井手のお宮へ行ってみると、生えとる葦の葉は、やっぱり片側にしかついておらんのやと。不思議なはなしやなあ。 |
|
|
美濃の国
今の岐阜県美濃地方。
須賀
岐阜県岐阜市須賀
片葉の葦
 |
|


|
|
|

