作品目録
凡例
1. 目録のデータは、カタログ番号、作家名、作品名、制作年、材質・技法、寸法、書き込み、来歴、展覧会歴、文献の順である。
2. この目録の解説等一部は1990年に刊行した『岡田文化財団寄贈作品集』を使用した。
目録執筆者中二名の現在の所属は以下の通りである。
中谷伸生:関西大学文学部
荒屋鋪透:株式会社 ポーラ化粧品本舗美術館設立準備室
1-1
ルノワール、オーギュスト
青い服を着た若い女
1876年 油彩・キャンバス 42.9×31.0
右下に署名 Renoir
1875年の春、ルノワールはモンマルトルの丘の上に建つ、庭つきの家を借りた。1870年代のモンマルトルは、まだ畑や風車のあるパリ郊外の田舎だったが、そこに代々製粉業を営んでいた主人が、田舎風のダンスホールを開いたのである。ルノワールは、倉庫のような建物に楽隊の舞台があり、客は庭園でダンスを楽しむという、この村祭りのような雰囲気が気に入り、さっそく制作を始めた。1876年に完成した作品は翌年の第3回印象派展に出品されている。代表作《ムーラン・ド・ラ・ギャレット》である。現在、パリのオルセ美術館が所蔵するその作品は、社交場で歓談する若い男女の賑やかな笑い声が聞こえてきそうな、明るい色彩となっている。
《青い服を着た若い女》は、この時期に描かれた肖像画。モデルは《ムーラン・ド・ラ・ギャレツト》に登場する、ダンスホールに通うパリ娘のひとりかもしれないが、より有力なのはフィリップス・コレクションの《舟遊びをする人たちの昼食》に描かれたバルコニーにもたれる女性、すなわちアルフォンシーヌ・フルネーズという説である。重要な点は、これらの作品に共通する油彩の制作技法であると思われる。題名が示すように、画面全体は青い色調で統一されているが、それは、この時代のルノワールを特徴づける色彩である。正面を見据える少女の端正な顔は、強い輪郭線と陰影ではなく、小さな筆触を丹念に並置して描かれている。濃い色のリボンが結ばれた白い襟によって、彼女はより鮮明に画面に定着される。オイルスケッチ(油彩下絵)のような、粗い筆致の処理を完成作品と見なす態度はまさに印象主義的である。現在、ワシントンのナショナル・ギャラリーが所蔵する、女優のアンリオ夫人を描いた肖像画は、背景と人物の色彩や筆触、また服装を簡略化し人物を丹念に描く姿勢といった点で、この肖像画に酷似している。モデルの詮索はともかく、ムーラン・ド・ラ・ギャレツトに集う多少コケティッシュな女性とは趣の異なる、この少女の表情もアンリオ夫人と共通するのではなかろうか。《青い服を着た若い女》は画商ウォラール旧蔵の1点である。
(荒屋鋪透)
[補遺]
近年、赤外線ビジコンカメラによる調査を行ったところ、赤外線を当てると、画面の右上端および左上端のそれぞれ三角形状の部分と、それ以外の部分の間に明暗の相違が生じることが判明した。その境界線は左右対称の弧を描いているようにもみえ、画面形式に何らかの改変が加えられた可能性も考えられる。確かに1877年に円形の画面をもつ女性像が制作されているが、ルノワールの肖像画にそうした特殊な画面形式をもつ作例はきわめて少ないようである。
また、本作品の現状とフランソワ・ドールト編の油彩カタログ・レゾネに掲載された図版(fig.1)を比較すると、助成の口元が明らかに異なっている。しかしこの点について、紫外線蛍光と赤外線ビジコンカメラによる調査では新たな情報は得られなかった。
(土田 真紀)
1-2
モネ、クロード
ラ・ロシュブロンドの村(夕暮れの印象)
夕暮れの谷間の風景を描いたこの作品は、静かな自然の姿を重厚に表しているが、風に揺れる樹木の描写などからは、いわくいい難い不気味な雰囲気が感じられる。同時代の小説家かつ劇作家であったオクターヴ・ミルボーは、憂愁と孤独感を漂わす1890年前後のモネの絵画群を指して、「悲劇的風景」と名づけた。この作品は、それら一連の風景画の中の1点である。
モネは、1889年に、西フランスのベリー地方南部に位置する中部高原地帯のクルーズ渓谷へ旅行して、大クルーズ川と小クルーズ川とが合流する地点のフレスリーヌに、3月から5月の中旬まで滞在し、絵画の制作に没頭した。渓谷の山や丘は、大半が灌木と苔におおわれており、深く暗い谷底を小川が流れている。女流画家ベルト・モリゾに宛てた1889年4月8日付のモネの手紙には、「ここは素晴らしい所です。ベリールを想い出させる荒々しくて野生味のある土地です。かつて、私が友人と一緒に来たときに、大変感動しましたので、再度、ひと月前から来ております。人々を驚嘆させるような作品を描けると思ったのですが、仕事を進めてみると、残念ながら、自分の思うようにはなりません。しかも、大変天気が悪くて、毎日、雨が降り続き、とても寒いのです。制作を行うには途方もない根気がいります。」
「夕暮れの印象」という副題が示すように、山の向こうへ太陽が沈んでいき、その光が、空を覆う雲を赤く染めている風景となっている。モネは、これとほぼ同様の構図と寸法によるもう一点の作品《沈む太陽のラ・ロシュブロンドの村》(Le Village de la Roche-Blond au Soleil couchant,fig.1)をこのときに描いている。山間地帯に特有のことながら、景勝の地クルーズ渓谷の天候は、きわめて変わり易く、モネ自身の記述を手がかりに推測するところ、二点のラ・ロシュブロンドの村の絵画は、天気の悪い4月12日の夕方に制作されたようである。両作品には、予備習作としての素描が残されていて、それは現在パリのマルモッタン美術館に所蔵されている(fig.2)。
1889年の6月に、パリのジョルジュ・プチ画廊で、モネと彫刻家ロダンとの二人展が開かれた。そのときの展覧会カタログには、モネについて書いたミルボーの序文が見い出される。この「モネ・ロダン展」は、新聞誌上で称賛を受け、モネの画家としての地位は、不動のものになったといわれる。このときにモネは、1864年から1889年に至る作品群を出品した。展覧会に際してつくられた年譜形式の出品リストを調べてみると、1889年の頃に、7点の作品名が挙げられており、その中に“Village de la Rocheblond”(ラ・ロシュブロンドの村)という作品名の記述が見られる。モネのカタログ・レゾネを編集したヴィルデンシュタインは、おそらく、この出品リストの記述を根拠にして、《ラ・ロシュブロンドの村》がその重要な展覧会に出品されたことを示唆しているが、上記の2点の中、どちらの作品が出品作であったかは、正確には分からないということである。
この点について、ここでは、ひとつの手がかりとして、作品名の「村」(Village)というフランス語に「冠詞」があるかないかという点に注目したい。つまり、《沈む太陽のラ・ロシュブロンドの村》のフランス語表記には、定冠詞の“Le”が付けられで“Le Village”となっているが、三重県立美術館所蔵の《ラ・ロシュブロンドの村(夕暮れの印象)》の方は、“Village”という具合いに、冠詞は付けられていない。作品名が、何時、誰によって付けられたかという、厄介な問題が控えているにしても、1889年の展覧会の作品リストにおいては、冠詞は付けられておらず、ただ“Village”となっていることから、三重県立美術館の作品が、この展覧会に出品された可能性が高いといえるかも知れない。もちろん、このことについては、さらに徹底した調査が必要であり、ここでは、ひとつの手がかりを示すにとどめておく。
《ラ・ロシュブロンドの村》は、19世紀の末に、アメリカ合衆国ボストン在住の個人が手に入れ、以後長らく、アメリカにあった作品である。ニューヨークのメトロポリタン美術館にも、この作品と同時期のモネの風景画が10点ほど所蔵されているが、それらの作品と比較しても、《ラ・ロシュブロンドの村》は、密度の高い絵画だといえるし、また、この時期に制作された数多くのモネの風景画の中でも、高水準の質を示す作品だといえるであろう。しかも、この作品が、1889年の歴史的に重要な「モネ・ロダン展」に出品された可能性が高いということであれば、この絵画は、モネの生涯にわたる数多い作品中でも、とりわけ貴重なものだということになる。 スケッチ帖より マルモッタン美術館(inv.5129.f。
晩年のモネは、美しい色彩を誇る睡蓮の連作を続々と制作した。それとは対照的に、この風景画では、斬新で大胆な構図を次々につくり出したモネの、反骨精神にあふれる迫力ある側面が、重々しくて、しかも繊細微妙な色調によって、見事に表明されている。一瞥では、きわめて単純な構成の絵画だと思われがちであるが、注意深く眺めれば、モネ特有の細い色の線描が、幾重にも複雑に絡み合い、驚くほどに豊かで深さのある油彩画だといえよう。また、画面全体から受ける力強さは、この作品の風格を如実に示していて、とりわけ圧巻である。
(中谷伸生)

fig.1 《沈む太陽のラ・ロシュブロンドの村》 1889年 |

fig.231 |
|
1-3 1891年頃 DEGAS,Edgar |
conté and red chalk on paper vente stamp lower left:Degas Vente AtelierⅡ(no.369) Le Garrec,Paris Collection A.Conger Goodyear,Buffalo Hammer Galleries,N.Y. 原精一 ドガ展(三重県立美術館1988)no.60 P.A.Lemoisne,Degas et son oeuvre,1946,p.680,no.1174ter Vente Atelier Edgar Degas,Ⅱ、no.369 |
 |
 fig.1 1894年頃 52×65 個人蔵 L1174bis  fig.2 パステル 1894年頃 30×40 個人蔵 L1174  fig.3 木炭 1896年頃 162×193 パリ装飾美術館  fig4. 水浴する女たち パステル 1896年頃 108.9×111,1 ダラス美術館 L1071 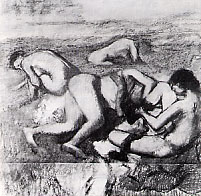 fig5.水浴する女たち パステル 1896年頃 104.6×108.3 シカゴ美術研究所 L1079  fig6.ティツィアーノ・ヴェチェルリオ ディアナとカリスト 油彩 1556~59年 187×205 スコットランド・ナショナル・ギャラリー  fig.7 アニバーレ(あるいはアゴスティーノ)・カラッチ ディアナとアクタイオン 油彩 56×80 ブリュッセル・ミュゼ・デ・ボザール  fig.8 舞台稽古 パステル 1874年頃 53.3×72.3 メトロポリタン美術館 L498  fig9. 《室内》のための習作 油彩 1866~68年頃 61×50 個人蔵 L351 |
三重県立美術館が所蔵するデッサン《裸婦半身像》はささやかな作品ではある。しかし、画面に顔を近づけて観察すれば、紙の凹凸と擦れあったコンテの濃淡、そこから想像し得るドガの筆圧に彼の存在も妙に生々しい。なによりも、自由闊達な線の動きに取り込まれた紙の肌理、赤茶のチョークと紙の地色を活かした陰影表現、メディウムと支持体の一体化こそドガのデッサンの妙技と改めて感動を覚える。 一方、どのようにして描いたのかではなく、何を、と問えば主題としての裸婦が前面に出てこよう。彼女はおそらく水浴する女で、腰の周りに巻いた衣類を左手でおさえ、体をなかばひねりながら右腕の先を見ている。ただ、官能的でない。裸婦がわれわれに想像させるであろう逸話めいた雰囲気を漂わせることなく、肉体としての存在感を訴えている。デッサンの妙技と主題の渇いた扱い、この奇妙な連携をヴァレリーは〈散文〉と呼んだ。 「ドガは彼のどの作品においても極めて真面目である。 ……彼は彼の作品において、詩にも、雄弁にも、達することがなく、彼はただ風格の裡に真実を、また真実の裡に風格を求めているだけなのである。その意味で彼の芸術はモラリスト文学者たちの作家に似ている。すなわちそれは最も、明確な散文であって、この散文が斬新な、そして実証出来る観察を包含し、或はそれに強烈な表現を与えているのである」(1)。 《裸婦半身像》は1891年頃の制作とされている(2)。画面左下にはドガの死後に開かれたアトリエの売り立てスタンプがおされている。売り立ては1918年5月6~8日、12月11日~13日、1919年4月7日~9日、7月2日~4日と都合4回にわたって行われ、アトリエに残されたおよそ1500点余の作品が競売にかけられた(3)。売り立てスタンプは赤と黒の二種類で、油彩、パステル、デッサンには赤のスタンプが押された。黒のスタンプは全体のうちおよそ66点におされ、これらは転写刷りとして区別されている。2回目の売り立てで《裸婦半身像》におされたのは黒いスタンプ(4)。したがって転写刷りとみなされる。 転写刷りとは、版画に精通していたドガが自分のデッサンを複製するために用いていた方法で、トレーシング・ペーパーを使って素描を反転させるか、あるいは漉き込み紙か網目透かし入り紙に素描を制作し、それを湿らせ、新しい紙を重ねてプレスした。こうして同じデッサンを繰り返すことが可能になり、ドガはしばしばパステルで色を加えた。 ルモワーヌが編纂したカタログ・レゾネには、《裸婦半身像》と鏡像関係にある転写刷りが1点掲載されている(fig.1)(5)。紙面の寸法が《裸婦半身像》より大きいため、《裸婦半身像》そのものかあるいはオリジナルデッサンからの転写と考えられる。しかし、ドガの複雑な転写についてはまだ解明されていない部分が多く、転写の過程を追跡することは非常に難しい。 転写刷りのピークは1890年代に訪れ、いくつかの限られた単身のポーズに対して頻繁に行われた。各ポーズはドガの1870、80年代の作品まで元をたどることができるが、90年代のドガにあってはもはやそれらはオリジナルから独立した、形態としての持ちネタであった。時として、そこからいくつのポーズが組み合わせられ、まったく新しい作品がつくりだされた。《裸婦半身像》の場合もそうした作品が2点見つかっている(fig.2、3)(6)。 個人蔵のパステルのエスキス(fig.2)に対し、パリ装飾美術館所蔵の木炭習作(fig.3)は、おそらく最終的な構図であろう。戸外での水浴図は1890年代のドガが集中的に取り組んだ画題であるが、なかでも風景の中に三人の水浴する女たちを配したこの習作(fig.3)は、ダラス美術館(fig.4)、シカゴ美術研究所(fig、5)所蔵の水浴図と並ぶ大作となる予定で、文学的な典拠を連想させる点で、他の水浴図に対して異色な存在となるはずだった(7)。メトロポリタン美術館のゲリー・ティントロウ氏、美術史家で日本でのドガ展(三重県立美術館1988~89年)の協力者でもあったロナルド・ピックヴァンス教授は、この場面を《裸婦半身像》のポーズと左側に描かれた熊(あるいは犬)のモチーフからオヴィディウスの『変身譚』に基づく「ディアナとカリスト(あるいはアクタイオン)」の逸話に帰している(8)。しかし、いずれにせよこの作品は習作の状態で中断された。 さて、パリ装飾美術館所蔵の習作に描かれた三人の裸婦のうち、ディアナ(《裸婦半身像》)を除く二人のポーズはドガの持ちネタの組み合わせである。左側のストッキングを履く(あるいは脱ぐ)ポーズは、ダンス教室の情景に頻繁に登場するし、右端の恥じらいの裸婦のポーズも、初期作品までさかのぼることができるだけでなく、1890年代には転写刷りを含めて少なくとも13点のデッサンが存在している(9)。しかし、ディアナのポーズは《裸婦半身像》を含めて転写刷りが2点あるのみで、形態的な持ちネタとしての足跡はつかめない。その代わりに、ティツィアーノ(fig.6)、カラッチ(fig.7)、プッサン、ドラクロワらが神話画として描いてきた「ディアナとカリスト(あるいはアクタイオン)」の定型を踏襲していると考えられる。この推測は、ドガのスケッチブックをもとにおこなった古典古代の模写についてのセオドア・レフ氏の詳細な研究では残念ながら言及されてはいないものの、ドガの古典古代に関する並ならぬ研究心とアングルやドラクロワの作品を中心とする膨大な作品蒐集を考慮すればまったくの見当違いではないだろう(10)。 それにしても、ドガは1860年代の終わりには歴史画を完全に放棄していた。したがって「ディアナとカリスト(あるいはアクタイオン)」の引用は、水浴図を描くための別の切り口、つまり演出効果と考えられる。むしろ、舞台こそ作品を構想するための重要なイメージソースとなっていただろう。背景の3本の樹木が構図を支え画面に奥行きをもたせているがために空間の完成度がかえって人工的な森の中を思わせる舞台装置。舞台袖からの眺めである左奥へと向かう視点。そして、画面右端の恥じらいの裸婦と左側の熊(あるいは犬)は、ディアナの怒りを恐れて舞台正面を意識するかのように上手、下手にそれぞれ退場していく。実際に、樹木の舞台装置はドガの描くバレエの情景に頻繁にあらわれており、よって、戸外のイメージは演出されたのである。 とすれば、舞台の要素がふんだんに盛り込まれたこの水浴図のなかで、《裸婦半身像》はディアナである以上にバレエのプリマドンナのイメージで制作されていたにちがいない(fig.8)。腕をふりあげたポーズは、彼女を見る誰かに応えるためのダンサーの肉体の動き(ム-ヴマン)のクライマックスであり、いわば見返す身振りなのである。この身振りこそ、ドガが第一番目に《裸婦半身像》に求めたもので、そうした意味において1874年頃に制作された《室内》(L348)のための習作(fig.9)こそ《裸婦半身像》の原点といえるのかもしれない。 ディアナの逸話は、戸外での水浴を背景に見る/見返すというクライマックスを迎える、ドガにとっては恰好の題材であり得た。しかし、バレエをとおして肉体の動き(ムーヴマン)の真実を見た1890年代のドガには、もはや文学的すぎたのである。中断は必至で《裸婦半身像》は〈散文〉のままにある。 (桑名麻理) |
(1)ポール・ヴァレリー(吉田健一訳)「ドガ・ダンス・デッサン」『ヴァレリー全集10芸術論集』(筑摩書房1967年)p.44 |
1-4
ルオー、ジョルジュ
キリスト磔刑
| 1939年 油彩・紙(キャンバスで裏貼)62.7×47.1 右下に署名 Georges Rouault ROUAULT,Georges Le Crucifix 1939 0il on paper and canvas signed lower right:Georges Rouault 原精一旧蔵 Bernard Dorival et Isabelle Rouault,Rouault: loeuvre Peint,Ⅱ,Monte-Carlo,1988,no.1650.(ベルナール・ドリヴァル、イザベル/ルオー/柳宗玄、高野禎子訳、『ルオー全絵画』第2巻、岩波書店、1991年) |
 |
十字架上のキリストを中央に、向かって右手に洗礼者聖ヨハネと聖母マリアが立ち、左手にマグダラのマリアが跪いている。背景は暗く、左手上には白い月がかかっている。ジョルジュ・ルオーは周知のとおり、20世紀の画家の中ではひときわ目立ってキリスト教的な主題を取り上げてきた。とりわけキリストの姿はルオーの作品群に繰り返し登場してくる。その多くはルオー自身が創造した新たなキリストのイメージであるが、伝統的な図像に基づく「キリスト磔刑」あるいは「十字架上のキリスト」もまた、各時期に少しずつ表現を変えながら再三再四現れてくる。本作品はそのうちの1点である。
 fig.1 《十字架のキリスト》 1920年頃 シルヴィー・マゾー氏蔵 パリ  fig.2 《ミセレーレ》 第31図 1923年  fig.3 《十字架上のキリスト》 1936年  fig4. 《十字架上のキリスト》 1939年 パリ国立近代美術館蔵 |
『ルオー全絵画』の著者ベルナール・ドリヴァルによれば、「十字架上のキリスト」がルオーの作品に登場するのは1910年代である。ルオーの娘イサベル・ルオーとドリヴァルの共編による『全絵画』のなかには1914年から1918年にかけて制作された6点が掲載されている(nos.841,842,843,844,845,846)。いずれも十字架上のキリストを中央に、向かって右に洗礼者聖ヨハネ、左にマグダラのマリアが描かれている。キリストの位置は低く、またその姿が画面いっぱいに描かれているため、両手、両足、十字架の先端は画面からはみ出すことになっている。後藤新治氏は版画集《ミセレーレ》に関する研究のなかで、「十字架上のキリスト」という主題を人物構成の点から3つのグループに分けている。それによれば、第1グループは左からマグダラのマリア、キリスト、聖ヨハネの三人からなるのに対し(fig.1)、第2グループはキリストただ一人、第3グループはキリストと聖ヨハネの間に聖母が加わっている。この分類に従えば、1910年代の「十字架上のキリスト」はいずれも第1グループということになる。一方、本作品は第3グループであるが、第3グループの登場は第1グループよりは遅れるようである。 1910年代に描かれた「十字架上のキリスト」は、墨による素描にグワッシュで軽く彩色されたものなど、下絵的な性格の強いものがほとんどであるが、この時期ルオーは画商アンブロワーズ・ヴォラールとの契約により版画集《ミセレーレ》の構想にすでに取りかかっていた。それは1912年の父の死を契機にルオーが構想し始めた、彼にとって最初の版画集の計画であり、1927年には最終的に版画集に納められた58点すべてが完成したが、ヴォラールとの複雑な関係ゆえに、実際の出版はヴォラールの死後の1948年となった。ルオーの最も重要な版画集であるのみでなく、彼の宗教思想、人間への洞察などの全体像を包み込み、あらゆる点でルオーの芸術の本質を示している。この《ミセレーレ》の第31図として、聖母マリアが加わった第3グループの「十字架上のキリスト」が含まれている(fig.2)。《ミセレーレ》の全作品にはルオーによる題辞が付されているが、第31図のそれは、新約聖書の『ヨハネ福音書』第13章34節「われ新しき誡命を汝らに与う、なんじら相愛すべし、わが汝らを愛せしごとく、汝らも相愛すべし。」から取られた《汝ら、互いに愛し合うべし》である。《ミセレーレ》の第31図は、銅版の右下に「1923 g Rouault」と入っており、1923年に完成したことがわかる。後藤新治氏の指摘によれば、この図のエリオグラヴュールのステート(第1ステート)には、当初ルオーが表題として考えていた《ミセレーレと戦争》の文字が上部に書き込まれていることから、もともと扉絵として構想された可能性があるといい、ミセレーレ全体のなかでも重要な位置づけにある作品と考えられる。 ところで、《ミセレーレ》第31図については、10年もの歳月を経て1934年から色刷りの試みが行われ、1936年に完成している(fig.3)。シュガー・アクアティント、アクアティント、ルーレット、スタレイパーの技法を駆使したこの色刷りのヴァージョンは、本作品により近づいている。十字架の位置は低くなって背景の建物が消え、背後の空間は抽象性を強めている。キリストの首の傾きは緩くなり、キリストの光輪はよりはっきりと描かれている。キリストの人体の表現や他の登場人物の細部の表現も本作品に非常に近づいている。また単色版にははっきりと書かれていた伝統的なキリスト磔刑図に登場する十字架の上端の“INRI”の文字がここでは判読困難な別の文字に変わっている。ただし、本作品と異なり、この画面には月は描かれていない。 『ルオー全絵画』のなかでは、本作品を含め、油彩、水彩、素描7点が《ミセレーレ》第31図の類作と位置づけられている。本作品と特に近い関係にあるのは同じ1939年の作であるパリ国立近代美術館蔵の作品(no.1651,fig.4)である。“INRI”の文字が消えている点、向かって左上に月が描かれている点も共通している。 以上のように、「十字架上のキリスト」は、ほぼルオーが《ミセレーレ》に取り組み始めた時期に登場し、《ミセレーレ》完成後も繰り返し描かれた。しばしばステンドグラスの技法に擬せられる太い輪郭線による単純化を特徴とするその形態把握と呼応するかのように、ルオーはキリスト以外の登場人物を最小限に抑え、十字架やキリスト自身の手が画面に納まり切らないほど、キリストの姿を画面の中心に大きく据えた。そして最初に構想されたこの基本形を踏襲しながら少しずつ変更を重ねつつ、繰り返し描いたのである。したがって本作品のように《ミセレーレ》の完成以後に単独で描かれた場合も、《ミセレーレ》全体の構想と完全に切り離しては考えられないと思われる。 《ミセレーレ》においてキリストは神である以前に一人の人間である。《ミセレーレ》の扉絵に続く第2図と第3図には頭を垂れて辱めを受けるイエスの横顔が描かれ、第2図から第4図にはルオーの創作による「イエスは辱しめられ、たえまなくむち打たれ、哀れな放浪者よ、お前の心の中に身を避ける」という題辞が付けられている。すなわちイエスは何よりも《ミセレーレ》の他の登場人物の多く、人生の重いくびきを背負いつつけなげにこの世を生きるすべての孤独な苦しむ人々の代表なのである。一方《ミセレーレ》の登場人物の残りは裁判官や軍人などの権力者、欲深い金持ちなどである。その中で、イエスがすべての人間の苦悩と罪とを一身に背負って受難する磔刑の場面である第31図に、ルオーは《汝ら、互いに愛し合うべし》という題辞を与えた。同じ《ミセレーレ》でも第20図や第57図の単独像の「十字架上のキリスト」は、あくまで孤独な受難の人として表わされているのに対し、聖ヨハネ、聖母、マグダラのマリアに囲まれた第31図では、この世のあらゆる苦悩と罪業からの救済の確かな可能性をもルオーは伝えようとしている。その意味で第31図は《ミセレーレ》全体のなかでも最も力強いメッセージを放っているように思われる。 技法の点で触れておかなければならないのは、本作品が紙に油彩で描かれている点である。紙はキャンヴァスで裏打ちされ、破損箇所を見ると、キャンヴァスと紙の間に補強のためか細かい網目状のものが狭まれている。こうした例は例外的ではなく、ルオーの場合、多くの油彩が紙に描かれている。この点について後藤新治氏の興味深い指摘を紹介しておきたい。それによると《ミセレーレ》の制作過程に関連して、ルオーは当初下絵として描いた墨による素描にグワッシュや油彩で彩色を加え、さらに銅版画の制作後にはそれらをすべて油彩画として描き直した可能性があるという。また銅版画の制作過程の修正図のなかにもグワッシュや油彩によって別の作品に仕上げられたものがあるという。同様のことは別の版画集《受難(パッション)》の場合に行われており、ルオーの油彩の多くが紙に描かれているのは、こうした可能性と関連があるとすれば確かに不思議ではない。本作品がそうした例にあたるのかどうか今後検討していく必要がある。 本作品には、ルオーの油彩における勢いのある筆遣いを見て取ることができるが、それは、版画集《ミセレーレ》にみる銅版画のあらゆる技法を駆使した重厚な画面や、その色刷版の水彩のように透明な色彩の輝きを誇る画面とも別個の魅力を画面に与えている。主題や構図は同じでも、油彩においては油彩ならではのマティエールや技法の探求が行われたことは当然であるが、1940年代以降、ルオーが油彩において厚塗りに向かう以前の、ある種の軽やかさを残した作品といえる。 (土田真紀) 参考文献
|
1-5
デュフィ、ラウル
黒い貨物船と虹
| 1949年頃 油彩・キャンバス 38.0×46.1 画面下中央に署名 Raoul Dufy DUFY,Raoul Le Cargo Noir et l’Arc-en-ciel c1949 oil on canvas signed lower center: Raoul Dufy 原 精一旧蔵 展覧会『海』(安田火災東郷青児美術館1996)no.48 Maurice Laffaille,Raoul Dufy Catalogue raisonné de l'oeuvre peint, Ed Motte,Genève,.T.I.1972,T.Ⅱ.1973,T.Ⅲ.1976,T.IV.1977,no.744 |
 |
デュフィは海をこよなく愛した画家である。海をモチーフとした作品には、ヨット、水浴する人々、釣人などがところ狭しと華やかに描かれる。そして、ときには彼が好んだそれらに混じり、海の女神が登場することもある。デュフィの生地ル・アーヴルに近いサン・タドレスの埠頭を描いた本作品にもそうした対象が取り入れられているが、それぞれのかたちが他の作品と比べ一層簡略化されているため、具体的に何であるのかの判断が難しい。手前の人物は、水浴しているともとれるが、この悪天候という状況を考えると海の女神である可能性もある。人物の周囲に散在する三角形も断定はできないが、他の作品から推測すると、子エビを捕るための仕掛けでないかと思われる。
〈黒い貨物船〉は晩年に近い1948年から1952年までしばしばとりあげられたモチーフである。豊かな色彩で光溢れる作品を描き続けた彼は、手記にあるように、この時期に黒から光を生み出す探求を始めた。1940年にドイツ軍侵入のためニースに避難して以来、南仏やスペイン、そして1950年から多発性関節炎を直すためアメリカヘ行くなど各地を転々としていたことから、本作品は記憶を頼りに描かれた可能性が高い。
(田中善明)
 fig.1 デュフィ《黒い貨物船》 1948年 ルイ・カレ社コレクション パリ |
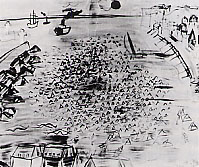 fig.2 《サン・タドレスの海岸》 制作年不詳 ジュール・シェレ美術館 ニース |
1-6
ミロ、ジョアン
女と鳥
| 1968年 油彩・キャンバス 100.3×65.6 image size:99.8×64.7 右中央下に署名 Miro MIRÓ,Joan Femme et Oiseaux 1968 oil on canvas lower center right:Miró 100の絵画・スペイン20世紀の美術-ピカソから現在まで-(三重県立美術館1991)no.16 Pere Gimferrer,Miró. Coipir sense nafrar,Barcelona,1978,p.70/pl.68 |
 |
この作品の原題はFemme et Oiseauxとなっていて、これもふくめてすべてのタイトルをフランス語でしるすのが習慣となっているミロではあるが、画家としてのキャリアをパリではじめたこと以外にとくにわけはなくて、そのこととかれがスペイン、というよりもそのスペインからの分離さえかんがえている独立心のさかんなカタロニアへいだくつよい愛着は矛盾しない。ピカソよりもダリよりももっとカタロニアの生命にふかく根ざした芸術家-それがミロなのだ。かれはじぶんの名をカスティリア語風のホアン・ミロでなくてカタロニア語風にジョアン・ミロとよんでほしいといっている。
できあがった作品だけをみるかぎりこの風土のちからはみすごされがちだけれど、ミロはじつにおおくのものを故郷の伝統的な造型のことばにおっている。たとえばかれの作品にしばしばあらわれる空中にたったひとつみひらかれた眼。宇宙の夜にひかるあれらはカタロニア・ロマネスクのふるい僧院をかざる壁にえがかれた天使たちの眼がもとになっているという。星をあらわす*印についてはいうまでもない。ようするにミロのせかいをつくるあれらのユニィクな形態の源をたどれば、どれもこれもついにはカタロニアの大地と空にはさまれた自然と歴史のながい影をひいて現にそこにあるなにがしかにたどりつかずにいないというべきか。日常のごくささいなものたちについての記憶の細部からあのだれにもまねようのない無限の宇宙の全体ができあがっている。
もちろんこういう魔術みたいな芸当は一朝一夕でできるものではない。ミロに天才があるとしたらそれは性急にならないでじっと耐える天才のほかではないだろう。「ものたちはとてもゆっくりとぼくのところにやってくる。ぼくはかたちを一瞬に発見したりなんかできない。それはむしろぼくにさからってぼくのなかでうまれる。」とミロがいうとき、そこにはどんな誇張もないというべきだ。ひとつのものから千のかたちをひねりだす手わざの才能ではなくて、千のものをひとつのかたちにしかえがけない不器用なら不器用こそかえって自由にいたるはやみちでありうるということの証明。ミロがミロであることの意味はこのあたりにある。
この《女と鳥》は1968年の作品。単純でつよいフォルムと色をひとめみるだけでもうとおくからでもミロとわかる。女と鳥のモティーフはすべて黒でえがかれているが、どこまでが女でどこから鳥なのか区別できないし、また区別しなくてもかまわないという風につくってある。こころを空白にしたあと、えがくことのカオス/無がおのずからかたちをととのえてあらわれたのが女と鳥だったからだし、そうでなくてもミロにとって山や雲が男であることとおなじくらい、丘や鳥は女の性をひめた存在だということがあって、女と鳥とはその意味でほとんどおなじ記号でありうる。もっとも鯨がチェロにらくらくと変身するミロのせかいでは、雲もときによっては一種の鳥なのであるが。なぜなら雲は飛ぶし、鳥もまた飛ぶのだから雲は鳥にひとしいというロジックこそここでの公準であり、かたちについてのただひとつのエチカなのだから。
いっぽうフォルムをフォルムとしてみていると、その原型というのだろうか、はじめに発想したかたちを無造作にすてたりしないでほとんどいつくしむようにそだてるのがミロの流儀だとわかる。ふりかえって《アルルカンのカーニヴァル》(1924-25年)や《鳥に石をなげる》(1926年)などに、バトンと弓のくみあわせとでもいえそうな鳥のモティーフの骨格はすでにあきらかで、それからおよそ40年、いっそう根源的に純粋に、鳥たちはゆっくりと樹木のようにそだって画面をとびつづけ《女と鳥》にいたったという風情である。
ところでかつてのグロテスクなまでの騒々しさ、恐怖と破壊のものがたりはどこへいったのか。どこへもいかない。より頑丈でしなやかに運動するカリグラフみたいな線やもっと野性にちかづいた色となったいれもののなかで、グロテスクとユゥモアがたわむれ、ミロは微笑しながら怒っているだけだ。こういうたたかいのしかたは、この世の怪物たちをそのメカニズムを理解することでそっくりそのまま征服したあのレオナルドのおしえとみかけほどはなれていない。
(東俊郎)
1-7
ゴヤ・イ・ルシエンテス、フランシスコ・デ
旅団長アルベルトフォラステール
|
この肖像画は20世紀の初頭より、マドリードのドン・ハビエル・ミリャーンの所蔵になるものとして、展覧会や作品目録に登場する。当初本作のモデルは、「ドン・アントニオ・フォラステール」と記載されてきたが(Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes,1900;Von Loga,1903;Calvert,1908;Stokes,1914;Beruete,1916;Mayer,1923)、1905年までパリのエドワーズ・コレクションにあり、1909年にニューヨークのアメリカ・ヒスパニア協会に収蔵された、同じモデルを描いた膝までの肖像画(fig.1;油彩・キャンバス、138,5×109.5cm)に「アルベルト・フォラステール、ゴヤによる1804」(“Alberto Foraster por Goya 1804”)との署名および年記が記されているところから、現在の同定に訂正された(Starkweather,1916;Museo del Prado,1928)。 また、ミリャーン家では本作のモデルは海軍士官と伝えられてきたというが、アントニオであれアルベルトであれ、その名は1717年から1834年までの海軍士官候補生の間には見出されず、また制服も異なっており、この伝承も捨てられなければならなかった(Museo del Prado,1928)。その後の調査によると、フランシスコ・メルチョール・アルベルト・フォラステール・モンタネールFrancisco Melchor Alberto Foraster Montanerは、1737年12月16日、スペイン北東部のタッラゴーナ地方アルコベルで洗礼を受けている。17歳の時騎兵に加わり、1792年11月にはラ・コンセプシオーン駐屯地の司令官に就任、同月ドーニャ・イサベル・ルエスマと結婚した。1800年4月15日には旅団長brigadierとなり、24,000レアールの俸給を受ける(Beyersdorf,1962,p,539)。以後、王立獣医学校で指揮官将校に任命され、1819年にいたるも同職をつとめている(Museo del Prado.1928)。最後に彼の名が公文書に現われるのは1820年で、この年に没したものと推測される(Beyersdorf,op.cit.)。アメリカ・ヒスパニア協会の作品が描かれた時点で彼は66歳(あるいは67歳を迎えたばかり)、旅団長の制服を身につけている(Museo del Prado,1928)。ゴヤにとっては、『ロス・カプリチョス』の出版(1799)、『裸のマハ』および『着衣のマハ』(c.1797-1800、プラド美術館)、『カルロス四世一家』(1800-01、プラド美術館)などと、『イサベル・デ・ポルセル』(1805、ロンドン、ナショナル・ギャラリー〉、『巨人』(1808?、プラド美術館)、『戦争の惨禍』の制作開始(1810頃)などにはさまれた時期にあたる。 |
 fig.1  fig.2 |
三重の作品とニューヨークの作品との関係については、前者を後者の習作とするもの(Mayer,1923;Fitz-Gerald,1928-50)、レプリカないし習作とするもの(Museo del Prado,1928)があって、見解は一定していない。そんな中グディオルは、ニューヨークの作品について一方で、「肖像は厳しく、とげとげしくさえある」、「この時期のゴヤにしてはコントラストが強く」、「線は普段のゴヤの技法よりも力強い」と記しつつ(Gudiol,1970,Ⅰ,p.296)、他方、「人物の頭部の堂々たる習作[三重の作品]を制作した後で、手早く、不承不承描かれたもの」と述べている(id.,p.122)。ちなみにニューヨークの作品は、Ⅹ線撮影によって、ポルトガル出身の画家ホセ・カエタノ・デ・ピニョ・エ・シルバが1793年頃制作したゴドイ国務長官の肖像画の上に描かれたものであることが判明した(Beyersdorf,1962)。また他に、下部がひどく傷んだレプリカの存在が報告されている(Fitz-Gerald,1928-50:油彩・キャンバス、130×108cm、旧デュラン=リュエル蔵、パリ)。
以下に1993年3月5日づけの田中善明による本図の状態調査報告から引いておこう;現状ではキャンバスに裏打ちが施されているが、Ⅹ線撮影から(fig.2)、「作品左部分および右上隅、右下隅にキャンバス布が継ぎ足されていることがわかった。また、上辺、右辺、下辺には等間隔の小さな穴が確認され、それがキャンバス釘の穴であることが断定できた。つまり、右上隅および右下隅に継がれた布は最初に描かれたものよりも広げられたことがわかる。右上隅と右下隅の継がれた布は明らかに原画の布とは異なった布であるからゴヤ自身が、絵のバランスを考えて継ぎ足したものではないようだ。画面左の継がれた布に関しては、釘穴が見あたらないため、後補のものであるかどうかはわからない。しかし、継がれた布の形状から一度は継がれる前の状態で作品は描き進められていた可能性は高い」。また赤外線撮影によると、「作品周縁部に補彩が見あたった。画面左側も右側の画面より色調が暗く、補彩部分の色調と酷似していたために後補によるものと考えられるが、この調査の時点では断定できない。しかし、幸いにも人物が描かれた部分に関しては殆ど後補がない」。
画面はゴヤの同じ時期の肖像画同様、赤褐色の地塗りを施した上に描かれている(cf.Catálogo de la exposición Goya.250 aniversario,Museo del Prado,Madrid,1996,cat.nos.105-109)。人物を描いた部分では概して、塗りは厚くなく、しばしば赤地を認めることができる。そんな中、額、目もと、顎など明るい部分が不透明かつやや厚めで、眼窩周辺、鼻と唇の間、眉等はより薄く、明るいグレーか暗褐色を薄くかけて陰とする。肌は赤みを帯びて血色のよさを誇示する一方、グレーおよび暗褐色の陰とあわせて、明るい部分でも、粘りのある筆致の暗示する微妙な凹凸が、肌がすでに張りや滑らかさを失なっていることを伝えずにいない。他方胸もとの白は、画面中もっとも堅練りで、キャンバスの上で筆をこねまわしたかのような速度のある動きをしめしている。グレーを敷いた上で襟の刺繍を表わす白もこれに準じ、襟の赤の鮮やかさと相まって、モデルの社会的位置を伝達するという肖像画の機能をはたそうとするのだろう。ともに〈絵画的〉な様式で処理されながら、また、暗部に対し同じく明部をなしつつ、顔面の沈静と衣裳の鮮烈さは対照的だ。左辺から幅4cmほどの布を継いだ部分はおくとして、胸像を描いた後で背景の暗褐色を埋め、さらに、右頭頂部から後ろ髪にかけて、黒か濃いグレーのきわめて粗放な筆教を走らせ、微かな奥行きをもたらすことになる。
(石崎勝基)




