4-39
前田寛治
《裸婦》

4-39 前田寛治《裸婦》
1928(昭和3)年 油彩・キャンバス
90.9x116.7cm
|
前田寛治の死後まもなく刊行された『前田寛治画論』(金星堂 1930年)の口絵に掲載されているのに加え、翌年に刊行された『前田寛治画集』(第一書房 1931年)にも《裸婦Ⅲ》として掲載されている。 後者に付された外山卯三郎による解説によれば、「一九二八年の帝展出品が終った余暇に生れたのが、このタブロオで一九三○年展に出品された」という(註1)。これに基づけば、1929年1月15日から30日まで東京府美術館で開催された「1930年協会第4回展」に出品された《横臥裸婦》が本作品であろうと推定される。第4回展に前田は《棟梁の家族》《少年像》《花》《裸》《仰臥裸婦》《赤衣の像》《坐像》《肖像》《横臥裸婦》の9点を出品した。このうち《仰臥裸婦》は現在神奈川県立近代美術館の所蔵となっている作品(fig.1)である。《横臥裸婦》の図版は、この展覧会を取り上げた当時の美術雑誌等にも掲載されていないが、昭和4年2月号の『みづゑ』の展覧会評「第四回一九三○年展 感」の中で、古賀春江が「『横臥裸婦』は一昨年の帝展出品の裸体と同系のもので揺ぎない写実である」と書いているのが注目される。「一昨年」すなわち1927年の第8回帝展で特選となった《横臥裸婦》(fig.2、『前田寛治作品集』美術出版社 1996年 no.261)と本作品とは、裸婦の向きやポーズがかなり近く、一見して類似性が指摘できる。外山卯三郎の解説と古賀春江の記述から、本作品が第4回展出品の《横臥裸婦》と考えて差し支えないものと思われる。 さて、1930年協会第4回展に出品された9点のうち最も注目を集めたのは《棟梁の家族》であった。現在もなお前田寛治の代表作のひとつと目されているこの作品は、各誌に図版が掲載され、批評が寄せられた。この《棟梁の家族》があまりにも注目を集め、また裸婦としては《仰臥裸婦》が新機軸を示す作品であったせいか、《横臥裸婦》に触れた展覧会評は少なく、先の古賀春江が唯一である。サイズも50号にあたり、《棟梁の家族》や《仰臥裸婦》など、前田にとって最大サイズの作品を前にしては、目立たない作品であったのも当然である。 |
註 1 『前田寛治画集』第一書房 1931年 17頁。  fig.1  fig.2 |
|
前田寛治による本格的な裸婦の制作はパリ留学中に始まる。習作としての小品は留学初期から描かれていたと考えられ、2年前に刊行された『前田寛治作品集』(前掲書)には1923年頃として裸婦習作が数点収録されている。1925年の作はさらに増える。本作品に直接つながる〈寝台に横たわる裸婦〉が描かれるのも1925年である。少なくともこうした主題による2点の大作(『作品集』no.123,no.130)には1925年の年記かある(註2)。これら2点の作品には、クールベ、マネ、アングル等の影響がそれぞれ指摘されているが、この頃から意識的に裸婦、それも〈寝台に横たわる裸婦〉という主題に前田寛治は取り組み始め、制作と平行して西洋美術のいわゆる「古典」の研究を開始している。研究の成果は、作品に直接反映されると同時に、帰国後に書かれた理論的な文章に示されているとおりである。前田は、これらの「古典」を「分析」することによって、絵画の「普遍的な」原理を探り出すことができると考え、そしてその原理を自らの作品で実践することができると考えていた。たとえば「裸体と背景の関係の要訣」(『アトリエ』昭和3年4月号)ではルノワール、マティス、ピカソ、ルオー、ドラン、ゴーギャン、セザンヌ、クールベ、マネ、シャヴァンヌ、ドラクロワ、アングル、ドーミエ、ゴヤ、別の論考ではジョルジョーネが取り上げられるなど、16世紀から20世紀にいたる代表的な画家の描いた裸婦が前田の研究の対象となっている。 |
2 今泉篤男によれば、前田寛治は、制作時に年記をいれなかった滞欧作に後からいずれも1925年の年記をいれたため、実際には1923年に描かれた作品で年記が1925年になっているものがあるという。また、2点の裸婦のうち個人蔵の1点(『作品集』no.123)は、背景が帰国後の1926年に「ほとんど描き直された」ということである(今泉篤男『前田寛治』アトリエ社 1941年 59頁)。 |
|
制作にあたってもきわめて明確な意識をもって研究を進めており、前田の意図するところは一作ごとに明らかに異なっている。また構想を示す鉛筆の素描を経て、小画面の油彩スケッチでまず試作が行われ、大画面にかかるという制作過程をとっている。本作品にも鉛筆による下絵(fig.3)が残っており、1993年に石橋美術館で開催された「前田寛治素描展」(cat.no.87)に出品された。この下絵には「116:90」という数式が書き込まれているが、本作品のサイズと一致する。素描展の図録で指摘されているように、下絵の段階ですでに構図は固まっており、「そのまま油彩画に拡大されている」。 |
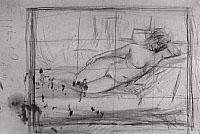 fig.3 |
|
そうして1点ずつ丁寧に描かれていった裸婦のなかで、1928年の遅くに制作された本作品はどのような位置にあるといえるのだろうか。残された作品の年記をみるかぎり、前田の裸婦研究はほぼ1928年で終了している。外山卯三郎のいうとおり本作品がこの年の帝展後、すなわち1928年10月以降に描かれたとすれば、一群の裸婦のなかでも最も遅くに描かれたもののひとつといえよう。古賀春江の評にあったように、本作品は前年の第8回帝展に《少女と子供》とともに出品され、特選となった《横臥裸婦》(図2)のヴァリエーションともいえる作品である。後者と比較したとき、裸婦のポーズにおける最大の相違点は右腕で、先行作では肘を曲げ、手をベッドについているが、ここでは体の線に沿って伸ばしている。左腕が頭部の前から横に移動し、腰から下の部分も曲げ方が浅くなっており、体全体が画面に平行に近づいている。裸婦全体が一続きの淀みないリズムをもつようなポーズをとっている。 こうして基本的な構図や裸婦の配置、ポーズ等にそれほど変化がない分、「描き方」の相違が目立って感じられる。まず、前作に比べ、背景を中心に説明的な描写がここでは少なくなっている。前作ではシーツの皺などに再現的な描写がみられたが、ここでは給具の筆触を生々しくみせており、再現性ははるかに薄らいでいる。筆遣いはこれまでになく大胆で、シーツの白、その上の赤、裸婦の頭部の背後の青が色彩のまま画面上で機能し、あくまでヴァルールと筆の動きによって空間の奥行きを生み出そうとする前田の意図を示している。裸婦も細部の表現がより単純化されている。陰影の表現はこの年の帝展出品作と似ており、より大きな単位で捉えられ,明部と暗部の対照が強まっている。影の部分にあたる顔はほとんど灰褐色をしている。そのほか、右手に施された青、寝台の青緑など、わずかな部分の彩色も注意深く行われている。細部の再現性を否定し、単純化を進めつつ、空間の奥行と裸婦の量感を最大限確保しようと試みている点で、前田のさらなる実験的な制作態度を示しているように思われる。これまでとりたてて論じられる機会のなかった作品ではあるが、彼の裸婦研究のひとつの最終段階を示す作品といえるのではなかろうか。 |
|
|
前田寛次の裸婦研究において浮き彫りにされるのは、絵具による見たものの説明的な再現という性格を可能なかぎり否定し、画面を色彩と筆触の集合へ還元しながら、なおかつ単なる物質としての色の塊や抽象的な空間へと向かうのでなく、あくまで裸婦を裸婦として、布を布としてその「量感」「質感」「実在感」(註3)を捉えようとすることの困難である。前田の「写実」とは現実と絵画との間のぎりぎりの均衡を探るものにほかならない。本作品がどこか未完の印象を喚起するのもそれゆえである。 (土田真紀) |
3 前田寛治「写実技法の要訣」『前田寛治画論』金星堂 1930年 45-51頁(初出は『1930年協会美術年鑑(1)』東京詩学協会発売 1929年)。 |
