『器物図集 巻三』と板谷波山のアール・ヌーヴォー
土田 眞紀
1 『器物図集 巻三』について
| 出光美術館所蔵の板谷波山のデッサン帳『器物図集 巻三』は、575枚の薄手の和紙に描かれたデッサンを綴ったもの(現在では保存上の理由から1枚ずつ分かれ、裏打ちが施されている)で、表紙中央に「器物図集 巻三」、左下に「虚舟庵」と墨書きされている。その大半は、花瓶や壺の輪郭に植物や動物などの図案が描き込まれており、墨による線に加えて美しく彩色が施されたものも多い。またこうした図の周囲には、様々な覚え書きが書き込まれており、そこからデッサンが描かれた年代やそのソースがわかるとともに、デッサン帳が唯一の機能を持っていたのではなく、そのなかには波山にとって少しずつ意味合いの異なるデッサンが混じり合っていることが窺える。 年記はすべてに入っているわけではないが、拾っていくと明治30年代から昭和30年代に及んでいる。そのなかで、全体の約3分の2を占め、その前後のデッサンとは明らかに区別できる特徴を示し、また波山の全デッサンのなかでも特に重要な意味を持つと考えられるのは、明治34年から38年にかけて集中的に描かれた一群のものである。この時期以後のデッサンは、直接彼の作品と結び付く準備段階としてのものが多くなるのに対し、明治34年から38年という時期は、ちょうど本格的に陶芸の研究を開始して間もない頃にあたり、実際に制作するしないに関わらない、図案自体の研究、模索が集中的に行われている。したがって、一口にデッサンといっても、外国作品を中心とする自作以外の作品の模写、自作のための図案の構想、実際に制作する際の色彩や技法上の指示・Lしたもの、投稿用と思われる署名人りのものなどが混在している。 明治34年以前に描かれたデッサンを含む波山のデッサン帳としては、出光美術館蔵の『模様集 巻二』、『模様集 巻三』、『花果粉本』、『器物図集 巻二』、個人蔵の『しみのすみか』全5冊などが現在遺されている。このうち『花果粉本』は、明治20年代から昭和30年代までの、自然をモティーフとした写生によるデッサンをまとめたものである。モティーフは草花を中心とする植物、および鳥、虫、魚など動物で、年代的には60年以上にわたっているが、スタイルの上での変化はみられず、ほとんど変わらぬ姿勢で身近なモティーフを丁寧に写し取っている。この『花果粉本』を除くデッサン帳は、いずれも主として日本と中国を中心とする東洋美術、工芸の名品の模写からなっている。それらは東京美術学校時代から石川県工業学校時代にかけて、帝室博物館や骨董商などで直接目にしたもの、あるいは書物で目に止まったものから、その全体や部分が写し取られており、ときには丁寧に彩色が施されている。ここでは後の陶芸家としての歩みに直接つながるような陶磁器の模写だけでなく、能装束を初めとする染織品など、平面的な装飾パターンの研究も盛んに行われており、『模様集 巻二』のなかには波山自身による友禅図案も含まれている。 |
 挿図1 器物図集 巻三  挿図2 器物図集 巻三 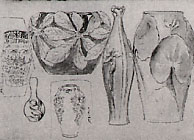 挿図3 器物図集 巻三  挿図4 器物図集 巻三  挿図5 起立工商会社 〈飾皿図案(青筋揚羽にシャカ)〉 明治15年(1882)  挿図6 器物図集 巻三   左)挿図7 器物図集 巻三 右)挿図8 エミール・ガレ 〈(花瓶図案(ダリア)〉 |
||
| 1点1点を詳しく調査した結果ではないが、全体の印象としては、明治34年依然の波山の目は、主として、東洋、しかも古美術に向けられているのではないかと思われる(註1)。この時代としては当然の姿勢であろう。ところが『器物図集 巻三』には、はっきりと同時代の西洋の影響、さらに限定するならば「アール・ヌーヴォーArt Nouveau」の影響が見て取れることがこれまでの研究で指摘されてきた。まず、客観的な事実として、デッサンのなかに「外国雑誌」、「『ステジオ』所載」、「アートデコレーション」などの覚え書きの付されたものがある(挿図1、2)。荒川正明氏によって指摘されているように、1893年にイギリスで創刊された『ザ・ステュディオThe Studio』誌や、1897年創刊のフランスの『アルテ・デコランオンArt et Decoration』誌など、ヨーロッパの装飾美術関係の雑誌に掲載された図版から花瓶などを模写しているのである(註2)。その他、アメリカの陶芸雑誌『チャイナ・デコレーターChina Decorator』とそれを引き継いだ『ケラミック・ステュデイオKeramic Studio』誌やドイツの雑誌からの模写も含まれている。これに加え、商品陳列館や帝室博物館で直接目にしたアメリカ、フランス、スイスなどの製品や、「東京高等工業学校蔵」と記された、アメリカの美術陶器の会社ロックウッドRookwood製の花瓶のスケッチも見出すことができる。またソースは不明であるが、ジークフリート・ビングSiegfried Bing(通称サミュエル・ビング)と関連するコペンハーゲンのビング・アンド・グレーンダールBing and Grohndahl社の製品のスケッチなども含まれている(挿図3)。 |
註1 | 荒川正明氏の論文「板谷波山とアール・ヌーヴォー-波山芸術への一試論」(『出光美術館館報61』、1988年)によると『模様集 巻2』にも「明治32年5月3日」と書かれた外国雑誌からの模写がみられる(62頁)。また同氏の「板谷波山デッサン『泰西新古模様』-明治30年代におけるアール・ヌーヴォー様式との出会い」(『出光美術館館報84』、1993年)では、西欧の器物の模写は明治25年に始まると指摘されている(45頁)。しかし同氏も述べているように、本格化するのは明治33年以降と考えられる。 | |
| 2 | 荒川正明「板谷波山とアール・ヌーヴォー」、63頁。 | ||
| 外国製品のスケッチから波山自身の図案に目を転じると、まず明らかにアール・ヌーヴォーを想起させるS字曲線が所々に見出される。たとえば図版144-(13)や挿図4の図案で繰り返されている曲線は、きわめて「アール・ヌーヴォー的」である。しかし全体としては、こうした一見してアール・ヌーヴォー的なモティーフや抽象的な図案よりも、身近なモティーフや基本的に写実的で絵画的な図案が目につく。写生を通じて学んだ描写力を生かし、自然のモティーフのもつ瑞々しい生命力を図案のなかにそのまま写し取ろうとする意志が随所に感じ取れる。すでに触れた外国製品のスケッチ、およぴそこから学んだ成果は、こうしたモティーフをいかに器の形と有機的に結び付け、その表面と一体化した形で配するかという追求に向けられているように思われる。日本画的な自然モティーフの表現を工芸図案へ応用しようとする傾向は、明治10年代の起立工商会社あたりの図案(挿図5)に始まり、20年代に盛んに試みられたが、この日本画的な表現の延長上で、さらに器とモティーフの関係の中に新しい図案を模索する方向である。似たような方向性は、同時代の他の工芸家の作品にもみられる。そのなかで、波山の場合注目されるのは、細部の表現に執着せず、全体の構成を重視している点であり、なかでも葉や花など部分的なモティーフの単位を、大きさや形を少しづつ変えながら、しかし決して単純なパターンにならないやり方で繰り返している図案である。ストレートな絵画的表現でもなければ、従来のようなパターンとしての装飾文様でもなく、生き生きとした自然らしさを残しながら、工芸図案独自のあり方を波山なりに見出しつつあることを示しているように思われる。 |
|||
| 2、3の例をみると、図版144-(9)は外国製品を直接の源とする例で、Art et Decoration誌に掲載された花瓶の模写(挿図6)に基づき、原作のアシンメトリーな構成を規則的なパターンに換え〔図版144-(45)〕、グロテスクなほど生々しい写実主義を退けている(註3)。しかし完全に抽象化してはおらず、細部の写実性は失われていない。(挿図7)は百合を全体に大きく配した図案で、最も写実性の強いものの一つであるが、日本美術の影響を相当に受けたフランスのガラス工芸家エミール・ガレEmile Galleのデッサン(挿図8)に驚くほど似た表現が見出される。図版144-(16)の3つの図案は、いずれも葉の部分のみが一定のリズム感をもって器の表面全体に配されている。しかし装飾パターンへと抽象化されてはおらず、それぞれの葉は陰影が施され、むしろ写実的である。様式的に幅をもつアール・ヌーヴォーには、大きく分けてガレに代表される自然主義とヴァン・ド・ヴェルドVan de Veldeに代表される抽象主義が並存しているが、この時期の波山は、少なくとも後者よりも前者への親近性がはるかに大きいようである。 | 3 | 図版144-(9)がArt et Decoration(1899年7月号)の図版に基づいていることは、荒川氏の調査によって判明した。同氏の調査によると、波山が模写しているArt et Decoration誌は1897年3月の創刊号から1900年12月号までである。このことから、これらのArt et Decoration誌は、1900年のパリ万博を訪れた誰かが持ち帰ったものと推測できるのではないだろうか。 | |
2 1900年のパリ万国博覧会と「図案」
| さて、ここまで波山のデッサン帳『器物図集 巻三』、なかでも明治34年から38年にかけてのデッサンを見てきたが、この明治34年から38年という時期が決して偶然でもなければ、波山という一人の陶芸家の生涯においてのみ特別な意味をもっているのでもないことは、明治33年すなわち1900年がパリ万国博覧会の開催年であることを想起すれば明らかである。 このときパリ万博を直接訪れた日本の美術関係者は、期せずしていずれも万博後の日本における図案改革運動で重要な役割を演じることになる。浅井忠、黒田清輝、福地復一、中沢岩太らであるが、彼らはアール・ヌーヴォー全盛の博覧会場で同時代のヨーロッパの装飾美術を直かに見、ほとんど同じような感想を抱くに至ったようである。たとえば浅井忠は 処が三十三年の巴里大博覧会で、アール・ヌー ボーだの、セゝツシヨンだのといふ斬新な図案 が発表せられ、我国から観覧に出かけた実業家 達が大に驚いたが、我もまた非常に驚いた。尤 もこの図案は西洋でも之れまで研究していた が、それを一堂に集めて発表したのは此時が初 めてゞ、かく西洋人が支那、日本、朝鮮などの 東洋趣味を参酌して、あれ程迄に研究していた とは思ひもよらなかつたのでした。(註4) と黒田天外に語っている。周知のように、万博前にはほとんど図案に関心のなかった浅井は、この万博開催中のパリで中沢岩太に出会い、彼の要請で開校が予定されていた京都高等工芸学校に赴任を決め、これをきっかけに京都での図案改革の動きの柱となるのである。また浅井と同じく洋画界の中心であった黒田清輝も、帰国後、橋口五葉と杉浦非水という日本におけるアール・ヌーヴォーのグラフィック・デザイナーというべき二人に重大な影響を及ぼしたとされる(註5)。さらに、帰国後「福地アルヌポー君」と呼ばれた福地復一の場合、パリ滞在中に浅井とともにジークフリート・ビングのもとを訪れているが、翌34年に日本図案会を結成、さらに翌年にはパリから持ち帰った参考品の展覧会を開き、東京での図案改革運動の先頭に立った(註6)。 彼らに共通していたのは、まず日本の工芸が、技術はともかくデザインの点でヨーロッパのものに劣っているという認識であった。浅井の博覧会評にみられる「日本畫家及び工藝家の欠点は意匠手工ともに大様なる所なく小刀細工に汲々たるに在り」(註7)はこの認識を代表するものであったといえよう。同時に興味深いことには、そうしたヨーロッパ工芸の長所が、もともと日本及び東洋美術の影響、すなわちジャポニスムの成果であるという認識も共通していた。 こうして新たな脚光を浴び始めた「図案」は、用語としては、英語のDesignの訳語として、納富介次郎が明治6年(1873)のウィーン万博の前後に用い始めたのが最初と一般にいわれる(註8)。納富は、日本が大成功を収めたウィーン万博に陶磁器担当の技術官として関わり、視察者の一人として派遣された。万博後もヨーロッパ各地で様々な技術を学んで帰国し、金沢工業学校を初め全国の工業学校の創立の中心となって活躍した。納富はウィーン万博の3年後に開かれたフィラデルフィアの博覧会への参加に際して、画家に図案を依頼し、その図案に基づいて工芸家に制作させるというはっきりとした分業方式を採用したという(註9)。この方式は、やはりウィーン万博を視察した松尾儀助らが創立した起立工商会社の場合とも似ており、四条派や南画風の絵画的図案がこれ以後主流を成すことになった。しばしば指摘されているように、明治期前半の伝統工芸品に焦点をあてた輸出振興策のなかで考え出された方式であったといえよう(註10)。 一方で図案独自の領域を確立する必要性も感じられていたようで、明治10年には大蔵省に図案調整局が置かれ、13年には別に製品図案協議員という制度が設けられた。また『東京芸術大学百年史』によると、東京美術学校の設立に際して、フェノロサと岡倉天心は基礎教育においても専門教育においても「デザイン」をかなり重視していたという(註11)。23年の規則改正で美術工芸科と入れ替わって一旦消滅した図案科は、29年に再び設置された。またこの頃には、民間でもすでに幾つかの図案研究会が結成され、懸賞図案募集も盛んになってきていた。波山も30年頃から『大日本窯業協会雑誌』に図案を応募していた(註12)。こうして「美術」や「工芸」と同じく明治維新後に新たに登場した用語としての「図案」の担うべき役割には、輸出振興、産業振興の立場から、また美術教育においても強力な要請があり、様々な期待が寄せられながら、その内容は未だ確立していなかったと考えられる。パリ万博の年が迎えられたのはこうした状況のもとであった。このとき、「アール・ヌーヴォー」というきわめて特殊な一つの時代様式は、日本の「図案」という概念に非常に具体的な姿を与えてくれたのではなかろうか。明治35年の新春早々の『読売新開』は、「デザイン時代來たらんとす」というタイトルを付けた論説を掲げ、そのなかで「此く我古代の製作も一たび彿人の意匠に觸るれば、忽ち新奇の畫風となる、皆意匠の力なりと謂はざるべからず」(註13)と、ジャポニスムからアール・ヌーヴォーヘという流れにおいて「意匠=デザイン」が果たした役割を強調している。 確かに、「アール・ヌーヴォー」がそれほどまで、当時の日本人が必要としていた「図案」に内実を与えてくれるように感じられたのは、浅井や福地も敏感に感じ取っていたように、その形成に日本美術の影響、すなわち「ジャポニスム」が大きく関わっていたからであろう。ほんの数十年前に日本からヨーロッパに出ていった大量の工芸品や版画、屏風などが、伝統的なヨーロッパの装飾美術のなかに様々な形で浸透し、ヨーロッパ人の美意識を大きく転換させたその成果が、一挙に日本人の前に現れたのである。そのためにこそアール・ヌーヴォーは、万博を見聞した日本人の目に、単に目新しいヨーロッパの一様式としてではなく、自らの伝統をベースに「図案」という新たな課題の領域を切り開いていくための、いわば切り札とみえたはずである。1900年前後は、ヨーロッパの工芸にとっても、機械生産を背景にモダン・デザインへと大きく転換していく時期であった。周知のように、パリ万博で勝利を収めたはずのアール・ヌーヴォーは、この直後に直線的・幾何学的様式へと道を譲り始め、やがて装飾がその死を迎える直前に開いた最後の華ともみえるようになる。 |
4 | 黒田天外『名家歴訪録 3巻』、山田芸艸堂、1901年。前川公秀『水仙の影 浅井忠と京都洋画壇』、京都新聞社、1993年、59頁から引用。 |
| 5 | 海野弘「橋口五葉」及び「杉浦非水」、『日本のアール・ヌーヴォー』、青土社、1988年(初版は1978年)。 | |
| 6 | 日野永一「アール・ヌーボーと日本の図案界」、『昭和54、55、56年度文部省科学研究費補助金総合研究(A)研究成果報告書 アール・ヌーヴォーと日本』、1982年、48-50頁。 | |
| 7 | 土屋元作「巴里博覧会 浅井忠氏の説」、『時事新報』、明治33年8月8日。 | |
| 8 | 榧野八束『近代日本のデザイン文化史 1868-1926』、フィルムアート社、1992年、56-57頁。及び出原栄一『日本のデザイン運動』、ぺりかん社、1992年、62-63頁。榧野氏によるとウィーン万博に参加する際に納富によって造語されたといい、出原氏によればフィラデルフィアの博覧会の準備を進めるなかでつくられたという。また日野永一「明治の博覧会とデザイン-美術とデザインの概念をめぐって」、『科学研究費補助金研究成果報告書芸術とデザイン』、1984年、84頁も参照。 | |
| 9 | 出原栄一『日本のデザイン運動』、ぺりかん社、1992年、62-63頁。 | |
| 10 | 金子賢治「工芸に生かされた絵画的図案」、『別冊太陽No.70 明治の装飾工芸』、平凡社、1990年、12頁。 | |
| 11 | 『東京芸術大学百年史 東京美術学校篇 第一巻』、ぎょうせい、1987年、65-67頁。 | |
| 12 | 荒川正明「板谷波山とアール・ヌーヴォー」、63-66頁。 | |
| 13 | 『読売新聞』、明治35年1月4日。 |
3 波山の図案とアール・ヌーヴォー
| 波山はまさに上述したような時期に、陶芸の専門家集団とは全く異なる背景の中から陶芸の世界に足を踏み入れたことになる。デッサン帳を見る限り、波山の場合も、彼の関心が決定的に西洋、なかでもアール・ヌーヴォーを向いたきっかけがパリ万博であったことはまちがいないように思われる。浅井忠や黒田清輝、福地復一など、直接にパリ万博を見聞した人々とほとんど同時的な共通項の多い反応であったといえよう。 |
|||
| 明治33年当時の波山は、決して図案改革の先頭に立っていたのでもなければ、またその責務にあたる立場にもなかった。しかし、明治20年代から『模様集』にみられるような東洋美術の意匠の研究を行い、その成果を『大日本窯業協会雑誌』に図案を投稿することによって発表していた波山は、この時点ですでに相当な図案への関心を寄せていたことはまちがいない。波山は浅井らのようにパリ万博を直接見聞したのでもなく、また自ら語っているわけでもないが、様々な情報源を通じてパリ万博の報告を耳にしており、彼らと非常に近い認識に達していたのではないかと推測される。それを何より明白に示しているのが『器物図集 巻三』である。また、日本図案会とほぼ同時に創立され、ともにパリ万博後の図案改革運動の核となった大日本図案協会の正会員に波山が名を連ねている事実も見逃せない(註14)。日野永一氏の指摘によれば、大日本図案協会が明治34年から39年にかけて発行した雑誌『図按』には、Art et Decoration誌やThe Studio誌から採った図版が掲載されており、当時これらの美術雑誌はかなりの数が輸入されていたはずだという(註15)。すでに触れた波山のデッサンにみられる事実とも一致する。 さて、波山の『器物図集 巻三』におけるデッサンには、アール・ヌーヴォー固有のS字曲線がしばしば登場すると同時に、モティーフを抽象化、パターン化する際のやり方にもアール・ヌーヴォーの影響が見て取れる。またモティーフをいかに器の表面に配するかという問題に関して外国製品を熱心に研究していることもすでに見たとおりである。ところが、実をいえば、一見アール・ヌーヴォー風の曲線を用いた図案の横に「光琳水卜都鳥模様ヲ応用」と書かれていたりするのである〔図版144-(13)〕。さらにこれらと同時に波山のデッサンに登場してきた写実的で絵画的なモティーフの扱いが、パリ万博に触発されたアール・ヌーヴォーの影響によるものかどうかという問題はもっと複雑である。すでに触れたように日本でも明治10年代から日本画的な図案の流れがあった。波山のこの時期の図案は宮川香山ら日本人の作品にも近く、数は少ないものの、波山は香山や香蘭社の作品にも注目し、デッサン帳に写している(挿図9)。しかし、エミール・ガレのデッサンにも非常に似たものが見出されるし(図版4及び挿図10と挿図11)、ヨーロッパに限らず、ロックウッド社を初めとするこの時期のアメリカの陶磁器(挿図12)にも似ている。しかも欧米におけるこうした表現は、ジャポニスムの産物であるということを思い出す必要があろう。 日本美術が19世紀後半の西洋美術に与えた多様で広範囲に及ぶ影響の一つに「自然主義」、なかでも人間と自然とのきわめて親密な関わりを示す、身近な植物や動物の表現があった。近年開かれた「ジャポニスム展」の図録では、馬淵明子氏が論文「ジャポニスムと自然主義」の〈動植物の世界〉という章で、「さて、三次元表現、つまり立体物における日本の自然主義の影響は、平面美術におけるより、更に庄倒的であった。そこでは小動物や昆虫、植物の様々な相が、日本において愛されたように、非常に生き生きととらえられている。それらは幾何学的に装飾化されたヨーロッパの伝統的文様とは非常に異なって、怡も本物の虫や木の葉が貼りついているかのような錯覚を与える」と述べている(註16)。波山のデッサンには植物と並んで動物のモティーフが頻繁に登場する。それらは、いかにもアール・ヌーヴォー的なグロテスクなものも含め、一見西洋風にみえるが、動物モティーフの扱いに卓越した能力を発揮してきたのはむしろ日本であった(註17)。 これに関連して、『器物図集 巻三』と並んで波山とアール・ヌーヴォーとの関わりを最も端的に示すデッサン帳『泰西新古模様』を挙げておきたい。すでに荒川正明氏によって紹介されているとおり、これは1898年にパリで刊行された『動物文様集L’Animal dans la Decoration』(M・P.ヴェルヌイユ Verneuil編)と1896-7年に刊行された『植物とその文様化 La Plante et ses Applications ornementales』(ウジェーヌ・グラッセEugène Grasset監修)という2種類の文様集から、気に入った図案を丁寧に写し取ったものである(註18)。このうち前者は、様々な動植物が限定された空間の中で互いに絡み合いながら、巧みに配された、きわめてアール・ヌーヴォー的な文様集であるが、序文を書いた当時のフランスの代表的デザイナー、ウジェーヌ・グラッセもまた、こうした動物モティーフの表現は「極東の職人たち」が得意としていることを指摘している(註19)。これらの文様集はそれ自体美しい豪華本であるが、加えて日本、東洋の影響を受けつつも全く異なる動植物モティーフの扱い、とりわけその巧みな文様構成に波山は相当な関心を寄せていたように思われる(註20)。 |
14 | 樋田豊次郎「工芸家の自己の存在証明にかける情熱」、「図案の変貌1868-1945」展図録、東京国立近代美術館工芸館、1988年、33頁による。 |  挿図9 器物図集 巻三  挿図10 器物図集 巻三  挿図11 エミール・ガレ 〈花瓶図案(玉ねぎ)1898~99〉  挿図12 ロックウッド社製品3点 左 花瓶 1903年 中 鉢 1889年 右 花瓶 1900年 |
| 15 | 日野永一、「アール・ヌーボーと日本の図案界」、53頁。 | ||
| 16 | 馬淵明子「ジャポニスムと自然主義」、「ジャポニスム展」図録、国立西洋美術館、1988年、30頁 | ||
| 174 | ビングが1888年から1891年にかけて発行した雑誌『芸術の日本Le Japon Artistique』の第21号(1890年1月)と22号(1890年2月)にアリ・ルナンの「日本美術のなかの動物Les Animaux dans l’art Japonais」という論文が掲載されている。 | ||
| 18 | 荒川正明「板谷波山デッサン『泰西新古模様』」。 | ||
| 19 | 『アール・ヌーヴォー装飾文様 動物文様』、学習研究社、1984年、68頁。 | ||
| 20 | 高野コレクションの間部時雄関係の資料のなかに、京都高等工芸学校の生徒作品として同じ『動物文様集』を模写したものが含まれている。浅井忠の弟子であった間部時雄は京都高等工芸学校卒業後、母校で教壇に立ったが、その当時の生徒作品である。1912年の年記が入っており、いずれにも武田五一のものと推測される武印印が捺されている。クリストフ・マルケ氏によると、この『動物文様集』も『植物とその文様化』も、ともに浅井忠が教材としてパリから持ち帰った可能性があるという(クリストフ・マルケ「巴里の浅井忠 図案への目覚め」、『明治美術学会誌 近代画説1』、1992年、21頁)。あるいは波山の写した原本も同じである可能性も考えられる。 石川県立美術館の寺尾健一氏のご教示によると、現在福井県陶芸館に所蔵されている、福井県丹生郡に築かれた小曽原焼の山内窯(大正2年廃業)に由来する図案の一括資料に、板谷印のあるものと並んで、波山と浅井忠のアール・ヌーヴォー様式の図案を写したものが含まれている。波山を写したものの横に「陶器 上絵 小花瓶ニ應用サル 賣行殊ニ良ナリ」と書かれており、波山や浅井忠の図案が地方の窯で研究され、製品化されていた可能性を考えさせるとともに波山と浅井忠との何らかのつながりについても推測を喚ぶ。やはり寺尾氏のご教示によると、山内窯の二代伊右衛門の長男山内春樹は明治37年に石川県工業学校を卒業し、44年には京都陶磁器絵具製造会社にいた。 |
||
| 高島北海が高等森林学校に入学するためナンシーに赴いたのは1885年のことである。そこで彼はエミール・ガレを初めとするナンシー派の芸術家たちと親交を結んだが、ガレはすでにそれ以前から日本美術にかなり強い関心を抱いていた。ガレと波山のデッサンの類似を、両者に共通する自然主義に求めるか、あるいは一種のジャポニスムの日本回帰というべき現象と捉えるかはむずかしい。しかしいずれにしても、波山にとって、パリ万博が自然主義的な表現を図案に積極的に取り入れるきっかけとなったとはいえるであろう。 | |||
4 図案と実作品
| デッサンに書き込まれた丁寧な技法上の指示をみる限り、これらのデッサンに基づいて相当な数の実作品が作られたと推測される。しかし現在では同時期の作品はわずかに数点が残されているのみである。明治末以降になると、この時期の図案に基づいて作品化された例が少しづつ見られる。たとえば明治44年(1911)「彩磁金魚文花瓶」(図版15)は、図版144-(50)の図案をかなり忠実に作品化したもので、明治43年(1910)「一輪生 麦」(図版13)と並んで現存する波山の作品としては最もアール・ヌーヴォー的な作例と思われる。図案と比較して気付くのは、グラフィックな印象が強くなっている点である。金魚は平面的な処理によってパターン化され、曲線の規則的な繰り返しと相まって、デッサンの墨の線が与える絵画的な印象は弱まっている。〈一輪生 麦〉からもやはり絵画的というよりグラフィックな印象を受ける。しかしこの2点を除くと、作品自体がはっきりとアール・ヌーヴォー的と感じられる例はほとんどないように思われる。写実的で絵画的な図案に基づいた実作品も少なくとも「アール・ヌーヴォー的」ではない。大正半ば以降の作品では、「葆光彩磁チューリップ文花瓶」(図版47)などは、明治34年1月の図案(挿図13)に似たモティーフが見出され、曲線や全体の洋風の印象にもアール・ヌーヴォーの残響が確かに感じられる。色彩的にもフランスで活躍したアール・ヌーヴォーのデザイナージョルジュ・ド・フールGeorges de Feureの作品(挿図14)などに近い。こうした例は他にも見出される。しかし全体として、明治34年から38年頃にかけて、まちがいなく盛んに行われたアール・ヌーヴォーの研究が、その後の波山の制作に果してどれほど生きているのか疑問に思われる部分も残る。それとも、明らさまな影響の跡を残さないほど同化吸収されたといえるのか。その一方で、時間の横軸で考えるとき、明治期の日本における「図案」の歴史のなかで、浅井忠の京都での活動などと並んで、『器物図集 巻三』はたいへん興味深い位置を占めているとも思われるのである。 (三重県立美術館学芸員) |
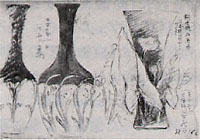 挿図13 器物図集 巻三  挿図14 ジョルジュ・ド・フール 〈氷入れ〉1902年頃 |
