|
荒屋鋪 透 悪魔のロベールと題されたドガの油彩が、ニューヨークのメトロポリタン美術館に所蔵されている。パリ・オペラ座で何やら不気味な尼僧の踊りを見る男たちを描いた作品である。「悪魔のロベール」はジャコモ・マイヤベーア作曲の歌劇で19世紀後半に大変人気を博したオペラ座の演目であり、1831年に初演されてから1893年までになんと758回も上演された記録が残っている。舞台は13世紀、シチリアのパレルモ。遍歴の騎士となったノルマンディ公爵ロベールはシチリア王女イザベルに想いを寄せている。友人ベルトラムは王女を奪う魔法の枝を尼僧院へ取りに行くようにロベールに勧める。実は彼はロベールの父親なのだが、悪魔でありロベールを地獄に導こうとしている。ドガの油彩に描かれた場面は第3幕第2場に挿入されたバレエ。悪魔の歌うモノローグによってサンタ・ロザリエ尼僧院の墓から蘇った尼僧たちの踊りなのである。姦淫の罪を犯した尼僧の霊がロベールを誘惑し、自分の姿を隠し人を眠らせる魔法の枝を彼に授ける。絵の中で画面下にはオーケストラ・ボックスと年間通しのチケットを持つ常連たちの席が描かれ、常連(アボネ)の一人は上階の棧敷席をオペラグラスで覗いている。この絵の主題はその題名の暗示するロマン派的な筋書きにはなく、実は観客の無関心にこそあるのだ。正装した紳士たちはバレリーナのパトロンであり、オペラ座の運営にも影響力を持つ人物だが、最近、高階秀爾氏が翻訳されたケネス・クラーク卿の『ロマン主義の反逆』(1988年・小学館)には彼らに関して興味深いエピソードが回想されている。「舞台は彼らの偏見で支配されていた。それはしばしば、芸術的には舞台をすっかり損なってしまうほど強かった。例えば、彼らは、劇的緊張感がそれで駄目になってしまうのも構わず、どんなオペラにも必ずバレーの場面を入れるように要求した。私の若い頃には彼らはまだ健在で、いつも幕が降りると皆一様に山高帽をかぶり、何かぶつぶつ呟きながら尊大な様子で立ち去るのであった。」(同書365頁)立ち去った後の紳士が、何を求めて何処に向かうのかは、今回の『ドガ展』に出品された「舞台上の三人の踊り子」が遠慮がちに告白している。山高帽の紳士は黒くシルエットになっているが丁寧に描かれ、彼に寄り添う二人の踊り子の顔は戯画化されている。はにかんだ三人めの踊り子の胸元は眩く肉感的だ。至極大雑把に扱われた背景の書割りが暗く描写されているので、踊り子の衣装は白く見え、それは決して鮮やかな白ではないのだがコスチュームの透明感が非常に巧みに捉えられている。そのため黒い男はまるで影絵の様に美しい。はにかんだ踊り子の髪飾り、胸飾りは鮮やかな色彩が施されており、彼女は矢張り画面の中心人物であることが分かる。ニューヨーク州立大学のリプトン女史は『ドガへのまなざし』という著書の中で、ドガの友人の画家ジャン・ベロー描く処の「オペラ座の舞台裏」を例に挙げ、このアボネと呼ばれる男達の実態を鮮やかに暴いている。「オペラ座は文化と富の表象である。より厳密に言うならば市民階級の経済力の結果新たに生まれたものなのだ。」E・Lipton,Looking into DEGAS,1986.p.78.確かにリプトン女史が指摘するように、その壮麗な美の殿堂は第3共和制時代の市民の芸術への趣向を反映させていると共に、その限界をも露呈させたのである。「悪魔のロベール」という怪奇趣味の通俗的な歌劇の人気の秘密もそこにあった。このオペラはドガの油彩制作が開始された1870年には3月から普仏戦争勃発の7月までに23回上演され、普仏戦争からパリ・コミューンを経た1871年の12月までにも10回オペラ座の演目に採り挙げられている。この時代のバレエは娯楽件の強いオペラの付属物になっていた。その理由はトゥ・シューズの出現によってポワントが可能になり、女性舞踊家の重要性が増大すると共に男性の役割が低下したこと、また審美眼のある観衆の減少である。エトワールたちの媚びた微笑、ピルエット(旋回)やポワントを多用したアクロバット的な舞踊、過度に物語性を重要視した内容などがこの時代のバレエの特徴である。しかしドガはその現実を現実として絵画に定着させようと試みる。彼はバレエの瞬間の動きとその永遠性を追求した画家であったが、同時に舞台と楽屋真の踊り子、舞台の栄光とフォワイエの現実といった近代生活の寓話とも言える劇場の持つ二面性を冷徹に見詰めた。「フォワイエ」とはオペラ座の楽屋、というよりも出演者の休憩室を兼ねた一種の社交場である。そこでは踊り子は手足を伸ばし本番の最中にでもパトロンである愛人と歓談した。ドガを捕らえて放さなかったのはまさにこの近代生活の二面性、つまり虚構と現実が同居する姿であった。彼がこの矛盾した現実を鋭く意識するのは、普仏戦争に志願した後のことである。1872年6月26日、ドガの弟ルネは伯母ミシェル・ミュッソンに宛てた書簡の中でドガの近況を報告している。「駅でエドガーに会いましたが、老けており顎髭には幾分白いものが見えました。彼は以前より深刻になり落着いていました。‥ 不幸にも両目を大変弱くしたので、細心の注意を要するのです。」第3共和制下のドガの芸術、とりわけ踊り子の連作に代表される前衛的な傾向を考察する時、普仏戦争の落とした影も無視することは出来ないのではないだろうか。 (あらやしきとおる・学芸員) |
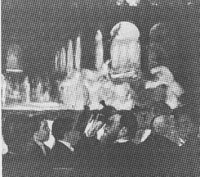
ドガ 「悪魔のロベール」のバレエ(部分)1871-72

ドガ 「舞台上の三人の踊り子」c.1879

ジャン・ベロー 「オペラ座の舞台裏」1889年
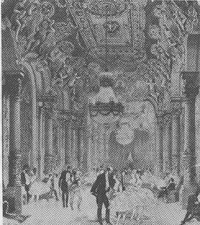
オペラ座のフォワイエ 「ル・モンドイリュストレ誌」1875
|
美術館 > 刊行物 > HILL WIND > ひる・うぃんど(vol.21-30) > ひる・ういんど 第25号 ドガの踊り子 舞台裏から観たモダニズム
ページID:000055517
