|
荒屋鋪 透 「親愛なるピョートル、イタリアに来て2年、私には貴重な年月でした。音楽家としての私にも、私の人生にとっても。昨夜恐い夢を見ました――伯爵家でオペラを上演することになっていて、第一幕は庭園で背景に数体の彫像が置いてあります。彫像の男達は白塗りの裸体で長時間不動です。私も彫像の一つでした。もし動いたら、容赦ない体罰を受けるのです。主の伯爵が 自ら観劇しておられる。大理石の台座から冷たさが体を襲い、秋の木の葉が 両腕にふりかかってきても動いたりできません。ついに我慢ができず、倒れそうになって目が覚めました。恐しかったのは、それが夢ではなく、現実だと分ったからです。ロシアに帰れないと思うのは、生れ育った土地に帰れないのは、(中略)死ぬより幸いことです。生まれた国、あの樺の林、幼年時代の空気に・・・。見捨てられし友より。パヴェル・サスノフスキー」(シナリオ採録・田中千世子,字幕監修・吉岡芳子/柴田駿。CINE VIV-ANT No4 p.39) 引用が長くなったが、この書簡には辺境ロシアからイタリアに留学したが故に、一人の知識人が経験することになる苦悩が率直に語られている。彫刻に扮した自分、裸体を大理石像に見せるために体を白く塗られた姿は、まるで衣装をとられた道化師であり、おどけさせられながらも虐げられる弱い立場を、寓意的に述懐する作曲家の口調は痛々しい。そして見過すことができないのは、若き芸術家のこうした経験は、続く世代へと引き摺られて、広く近代知識人の背負う重任となってゆくことである。もっとも、サスノフスキー個人が、誰よりも悲惨に描かれるのは、イタリアの空の下では憧れ愛した故国へ戻ると、作曲家は農奴階級の貧しい村娘と恋に堕ち、報われぬ寂しさから酒浸りとなって自殺するくだりだ。タルコフスキーの他の映画作品の手法と同様、『ノスタルジア』においても、これらの挿話は詩的連想のモンタージュとして映像に組み込まれているため、画面の中に村娘や作曲家が登場してくるわけではない。ただ現在に生きるソ連の知識人ゴルチャコフの身辺に起りつつある、本質的に不可解な現実が映し出されるのみである。にもかかわらずタルコフスキーは、執拗に一人の過去の芸術家の苦悩から焦点を外さない。彼は『ノスタルジア』におけるドラマトゥルギーの排除を認めているが(イメージフォーラム、1987年3円p.59)、それは画像を即興的に繋ぎ合わせる口実としてではない。あくまで近代的ドラマトゥルギーに付着した胡散臭いリアリズムに異議申し立てを行っているのである。それ故タルコフスキーの「モンタージュ技法」は、本来的に複雑な人間の思考や世界を、あえて明白性という枠の中に閉じ込めることなしに、主題が結論をあらかじめ用意することを慎重に避けながら、作者の側に巣くう頑迷なこだわりさえも、恐ろしい程に客観化してみせるのだ。そこには、例えば遠近法やリアリズムによって視線に思考を従属させようとし、その視野から逸脱するもの、例えば人間と世界との不条理な緊張関係などは捨象しようとする態度に対する痛烈な批判、すなわちアヴァンギャルデイズムの表明がみられる。さらに興味深いのは、タルコフスキー自身亡命中のソ連の知識人であるということで、私は彼の特異な立脚点を誇張し、強引に作品の生成要因に結び付けることを意識的に避けたいと思うのだが、やはり文学や演劇、映画のみならず、特に音楽や舞踊(バレー)という部門において常々話題になるように、ソ連は現在もなお国家的規模で芸術家を育成しており、第一次大戦前のヨーロッパ諸帝国がそうであったと同様、伝統的メトードを美の殿堂で育む国であることは無視しえないのではなかろうか。善し悪しは別として、この国の中では19世紀的色合の濃い、国家と芸術家と観者の相互関係が、生き残っているのである。 国家を背景にした芸術のアカデミズムと、亡命という政治的手段に訴えずとも、絶えずそこから逃れよう越えようと試みる芸術家、そして優れた芸術家を擁護し、芸術家として評価する国民が、厳然と存在する。私が映画『ノスタルジア』を観て感じたのは、この作者はまだアヴァンギャルドを棲息させる土壌にあるなということであった。パリ大学のジャン・フランノウ・リオタール教授が、1986年に出版した『子どもたちに説くポスト・モダン』(管啓次郎訳『ポストモダン通信』朝日出版社、1986年)の中で鋭く指摘している様に、現在、西側先進諸国の芸術家が置かれた状況は、これとはかなり質を異にしている。彼らにはもはや戦うべきアカデミズムも、誤解を解くべき大衆も存在しない。リオタールがティエリー・ド・デューヴの洞察を引用して「近代の美学的問題は『美とは何か』ではなく、『何が芸術に(中略)属するのか』ということなのだ。」(前掲書19頁)と結ぶ意味における芸術の自立性を、変転する技法により提示することを繰返しながらも、今日の芸術家にとってアヴァンギャルディズムは、明らかにそれ自体一つのクリシェ(常套句)となってしまったと。彼らはそのことを充分認識しているはずだが、多くの芸術家にとってそれは、怒りにも似たアンチ・モダン(逆行近代的)な打開によって振分けられているに過ぎない。そうした苛立ちの中からは、さらに安易な解決策として、ネオ・アカデミズム(新伝統的形式主義)やイクレフティシズム(折衷主義)がはびこることは容易に察しがつく。リオタールが憂える様に、今日の芸術の弛緩した現状は、大衆を安直に惹付けるキッチュ(紛い物)となることで、「芸術は、愛好家の〈趣味〉を支配している混乱におもねる」(前掲書21頁)ところに起因していると言えよう。リアリティがキッチュと同義語になった時代、第二帝政期のフランス、両大戦間のドイツ、そして革命後のロシアに吹荒れたリアリズムの嵐は、リアリティが大衆に対して唯一絶対性、伝達可能性、統合性をもつが故に、全体主義を誘発しうることを証明した。タルコフスキーは、近代的ドラマトゥルギーを拒否し、作者が意図的にリアルでないと判断したものの表現を捨象する方法を回避して、極めて抽象的であるがために、純粋なリアリティを獲得した映像作家であるといえよう。彼は聖人や修道僧と峻別して、芸術家を日常生活に関わる者、つまり誤りを犯し汚れる傾向にある者と言明する。そして芸術家は、その魂を危機に晒すが、芸術作品は、人間が精神的に向上することに奉仕すべきであると主張している。『ノスタルジア』という標題は、作者自身にとっても、私たちにとっても含蓄の深いものであるといえよう。 (あらやしき とおる・学芸員) |


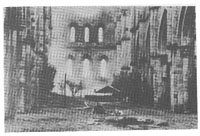
映画『ノスタルジア』より |
