|
今回出品された90余点の作品中で、機械万能の現代社会のイメージ及びそれと密接な関連をもつデザイン的造型法の両面から、もっとも離れた地点に位置していると考えられるのは、遠藤利克、竹田康宏の立体作品であろう。両者の作品は表現の中核部分に明確な概念や明快な論理をもってしては把握することのできない、ある種のつかみがたい性格を包含している。彼らの表現行為には、20世紀の後半に至るまで、そして特定の人々を除けば、今日でもなお多くの美術愛好家の既成概念として重視されている、近代的な意味での「彫刻」の観念(すなわち形体の絶対的な中心部分を軸にして完結した量感表現を誇示する造形思考)を基本的に拒絶する発想が示されているはずである。ここには構造力学的側面や素材の処理において、若干の難点が含まれているとはいえ、少なくとも既成の「美術作品」という枠組を突破しようとする斬新な試みと方法論とを彼らの作品が確実に示していることは評価されねばならない。 遠藤利克の「無題」は、高さ1.4メートル、直径25センチ・メートル前後に切り整えられ真黒に塗装された22本の木材の円柱を、床に直径4メートルの円をつくるように並へた作品である。林立する黒い柱が中央部の空間を囲む構成となっているため、全体を眺めると、ひとかたまりの作品というよりも、各々の形態が周囲の空間へと拡散してゆく印象を生じさせている。つまり中心部を有する可視的な有機的統一体といった性格が故意に弱められているため、いわゆる近代彫刻における一個の塊量性の観念を後生大事に抱き続けている人間に、とまどいを感じさせる代物であろう。そして電信柱を切断したものというよりも未加工の材木とでもいうペさ素朴で荒々しい性格をもつ22本の円柱は、作家自身の言葉である「原初的image(イマージュ)」、すなわち現代文明が小綺麗な表象を志向して、文化の名の下に切り捨ててきた人間の不可思議な感情を表わしていると考えられるかも知れない。私はこの作品を前にして、ドルメンなどの巨石群を想起させられた。ただ遠藤の「無題」においてもっとも感動的なのは、ほぼ大人の目の高さにある円柱の上部に注がれた水の存在と、水が形づくる自然であるとともに洗練されたフォルム及び光の形象である。表面張力の作用で木材の縁より僅かに高く盛り上がった水面は、まるでアクリル・ガラスをはめ込んだように見える透明な輝きと、極めてすっきりとした形態を示している。この自然が創造し仁水面の完璧な水平性は精巧な水鏡となって外界の光を反射し、その容器である簡素な木材と際立った対照を示している。その意表を突くような組合せは、見る者の感情を瞬間的に一撃する説明し難い構築物を形成している。基本的には芸術的熟練とか技巧などの職人芸を放棄・拒絶する志向が、遠藤の作品の本質に内在していると考えられるが、この志向こそが、多産な現代美術の作品群において頻繁に見受けられる、中途半端なデザイン的作品(純然たるデザイン作品が悪いと言っているのではない)と明確に一線を画する作家の感性の顕われと解されるであろう。 竹田康宏の「環-Mie-」は、まず4メートルもの巨大で不恰好な鉛筆を床面に逆さに突っ立てたような木材の存在によって、観者の心理に衝激を与える。栂(ツガ)の木を使った作品で、木材の上部を天井裏に出してワイヤーで固定しているので、震度4程度の地震では倒れない構造になっているということだが、どのようにして固定されているかが、観客の視覚に入らないため、木材の細い先端のみで重量を支えている印象が生じ、非常に不安定な緊張感が効果的に産み出されている。この鉛筆型の作品とバランスを取るように、隣接する空間に、同じく長さ50センチ・メートル、直径30センチ・メートルほどの木村で、ごつごつした大きな半円形アーチを形づくる構築物が置かれている。さらにそれらと対照を成すように、だいたい3センチ・メートルほどの太さの細い棒を接ぎ足して、逆角錘形の空間を形成する華奮な作品が天井から吊り下げられている。全体的には下部が矢印のように尖った細い線状の形態にされその鋭角的な尖端よリ1メートルほど上部に円い環が宙に浮くような構成で載せられている。これら3つの構築物、というより粗削りの材木のかたまりとでも形容する方が似つかわしい作品は、作家が木を素材にして個性的な造形作品を創り上げるというよりも、むしろ木というものの生の存在をそのまま利用して作品化していると考えた方が正鵠を射た解釈といえるに違いない。 つまり、ここでは木という素材自体が露にしている自然の形と、作家が想い描く表象との、造形的な次元での格闘が演じられていると考えられるであろう。「木が木でなければならないと同時に、私という存在がある故に、木は木であってはならない」と語る竹田の思考は、基本的に遠藤の作品と共通の志向に到達している。ここでは彫刻作品を創るといった、いわば近代芸術の思想は拒否され、また現代社会が氾濫させている、美しく精巧なデザイン感覚は、徹底的に放遂されているといえよう。 遠藤利克と竹田康宏の作品は、短期間の会期中にカビを発生させたり、塗料が剥げたりという弱点を見せてしまった。現代芸術は、過去の芸術家が執拗に守り続けようとしたように、完成作品めフォルムを永続的に保持するための堅固な性格を追求するものではないかも知れない。だが、作家が社会の内部、例えば美術館などで作品発表を行う限り、それらの作品に内在している構造的弱点とか堅牢性をめぐる難点、ひいては観衆に対する物理的な危険性(もっとも最後の危険性については両作品とは関係がない)などは、作家が克服すべき最底眼の課題である。遠藤、竹田両名の作品が部分的に示したこの難点は、今日見られる多くの現代美術の作品群において、もっと極端な形で、しばしば見て取ることができるものである。ただ以上の大きな問題が残されているにしても、私が両名の作品に強く惹きつけられたのは、これらの作品が、冒頭で述べたように、多くの現代美術がはまり込む落し穴である、不徹底なデザイン的発想に寄りかかった小椅麗な作品や、論理や概念のみを形象化したにすぎない悪い意味での観念的作品とは対極的な位置を頑固に守ろうとしている点である。作品の完成度という観点からすれば、種々様々な疑問を湧き上がらせる両作品に、如何なる言葉をもってしても言い尽くせない、曖昧で、われわれの論理的思考を突き崩す、把握し難い特定の気分、換言すれば精神的な何らかの感情が表現されていることに刺戟を受けるのは、少数の観者のみではないはずである。私はこの理性的には曖昧であるが、観る者の精神を確実に活気づける気分の表現を見て、明確な解答を得られづとも問い続けること、表現すること以外にやり場のない気持を持つ無骨な人間、すなわち遠藤、竹田両作家の生真面目な感情を理解することができるように思われてならない。そしてこうした性格こそが、二人の作品を他の多くの作品から大きく引き離している決定的な特徴であると考えて差しつかえないはずである。 (なかたにのぶお・学芸員) |
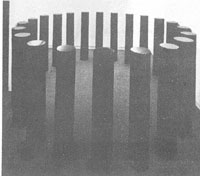
遠藤利克|無題
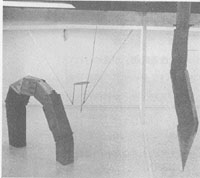
竹田康宏|環-Mie- |
美術館 > 刊行物 > HILL WIND > ひる・うぃんど(vol.1-10) > 現代美術の新世代展-遠藤利克・竹田康宏-
ページID:000055400
