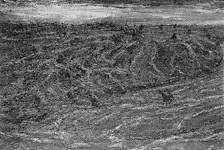鳥海青児と黄色の系譜
東 俊郎
|
一、 鳥海青児の作品を初めてみたのがいつで、それがなんといふ題だつたかはつきりとおぼえてゐないから、であひは残念ながらそんなに劇的とはいへないが、そのうち氣がついてみると好きな作家のひとりになつてゐた。晩年ちかくの艶をうしなつて粉つぽくなつた繪肌には、どう贔屓めにみても力のおとろへと疲労がかくせないものの、それでも出來の差がさう極端にはしらない型に属する鳥海をみて失望することはめつたにない。一生をつうじてたかい水準を維持しつづけた稀な畫家だつたことは、たとへば夭折の畫家とよぶしかない、彼のわかき日の盟友三岸好太郎とくらべてみてもわかる。鳥海の『芦屋風景』『水無き河』『セーヌ河』は三岸の『北海道風景』(一九二四―五)なしにはありえないとおもはれるが、この三岸にしても書壇にあらはれたばかりの頃の、『レモンもてる少女』の冴えた青や赤や黄色がつくる稠密なせかいをぬくことはつゐにできなかった。 さて、この鳥海の傑作のひとつに『黄色い人』となづけられた作品がある。一九五六年の第二十四回独立美術展に出品されたこの油彩畫は、縦六十・六センチ、横七十二・四センチとさほど大きくはないが、實際以上におほきくみえる。かわいた粘土のやうなうすい褐色に塗られた地のうへに、みづのなかだつたら自然かもしれない不自然な姿勢で坐つて、目鼻をもたぬ頭をうつむかせつつ膝がしらのうへで兩手をくむ、男とも女ともみさだめがたい人物がひとり辛子色で描かれてゐだけの單純きわまりない構圖は、ちかづいてみればみるほど抽象畫とかはりなくなる。つまり人物でなくてもよくなるわけで、それがひとだとしても、そのかたちからどんな意味へも等距離といふのか、かすかな氣配〔ただしこの氣配なら、『うずくまる』とか『彫刻(黒)をつくる』とか、さらに『石をかつぐ』に共通するが〕以外の意味は無化されてゐる。だからこれが文学だったら、心理も物語もなくエクリチュールだけが過度につよい作品とでもいひたいところだ。 そのまるく刻んだ石をおもはせる頭部にいくぶん量感があたへられる以外は、色はちがってもほば均一のマティエールで、奥行きの暗示は慎重にさけられてゐる。背後は畫面のほぼ中間あたりで二分されてはゐるものの、一九五九年の同名のヴァリエーションにくらべれば空間をつくるちからはよわく、ほとんど平面といってよい。空間をさぐろうとする視線は遠近をきめる焦點をみうしなってしまふはずで、すると順序としてまづ注意がひきつけられるのはマティエールとしての黄色だらう。この黄色はじつによく練られてゐる。弦楽器の音が倍音をそのなかにふくめばふくむほどくすみながらも澄んだあたたかい音になつてゆくのとおなじで、ここにあるのはさまぎまな色を溶かしこみつつ一である色にしかない芳醇である。 いつたいこの世界には影といふものがない。光の無重力状態といつても、又無数の光源から光の粒がひとしいつよさで垂直にならんでゐるといつてもおなじことで、それに相乗するやうに、閉じたロープを凹凸させたらできあがつたとでもいひたいそのからだつきによつて、たとへば『夜のノートルダム』にいちぢるしい重力さへもここから蒸發してしまつた。どんな感情もどんな物語もない魂の真畫。ためしに須田國太郎のゑがいた世界をここでひきあひにだせば、鳥海のこの作品などは暗黒といふものをつひに知らないノンシャランな精神ではないかと、ついうつかりいひたくもなるひともゐるだらう。強力なひとつの焦點のなかへぼくらはその眼もろともにとびこんでゆくのでなくて、ぼくらをその場に釘づけにしたあとで、この人体である黄色のちからは離散的なひろがりをもつてぼくらを包みこむ。 いふまでもなくこのやうな印象をひきおこすもつともおほきい力は色彩─黄色からきてゐる。そしてこの黄色は一九五六年のこの作品にかぎつて偶然あらはれたものでなく、鳥海のこころのふかいところに根差す色であることは、『黄色い人』の前後をすこしばかり注意してみればだれにもわかるのである。 |
|
|
二、 第二次世界大戦のはりまでの鳥海の作品で、こと色彩にかすするかぎり黄色が記憶にながくのこるやうな例はない。『牡丹』(一九四六)や『無花果』(一九四九)になつてやうやく、しかしまだ背後の色として間接的だけれど當の黄色があらはれるものの、まういちど畫集でたしかめてみなければ不安なほどその印象はうすい。またアンダンテ・カンタービレのはやさでうたふ木管楽器のハーモニーがきこえる『かぼちゃと壷』『かばちゃとレモン』をはじめとした静物畫もあるにはあるが、ここで黄色は依然限定されたつかひかたしかしてゐない。はつきりと積極的にその存在を主張するのはそれゆゑ『狸穴風景』(一九五四)をまたねばならないといふことになるだらうか。 もつともそのまへに『段々畠』の一連の作品があつた。 今迄は多少なり自然の形体そのまゝのものがあつた。しかし、今度はその自然的外形のまゝでは表現しきれなかつた、同時に整理しきれなかつたものを全部整理した。究極の画面構成上必要なもののみを残して、それを画面の上に構成したつもりである。▼1 とは鳥海自身の解説であるが、たしかにここでは描寫の努力はすつかりすてられ、分散和音をかなでて微妙にうきしずみする緑糸統の四辺形のなかにときをりはめこまれてゐる黄色の部分が眼をひく。それは抽象化された菜の花畑とみえないこともないが、よくよくみればそこから日本の土がもつてゐる不變のいろあひが顔をのぞかせてゐる氣配なのである。とはいひながら土は土でも、水分を吸収してくろずんだり、重たくなつた田畑の土の色といふ以上に焼きしめられて堅くかわいた土器のかけらとか、釉薬が剥げおちたところにみえてくるそんな土の色を連想するのである。 『狸穴風景』の黄色はそれからさらに一歩すすんで、効果だけを狙つた装飾とみてみえないこともないくらゐあやふい均衡のうへにたつといつていいほど、畫面の下五分の二ほどをきはめて平面的にかつ大胆に塗りこめてしまつた。もちろん鳥海に装飾の意圖はあるはずもないけれど、風景を再現するためのちからも又やんはりとしりぞけられて、なにかしら別の磁場が畫面にみなぎる。セザンヌのゑがいた緑や黄土色、カンディンスキーの青、ルドンの赤、さらに須田國太郎の朱色とおなじく、これは鳥海のいはば精神の色なので、その光なら光は内部から發するといへばいひすぎだとしても、けつして外光にたよつているわけではない。ついでにいつておくと、鳥海は夜型の畫家の典型で、自然の光をきらつてでもいるかのやうに深夜にならないと繪をかかなかつた。 ところでここに一九五四年の第二十二回独立美術展に出品された『うずくまる』といふ作品がある。朝鮮の民族衣裳に似た服をきて、ただし肩から腕をあらはにした女がひとり、ややうつむきかげんに坐るすがたを側面からゑがいたもの。その畫面のどこにも直接黄色を感受させる色づかひはなく、次のやうな鳥海のことばがなかつたら、いまかたらうとしはじめた黄色の系譜にこれが属するものとみえず、いたづらにとほりすぎるのみであらう。實際はこれをおいてかれの黄色はないのだが。すこしながいがそれを引用してみる。 私にはいろいろな場合の発想がある。たとえば「うずくまる」に見られる人物の腰の線は、家蔵の黄瀬戸の掛け花生けを見ているうちに得たフォルムで、そのすぐれた高台の安定感を、画面に人間らしき形をとって表そうとした。だから、人体としても、解剖学的にみればおよそ人間らしくないだろうし、といって黄瀬戸そのものでもない。物や風景を見ての感動というものが、人によって具象の形をとったり、抽象で出てくるというわけである。だから私の場合も、黄瀬戸のもつ色彩的な魅力、つまり黄の一歩手前ともいうべき微妙な度合(茶碗黄瀬戸の場合、黄色かったら、たとえば菊皿の類はもはや黄瀬戸ではない)やそのフォルムから、連想のような形で、頭中に一つの絵としてのフォルムが浮かび上がってくる。▼2 「いろいろな場合の発想」のひとつといつてゐるが、これこそかれの發想の原形とぼくらはみくいい。鳥海の工房のなかではたやすく花生を女に仕立てる造形の錬金術がふるはれる。或るものはつねに別の或るものに變身するわけで、鳥海は描寫をしないといふゆゑんの一端はここにあきらかだらう。かれは構成するのだ。それはそれとして、いま焦眉の急は「黄瀬戸」をめぐる黄色といふ色だつた。 どれだけ眼をこらしても、かつての鳥海にはかんがへられなかつた簿塗の、一見くらくみえる『うずくまる』の色づかひがよくよく色を感じさせなくはないとしてもつゐに黄色があらはれることはない。ところで土の乾いた色ともつかぬ色を黄瀬戸と呼んだのは古人の達識である。「黄色の一歩手前」はすなはち黄色とみなすこの判断力をそれでは『うずくまる』ではたらかせることはできないだらう。しかも自然釉とか灰釉とかとよばれてゐる焼物の肌ざはりと鳥海の『うずくまる』の触感とのあひだにはひとめでわかる聯關があるのだ、とは繪のはうにも黄色がかくされてゐるかもしれないといふこころである。隠されつつ顕れる─つまり『うずくまる』は黄色の零度なのだ、といふ。可能的な黄色。そこからすべての黄色がうまれてゆくとして、それ自身は生みだすといふまさにそのことゆゑに黄色であるともないともいへる場處。さふいふ場處としてかんがへられるのは『うずくまる』以外には絶對ないのだ。 |
|
|
三、 畫家だつたらどんな色彩でも自由につかへるといふのもひとつの神話だらう。たとへ寫實的な繪のばあひでも畫家がじつさいにおこなつてゐることは、繪具をまぜあはせることで眼にみえるせかいの色にできるかぎり接近するのではなく、現實のどこにもないがかれがつかふことのできる限られた虚構の色を構成して、せかいのモデルを提出することにすぎない。似てゐるとはちがふといふことだ。パスカルはそこでつまづいた。かたちはもちろん畫家にとつて色彩は獲得すべく發明すべきものであって、パレットから畫布への輸送はそこではじまる變換のためのほんの端緒以上ではない。 言はもと清濁なし志高ければすなはち澄む、とは單にことばのせかいの消息だけをつたへるものでなく、眼にみえるものとみえないものとの聯關がとはれるすべての場處にはたらく無形のちからを暗示することばである。畫家がしろいカンヴァスをまへにして手にとる繪具は辞書のなかのことばも同様にまだちからの磁場がかたちづくられるまへの無重力─といふか、より正確にはあらゆる方向からひとしいちからをうける状態にあつて、無意味かつ過意味である物質にすぎない。或る畫家はそれと格闘しなければならないし、また或る畫家はそれと對話する。それがうまくいつたときだけ意味はうまれる。もちろんそのときに意味とよばれるのは、畫家がふるふ力がおほきければそれだけ単純な、しかしバイアスをかけられたながれ以外ではない。 手をのばしてかたはらの樹から林檎をもぎとるやうに、いかにもやすやすと得たかのごとき印象をあたへるときでも、その色のつよさは、じつは物質が物質である抵抗をねじふせるなり利用するなりして、みえないものをみえるものとする畫家のリョ力による、といふことはつまり色はつくられるのである。ひとしれぬ工夫と錬金術によつてつくられた色であるのに、一方みるひとはあたかもそれが自然にそこに生れたとみなすしかない。この錯覚は感嘆とつりあつてゐる。そのときほんたうはなにがおこつてゐるのか。だれも外界をみるやうに繪をみはしない。そのときひとは精神との相關のふかさ、或は密接にこそ自然をかんじてゐるので、それ以外ではない。鳥海の黄色をめぐつても又さういふ機微がはたらいてゐる。種子せかいを無とみてその無から現成したのがかれの黄色だといへるだらう。その現成のまへに鳥海に黄色はあつたかどうか問ふのはそれこそ無意味にちかい。 これが牽強附曾ではないかとうたがふひとのためには、さひはひ、鳥海夫人美川きよが『春の段々畠』について残してゐることばがあつて、この連作がながいあひださがしもとめてゐたモチーフだつたこと、そしてそれを広島県福山郊外の春景色にみつけたことがかたられたあと、東京へもどつてしあげたその劇的な瞬間を記してゐる。 鳥海の絵の中に黄色が入ったのもこれが最初だ。俺の絵の中に黄色が入つた、と叫んだ。▼3 かれをおそつた昂揚の状態に身ぢかにゐて感染したひとの口調がよくつたはつてくる。軽妙な都会人鳥海が叫んだなんて、よくよくのことと解するほかない。鳥海の生涯にふたつとない事件である。これを裏書きするかのやうに、土方定一がほとんどおなじことばを記憶してゐたことをぼくらは知つてゐる。 このとき、鳥海青児は「俺のなかに黄色が生れた」 といつた。▼4 残念ながら三つめの例はしらないが、別の回路をとほつてかきとめられたこのふたつの証言だけでことの重大さを知るにはじふぶんだ。ただし土方のかたる「このとき」は美川のそれとおなじではない。作品のこととして美川があげたのが『春の段々畠』だったのに對して、土方がおぼえてゐる黄色の誕生は『狸穴風景』なのであった。しかしそれはどちらでもかまわなくて、大観すべき要は、すべて「俺のなかに黄色が生れた」といふことばのなかにふくまれる。なんなら「黄という色は私の持っている色ではない。」といふフレーズをそのそばにおけば、かれの感動はその形影参同の妙によつていつさうきわだつ。しかもそのことばはけつして架空ではなくて、じつさいにも鳥海の口から發せられたのである。▼5 ふりかへつて、一九五三年は鳥海にとつてすでに五十一歳をむかへる年である。鳥海の精神の衰へをしらぬ柔軟にあらためて驚くが、むしろみるべきは黄色の發明を成就するためにかけられた厖大な時間であり、平板にのびてしまはうとする歳月に屈せず耐えたかれの持続力であらう。なにかのをりに「俺はしつこいからね」と鳥海はいつたことがあるときく。鳥海が『夜のノートルダム』を二十年ちかく描いて、はじめの夕景色が深夜となりつゐには夜があけてしまつたといふ有名なエピソードに端的にあらはれてゐるものこそ、他でもないこの持続するちからだ。刻苦も不斷となればかへつてその姿は日常のなかにまぎれやすく、又それをあらはに作品にしめすには含羞のひとの誇りがゆるさないから、かれになくはない軽妙とか才氣のうはべがかへつて目につくのは是非もないが、畫家鳥海の手柄の第一はやはりこの持続する意思におくべきではないか。天受の色感においてかれを超える畫家はたぶんゐるだらう。しかしかれらの意思はそれゆゑかへつて弱い。色彩をつくりだす意志の持続にかけて鳥海に肩をならべる近代日本の畫家をぼくはほとんど知らない。 |
▼3 美川きよ『夜のノートルダム』、中央公論社、一九七八年、頁二五二 |
|
四、 さてこの邊で「黄色」の系譜と名づけようとする作品群の跡をまういちど確認しておきたい。年代の順に、『かぼちゃと壷』『春の段々畠』『狸穴風景』『黄色い人』『女人像』『壷をつくる』『彫刻をつくる』『ピカドール』『伊賀瓶子とメロン』『家の修理』『壁の修理』『スフィンクス』『石だたみ』『北京』などをいま畫集からひろひあげることができる。これらのうちで管見することができたものはその記憶をよみがへらせつつ圖版とつきあはせてその揺らぎを補正してみると、いかにもこれは野心的で大胆な實験だと思はせるそぶりを野暮と嫌ひながら、ふりかへつてみれば著しい進境ぶりは疑ひなくそこにあると同時に、きびしい審美のふるひにかけられて、たつたひとつの究極の黄色なら黄色へ練りあげられてゆく底の直線的に行進する歩みなどより、むしろ箇々の具體的な要求に應じようとして、その場その場で結飾/結晶してゐる多様性のはうを目立たせてゐはしないか。多様體としての色。作品相互のあひだのことはもちろん、ひとつの作品を塗りつぶす色のうちにも又この多様は内包されてゐて、黄色にかぎらず鳥海の色は單一からうまれる勁さもつとしても、なめらかに無方向にのびる金箔とかバターのそれとちがひ、もつと厚みと陰影に富んだざらざらする大地で、さらに凹凸や屈曲する襞のやはらかさを蓄へてゐる。多くの色を感じさせるゆゑんである。この單一は人生のやうにおほくの含みからできてゐるのだ。これを稱してひとは鳥海の色の澁さといふのだらうか。しかもそれは明といへば明、暗とみれば暗の、いづれにもとれる微妙なテクスチュアで、濁ることなく艶を殺して粒だつそれのうへになにかが描きだされるまへにすでに最小限度の量感をそなへる。量感としての色。 さういふ色をかたるならマチエールにも触れるべきではないか。いつたい色/量感とマチエールは重力と運動に似て或はおなじものの別の名前かも知れず、ただ不即不離といつておくだけが曖昧なやうでも實は正しく、畫家の認識の度合はそれをかれ自身の造形でどう鍛へあげるかで証明するしかない。鳥海がこれを高度な次元で達成してゐるのはもちろんであるし、又それゆゑ、 色と離してマチエールを考へたりしても駄目なんだ。あるマチエールを獲得したときはじめてこつちの思つてゐた色が、出るんでね。▼6 といふ發言がただそれだけでをはらず精彩を帯びるにいたる。もつともここに一種の力学がはたらくとみて、たとへば直角をなすふたつのヴェクトルに分解は可能であり、さう解析するとき、さきにいくらか例をあげた黄色の系譜を迫ふことは即ち鳥海のマチエールのヴェクトルが小さくなる分だけ、逆に色めヴェクトルがおおきくなる歴史にたちあふことになりさうである。『信州の畠』などであれほど繪に迫力をあたへたマチエールが色に殺されてゆく過程。殺されて運動することをやめた、カオスではなくコスモスとしての、波動でなく粒子としてのマチエールこそ、この時期の鳥海のマチエールすなはち色なのだ、と。 周到に下塗の準備ををへたあとは一氣呵成に仕上げるだけだといふゑがきかたを鳥海はしない。かれの制作はスポーツの一種でなくて、もつと呼吸の起伏のなだらかな散歩にたとへられる。どこではじまつてどこで終つたのかみわけがたいとしても、植物が生長するやうに繪はまちがひなく生長し花を咲かせるが、しかし植物にとつて開花が最終の目的でなく結實があり種子をうみ地にかへつてふたたぴ芽ぶく無限の循環のどこを切らうとその斷面にすべてが成就されてゐるのと同様、下塗はすでに繪であるその上にさらに何層も色を堆積させながら、そして時としてペインティングナイフをもちゐて削ることがあつてもそれでもすべての色は生きてゐなければならない。いつたん存在したものを殺してはいけないとする藝術による菩薩行を、水墨畫はいざしらず、或る意味ではそれをもつとも不得手とする油繪といふ表現形式のなかで積極的に實践していつた結果としてこの粒子としてのマチエールはあるのだ。 あれ〔畫家スゴンザックの作品〕はナイフで上へ上へ重ねて行くから、下絵の絵具が上の絵具の中に生きて来ないんだ。下積みで死んでしまつてゐるわけだよ。それぢやいけないと思ふんだ。それや途中で失敗することもあるよ。だからつて、それを見えなくしようとして、外の色で塗りつぶしちやいけないんだよ。その失敗したパートでも、生きるやうに、その上に塗るパートを調へて行かなきやならないんだ。▼7 鳥海の狙ひはあきらかに一枚の畫布を缺けるもののない全圓のせかいとした全機関同時現成である。ここで犠牲といふ観念はゆるされない。スゴンザックのペインティングナイフを斷罪する〔鳥海もペインティングナイフを使ふには使つた。ただしゑがくときでなく削りとる場合にかぎつて。かれの厚塗のマチエールは一刀三拝にも似た精神の集中と入念きはまる手仕事の集積なのだ。〕のも、單なる技術論を超えて、はてはこの世に無用のものはないといふ思想にいきつかずにゐない、そんなゑがくひと鳥海の精神のはたらきの一端にそれがふれたからである。無用の色も無用の筆づかひもなく、削りとつた繪具さへ練りなほして再びつかはれる。なにをゑがくかでなく如何にゑがくかを巡つて意識がつねに現在にあつまるために即興性がつよくなることもここでいつておきたい。なにが出来るかは筆をおくまでわからないのだ。これも又鳥海にヴァリエーションを多くさせる理由になつてゐる。 ところでさきに引用した文に「あるマチエールを獲得したときにはじめてこつちの思つてゐた色が、でる」とあつたが又別のところでは、 色を追求してゐるうちに、副産物みたいに、そのときのマチエールが成り立つて行くんだよ。副産物と言へば聞えが悪いけれど、いい加減な色で満足してゐると、マチエールもきたないし、堅確にならないんだ。▼8 ともいつて、これは矛盾といへばいへるが、むしろこの揺らぎにこそ真實の鳥海があるとみればどうか。どちらかだけをとるのはむしろ偏狭だ。ただ三次元のイリュージョンを排し、運動はもつぱらものとものとの關係でとらへて平衡めざす平面性がつよくなつた黄色の系譜をかたるためには或は後者のはうが便利ではあるかもしれない。 均質にならされてゐるだけで、對照的な疎密とか落差とかによつてこそあきらかなエネルギーに就てはその総量はけつして減つてもゐないはずだが、それでも年を追って洗レンの度をくわへるその色がかつてのフォーヴィスムを思はせる重く激しい運動感を失つてしまつたのは認めてもいい。畫布のテクステュアがすけてみえる『うずくまる』のやうな薄塗はかつての鳥海には考へることもできなかった。又古楽器の澄んだ音が静けさをやぶつて聴こえてくる一聯の静物畫も。それならぼくらは鳥海の様式のうへに極端な斷絶と變化しないもののふたつながら同時にみるといふことのはうがもつと肝要なのだ。 |
▼6 鳥海青児『厚塗りのマチエール』、アトリエ増刊号、一九五五年 |
|
五、 土の性の畫家鳥海は畠の連作をときをへだてたふたつの時期にゑがいてゐる。第二次世界大戦後着手した例の『段々畠』をここで仮に雅とよぶなら、一九三〇年代の『信州の畠』はそれとは對照的でその怪と力にこちらが圧倒される作品といへる。イタリア施行の紀念である」一九三三年作の『寺院(フローレンス)』『フロレンスの寺院』ではぼくにスーチンをおもひださせる捻じれたちからが畫面から溢れて、こちらの身體にまでそれが傅染するし、又『フローレンス風景』をみてゐると、花の都といつた観念などかけらもなくてただ洪水のあとの泥が過ぎた濁流のすごさをとどめるそんな風景畫としかおもへない。重たく粘る筆触ばかりが目にやきつくのである。このちからの線をのばしたところに一九三六年制作の『水田』『信州の畠(一)』『信州の畠(二)』があり、さらに二枚ある『紀南風景』をへて『石橋のある風景』につづいくゐる。一九四〇年第十八回春陽会展に出品した沖縄の風景畫には轉調のきざしがみえる。或る意味で鳥海作品のうちでももつともみごたへのあるのがこの邊りで、かういふ繪をみてゐると、『段々畠』とあはせてつくづく鳥海の本領は風景畫にあるなとおもはせるが、はなしを畠にもどし、この鳥海様式の標本としていいくらゐたかい水準に達した各々の連作にあらはれた表現のちがひが氣にならないこともないのだ。そこに一種の斷絶がある、といつた風に。 そのちがひは『水田』にすでにあきらかである。その題名にもかかはらず一切の水氣が畫面から蒸發してゐることは譲るとしても、なにがゑがかれてゐるのかがまづわからない。不明不暗、曖昧模糊のあひだでものの大小を判斷する距離感覚といふ仕掛が奪はれるからで、さういふときぼくらの眼といふのは無限遠のはうへいつたん引きさがつて焦點をさがすためかなにかとてつもない風景を捏造してしまふ。そしてそれは、乾燥してやせた大陸性氣候の荒蕪の風土であつても、ぜつたい箱庭のやうな日本の田園ではありえないのだ。 或はこのとき鳥海は生涯において抽象畫へもつとも接近したのだといつてもいいくらゐ、マチエールのちからだけが突出して他のすべての要素を蔽ひかくしてゐる。この飼ひ馴らされることを拒んだ暗褐色の書面は『信州の畠(一)』『信州の畠(二)』にそのままつながり、さらにそこでは大地は荒れた海とにえ、又みずからが意志をもつ生物も同様に褶曲をくりかへして繪具は凹凸する。もしここで鳥海が自然の構造といつたものをつかまへようとしてゐるなら、その構造なるものの根本はぜつたいに均斉においてはゐない。天地玄黄、宇宙洪荒のことばこそふさはしい。或はひとのこととして鬱屈するエネルギーがそのまま物質としての繪具にのりうつつたかのやうでもある。 ところで一方贔屓のすじからみても、ここは鳥海をかひつづけるかどうかをむしろ畫家のはうから逆に試される難所であるかもしれない。現在の位置とともにその運動につまり未來に敏感であるべき批評家にしても、鳥海作品の熱度はみとめても繪具の乱暴ともいへるあつかひをまるごと認めるには相當の勇気がいつたのぢやないだらうか。一九三五年春陽会展にふれて荒木季夫が「鳥海君の作品は今年は随分といいと思ふが、實際汚ないね。春陽会にはたしかにキタナイといふ感じの繪が多い。」といつてゐるのがそのひとつの例だ。この「キタナイ」といふいひかたに多分の含みをもたせてゐるが、さういふ手軽なやりくちで間にあはせた怠惰の分だけ、鳥海の繪はなんだかわからないがその穢いところに勢ひがあるといふ通念のまへで足踏みし、まづ白紙に還元したところから繪をみるといふ無垢の眼を閉ざすことになる。これが批評のことばでないことは情理のうちの情さへ籠らない口調にはつきりするのに對し、海老原喜之助の、 脂色と淡墨を捏廻した一見穢い色を、ベラボーにエネルギシュに畫布の上に練り廻して居る彼の作品は實に立派なものである。乱暴な塗り方はよく薫然とする調子までに使はれて只美しいだけである。風景畫家の最も心すべき水平線を、心憎い迄に愛用し、活用して居る、黄ばんだ、人物の居ないのに人を感ずる「信州の畑」の如きは私の最も好きな作品である。▼9 には、ものをものとみる正確な眼がはたらいてゐる。單なる仲間褒めでをはらずに批評になつてゐるのはさすがといふべきか。かれが、「只美しいだけである」といふとき、穢い/美しいといふ』二項對立をしりぞけはしてもそれ以上の表現をついにもてずに絶句したその真空をやむをえず充たすことばであることが文脈にそつてあきらかで、ここに一瞬みえる裂目をとほして言詮を絶した色が海老原の、ひいてはぼくらの目に幻ゆゑに真の残像をつくる。 ではその色は。ふれた瞬間にまう書面からはなれるかるい筆跡が直線とのび曲線にかはつて屈伸するにつれ、黄金色にかがやいたレンブラントをおもはせる『うずら』(一九三〇年)のやうな例外は例外として、色の魅力にとらへられるまへに一種潜熱を帯びたエネルギーがそれを追ひこしてぼくらを圧倒する作品がふつうだ。色の砂地に吸収されてしまつたマチエールが零度の『黄色い人』のばあひとは逆に、ここでは色はマチエールのちからにくみふされて、眼をよろこばせることができず、色はないにひとしい。ないにひとしいので、色がないわけではない─といつても同じことなら、色でなくて光がないといひかへるべきだらうか。いつたい印象派の畫家たちが苦心してとりこもうとしたあの光の表現に鳥海はたいした執着をみせないらしく、ドイツ表現派の色に似るのはそのせゐである。、又いふまでもなく光をとらへようとして黒を追放した印象派の畫に對し鳥海の畫面はどこを切つても黒といふのか明暗がないところはない。 かれがヨーロッパに留学して得たもつともおほきな成果はゴヤとレンブラントの發見だつた。 スペインのプラド美術館で滞欧の方針は完全に決定してしまった。グレコ、ベラスケス、ゴヤ、の作品、特にゴヤのモノクロームの怪奇的な数々の傑作には茫然とりこになつてしまった。私はプラド美術館に一ケ月一日もかかさずゴヤを訪れた。▼10 といひ、さらにつづけて「しかし、体質が受け入れられる名画こそ、作家の血肉になる作品である。ゴヤは私の生涯に決定的な影響を与えて呉れた。」、「かくて私はレンブラント、ゴヤのはるかなる亞流となって帰国した。」と書いたのは、一方で、渡欧以前にやつてきたことは基本的にまちがつてはゐなかつたといふ自信と別に抵触しない。ゴヤとの出会ひはすなはちまうひとりの別の鳥海、しかもはるかにさきをゆく自分であるゴヤとの出会ひにほかならず、その場が例の「黒い繪」に集約されるだらう黒色の圧倒的な表現力であることは、『信州の畠』と「黒い繪」との親近に欲してあきらかだ。 暗黒のなかに漂ひ、集散をくりかへす粒子の群れにほかならぬ光なき光。ゴヤにあつてそれは酸鼻をきはめるせかいをゑがく絶對的な孤独のなかでも物心両面からせまる暗黒にからうじて括抗しつつせかいに色を与へる精神のくすんだ輝きで、そのことはレンブラントにいたればさらにはつきりする。ところで鳥海の色づかひはレンブラントよりゴヤに近く、色の粒子は結局光に轉化しようとしない。光を表現しない色、外光がなくてもせかいの存在をゑがける色、或は光があるとするならそれが精神の光以外ではない、そんな色の發見。と、かいていまぼくは明暗のニュアンスだけで書面をつくりあげた須田國太郎のことをおもひださうとしてゐる。 畫家の留学といへばパリと相場がきまつてゐたときに、ひとりスペインにおもむき、プラド美術館を自己の学校とした須田がもとめてゐた色と鳥海のそれとは、どこかふかいところで通底するもの―鳥海がいふまさに血脈があるはずだとぼくなどは漠然とかんじる。なにがといつて他ではない須田のあの黒色である。暮れきればあとは明けるしかない現實のせかいとちがつて、明暗の諧調のなかに無数の色を聲もなくしづませていつまでも明けることのない、かれの畫面の真の支配者であるあれら黒色たち。 鳥海のせかいの基調となる色もまた黒色なのである。墨に五彩ありといふ。その逆もまた真であるとき五彩、すなはち數ある色を撥無して現成する墨にたとへていいのがこの鳥海の黒といはふか。夜の闇の物質化である須田の黒にくらべれば動きやすい土や砂の表層を風雨がゑぐりとつたあとに残る不動の岩と粘土質のやうな鳥海の黒。また「穢い色」、印象派の光とそれをまがりなりにもちこんだ近代日本のそれから身を剥がさうともだえる色でもある。もつとも身ぢかな現在ばかりか、もつととほい記憶をも蘇へらせることができる光をみつけようとして、印象派を経由する虚構の光を殺したためにブラックホールとなつた光である黒。鳥海はまづ光を否定したのではない。なにものかに強ひられつつその場をしのいでいつたそれ自體はちひさな積重なりが結果的にかれの畫面から時間の函數としての光をしめだしたともいへる。 又鳥海青児氏の黒い繪が澤山あつたがベニスのスケッチを見て、明るい景色でも皆一様に暗く描く人と思つた。▼11 黒田清輝以来の近代洋畫はすでに制度をかたちづくつてゐる。ありもしない畫家の眼といふ神話ができてゐるなら、鳥海はさういふ眼から自立しようとする。かれは視覚にかんしては恐るべきリアリストだ、とはかれの眼がみたものに素直であつたにすぎない。あかるいはずのものを暗くゑがく成心などかれにあるべくもない。それまでに培つた風土をみるおのれの眼を信じ、そのかはらぬしなやかさでヴェニスその他に正對する度胸があつただけである。 |
|
|
六、 海老原に脂色と淡墨をこねまはしてゐるといはせた鳥海の筆づかひは『春の段々畠』以後すつかり影をひそめたかのやうにみえる。もつともそれは観見の眼といふときの、分析するちからに長けた見の眼にさううつるだけで、一方、観の眼をはたらかせば事情は一變するといふもの。そのときたちあらはれるのは、『信州の畠』とさうちがはない、畫面の奥へとしづんでゆく黒の印象といへばいへる。區々別々にみてゆけば色がないどころではないのに、いざその印象を湊合したとき奇妙なことにどこか水墨畫に似てしまふ日本の風景に、これは通底する色だ。緑はふかく暗く(『壁の修理』)、青は濃い群青に(『北京天壇』や『川沿いの家』)、そして赤も燃えるやうな色でなくて代赭とか紅殻色で(『うずくまる』)、昏いのである。黄色でさへもじつは影を帯びてゐる。 しかしこの同じ観の眼―狭くするどく焦點をあはせるのでなくて視界の果てのはうから結像するゆるやかな眼をもつて初期鳥海にもかへば、今度は逆にすでにさういふ色があらためてみえてくるはずである。たとへば、次のやうな文章がある。 鳥海青児君は、サビと雅味とを帯びた独特の表現を持つ、よい天分の人です。▼12 「麓人社素描展」にふれて小林和作がこれをかいたのは一九二九年といふから、鳥海には、欧州旅行よりさらにまへの氣鋭の新人とよばれる時代のことである。鳥海とあひ前後して春陽会にくははつてゐるので、、小林は當然『水なき川』や『芦畠嵐景』や『北海道風景』といつた初期作品を知つてゐるはずで、さういふ背景からこの批評はでてゐる。渋いやうな華やかなやうなじつに含蓄といふか奥がふかい鳥海の色彩を寸言でとらへたのは、他でもない小林の観の眼のはたらきであつた。けれどここは小林の具眼にあらためて感心する場所ではなく、鳥海青児の色をかたるとき外せない古雅な味ひがその出發の時點からすでにあり、又それを失つたことはなかつたといふことがわかればそれていい。逆にたとへば年をかさねるにつれて圭角のとれたかれの畫が、ついに趣味のせかいに低徊沈価していつたといふたぐひの鳥海評は、このことからもその根底をうしなふだらう。進歩とか圓熱といふ符牒をはねのける清新さが鳥海の畫からきえることはなかつた。 ただ小林和作の観の眼を以てのみよくわけられた「サビと雅味とを帯びた独特の表現」がやがて見の眼にさへはつきり寫るやうになつたのはたしかなので、そのことにふれるためにも、ここでまう一度『黄色い人』その他の黄色をふりかへつてみようか。唐突かもしれないがここでrealisationといふセザンヌのことばをおもひだしてもいいので、誰もが日常につかふ単純なこのことばをおもはず深讀みさせたのはセザンヌの哲学でなくその當の繪である。かれの達成がこのことばを定義したのでその逆でなく、セザンヌの繪をみてゐてrealisationといふことばに到れば繪はいつさう輝きをますけれど、realisationから出發すれば迷路にまよつてセザンヌの繪の「頂點」どころか麓にもゆきつけないだらう。おなじことは鳥海にもいへて、とにかく、日本語で「實現」といつていいそのことばに受肉する或る手ざはりを鳥海の畫面にみるのである。 鳥海が切りひらいた色のせかい。そこでは『信州の畠』の色は殺されることなく『春の段々畠』に、さらに『黄色い人』にさへ生きてゐる。それをとりあへず光を否定した色といつてみても別のいひかたは當然あるだらう。たとへば『黄色い人』の黄色よりも『彫刻(黒)をつくる』の黄色のはうがよくわかるが、それは油繪のいちばんの長所であるだらう輝きを括弧にいれたうへでの、きはめて間接的な色なのである。これは黄色だけにかぎらない。鳥海がつくるすべての色に共通する油氣のぬけた非現實的な色感は、なぜかそれをみながら同時に色のない水墨畫をみているやうな奇妙の経験をぼくらにしひることがある。モノクロームにかぎりなくちかづき、そしてその幽明境を接する底からふたたび浮上してくる色ともいへぬ色。いはば精神的な色だが、闇でありながらその重さが物質をつぶして黒い光を發する須田國太郎の色ほどの勁さはここにない。骨を凍らせる寒さではなく、温みをもつてゐる。むしろいたづらに哲学的と誤解されてゐる坂本繁二郎の色に似て、しかも鳥海のばあひ神韻縹緲といふには感覚的でありすぎ、かたちは影ととけて輪郭からにぢみでて色となる。 まづそこから時刻が消される。光がないといつても又むらなく均等に滞留するといつても同じで、そのせゐだらう、色は現實の再現といふ機能をすててしまふ。他に制肘されず、なににも依存しない自立した色とでもいふべきだ。ここで鳥海は抽象繪畫にあたふかぎり接近してゐるといつても別に不思議でもないくらゐである。 しかしさうはいつても全體として鳥海の色として眼と記憶に刻みつけられるのが黒のせかいである といふことが残る。「サビと雅味」のなかに沈んでゐる、まうひとつの色としての黒。この色は、フランスの景色は友禅みたいでコクがないといつた坂本の色感を刺戟し、須田に黒をゑがかせたものとあきらかにおなじ對象にかかはる。そして鳥海のばあひ、それは平安仏畫はじめとする古畫や陶器など、近代以前の日本がつくりだしてきた古美術からの影響といふことになるのか。たしかに鳥海は書畫骨董のすぐれた目利であると同時にコレタターでもあつた。だからといつてその作品に古美術の影響があるといふのは短絡で、ありやうは、自然のかたちと色をみるおなじ眼が古美術に注がれるとき、そこにも又人の手の巧みをこえて同一の自然のちからを感ずるなら、そのちからを信じてゐるかぎり作品から摸倣しようが自然から摸倣しようが違ひはほとんどなくて、それは模倣ですらないといふことだ。鳥海の作品はさういふことを信ずるひとによつてしかゑがけない古色を帯びている。 ここですこし飛躍して、たとへば日本と呼ぶことになれてゐる土地の、これは色なのだといへばいひすぎか。風土がもつ色はかならず色ならぬ色だから、その内部にゐるだけでは絶對にみえてこない。外部から幻視しなければならず、いひかへれば、内部と外部を自在に往き來する眼をもたねばならない道理だが、さういつたちからに恵まれて色でない色をみてしまふひとを土地の霊の守護者といふなら、鳥海はまさしくそのひとりに名をつらねられていい。しかし土地の霊の呼びかけが誰にもおなじ單一の呪文でないのは、さきにあげた坂本繁二郎、須田國太郎、鳥海青児それぞれの繪が他ととりかへやうもなく自立してゐることにあきらかである、と書いてきて次のやうな文章が鳥海にあつたことを思ひだす。 僕は三年前、なぐさみに初めて日本畫に手を染めて見た。手初めに草花類の写生を初めたある一日庭に出てふと枯草の美しさに愕然とした事がある。この片々たる雑草の美しさは紙と硯なくして到底表現切出來ぬ可憐な美しさだつた。たくましい油繪の生活にはまつたく一顧もあたひしないものだつた。いはゆる風景明眉な日本の自然が、繊細な可憐な美しさ以外のなにものでもない事を思つた時、今さらながら苦汁をのまされた感があつた。▼13 日本の近代洋畫の歴史がはじまるやいなやくりかへされた叫びならぬ叫びを鳥海も又ちひさく叫んでゐた。しかしかういふ問ひのたてかたが、日本語ははたして英語とかフランス語に劣らぬ論理の構造をもてるかとあやぶむのと同様、或る意味では滑稽きはまりないと氣づかないかぎり、そこから一歩もふみだせず、たたらを踏むだけだ。いつたい日本的油繪といふ観念の砂漠には死屍累々たるものがある。鳥海はこの不毛をからうじて免れたとぼくが信じるためには、問ひに愚直にこたへるのでなくて問ひそのものを變へ、抽象畫と具象畫の境をこえつつ蝉脱していつた作品の跡をたどるだけでいい。そこで「繊細な可憐な美しさ」をみるかれの視線が同時に、雑草を生かす餘地をもたぬヨオロッパの比ではない、この土地がもつなにか不死身の生命に似てゆたかな繁殖力をみとどけてゐるからである。かれのゑがいた黄色のなかに四時沈んでゐるさういふ土地の豊ジョウを暗示するちから。それはけつして明るくはないが、水分を最後の一滴まで抜きとつた繪肌のためそれ以上やせることはなく、鳥海ゑがくノートルダムをのせたフランスの大地のやうにいつまでもそこに存在する。 |
▼12 小林和作『麓人社素描展評』、「アトリエ」、一九二九年七月号 |