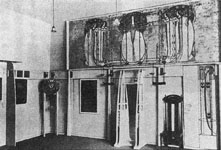一九〇〇年のインテリア・デザイン(上)
芸術作品としての部屋
土田 真紀
|
一、 序-「貧しく富める男」(ザ・プーア・リトル・リッチ・マン)のインテリア 近代建築の先駆者と見なされながら、自身はそうしたレッテルをきっぱりと拒否し続けたウィーンの建築家アドルフ・ロースは、一九〇〇年四月二十六日付の「ノイエス・ヴィーナー・ダーグブラット」紙に「貧しく富める男」というエッセイを発表した。▼1ウィーンの新興市民階級に属する「貧しく富める男」は、財産と幸福な家庭を築き上げたが、ある時ふと自分には「芸術」なるものが欠けていることに気付き、さっそく高名な建築家を訪ね「私に芸術を、わが家に芸術を与えて下さい。費用はいくらかかってもかまいません。」と自宅のインテリアの設計を依頼する。そうして彼は望みどおり、見事に統一され、隅々まで芸術が行き渡った住居を手に入れたのであるが、それこそが彼の悲劇の始まりであった。「芸術的な」部屋は彼の生活を徹底的に束縛することになったのである。彼は建築家が整えた部屋に、何一つ無断で付け加えることができないどころか、部屋の中のものを動かすことさえ禁じられてしまった。建築家がつくりだした完璧な調和、完璧な統一性。たとえ部屋の所有者であろうとも、それを破壊することは許されないというのである。住居における自由、住むことの喜びを一切奪われた「貧しく富める男」は、こうして気の毒にも幸福の絶頂から不幸のどん底に転落してしまったのである。 同時代の建築・デザインの諸相に対する痛烈な批判と攻撃を次々と発表していたロースであったが、なかでもこの一文は、たとえ話の形をとりつつ、痛烈な皮肉による最も手厳しい批判を展開している。ここで真に批判の対象となっているのが、この小文の主人公である「貧しく富める男」ではなく、ヨーゼフ・ホフマン、コロマン・モーザーといったウィーン分離派の「高名な」建築家やデザイナーであることは疑問の余地がない。ウィーン分離派こそはロースにとって最大の批判の鉾先であった。ある時は名指しで、またある時は暗にほのめかす形でロースは繰り返し徹底して分離派を攻撃している。 ところでロースが描き出す「貧しく富める男」のインテリアとはいかなる特徴を備えているのだろうか。 各部屋は色彩のシンフォニーをなし、それ自体で完璧であった。壁面、壁紙、家具、そして素材はきわめて巧みなやり方で調和を生み出していた。家庭生活に不可欠な品々はそれぞれ特定の位置を占め、他のものと一体となって絶妙のコンビネーションを生み出していた。▼2 ロースのこの描写は、現実的というより、むしろ予見的であるように思われる。スコットランドの建築家チャールズ・レニー・マッキントッシュが分離派の招きを受けて、〈ザ・フォー〉の他のメンバーと共に第八回分離派展に参加したのは、同じ年の十一月のことであった。その際にマッキントッシュが提示したインテリアこそ、ロースが描き出した「貧しく富める男」の部屋そのものであったからである。確かに分離派の建築家たちのインテリアにはこれ以前からすでに大きな改革の兆しが見え始めていた。ホフマン、レオポルド・バウアーらが交替で担当した分離派展の展示室、一九〇〇年のパリ万博におけるオルブリッヒやホフマンの展示室、ホフマンがホーエ・ヴァルテの丘に手がけつつあった住宅群のインテリアなどがその実例である。しかしそこに決定的な変化が現れるのは、マッキントッシュのウィーン訪問以後のことであった。そして一九〇二年の第十四回分離派展のホフマンによる展示室において、この影響はまず一つの結果を生み出し、さらにはブリュッセルにやはりホフマンが設計したストックレー邸において頂点に達することになる。これをマッキントッシュがもたらした一つの輝かしい成果とみるか、災いとみるか。ロースは後者の立場をとった。徹底してものごとを感覚ではなく論理で捉える合理主義者ロースにとって、完璧な調和のもとに統一された住居などというものは滑稽であり、インテリアは住み手の自由に委ねるべきものであった。しかし同じく合理主義者でありながら、マッキントッシュを、なかでもその芸術作品と化したインテリアを、最大に評価した人物がドイツ人の建築家へルマン・ムテジウスである。 |
▼1 Adolf Loos,‘The Poor Little Rich Man '.Spoken into the Void. Collected Essays 1897-1900,Msssachusetts,1982,pp.125-7. |
|
二、 マッキントッシュとムテジウス 一九〇二年、ミュンヘンの芸術雑誌『装飾芸術』の編集者であるアレタサンダー・コッホは、三つの建築設計案のポートフォリオを出版した。これは、同誌が主催した「芸術愛好家のための住宅」をテーマとした設計競技への応募案の中から選び出されたもので、イングランドのペイリー=スコット、オーストリアのレオポルド・パウァー、スコットランドのチャールズ・レニー・マッキントッシュの三人の建築家によるものであった。選ばれた三人のうち二人までがイギリス勢であったという事実は、ヨーロッパの建築・デザイン界におけるイギリスの優位という当時の状況をよく示しているが、このとき、この二人のイギリス勢のポートフォリオに序文を書いたのがヘルマン・ムテジウスである。後に、〈ドイツ工作連盟〉を舞台にドイツの建築界できわめて重要な役割を果たすことになるムテジウスは、先進国イギリスの実情を学ぶため、ドイツ政府から派遣された産業担当官として、当時ロンドンに駐在していた。一八九六年から一九〇三年まで七年に及んだこの滞在期間中に、彼は精力的にイギリスの住宅建築の調査研究を行っており、序文の執筆者としては最適人者であった。その調査研究の真の成果は、帰国後の一九〇四年から五年に出版された三巻本の大著『イギリスの住宅』に結実している。 明晰な分析力と優れた芸術的批評眼の持ち主であるムテジウスは、マッキントッシュの生前彼について最も多くの批評を著した人物である。すでに述べたポートフォリオの序文のほかに同じく一九〇二年に書かれた『装飾芸術』誌の多数の図版を含んだ長い論文、▼3さらに『イギリスの住宅』における記述などがある。現在グラスゴー大学附属ハンテリアン・ギャラリーに保管されている書簡からも窺うことができるように、ムテジウスは個人的にマッキントッシュと親交を結んでいた。▼4ムテジウスが駐在していたロンドンとマッキントッシュの活動の場であったグラスゴーとの間には、少なからぬ距離が介在していたとはいえ、機会あるごとにお互いに訪ね合い、ムテジウスはたびたび直にマッキントッシュの作品に接する機会を持っていたのである。 『ザ・ステュディオ』の編集者で、〈ザ・フォー〉を好意的に取り上げようとしていたグリーソン・ホワイトが急死して以後、グラスゴーを除いたイギリスにおいて、〈ザ・フォー〉はますます孤立した状態に追い込まれつつあった。そんな中にあって、小なくとも一九〇〇年にウィーンで成功を収めるまで、ロンドン滞在中のムテジウスは、マッキントッシュにとって数少ない貴重な理解者であり、激励者であったと考えられる。他方、ムテジウスにとってのマッキントッシュは、イギリスの住宅への関心のなかで出会った最も興味をひかれる建築家の一人であり、その最大の旗手と見なすべき人物であった。 こうした両者の交流の中から生み出されたムテジウスの著述は、すでに同時代において、マッキントッシュの本質がきわめて的確かつ明確に捉えられていたことを示している。まず「芸術愛好家のための住宅しのポートフォリオの序文から引用すると、 スコットランドと大陸の芸術運動は並行して進んできた。両者は共に、基本的にイングランドの運動にその基礎を置いているものの、イングランドの展開をはるかに超える問題へと前進したのである。・・・スコットランド人の芸術家たちがイングランドの運動に全く新たに導入した要素は、室内装飾の目的という概念を従来よりも広く捉えたという点である。この概念は、現在大陸に広がりつつあるものにきわめて似通っている。・・・それは住居を統一的な全体として扱うということ、プラン、装飾、家具を考慮に入れて各部屋を調和のとれた芸術作品として設計するということである。細部の色調における調和、そしてとりわけ様々なものを組み合わせてインテリアに配する際に統一的な色彩計画でまとめることが絶対的なルールとなったのである。▼5 ・・・全体的効果あるいは全体の印象が前面に出るようになった。部屋は次第にそれ自体が一個の芸術作品と見なされるようになったのである。▼6 また『イギリスの住宅』では次のように述べている。 これらのメンバー(訳註:〈ザ・フォー〉のこと)の中心となる目標は、芸術作品としての部屋、すなわち色彩、形、雰囲気を一つに包み込んだ有機的統一としての部屋である。 しかしグラスゴー・グループの芸術の精髄は、実際、底流にある感情的かつ詩的な特質にこそある。それは、芸術的な雰囲気を大いに醸し出すこと、あるいはもっと限定すれば、神秘的、象徴的な類の雰囲気を醸し出すことを求めている。▼7 ここで、ムテジウスが捉えたマッキントッシュのインテリアの最大の特質を、ムテジウス自身の言葉にしたがって、〈芸術作品としての部屋〉と規定することができるだろう。一人の建築家によって、床、壁、天井はもちろん、家具、装飾品など、あらゆる細部にわたって丹念にデザインされ、形態、色調の統一が完璧になされたインテリア。それはすでに述べたように、ロースが痛烈に皮肉った「貧しく富める男」のインテリアそのものにほかならない。と同時に忘れてならない特質は、それらすべてが一体となって醸し出す〈雰囲気〉、すなわち神秘的で象徴的なある雰囲気がインテリアを包み込んでいるというムテジウスの指摘である。 |
▼3 Dekorative Kunst,V,No.6,Marz 1902,pp.193-217. |
|
三、 芸術作品としての部屋 十九世紀の後半に、インテリアは芸術家の真摯な追求の対象となった。第一級の建築家の関心が大規模な公共建築から小親模な個人住宅へと移っていく過程は、他方で、優秀な芸術家が、自らの生涯の仕事とするに足るほどに意義深いものとして、工芸品のデザインに取り組み始める過程とほとんど重なり合っている。ピュージンにすでにそうした兆しが現れ始めているとはいえ、これらの点に関して決定的な影響力を及ぼしたのはウィリアム・モリスであり、住宅建築に関して、後の多くの試みを鼓舞し、一つの原型を提示したのは彼のレッド・ハウスであった。 レッド・ハウスは、ジェーン・バーデンと結婚することになったモリスが、新居としてロンドン近郊のベックスレー・ヒースに建てた住宅であり、一八六〇年に完成した。モリスの親友でもあったこの時代を代表する最良の建築家の一人フィリップ・ウェッブが建築の設計を担当し、ラファエル前派の芸術家たちが、家具を初めとする様々な工芸品の制作に協力した。綜合芸術への志向、共同制作のあり方など、多くの点でレッド・ハウスは理想の住宅の一つのモデルとなり、それ以後の建築家に対し、芸術的な住宅の創造というきわめて重要な一つの課題を提起したとみなすことができる。 『デザイナーとしてのウィリアム・モリス』の中で、レイ・ワトキンソンは、ウェップによる建築も、芸術家による共同制作という概念も、従来言われ言たほどオリジナルではなく、すでに前例があったことを強調している。▼8その事実の是非はここでは置くとして、後への影響力という点ではレッド・ハウスがやはり決定的であったと考えてよいであろう。先の引用の中で、ムテジウスが、マッキントッシュと大陸の運動はいずれもイングランドの運動に基礎を置いていると述べているのも、究極的にはレッド・ハウスを源とする流れを指してのことである。実際、モリスの試みは、アーツ・アンド・クラフツ運動として、彼の直接の影響下に繰り広げられた展開のなかで様々な反響を呼び起こしていくと同時に、アーツ・アンド・クラフツからはむしろ不健全とさえみなされたグラスゴー派や大陸のアール・ヌーヴォーにも決定的な影響を及ぼすことになった。 ラファエル前派の画家であり、モリスの良き協力者でもあったバーン・ジョーンズは、レッド・ハウスを「世界で最も美しい家」と呼んだという。▼9その創造に関わった者にとっては、確かにそうあるべきものであっただろう。しかし四〇年後のムテジウスの目には、モリス以来のイングランドのアーツ・アンド・クラフツ運動は、個々の品を美しく優れたものにつくり上げはしたが、それらを有機的に結び付ける場としくの全体という観念が欠けているように映っていた。確かにレッド・ハウスは個々の芸術家の自発的な作品の集合体であり、全体にきわめて古風な中世的住宅の雰囲気が漂ってはいるが、明確な統一的プログラムのもとにすべてをまとめ上げようとする意図が、モリス自身にも、また建築家ウェッブにもなかったのは事実である。そうした意図をもって〈芸術作品としての部屋〉を真に実現したのはマッキントッシュや大陸の建築家たちであると先の文章でムテジウスは述べている。 ところで、こうした彼の見解がさらに詳しく、歴史的、体系的に展開されているのが、そのイギリス滞在の精華ともいうべき大著『イギリスの住宅』である。そこではインテリアに対する建築家の姿勢の変化について、世代を追って詳しい分析が行われている。〈芸術作品としての部屋〉という理念は、マッキントッシュにおいて一つの到達点を見出す以前に、徐々に展開されてきたのであった。 (一八八〇年代の審美主義の意義として)最も 重要な点は、一般大衆の注意がインテリアを芸術作品としてみなすことに再び向けられるようになったことである。 一八八○年代に至るまでにそれぞれ個別に展開してきた二つの運動、すなわちノーマン・ショーの名において進められてきた住宅建築の改革とウィリアム・モリスの名において進められてきたインテリアの改革とが、この両者の弟子たちによっていまや結び付けられ、一つの大きな流れを形成することになった。▼10 ノーマン・ショーに率いられたクィーン・アン運動の建築家たちは、非常に独自のインテリアを確かに創り出したが、なおあまりにも過去を振り返りすぎており、あまりにも回顧趣味で、完全に自由に制作するには至らなかった。モリスは独自の完全に個人的な道を浪求したが、恐らく装飾にいれ込みすぎていたのであろう。真に現代的なインテリアはこの次の世代と共に、現在アーツ・アンド・クラフツ運動を構成している人々と共に初めて出現したのである。▼11 これらの見解は、こうした一連の動きが起こって間もない時期に発表されたものであるにもかかわらず、きわめて的確であり、今日でもほとんど異論の余地はないように思われる。一九七七年に初めてこの本の英語版が出版された際に、その序文でテニス・シャープが述べているように「当時、ムテジウスほどの正確な観察力と明確な理由づけに対する直感力を備えた批評家はほとんどいなかった」といえよう。モリスとノーマン・ショーの「次の世代」の建築家、すなわち、過去の様式を捨て去って、全く新しい住宅の理念を実現しようとしたまさにムテジウスと同世代にあたる建築家たちを順に分析していく際にも、こうした彼の慧眼はますます鋭く発揮されている。ロンドンのアーツ・アンド・クラフツの建築家たち、その中でも最も独自の様式をつくりあげたヴォイジーから始め、次第に北上し、マンチェスターのエドガー・ウッド、マン島のベイリー・スコットを取り上げた後に、グラスゴー派、すなはちマッキントッシュへと筆を進めている。一見この叙述の順序は南から北へという単なる地理的なものに思われるが、実は同時にもう一つの意味を含んでいることが明らかになってくる。すなはち北上するにしたがい、建築家の生み出す空間が、次第に詩的、情緒的な性格を増していくことにムテジウスは着目したのである。エドガー・ウッドをロンドンと北との橋渡しとなる建築家、そしてペイリー・スコットとマッキントッシュを、インテリアに対する新しい理念、すなわち 「自律的な芸術作品としてのインテリア」という理念を大陸の建築家たちと共有し、しかも詩的で神秘的な独自の色彩を付与した建築家と見なしている。ムテジウスは、マッキントッシュを初めとする北方の建築家が、「リアリスティックな」ロンドンとは対照的な「イデアリスティックな」性格を示していること、▼12そして前者の方がむしろ大陸に近い位置にあることを見抜いていた。 こうしたムテジウスの分析、そして評価は、実はウィーン分離派が下した評価と非常に近いものといえる。ヨーゼフ・ホフマンはムテジウスより早く一八九七年に、「イングランドの中世的な形態に偏りがちな趣味は、我々の模範となるべきものではない」▼13と述べているし、第八回分離派展の際にC.Rアシュビーが不成功に終わったのは、その重く厳格な様式がウィーンに受け入れられなかったためであった。一方マッキントッシュについて、特にその 「夢みるような気分」が魅力的であったとホフマンは後に語っている。▼14これがウィーンでのマッキントッシュの成功に大きく寄与したのであろう。 一方でムテジウスやホフマンらウィーン分離派がマッキントッシュによる〈芸術作品としての部屋〉を高く評価し、他方で分離派に対立するロースがそれを厳しく攻撃していたという事実は、インテリア、とりわけ住宅のインテリアの問題が、一九〇〇年の前後に一つの重要な課題を提起していたということを窺わせる。しかもそれはムテジウスが正確に把握していたように、イギリスではモリス以来徐々に展開されてきており、また同時に大陸でも同じような動きが起こりつつあったのである。こうしたことを考え併せるとき、〈芸術作品としての部屋〉という概念を中心に据えて、一九〇〇年前後の建築・デザインを捉えてみることは意味あることのように思われる。とりわけインテリアが当時の重要な芸術思想である〈綜合芸術〉の実現の場を提供したとすればなおさらであろう。 ここではマッキントッシュに焦点をあてて、ムテジウスが「真に現代的なインテリア」が出現したと見なしているイギリスの一八八〇年代以降のインテリアを検討し、さらにそれと並行する動きである大陸のアール・ヌーヴォーのインテリアにも触れた上で、マッキントッシュの〈芸術作品としての部屋〉を具体的に追い、さらにはウィーンでの展開との関係を見ていくことにしたい。 |
▼8 Ray Watkinson,William Morris as Designer,London,1967,p.16. |
|
四、 ヴォイジーとゴッドウィンのインテリア─単純さ(simplicityn)への志向 イギリスの一八八〇年代以降に登場してきた新しいインテリアの代表としてC.F.Aヴォイジー、またムテジウスはそれほど関心を寄せていないが、それに先立つ一八七〇年代の興味深い新しいインテリアとしてE.Wゴッドウィンをまず取り上げたい。この両者は普通、互いに全く異質な建築家と捉えられていると言ってよいであろう。ゴットウィンが、よく知られているように、ワイルドおよびホイッスラーの建築家として、唯美主義運動の流れの中で捉えられるのに対し、ヴォイジーはアーツ・アンド・クラフツ運動を代表する建築家の一人である。理論上、倫理的な性格が強く、実践的に社会運動的な色彩が濃いアーツ・アンド・クラフツは、通常ゴッドウィンのサークルとは正反対の立場に立っていたと考えられている。しかしたとえば、ロビン・スペンサーの著書『唯美主義運動』のなかでは」、ラファエル前派に源を発し、アール・ヌーヴォーにいたるこの運動のなかで、ゴッドウィンもヴォイジーも共に位置づけられているように、アーツ・アンド・クラフツのなかに唯美主義的な一面が含まれていたのもまた事実であり、両者の登場は全く無関係とも言い難いところがある。実際、ヴォイジーとゴッドウィンのインテリアは、一見したところ全く異なる外観を呈しているものの、それぞれのやり方で、違った角度から共に単純さを志向しており、しかもこの単純さによって、それ以前にはない現代性をはっきりと獲得しているという点は共通しているように思われる。また両者の家具のうちには、装飾を排除した簡素さの点できわめて近いデザインのものも認められる。とはいえ、その単純さの中味がやはり両者ではかなり異なっているといわなければならず、この点を中心に両者を比較してみたい。 「装飾における単純さは、それなしには真の豊かさが得られないほど、最も本質的な性質の一つである」とヴォイジーは語っている。▼15壁紙のデザインが重要な活動の一分野であり、それによって一九世紀末イギリスのデザインの最良の部分と今日見なされているものを遺したヴォイジーの発言としては、奇妙に響く言葉かもしれない。しかしたとえば、ヴォイジー自身『ザ・ステュディオ』のインタビューに答えて、「壁紙はもちろん背景にすぎず、家具の形態と色彩がよい場合には、非常に単純な、あるいは全く無装飾の壁面の扱いの方が望ましい。」と述べていることに注目したい。▼16実際、彼自身のインテリアでは、壁紙が用いられた例はほとんど見あたらない。「板パネル張りが最もよい」と同じインタビューの中で語っているとおり、▼17白い壁に自然な仕上げの木材が最もよく用いられている。壁紙は、そこに置かれる家具やその他の工芸品が望ましいものでない場合に限り、その醜さを日立たなくするという、いわば消極的な理由においてのみ、価値が認められているのである。この論理にしたがえば、ヴォイジー自身は壁紙を使用する機会が少なかったのも、当然のことといえよう。自らの手になる住宅では、家具デザインを初め、インテリア全体をトータルに設計することが多かったからである。「家具の形態と色彩がよい場合」とは必然的に自らがデザインを手掛けた場合ということになる。ヴォイジーの場合も、こうした観点からトータルな設計が理想と見なされていたのである。 「今日、危険は装飾過多にこそ潜んでいる。我々は単純さを欠き、落ち着きを忘れてしまったのである。そのため美の相対的価値が混乱してしまっている。近頃の居間において我々を真っ先に印象づけるのは混乱である」▼18先のインタビューでヴォイジーは同時代のインテリアをこう批判している。こうしてヴォイジー自身が単純さを強調する一方で、批評家もまた、ヴォイジーのインテリアを評する中で必ずこの「単純」という言葉を用いている。たとえば、『ザ・スチュディオ』の「イギリス住宅建築の復興」と題した連載記事の第六回はヴォイジーを取り上げているが、そこでは「個性が単純さを通じて示されることは稀である」▼19と評されている。先のインタビューに伴った論評の中では、「単純であることがデザインの始まりではなく、目的となっている」▼20と述べられている。ほとんどすべてのヴォイジーのインテリアや家具において、象徴的な意味をもつわずかのモティーフを除けば、装飾らしい装飾は全く排除されている。家具の形態はぎりぎりまで単純化され、仕上げも塗装すら施さないごく自然な扱いのものが多い。白い壁と天井に木の梁やピクチャー・レールを配し、家具が最小限置かれただけのインテリアは、今日でも単純と感じられるが、装飾過多といっていい当時の一般的なインテリアを基準にすれば、我々が想像する以上に単純と映っていたにちがいない。壁紙のデザインの豊かさを思うとき、ヴォイジーのなかにもやはり一種の予盾を感じないわけにはいかないが、単純さという一点をめぐっては、ヴォイジーは理論と実践とを一致させ、しかも一貫してその実現に督取り組んでいたといえよう。 現在でも幾つかの作例が残っており、また数多くの当時の写真からほぼ様子を窺うことのできるヴォイジーに比べて、ゴッドウィンの場合には、彼のオリジナルのインテリアをほぼ完全な形で知ることは現在ではほとんど不可能になっている。失われたもののなかには、ホイッスラーの自邸ホワイト・ハウスやオスカー・ワイルドの自邸などが含まれているが、それらに実現されていたのは、一日でいえば、日本趣味という、モリスやラファエル前派の中世趣味とも異なる一つの新しい趣味を盛り込んだインテリアや家具デザインであったといえよう。彼による一連の〈アングロ=ジャパニーズ〉家具は、彫塑的な装飾を一切排し、直線的な細い部材を用いた単純かつエレガントなデザインが特徴となっている。キャビネットなどにおける棚の配し方には、確かにそれ以前のヨーロッパの家具には見られない空間の意識があり、日本の違い棚などからの影響を窺わせる。一方インテリアは、これらの家具を中心に展開されたものであったが、すでに述べたようにそのほとんどが失われてしまった。エリザベス・アスリンによれば、その理由の一つは、ゴッドウィンが主として壁紙とペイントワークを装飾に用いたからということである。▼21ホイッスラーのホワイト・ハウスの場合などは、画家が財政的危機から一年も経たないうちにこの家を手放すことになり、すぐに改装されてしまったほどであった。しかしゴッドウィン自身の言葉や、彼のインテリアについて書き残した人々の言葉から推し量る限り、特に印象深いのはその色彩構成である。たとえば、一八七四年に自邸のインテリアを手掛けた際には、黄色と緑を中心に「パイナップルから拾い集めてきた」色彩でまとめている。▼22ここでは一階の部屋はカーペットを全くひかないという思い切った処理を行い、当時の装飾過剰といえるインテリアへの反対姿勢を明確に打ち立てている。当時ゴッドウィンは女優エレン・テリーと暮らしていたが、エレン・テリーによれば、彼らの二人の子供は日本の浮世絵と扇面画がかかった子供部屋で育てられ、着物を着せられていたといい、あらゆるものを自らの趣味によって統一するという姿勢が徹底して貫かれていたということを示すエピソードとなっている。また一八七八年のパリ万樽の展示では黄色を主調色としたデザインを行い、一八八四年の結婚に際してオスカー・ワイルドがチェルシーのタイト・ストリートに借りた家の内装では、白という単色のヴァリエーションによるインテリアを展開した。 こうしたインテリアにおける色調の統一という点で重要な同時代のモニュメントとして思い出されるのは、ホイッスラーによるレイランド邸の食堂、すなわち〈ピーコック・ルーム〉として名高い、「青と金のハーモニ」と名付けられた部屋である。ゴッドウィンとホイッスラーは一八六四年に知り合って以後、密接な関係にあり、内装の仕事においてもしばしば共同作業を行っている。恐らく両者に共通する熱狂的な日本趣味が二人をそこまで結び付けたのであろうが、この食堂もまた中国趣味と混じり合った日本趣味を基調としている。もともとは、一八七五年にトーマス・ジェキルがこの内装を手掛け、天井と壁にはスペイン製の革を用い、また壁面に沿って染め付けの陶磁器を展示するための大規模な棚が作り付けられくいた。レイランドが、所蔵していたホイッスラーの絵画作品「陶器の国の姫君」を完成した食堂に掛けていたところ、ホイッスラーはスペイン製の革がこの自作に合わないとして改装を申し出、当初は小さな変更であったはずが、結局大規模なものに発展し、革は塗り直され、明らかに日本的なモティーフである金色の孔雀が青緑色の地の上に大きく描かれることになった。 日本の陶磁器を陳列するために特別にしつらえられた大きな棚。襖絵や屏風を想起させる壁面装飾。孔雀のモティーフの一つについては、一八七四年に出版されたオーズリーとバウウェズの『日本の陶器芸術』に掲載された図版に由来するという指摘がなされている。▼23それらの中央に位置する「陶器の国の姫君」の絵画。ここに日本趣味という一つの趣味で統一されたインテリアが出現する。この日本趣味は、あくまでも当時の最先端の趣味であって、一体どれほど正確に日本の建築空間、あるいは家具調度品の理解に基づいたものであるかは問題ではない。たとえその理解が勝手な解釈に基づいたものであったとしても、ホイッスラーが自らの作品にふさわしい室内空間を強硬に主張したことの方がむしろ重要といえる。その徹底ぷりは、陶磁器のコレクターでホイッスラーの作品の持ち主であり、自身日本趣味に浸ったレイランドとさえ、最終的に衝突が避けられなくなるほどであったのだ。と同時にこの部屋が「青と金のハーモニー」と名付けられ、色調の統一を重視していることに注意したい。オスカー・ワイルドは、一八八二年にニューヨークで行った「住宅装飾」と題した講演の中で、ホイッスラーのインテリアに触れ、「天井は明るい青、指しものや家具は黄色の木材、窓のカーテンは白に黄色の刺繍がしてあり、上品な青磁とともに食卓がととのえられるとき、これほど単純であると同時にこれほど楽しいものは考えられないのです。」と語っている。さらにこれに続くのは次の一節である。「みなさんのお部屋の大半でわたくしの認めた欠点といえば、色彩の明確な計画が見られないことであります。一切のものが、あるべきように基調に合っていないのです。アパートは互いになんの関連もない結構なものがぎっしり詰まっています。」▼24 ゴッドウィン、ホイッスラー、ワイルドの唯美主義のサークルにおいて、日本趣味を一つの基調として、目新しいインテリアのタイプが形成されていたのである。家具デザイナー兼建築家、画家、作家と本来の領分を異にしながら、それぞれの立場から住居というものを重要な自己表現の手段と見なし始めていたのが彼らであった。その彼らが特に重視したのが特別な雰囲気を創り出すものとしての色調であったが、それはすなわち色調の統一性を前面に出すことによって、いわば〈自律的な絵画〉を摸索しつつあったホイッスラーの絵画に呼応するインテリアであり、まさに〈芸術作品としての部屋〉と呼んで不思議はないインテリアの誕生であったといえよう。一八七三年に顧客の一人に宛てて書いた手紙の中には、ゴッドウィン自身の「私と道を共にする同業者はわずかにすぎませんが(残念ながら本当にわずかなのです)、私は自分の仕事を芸術作品と見なしています。私にとって建物は、画家にとっての絵画、詩人にとっての詩と同じなのです・・・」▼25という言葉が見出される。 ヴォイジーとゴッドウィンのインテリアは一見すると対照的である。〈芸術作品としての部屋〉という性格は、すでにホイッスラーやゴッドウィンのなかに明瞭に現れている一方で、ラディカルという点でいえば、「ピーコック・ルーム」よりも、ヴォイジーの方が先を行っているといえるだろう。家具同様、ゴッドウィンのインテリアも、当時の一般的なそれに比較すれば、単純であるにちがいない。しかしそれは単純ではあっても決して簡素ではなく、むしろ新しいタイプの贅を尽した趣味を呈示している点で、ヴォイジーを初めとするアーツ・アンド・クラフツとは一線を画している。家具から推し量る限り、ゴッドウィンは日本の家具や住居から、何よりもまず洗練された単純さの感覚を汲み取り、自身のデザインに取り入れようとしたのである。しかし、日本趣味という一つの流行への追随という性格を完全には免れておらず、その意味では未だヴィクトリア朝の一般的なインテリアの延長上にあるといっても間違いはないように思われる。できるだけ多くの芸術作品を詰め込むことが最も芸術的なインテリアへの道であるという当時の常識からすれば、ヴォイジーのインテリアの、装飾に対する未練を残さない徹底した単純さこそ、むしろ当時最もラディカルなものであった。 |
▼15 E.B.S‘Some Recent Designs by Mr.C.F.A. Voysey',Studio, IV,1896,p.216.
▼25 op.cit.,E.W.Godwin,p.8. |
|
五、ベイリー=スコットのインテリア─詩的な雰囲気 先に触れた「芸術愛好家のための家」の設計競技で二等賞を獲得したベイリー=スコットは、実はムテジウスがマッキントッシュと並ぶインテリアの改革者とみなした建築家で、大陸で早くから高い評価を受けたイギリス勢の一人である。ヴォイジーよりも六歳年少、マッキントッシュよりも五歳年長で、一八八○年代に活動を開始し、九〇年代には独自の様式を確立したが、マッキントッシュに似て、初期の活動の舞台はロンドンではなくはるか北のマン島であった。 ムテジウスは『イギリスの住宅』の中で、ベイリー=スコットを「住宅建築家の中の詩人」と呼び、そのインテリアの特徴を次のように言い表している。 と同時に彼は、住むための空間にふさわしい最も親しみやすくかつ詩的で純化された感じをすべての部屋に与えている。彼が一つの部屋を考えるときは常に家具を計算にいれており、設計に際しくは、完全に家具が設置され、人が住んだ状態の部屋を常に顔に描いている。こうして隅々まで住み心地がいいかどうかに照らし合わせて考え抜かれている。ドアの位置が何気なく決定されるということはないし、また窓はそれが照らし出す部屋に対して必ず正しい関係を保っている。 そうして生み出された空間の具体的な印象は「優しげで親しみやすく、かつさわやかで健康的な田園詩」になぞらえられている。人はそこでは咲き誇っている牧草の花の柔らかな香りと混じり合った耕された畠の土の匂いを嗅ぎとる」のである。▼26ロンドンの建築家のインテリアには欠けていて、ベイリー=スコットには見出されるもの、それをムテジウスは何よりも「詩的な雰囲気」であるとしている。 確かにベイリー=スコットのインテリアは、単純さという点においてヴォイジーほどラディカルではない。エクステリアにおいては、初期の十五、六世紀の様式に影響を受けた古風な外観が次第に単純化され、ヴォイジーに近い厳しい単純性を獲得していくのとは異なり、彼のインテリアには装飾はむしろ不可欠の要素となっている。それはアーツ・アンド・クラフツの趣味を典型的に体現したものであり、モリスとラファエル前派が試みたような壁画やステンドグラスが設置され、自然から想を得たプリミティヴな雰囲気をもつ装飾モティーフが、家具を含め、そこそこに配されている。色彩も豊かに用いられている。しかしながらそれらの装飾が当時の典型的なインテリアの装飾過剰とは全く別のものであるのはまちがいない。この点についてベイリー=スコット自身の考えは次の通りである。 芸術的な住宅を建てようとすると多くの費用がかかるとみな思い込んでいる。芸術と装飾とは同義語であると理解されがちであり、装飾が多いほど芸術的な家であると思われがちである。したがつて、これとは逆のことが実は真実であり、住宅はそのデザインに示された熟練と思考の大小に応じて芸術的かどうかが決まるのであって、装飾の量に応じてではないということを明言しておく必要があるだろう。▼27 これは一八九〇年代の後半にベイリー=スコットが住宅や家具の設計をテーマに『ステュディオ』誌に発表した幾つかの論評からの引用である。ここに示された「芸術的な住宅artistic house 」に対する考え方は極めて重要な意味をもっているように思われる。ここまで述べてきたのは、すべてモリスのレッド・ハウスに源をもつ「芸術的な住宅」 の問題であるが、ゴッドウィン、ヴォイジー、ベイリー=スコットといったそれぞれ独自の個性を示す建築家がその担い手であっただけでなく、他方では、その普及版というべき〈クィーン・アン様式〉という一種の流行さえ生み出されていたのである。ベイリー=スコットの批判は、直接にはこのクィーン・アン様式の住宅に対してなされていると考えられる。別の箇所で「デザインの要は単純性と家庭的なくつろぎてあるといってもよいだろう。煉瓦造りの郊外住宅に見られる庶民的な箱ののっそりした醜さが望ましくないのと同じく、いわゆるクィーン・アンの洒落た邸宅のドール・ハウスのような小奇麗さもまた決して望ましいものではないのである」▼28と述べている。 十九世紀の後半、住宅への関心が増すと共に、そこに次第に芸術性が求められるようになる。しかしその多くはジャポニスム、オリエンタリズムといった、次々と入れ替わり立ち替わり流行する様々な趣味に応じて集められてきた雑多なものを詰め込んだインテリアであり、集められた芸術作品の数が多いほど「芸術的な」インテリアであると信じられていたのである。その中でクィーン・アン様式のインテリアは、快適さを重視した比較的単純な様式を提供し、人気を博したが、結局のところ一般受けする折衷的なものでしかなかった。これに対してベイリー=スコットが主張する住宅の美しさの基準はヴォイジーに通じる単純性の原理に基づいている。 主として引算的な方法で得られるであろう。数少ない不可欠のもの以外、効果を損うようなものは一切そこに付け加えず、適切なものを適切な位置に配する以外何もしないことによって得られるであろう・・・家具は、それが置かれる位置と用途にぴったりと合っていなければ、たとえ美しさが内に備わっていたとしても、それだけでは充分ではない。家具はそれが置かれる部屋の一部分であり、周囲と完全に調和して見えなければならない。▼29 この言葉はヴォイジーによるといっても違和感なく響くであろう。ところが現実にベイリー=スコットが設計したインテリアはヴォイジーとはかなり様子が異なっている。 「ル・ニッド(巣)」と名付けられた、一風変わった住居のためにベイリー=スコットがデザインしたインテリアを例にこの点を見てみよう。この住居は、ルーマニアの王女のための一種の隠れ家として、文字どおり鳥の巣のように、大樹の幹の上に建てられた。スコットはそのインテリア・デザインのみを担当している。おとぎ話の世界にしか存在しそうにないこの住居にこそ、ベイリー=スコットのデザインは最もよく適しているように思われる。住居は四つの部分からなり、台所以外に、祈り、睡眠、生活という三つの機能のための空間に分かれている。中心となる空間は生活のためのもので、生命と豊壌の象徴である「太陽とひまわりのサロン」と名付けられ、黄色と青を基調としている。その隣には祈りの場としてアルコーヴがあり、百合のモティーフと白、青、緑の三色が基調となっている。これと反対側の寝室は、赤いけしの花のモティーフがベッドの刺繍や壁面、家具の装飾として施されている。 ある嵐の晩、この可憐な住居は突然崩壊してしまったといういかにもふさわしい結末のエピソードが残されているように、現在ではその完成時の様子は、残されたデザイン画や当時の記述などから推し量るしかないが、ベイリー=スコットのインテリアにおいて、象徴的な意味をはらんだ装飾モティーフと色彩計画が非常に重要な役割を果たしていたことがまず窺われる。装飾がほとんど部屋全体を埋め尽くしていることによって、ヴォイジーに比べ、スコットのインテリアが今日では古風に感じられるのは事実であるが、あらゆる細部にわたって統一的なデザインが試みられている点において何よりも革新的であるといえよう。これこそ〈芸術作品としての部屋〉を規定する最大の特質であることはすでに見たとおりである。そしてムテジウスが「詩的な雰囲気」と呼んだ、そこに生み出される独自の雰囲気に我々は注目すべきであろう。「ル・ニッド」においては、王女のための避難所、隠れ家であるという性格にふさわしく、現実の住居というより、おとぎ話に登場する魔法の家のような雰囲気がますます強められているが、これに限らず、ベイリー=スコットの住宅には常に子供の世界、童話の世界に通じる素朴さが感じられる。これは、何よりも簡素であるという点において素朴であるヴォイジーの住宅とも異なる彼の特質である。 かつてオシアンという謎めいた人物の遺産であると考えられ、スコットランドの中心から世界に新たな感情のスリルを与えた、古代ケルトの吟遊詩のファンタジーとロマンスの世界に我々は足を踏み入れたように思われる。ペイリー=スコットと共に、我々はイギリスの建築家の中で純粋に北方的な詩人たちの間にやってきたのである。▼30 「芸術愛好家のための家」の設計競技でベイリー=スコットは一等質なしの二等賞の入選しているが、その際に高く評価されたのも主としてインテリアであった。「熟慮した結果、審査委員会は、先述した設計案、すなわちドルチエ・ドムームは、すでに強調したように、インテリアが芸術的に非常に優れているにもかかわらず、エクステリアが全体としてここで求められている現代的な性格を充していないという結論に達した。」と後に発表された競技の結果で報告されている。▼31彼の設計案が応募案の中で最も高い質を与えられながら、一等質ではなかった理由がここから明らかになる。設計競技の目的ははっきりと「現代的な性格」にあり、彼のインテリアがその点でも高い評価を受けていたのとは裏腹に、エクステリアに関しては通常の彼の住宅以上に中世的な性格の強い設計案を提出し、それ故に一等賞を惜しくも逃したのであった。 今日、ヴォイジーやマッキントッシュと比較したとき、ベイリー=スコットが占めている位置はより一層曖昧なものに思われる。彼の理論と実際に設計されたものとの間には明らかに隔たりがある。理論と実践の間には常にずれがつきまとうという点や、当時の一般の趣味に比較すれば少なくとも単純であるという点を考慮に入れても、ベイリー=スコットにおける単純さの原理と豊かな装飾性との間のずれは注目すべきものであるように思われる。そしてさらに興味深いのは、このずれがそのまま、ムテジウスのイギリス住宅の評価にみられる矛盾と呼応している点である。彼はイギリスの住宅全体としては何よりもその合理性を高く評価しているにもかかわらず、建築家による個々の住宅を論じた箇所では、むしろ詩的な雰囲気をもつ住宅、すなわちベイリー=スコットやマッキントッシュの住宅をより高く位置づけているように感じられる。『イギリスの住宅』全体を貫く姿勢は、そこに見られる、大陸の住宅にはない質実さや合理性への評価であり、そのため内部の設備などに多くのページが割かれているが、彼が最も親近感を覚えているのはマッキントッシュを頂点とする、むしろ詩的な性格の強いインテリアである。後に後者を完全に切り捨てていくことになるムテジウスであるが、この時点では非常に大きな振幅の中にいたのであり、しかもその矛盾に自分では全く気付いていないような、むしろ彼の中ではごく自然に両者がつながっているような印象を受けるのである。一方ではこのずれは、ドイツ政府から正式に派遣された調査官としてのいわば〈公〉の視点と、個人的に共感を覚える建築家としての〈私〉の視点という、ムテジウスが抱えていた二重の視点から生じてきているように思われる。しかし同時にこのずれは、実はベイリー=スコットやマッキントッシュに内在していたいずれでもあり、さらに視点を広げれば、いわゆる近代建築・デザインの先駆者として位置づけられてきた世代の人々の最も重要な特質の一つの典型として取り上げることで、この問題に一層具体的で明瞭な光をあててみることとしたい。(続) |
▼26 op.cit.,The English House,p.49.
▼27 James D.Kornwolf,M.H.Baillie Scott and the Arts and Crafts Movement,Baltimore and London,1972,p.122 |