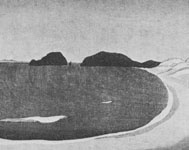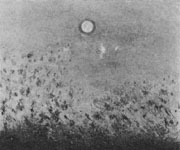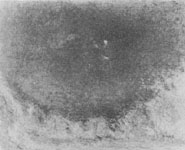坂本繁二郎と満月の絵
東 俊郎
|
(1) 『放牧二馬』と題された坂本繁二郎の絵(一九三五年制作)を偶然みる機会にめぐまれた。坂本独特のエメラルド・グリーンの空と大地にひきつけられるようにしてその世界へはいってゆくと、はじめの印象ではもつれた糸玉にすぎない雲形図形であったもののなかからふいに馬が二頭横をむいて、そして重なって現われ、消える。しかし一度姿をみせたその馬たちは、注意力の集中と弛緩の波間をぬって再生するたびに少しつつ実在感をましてくるのだが、奇妙なこの馬は立体性を欠き重さを感じさせぬばかりか眼もたてがみも蹄ももたないくせに、かえってどんな馬より馬らしいとぼくらは感じる。 この経験のなかにはなにかとてつもなく複雑なものがあるのだけれども、ひとつのことだけに注目して比喩的に語るとすれば、この絵画『放牧二馬』は「馬」という字を見慣れぬ記号に、すなわち象形文字の発生現場へ送りかえす。絵画の全体が有機的に組織づけられることによって馬が定義される過程、馬が生まれつつある状態を感じる経験といいかえてもよい。そしてそれは言葉になってくれないときの胸になにかつかえたようなもどかしく苦しい思いに酷似するとはいえ、言葉の働きについてはまったく逆で、この場合めざすところは言葉のゼロ地点における言葉とでもいうべき領域なのである。馬という字はこの画面のどこをも指さないが、この不透明な色塊の全体が馬という字を形成するという風な。 それは意味という便利な道具をつかわないで思考せよとせまられた時の苦痛にちかいし、さらにひとひねりするならこの苦痛は、思考する主体として自明のものと信じていた「我」、発語の主体として空間内のある部分に凝集していたそれが拡散し、いわば空間そのものと化することによって、思考もまた不定形となりながら漂い、画面なら画面に描かれたすべての対象にとりつく、そういった風景を想定すれば理解される底のもどかしさと表現できるかもしれない。牛であれ馬であれ、あるいはリンゴや柿やハサミであれ、坂本の描くあらゆる対象がそれ自身「何か考えている」ようにみえることは、たぶん以上のことと無関係ではない。 |
|
|
ところでいま引用した「何か考えている」という表現は周知のように夏目漱石の言葉であった。大正元年(一九一二)第六回文展に坂本が出品した『うすれ日』をみた漱石は次のように語っている。 此荒涼たる背景に対して、自分は何の詩興をも催さない事を断言する。それでも此画には奥行があるのである。さうして其奥行は凡て此一疋の牛の、寂寞として野原の中に立ってゐる態度から出るのである。牛は沈んでゐる。もっと鋭どく云へば、何か考へてゐる。「うすれ日」の前に佇んで、少時此変な牛を眺めてゐると、自分もいつか此動物に釣り込まれる。さうして考へたくなる。若し考へないで永く此画の前に立ってゐるものがあったら、夫は牛の気分に感じないものである。電気のかからない人間のやうなものである。▼1 考えているのは牛ではないし、またそれを見ている漱石でもない。漱石が使った言葉をかりるなら「気分」という、みるものとみられる対象のあいだにはりめぐらされる磁界が考えるので・ꀀって、それならこうした絵をみていてあれこれ考えたくなるのは当然なのである。なぜならすでに「場」と化した「我」はそれについてすでに考えていたのだから。ただ、こういう考えは神秘主義にすり寄ってゆく危険を感じるのだが、坂本繁二郎の絵につきまとう一種の薄気味悪さを追求してゆくとき、ぼくにはこういった非論理にあたうかぎり接近してゆく超(メタ)論理の視点をすてられない。もちろんここでぼくのいう超論理とは禅の言葉と同じく一種の論理を意味する。平面的描写でありながら奥行を感じさせ、量感をもちつつ空虚であることをはじめとする坂本の絵画の矛盾のすべてが生まれ出る源としての論理、おそらく近代の原理のひとつである一対一対応にささえられた、どれだけ精緻をほころうが結局は機会論の枠からはなれられない芸術上のからくり〈写像〉から自由になるための論理の糸口なりとも発見したいからである。 |
|
|
(2) 人間の世界をこえてしまったかのような独得の神秘に、坂本の作品ではしばしばでくわす。しかもそれが光の粒子さえ眠らせてしまう暗黒に胚胎した、非日常のいわゆる幻想からくるのではなく、どこまでもはっきりと見わたすことができてくまなく光が照りわたっているにもかかわらず、可聴範囲を逸脱したみえない音の大群におそわれたときの不安に似た、どこか異様な不気味さをただよわせるところに由来するところが、坂本の坂本らしい点だ。「この人は白昼夢の画人である。」▼2と萬鉄五郎に評される所以であろうか。もともと光なしには存在できないはずの影がその従属関係から脱して光に拘束されないばかりか、かえって自己増殖しつつ生物的な顔つきさえうかべはじめるその絵から、魂の正午ということばが連想され、そうすれば牛島憲之の絵画を想起することはさほどむずかしくはない。牛島憲之が坂本繁二郎を尊敬しているらしいことを別にしても、この二人の作品にはつねの絵画表現の約束から逸脱してしまう感性にかけてなにか共通項がみてとれる。たとえばそれを牛島の側から接近して、エロスのもんだいとして展開することも可能のような気がするけれども、それはそれとして、こういった奇妙な感情を、みるものに喚起する道具立はじっさい坂本の画面のいたるところに星散している。 女の髪、樹木、水、能面のひも、布─それらがひとたび坂本繁二郎の手にかかれば、それぞれに不思議な意志が宿り、緩慢だが無窮のアメーバ運動を展開する生命体となったり、あらゆる方向にひとしく重力が分散される結果どんな中心ももてずに真空中を浮遊する不定形の相貌を帯びる。そして雲。『放水路の雲』(一九二七年)、『鳶形山』(一九三二年)『暁明の根子岳』(一九五三年)などに描かれた雲をみると、そこでもとてつもない異物というか、額縁で限界づけられた絵画世界のなかでのみ存在しうる、重力を欠いた奇天烈な物体としての印象がつよくせまってくるのだ。 |
|
|
ところが坂本繁二郎は、ひたすら対象をみつめること、「どこまで写実、あくまでも写実を突きつめて」▼3ゆくことの重要性を晩年にいたってもなおくりかえし語っている。画面の全体をおおう非物質性への傾き、抽象思考とさえよべそうな傾向とこの徹底した写実への執着。これは両立しがたく肉離れをおこしやすい関係だ、というより、もし成立するならきわめて特殊な情況や特異な個性を前提とせざるをえない関係のようにみえる。坂本繁二郎においてもしそれが、一過性をこえ、さらに表層の矛盾そのままにひとつの構造をつくっているなら、それを明らかにすることと、写実ということのほんとうの姿をみきわめることとは一であって二ではないはずであるから、坂本における写実の位置について考えてみよう。すぐに思いつく次のような坂本の言葉がある。 |
▼3 坂本繁二郎「私の絵 私のこころ」『私の絵 私のこころ』坂本繁二郎、昭和四十五年、日本経済新聞社に収載、四〇ページ。 |
|
近ごろはすべて物を見ながら描き続けるというわけにもいかず、仕方なくある程度は記憶で描いています。以前 のことですが、出歩かなくなってから「馬の絵を」と依頼され「見ない物は描けない」と、記憶で絵を描くなど もってのほかとかたくなに思っていたものですか、こうなってみると、かえってその方が自由で、楽しくもある ようです。▼4 いうまでもないが坂本が写実についてかたるときの念頭にあるのは、ヨーロッパの、なかでも十九世紀以降の近代絵画の概念であって、日本や中国のそれではない。クールベにおいてもっとも端的に裸形をさらす西洋絵画のレアレスムの骨格は坂本の絵画にあって最後までくずれなかったとぼくはみているが、この考えを支えてくれるのは、自分がいま・ここでみているものだけを描くという坂本の身ぶりなのである。そしてこのD'apres natureという身ぶりは、坂本における精神指導の規則にまでたかめられ、そのことで精神をみちびく。世界─たとえばメルロ=ポンティのいうcette nappe de sense brutにたいして身体(=視覚)をかしだすことによって世界に参加し、さらに透過変換をつうじてキャンヴァスに対象、ではなくて対象と等質の世界を構築するという命題を坂本もまた懸命にいきたいということだ。 自然あるいは対象ではなく、それと等質の価に変換するというところに写実の真の意味がある。たとえば自然を再現するということと、自然と等質の表現を実現するということは、この考えにしたがえば、世界を描きだす方法として、まったく相反する姿勢を示すのである。現実と作品とが無媒介に嵌入しあっている前者にあっては、自然と人との相互浸潤によって、自然のけわしい表情を人の視線がやわらげ、逆に個をめざす人の意志は自然にもてあそばれてとけさる。いっぽう自然と人との安易な同化にむしろ人の努力の頽廃をみる後者がめざすのは、お互いがお互いに対立することを通じて、本来の輪郭をとりもどすことにある。坂本繁二郎の絵画はもちろん後者に属する。 |
▼4 「私の絵 私のこころ」『私の絵 私のこころ』八ページ。 |
|
具体的に坂本の作品を例にあげるなら、「日本風景版画筑紫之部」の一枚、『神湊』(一九二〇年)が恰好だろう。油彩とはちがって坂本の木版画はその色彩といい線といい、いずれも江戸の浮世絵版画をたやすく連想させて、坂本芸術の出自のひとつを暗示させるものの、むしろそのことでかえって坂本の近代性があきらかになるということもできる。なぜなら、その類似にもかかわらず江戸版画と坂本の『神湊』を截然とわけるなにかを、それを見つめたひとは感じないでいられないからだ。色彩と線をえたむこう、といわず色彩と線の表層といってもけっきょくおなじことだが、そこに刻印されている写実の力。踊り子は踊るのではなくまた女なのでもないといったマラルメ、そして芸術にあっては動かないものこそ動くのだと語るロダンの言葉をまつまでもなく、『神湊』に描かれた白色のかたまりは現実の波と同質のものとして、またその波の運動をたしかにみたという経験としてそこにある。 またここで、さきに異様な形態を指摘した坂本作品中の雲をレアリスムの視点からとりあげてもよくて、写実を無視して描いたとみえる彼の雲が、じつは北九州から筑紫平野をぬけて阿蘇にいたる風土に条件づけられた雲の生態を克明に観察したあげく構成された表現であることは、坂本の故郷八女地方へちかづけばただちに了解されよう。自然に発生するどの雲ともちがうと同時にどんな雲でもある坂本の雲だけとりあげても、どんな近代日本の洋画家の描いた雲にもましてつよい実在感があるとするのは付会にすぎるだろうか。 ようするにぼくは坂本の絵画の基本を写実と考え、しかもそれが自然の表現ではなく、みかけはそれとほとんどちがわないが千里の径庭があるはずの、自然と同質のものの表現であるということが示したいわけだが、問題点をさらに絞るにあたりここで坂本の敬愛したただ一人の画家ともいうべきコローを語った言葉が手がかりとなる。 |
|
|
コローののびのびとした精到無比の筆の導きについて心をたどらせていると、微に入り細をうがつ諸々の事物、人も水も土も石も家産もありのままの深いささやきが何ともいへぬ奥底をにじみ出させる。ここでは写実も象徴も立体も時代も超越されてゐる。▼5 と語られるコローは、自然に神の代同物をみて、信仰に近いほどの深い信頼をよせたヨーロッパ十九世紀人の典型として、もっとも大切なことは何ものにもよらずひたすら見えるものを見えるとおり描こうとするコローである。世界があるということ、いいかえれば世界がみえるということをめぐるふかい謎にはじめて気づいたのは二十世紀の画家であって、彼らの作品のもつ錯乱したリズム、あるいは自然な呼吸を許さない窒息感はその必然の代償だとうっかり言ってしまいたくなるほどの〈自由〉を感じさせる十九世紀の画家の一人である坂本が考えつくした限りの絵画の可能性のほぼすべてがセザンヌやピカソではなくコローにおいて、解決されているといいたげな口吻をかぎあてなければ、坂本のコロー讃のもつアクテュアリティーは無視されたに等しくなる。坂本にとってのコローは、ぽくにとってのジャコメッティと同じ位置にあり、ジャコメッティにつながる画家なのだ。すなわち、 |
▼5 坂本「偶感」西日本新聞、昭和二十四年一月四日。『坂本繁二郎文集、増補改訂版』昭和四十五年、中央公論社に収載、二七六ページ。 |
|
あらゆる絵画において、私が興味をもつのは、似ているということ、すなわち私にとっての 似ているもの、つまり、私に少しでも外界を発見させてくれるもの・・・。▼6 と語るときのジャコメッティに。ジャコメッティがなにかしら悲願をこめたようにつぶやく、この言葉の低音部に聴きとることができる不安と乱れ、それは外界(=自然)への違和である。自然と人、この排中律的に対立するというより、一方のおわりが他方のはじまりとなり、自然とみればすべて自然、人とみればすべて人で整合した論理がくみたてられる奇妙な開係。それに対して無意識の位相をとる、つまり親和的な感性を示すコローと坂本繁二郎はあきらかにちがっている。ジャコメッティが襲われた吐き気を催すような物自体への度をすぎた関与とその反動としての放心状態のあいだの大きな振幅こそみられないとしても、坂本には自然がおわって人がはじまる地点、あるいはその逆の人がおわって自然がはじまる地点について、あきらかにコローのあづかりしらぬ困難にであっていた。 (3) 自然はいつも人の胸中で人に相対しているのだという。またそのように自然をかかえている人自身自然の一部であるという。大自然のまえの豆人─はじめてぼくが坂本の『大島に往って来ての話』をよんだとき残った印象は海と火山という自然の圧倒的な力であり、その自然力の渦動のなかにのきまれて無力をかこつ存在としての人がかなでるさみしさの基調音が全体を貫いているというものであった。 |
▼6 矢内原伊作・宇佐見英治編訳、ジャコメッティ『私の現実』昭和十二年、みすず書房 一四一ページ。 |
|
岸と云ふ岸は船も寄り附かれぬ、魚類はあまり棲んで居ない、何しろ火山の下だから海草も至って少い、淋しい、国に居る頃見た海は広いと思った、果しもなく広い海と思った。さてこんな孤島に来て見ると一向海が広く見えない、いや浪の大きさも只大きさから云へば此辺はずっと大きい、それが一向大きい心持がしない、大きい心持はしないで唯々島の方が小さい、心細い気持ッたらない、ただ何となく便りない、今迄は地の中に在る海と思って居た、此処では海の中の地である。足元に浪の押寄する時心細さが身に染みる、此僅許りの地べたが身を安ずるより何よりの便りであると思ふと又中々懐しい、▼7 この言葉は全文の象徴であると同時に、ある事態をそのようにみる坂本の心のありかたの象徴にもなっている。この象徴を解読すれば、当時二十四歳だった坂本にある種の精神的な危機がおとずれていることが認められる。これは坂本の認識と感覚の質そのものをまきこみ、そこに根ざしているため、彼の企画業にかかわってゆくことになる。言葉をかえれば全身の認識力を描いたその刻々の仕事のなかでのみ解決してゆける事項に属するのだが、この間の事情をさらにあきらかに証言する文章として『阿蘇行』以上のものはありえないだろう。 『大島に往って来ての話』から四年後の明治四十四年『方寸』第四巻第七号と第五巻第三号に発表された紀行文『阿蘇行』では、自然への詠嘆をこえて、自然に対する人為の業のはかなさの感覚が虚無の数歩手前までつきつめられた暗鬱な表情があらわにされた趣がある。坂本繁二郎という人が、人為の努力をふみつけてたちまち無と化す底の自然=力に対して異常なまでの鋭敏さで反応してしまうたちの人間であることをこの文章は逆照明しているので、全篇にみなぎる恐怖感覚はただごとではない。けれどもみのがすことのできないのはこの恐怖感というより、その恐怖の中心ににじりより、それをそれとして人為の結晶としての認識力でつかまえることで抵抗しようとする姿勢なのであるが、ともかく裸にさらされた坂本の感受性を少し長いがたどってみよう。久留米を発ち熊本をすぎて阿蘇山へ近づくにつれて視界が雨気を帯びて荒涼とした殺気が告ぎり、自然の力があらわになるのとは逆に人の背たけは低くなってゆく歩みの最後の絶項に、地獄の釜のような阿蘇の火口が待つ。 |
▼7 『坂本繁二郎文集』九ページ。 |
|
周囲過半は此形で囲まれて足元は頭の尖った五山が集まって居る、九州中の地べたは此処から皆流れ出たのかもしれない、遠方は自分よりも低い事は分かるがぼーっとして有耶無耶の間に横はって居る、或る威力の飜弄に自分のちっぽけな体の処置が恐縮でたまらない、何だ貴様は人間か鳥か虫か埃かと云はれてる様だ、(中略)穴の中は何が何だか只真白だ、『ごおう』と云ふ地響か風の響か分からぬがして居る、『煙』『響』『焼石』『風』底抜けの力を誇りげに大空に向って嘯いて居る、庭園の草木の間に居慣れて自然の有難さと恐ろしさを忘れて居るとき、無機物のみのやうな眼界に身を置いて今更の如く生物の血の鼓動を思はせらるる、今自分が石ころになってしまはうと思へば只一飛びすればいゝのである、数分時をもいらぬのである、かくて世界の生物は数分時にして石礫と化し得る、世界永遠の寂滅はたった一皮の自分のそばに存在して居るのである、世界の生物が悉く申し合せて一思ひに死んでしまったならば折角に生物を成した自然はがっかりするだらうか、それとも其の事それを自然として矢張りしゃあしゃあとして自然で寂滅の儘進行するだらうか、生物が自づから出来たところにはそれ丈の意味があるに相違ない、それかとて又死ねば死んだ事が意味となるだらうか、空には鼠色灰色の雲が入交り立交り急はしく動いて居る、恐ろしさの喜びとでも云ふ様な妙な気持だ。▼8 彼が現実には友人と軽口をたたきながら登ったとしても、文章をよむかぎりそこにみえてくるのは無機質の自然のまえに生の原形質にまで退行してゆこうとする坂本一箇の姿だけである。「たった一皮のそばに存在する」死にとりまかれている存在として人はある、ほとんど無にひとしい量としてかろうじてあることが人としての必然だ─この坂本胸中の原風景をわざわざ確認するために、阿蘇にのぼり、人にもわれにも無情ともいえる文章を書いたときさえ想像されるが、この坂本にとって不可避の道行だったとぼくは解したい。つまりこれは一種の通過儀礼なので、人として画家として生きるためにまず死なねばならなかった坂本にとって、阿蘇こそは恰好の死場所であったわけである、と。 ではどのように生きるかが次にもんだいとなるだろうが、それは死ぬという言葉が象徴しているように、自然と人との関係としての無を内在化させること、無となるのではなく無を再構成することだという方向にすすむことによってであり、感覚をこえた造形世界をうちたてることによってであった。たとえば火口を下ったあとの次のような記述、 |
▼8 『坂本繁二郎集』四七─四九ページ。 |
|
自分よりも一丁許り先を歩く旅人の話声がする、其声は其人々より離れて声許りがかって互に に話し合って居る様だ、『ハッハッハッ』と笑声が出る、其声のみは或る有形のものとなって例えば半球円がハ、、の数丈け珠数繋ぎになって人の口から宙に上って行く▼9 という箇所にみられる、受け身の弱さをかくしようもないが、しかし生きることの意味の最小値は確認したとでもいいたい、ハハハの「半球形」を絵画化してゆくことがさしあたってそれにあたるだろうか。しかも写実に徹して。ここに坂本の写実のアポリアが成立することになるわけだが、それについて別の側面を迂回してみよう。 |
▼9 『坂本繁二郎文集』五〇ページ。 |
|
(4) 八十三歳の坂本へのインタヴィュー記事のなかで東野芳明は坂本のように「言葉がいつも腹のなかに煮えくりかえってくるように、とめどもなく飛びだす」老画家ははじめてだと述懐しているが、▼10これは、坂本繁二郎ののこした文章に共通する印象であり、時代を遡るほどその傾向はつよくなる。今ここでとりあげようとする『存在』▼11はその「煮えくりかえ」り度において白眉をなす、強力な思索力と必ずしも強力とはいえぬ文章力との格闘の跡がなまなましい、坂本芸術の現場報告といってよい。そして、いうまでもなくこの『存在』の意味は、『阿蘇行』の延長線上にあってさらに一歩をすすめ、回心にも似たこころの動きに形をあたえたこと、彼の全的な世界認識を人間にむかって宣言したことにある。ここではっきり腰をすえた坂本は以後その信条にしたがって、忍耐づよく仕事を継続してゆくことになった。 ところでこの『存在』が一種の認識論であることをうたがうことはできないとしても、存在についての一般的定言を語っているのでなく、わたしはこう考えるという呈示の範囲をこえて呈示の範囲をこえていないことには注意しておくほうがよい。あくまで画家という立場、音楽や文学とはちがった表現手段をもつ芸術家が、その表現性を超越して芸術の学としての形而上学へむかおうとするためではなく、まったく逆に、造形表現の充実に言葉が利用できるところでのみ言葉を利用する態度をくずさない。この言葉の描く図が示唆している地はそれならなにかといえば、それは視覚をめぐるもんだい、換言するなら、見るあるいは見えるということと「ある」ということのあいだに点じ減する関係である。 ただこの文章は言葉の屈曲がはなはだしく論理をたどれない欠陥があらわで、とくに「意識」という言葉の意味の錯雑ははなはだしい。何回読んでも意味不明の呪文に似た箇所がのこることを承知のうえで全文をくだけば、坂本がもっともいいたいことは劈頭の一文 物の存在を認むることに依って、自分も始めて存在する に凝縮された、この場合は逆もまた真である命題である。つまり、このセンテンスは一種のトートロジーだとみてはじめて坂本の表現に整合性があたえられるわけで、それにつづく |
|
|
自分なる者があっては、それ丈認識も限度が狭くなる、自分を虚にして始めて物の存在をよりよく認め、認めて自己の拡大となる。▼12 という主張がこの命題に矛盾し亀裂をみちびくとする考えかたがあるなら、それは「自分を虚に」するという表現の中心にある「虚」を、機能や場としてでなく実在(の裏がえし)とみ るからだろうが、そういう考えは坂本にはない。むしろここでは存在を補強し、厚みをあたえつつその全一性を明示するためにつかわれている。もんだいは存在であり、存在を存在にする認識なのである。 存在から出発しても、認識=意識から出発しても世界は縫い目の見えない完全で純粋なテクスチュアをつくる。しかしその整合性のなかで両者は絶対に出会うことがない。それはものについて、一人単数「我」についてなにも語ってくれないにひとしい。このみせかけの世界の整序の不毛をやぶって自他を交錯させ、同時に現存させるためになにが欠けているか。その鍵は画家にとってもっとも日常的な視覚のはたらきにあるということの坂本的表現が 自分を虚にして始めて物の存在をよりよく認め、 |
▼12 『坂本繁二郎文集』五六ページ。 |
|
という形をとったので、ここにいわゆる東洋的無を認めては、むしろそれを撥無するテコともいうべき「意識の欲望と其可能性」▼13を語りつつ、〈ある〉ことと不可分の、〈みる〉/〈みられる〉が相互交換される世界の次元に触れはじめた坂本を否定することになってしまう。むしろ虚と名づけられた機能のもとに姿をあらわす〈身体〉感覚に着目すべきなのだ。 |
▼13『坂本繁二郎文集』五七ページ。 |
|
一元意識に住する間は、其脈動の通じ得る総べては自分たり得る境地である、他人は勿論木片草虫其事の存在を認め、真に之れを意識し其処に自己を認めたものである。脈動界の其総ては之れ自己の生存である、頭である、血である▼14 身体と世界とがそれぞれ一なる存在として合同(相似ではない)図形を描くこと、あるいはこの合同を成立させるべく身体のなかにものが出現し、もののなかに身体があらわれることを予想させる言葉が生まれでるぼくらには死角にあたる視覚─画家のまなざしなのである。存在を勦滅せずにはやまない思考の純粋を濁らせ、世界を活性化するために点晴されたまなざし。このまなざしに内包された坂本の身体感覚が単なる比喩でなく、神秘をてらった発言でもないことは坂本の語った言葉をつぶさに点検すればあきらかとなるはずだが、たとえば次のような文をぼくのこの考えを補強するために援用してもよい。 |
▼14『坂本繁二郎文集』五九ページ。 |
|
見えるものであり、動かされるものである私の身体は、物の一つに数え入れられ、一つの物である。(中略)しかし、私の身体は自分で見たり動いたりするものだから、自分のまわりに物を集めるのだが、それらの物はいわば身体そのものの付属品か延長であって、その肉のうちに象嵌され、言葉の全き意味での身体の一部をなしている。したがって、世界は、ほかならぬ身体という生地で仕立てられていることになるのだ。このテン倒した言い方、この矛盾した論法は、視覚[見るという働き]が物のただなかから取り出される、あるいはむしろ、物のただなかからみずから生起してくるのだということを、さまざまに言い換えようとしているにすぎない。物のただなかにおいてであるからこそ、或る〈見えるもの〉が〈見ること〉を始め、自分にとって〈見えるもの〉となる、しかもあらゆる物を見るその視覚によって〈見られうるもの〉となる▼15 もうすでに了解されるかと思うが、坂本のいう自分を「虚」にしてものを認識するという表現も、哲学者メルロ=ポンティの肩ごしにみるなら、自己否定に裏づけられ有と対比された「無」へ傾斜する心境などではなく、おどるように出現してくる〈もの〉を通じて開かれた存在となった自己の確認以外のなにものでもなく、ここから、〈みえるもの・こと〉に固執するかぎりぼくらの身体が発する絵画の問いかけへみちびかれることもまた必然なのである。 |
▼15 M・メルロ=ポンティ「眼と精神」。『眼と精神』M・メルロ=ポンティ、滝浦静雄・木田六訳、昭和四十六年、みすず書房に収載、二五九ページ。 |
|
そして坂本が〈みえるもの・こと〉に執着しているのははっきりしているのだから、メルロ=ポンティのいう絵画の問いかけ、つまり造形芸術の本質とは「〈知らない者〉が〈すべてを知っている視覚〉へ向ってなす質問」▼16であるという地点から坂本繁二郎へ接線をひくことはむずかしくない。なぜなら、この質問にふくまれる逆説的な世界認識の方法が、絶対の他者を媒介しなければ自己はついに認識できないとする透徹にささえられていることはあきらかであり、また同時にこの透徹をとおい淵源として坂本の「存在」巻頭の一文 物の存在を認むる事に依って、自分も始めて存在する という命題が生まれただろうからである。〈もの〉(=存在)が他者にであう経験、ひるがえれば、もっと迂路とみえながらじつはもっと近い、自己へ直結した経験にほかならないと坂本は語っているのであり、もちろん佶屈な彼の文章を解読するまでもなく、無記のカンヴァスの内部から〈すべてを知っている視覚〉の答えのようににじみ出た感のある彼の絵画に端的に、雄弁にそれは語られている。 (5) いったい自分がなにを語っているのか、もし視覚が答えてくれなければ、実は自分にもわからない、というのが坂本繁二郎の基本的な考えであると今はもういってもよいとぼくは思う。それならばこの理路をもうすこしたどって、坂本の絵画のレアリテの質を類似の観点をつうじて再検討することができよう。すでに引用した『眼と精神』の著者メルロ=ポンティによって、みせかけの類似、すなわちデカルトに代表される操作的思考において物とその〈投影〉の関係として理解された類似関係が、身体を場として形成される視覚の作用の神話にすぎないことが暴露されてしまった。知覚という最上の判断者がAとA´との類似の(逆からいうなら差違を)認識するのではないというわけだ。発想の百八十度の転換を必要とする─類似は知覚の発動力であってその結果ではない、と。坂本繁二郎の作品の最大の魅力は、少なくともぼくには、この類似という謎をつうじて世界を一度停止させ、そこに生まれる神秘から日常への還相において存在の意味をレアリテのテクストの下にひろげてくれるその表現にあるのだ。 なるほどかれのさくひんのいんしょうが、とくに室内の静物を手がける昭和十五年頃以降、堅固な実体をめざすことの対蹠をいって、すべてを霧のなかにとかしこもうとたくらんでいるかのごとくみえる人にはみえる。しかしそれにふれながら、厚い霧がさらに濃度をます瞬間、それをさしちがえるように運動し、記憶の回路を周游しつつしだいにレアリテをます一種独特のあと味に言及しないのは公正を欠く。彼の絵画はしこるのだ。そしてそのことで、藤島武二の作品とはべつの、だがひとしく強い誘惑力で人をひきつける。いい意味でその場かぎりの藤島の絵が目をとじれば存在しなくなるのにくらべ、坂本の作品は夢のほうがうつつであるような、みなくなったときにこそはじめるレアリテがあって、おそらくそれこそ牽引力のもとなのである。そしてその誘惑をまるごと受けいれたときぽくはジャコメッティの願ったように、外界を発見したかもしれないのだ─坂本とともに。 |
▼16『眼と精神』二六五ページ。 |
|
彼の描いたリンゴや柿、それは腐っているわけでも化石しているのでもないが、食べられることを拒否する。彼の描いた能面、それは奇妙なオブジェで、能面であることを脱落した姿をしめす。おもしろいエピソードがある。第二次大戦中、馬の専門家である騎兵将校が坂本画中の馬をみて、「坂本の描く馬は病気にかかっているから使いものにならない」と評したところ、坂本は「実際の馬は病気をするが、私の馬は死なないよ」▼17とやりかえしたという。使いものにならないとは巧まずして坂本の芸風をうがった言葉だし、死なないという自覚も、自負と自省ふたつながら、いかにもそれらしい。 たしかに用不用の観念をはなれたオブジェの追求かともおもわせるところが坂本の絵画につきまとう。用途をそなえ生命を内部にふきこまれればその生の必然の半面として蔵さざるをえない脆弱と空虚から解放され、不生不滅、生をも死をも無化した〈永遠〉にくりひろげられた宇宙の劇、そしてそこにうまれる奇妙な味。そこに映しだされるレアリテに、ものが人に対していだく激しい感情とか凶々しい相貌が関与していないことはない。しかしそれが、ものに対し、ものがどうなっているのかを尋ねた坂本にあたえられた、ものからの答えの核心でない。 |
▼17 坂本「私の絵 私のこころ」『私の絵 私のこころ』九〇~九一ページ。 |
|
坂本繁二郎の作品が放射するレアリテ。それは、性能のよい顕微鏡や望遠鏡をつかってえられる底のものとは逆に、あくまでぼくらが肉眼をつかうことをもとめる。物質から構成されながら、その物質と精神とをであわせるべく模糊とした画面のさらにむこうに焦点を結ぼうとする眼の努力の現場にあらわれ、そして消える。この一瞬一瞬の現実感を比喩するなら、実体的な太陽光線ではなく、それを反射することで機能としての側面がつよまる月の光、心月孤円、光呑万象、光非照境、境亦非存、光境倶亡▼18といわれるときの非存在の存在として輝きだす光のイメージがもっともふさわしい。 たとえば印象主義研究のあとがみえる明治43年第4回文展出品作の『張り物』をあげてもよい。板に張った赤い布が光をあびて仕事中の女の顔と和服の袖に反射している。一見制作された時代がただちに想像され、新しさを失なって不透明な物質にかえろうとしているかにみえる光の表現に眼をしばらくたちどまらせていると、色絵具から物質性をゼンダツして奇妙な生気を帯びてうまれでる光をみることができる。光で〔なにかを〕みるのではなく、光をみる、みたという強烈な印象。こういう経験はけっして幻想的とはいえないので、メルロ=ポンティが次のように語った言葉に対応するものである。 |
▼18 景徳伝燈録七、盤山宝積章。道元『正法眼蔵』第二十三都機に引用されている。「新月孤円」について語った画家では他に熊谷守一がいる。熊谷守一『蒼ヨウ』昭和五十一年、求龍堂、一九九─二〇〇ページ。 |
|
たとえば印象主義研究のあとがみえる明治43年第4回文展出品作の『張り物』をあげてもよい。板に張った赤い布が光をあびて仕事中の女の顔と和服の袖に反射している。一見制作された時代がただちに想像され、新しさを失なって不透明な物質にかえろうとしているかにみえる光の表現に眼をしばらくたちどまらせていると、色絵具から物質性をゼンダツして奇妙な生気を帯びてうまれでる光をみることができる。光で〔なにかを〕みるのではなく、光をみる、みたという強烈な印象。こういう経験はけっして幻想的とはいえないので、メルロ=ポンティが次のように語った言葉に対応するものである。 ラスコーの洞窟に描かれている動物は、石灰石の亀裂や隆起がそこにあるのと同じようなふうにそこにあるのではない。といって、それらの動物がどこか〈ほかのところ〉にいるというわけでもない。この動物たちは、それらが巧みに利用している岩の少し手前、あるいはその少し奥に、しかもその岩によって支えられながら、そのまわりに放散しており、目に見えないそのケイ索を引きちぎることはないのだ。▼19 メルロ=ポンティはつづけてこういった絵を「絵に従って、絵とともにみる」経験だとかたっているが、ありようは、絵画における真のレアリテ、物質であっても反物質であってもいけない存在としての非在、非在としての存在にふかくかかわる。坂本の作品に月光のごときなにかを感ずる所以である。あくまで絵画の二次元平面を表層的に戯れつづけることと、そのどんな瞬間にも表面を破ることとの同時存在。夢みられた〈深さ〉。いや、絵面の〈深さ〉はほんとうに仮構された夢なのだろうか、とか、絵画の経験とは(二十世紀の絵画の革命以来常識のごとくささやかれているような)二次元の経験にすぎないという命題こそ、かえって深い迷蒙にとりかこまれているのではないかという疑問が、静かに息をふきかえすのは、こんなときである。 (6) 昭和57年の東京、京都の両近代美術館で開かれた「坂本繁二郎展」をみて心に残ったのは、ひとつは滞欧期の作品群であり、もうひとつは昭和39年頃頃に始まったとされるいわゆる「月」のシリーズであった。それ以外の作品は、その時々の全身全霊をあげて制作にむかう坂本の態度の必然として、年代順に並べられると飛躍・断絶の面がうすれ、漸進にともなう単調さが目立ってしまう。多くの作品を一堂にあつめてみなくてもよい面家、むしろ一枚の絵に根気よくっきあったほうがいい画家なのだ。 滞欧期の作品のみずみずしい軽快さと知的な構成力、とくに前者は坂本の水彩画につながって心楽しませる雰囲気があるものの、もっとも感銘をうけたのは「月」のシリーズで、坂本繁二郎の作品をひさしく月光のイメージでおもいつづけてきたぼくとしては、一種不可思議な冥合をかんじないわけにはいかない。しかしこの「月」のシリーズには、それまでの作品をこえる契機、他からの反射や影響をはねかえしてそれみずから発光体となったものだけがもつ逞しさが付加されている。能面から、それにまつわるすべての装飾をはぎとってオブジェとみた非情の眼と手が、能面とおなじようにアトリエのテーブル上にごろりと月をなげだし、月以外のなにものでもない月、それがそうであるところの月を描いた、そんな画風であると同時に、なにか童話の清澄さに達してもいる。 |
|
|
昭和43年作の『月光』、その翌年の『幽光』にこの感がふかく、ものの世界がどうなっているのかものに問いかける作者の姿さえ消えたところの、ものがものを描きだす現場に臨む趣があり、神韻繚渺の気がみなぎるとさえいえそうだ。 しかし、画面はつねに有機的に組織化されて、「力学的な相関関係の中に生き」▼20た均衡をもたねばならないとする坂本の造形思考が放棄されたところにうまれた朦朧ではないことはもちろんである。これらは極度に構成され、知性に裏づけられた絵画なのだ。コローの絵画がその外観の矛盾に隠れたたくましい骨格をもっていると同程度、分節を無化する坂本の作品は全体の調子、絶妙なヴァルール感覚にあふれている。ただ以前には細部の力のバラ・塔Xを明晰に計量した同じはたらきが、ここでは分割可能な部分の壁をとりはらって全体の一に帰する役割をになって、理知のたくらみを隠しているにすぎない。たとえば、綿にくるんだ十字架のような雲が夜空にうかぶ『月』(一九六七年作)の画面中央右にひかれた二本の(棒)の効果を考えてみれば得心がいくこととおもう。 ところで、これはすでに指摘されているかどうか寡聞にしてしらないが、昭和39年以後の「月」の連作だけにとどまらず、それ以前に描かれた坂本画中の月のほとんどすべてが満月であることに▼21今さらながら気づいたのだが、これは単なる偶然なのだろうか。坂本を「写実」家としてとらえ、また逆に坂本の絵画という具体を通じてさらに「写実」の意味を少なくとも近代絵画のそれより拡張したいと考えるぼくにとって、この事実は坂本繁二郎の言行不一致を斥する符号にならないどころか、ぼく自身点晴を欠くうらみを感じていた坂本の写実精神についての論考に全円をあたえる最後のしるしとうけとれなくはないのだ。 なぜ月でなくて満月なのか。それは月というのはすべて満月なのであり、満月こそただひとつの月、月そのものである月であるからだ。坂本が仏教、なかでも禅宗の教えについてどの程度知っていたか、ぼくはよく知らない。けれども彼ののこした文章を収録する『坂本繁二郎文集』(中央公論社刊)をくりかえし読んでみると、「対境」「直指人心自然認識」▼22など禅語がらみの単話がいくつかみつかる。ただこれは禅語ではないが、拈華微笑を蓮華微笑▼23と誤っているところなどをみると、禅にかんしてそれほど知識があったとは考えられない。けれど彼が彼の真実をもとめてつねに対象と正対して妥協を排した歩みに関して、かえって禅に近づいたけはいはある。むしろ濃密にあるといってもいいくらいだ。 もちろんそれは、見諸相非相を諸相ヲ非相卜見ルと訓む癒しがたい無への傾き、それに発動する現実蔑視と超越への願いをはげしく内在して不立文字を玉条にいただく禅ではなく、諸相卜非相トヲ見て、どんな絶対をも否定しつつ現実である有と無とをただしく判断し、その判断を言語化することで自から他への道を切りひらく、つまり「道得」する気迫をつねにもつ禅ではあるが。あらゆる現象は、無でさえ無として見なければいけないし、見えたものは見えたと表現しなければいけない。そのとき表現に暇瑾があってはならず、過不足のない十全の表現は、全機関同時現成という言葉が示すように、かくれるものなにひつとない世界を証す、というのが禅本来の考え方なのだ。 |
▼20 「私の絵 私のこころ」『私の絵 私のこころ』一〇八ページ。 |
|
道元の 「正法眼蔵」第二十三は都機と題する。これはここで思考の対象にされているのが月(都紀、都奇と万葉がなにあるという)であること、都という漢字が現代中国語でもそうだがすべて=全という意、したがって都機が全機に通ずることで、月を考えるなら区区別別の特殊化された月を考えてはいけない、もっとも純粋に月である月を考えなければおよそ思考と呼ぶに値する思考といえないこと、その二点を暗示するという。▼24そして、純粋に月である月を考えるとは、「円成」である月、いいかえれば満月を考えることに等しいとつづくのが道元の考え方なのだ。もちろんこのとき言われる「満月」は比喩でもあるわけで、さらに正確を期すなら、新月から満月にいたるどんな時期の月も他と比較されて質や量を相対化されることがない、「それらのすべてがそれなりに「円成」なのだ、満ち足りているものなのだ」▼25という意味の象徴だといえよう。機能として考えられた「満月」。 なにか本来そこにあるべきものが、あったものがいまはないという欠如の感覚ほどこれに対して異質なものはない。欠如は欠如のままで、というよりさらに積極的にうってでて、欠けたもの、未熟なもの、歪んだものはそれがそうであると認識する条件のもとで、まったきものに変ずる。三日月も十六夜も残月もすべて月であり、人の目的的な思考をはなれた自足の形態をそれとしてみるなら、すべて円成であり、満月である。そしてこういった思考は、外界を無視して空転しやすい言葉をいたずらにもてあそぶよりも。坂本繁二郎のようにものをひたすら「見つめて見つめて見つめ直す」▼26タイプの画家によるほうが、かえって深く身体の源泉につながるゆえに、露堂々と得心されるのだといえば、あまりに牽強付会にすぎるだろうか。 もちろん楯の反面をわすれているわけではない。すべてがある、全機関同時現成とは、すべてがないというにほぼひとしい。実の壁をたかく築けば築くほど、虚の淵はそれにしたがって深まるのが道理、反作用をともなわない作用はないとすれば、きりたった山の尾根をかろうじてすすむ危険を、壺は空虚に形を与え、音楽は沈黙に形を与えると声低く語る詩人の優雅をまねて表現する以外、どんな処理も許されない地点へと、坂本は自己をおいつめていったのだ、 と。それは人としての坂本が円成するための不可避の往相であったようにおもわれる。そしてそれなら、還相をあるく坂本にとって満月が円成の象徴としてもっともふさわしいと、これはもういう必要がないくらいだ。 ここにもうひとつ興味ぶかいじじつがある。これも『増補坂本繁二郎作品全集』の、それも表紙に刻印された坂本の印章「一心」があって、その漢字一は円型にあしらわれて心という字をつつんでいる。ちなみに、正法眼蔵都機本文中に、 |
▼24 寺田透「正法眼蔵都機講読」、寺田透『道元の言語宇宙』昭和五十一年、岩波書店に収載。 |
|
古仏いはく、「一心一切法、一切一心法」しかあれば、心は一切法なり、一切法は心なり。心は月なるがゆへに、月なるべし。▼27 という言葉が記された箇所がある。仏教でいう法には、理法・法則という意味の法ばかりではなくて、その反対概念とみなされるのがふつうの「現象」を表示するときもあって、いまの場合も、月は現象でありつつ法則である法そのものとして心に対応し、相互に他の象徴作用をはたらかせることを通じ独立しながら一なる全の存在を暗示している。 いいかえれば、ここに語られているのは「部分は全体より小さい」という公理の否定、部分と全体との関係についてのさらに厳密で海闊な思量、というか、思量を超えようとする思量、透体脱落する思考の身体をもった感覚なのである。さらにそれを絵画のもんだいに即していうなら、レンズというブラックボックスを前提として一対一対応という因果の鎖でむすばれる対象と像とのあいだの「写実」ではない、全然別の体系にたつ「写実」についての洞察をぼくは坂本の「満月」に感じるので、たとえば最近知ったホログラムの理論などに坂本の「満月」をめぐるものと同質の思考のパターンをぼくは思い描くのである。 |
▼27 寺田透・水野弥穂子校註日本思想大系『道元 上』昭和四十五年、岩波書店 二七九ページ。 |
|
(7) ここでもういちど坂本の自然観にふれてみる。自然との一体感をもって坂本の芸術観とし、また『存在』にのべられた「虚」の理論を援用して、ありのままの状態では人と対立せず人をその内部へとかしこむ主客未分化の胎内世界のような自然を、つまりそこでは人という価値が無と化す底の自然を東洋的とよび、坂本的とも名づける論考があるが、これは禅の教えをまつまでもなく、仏教にあって天然外道とか先尼外道とかよばれた思考に類する。それに傾く心性が坂本になくはなかったことを、ぼくはこの論考のなかですでに確かめたのだが、それはあくまで坂本の自然観の出発点、あるいは絵を描かないときの坂本の自然観にすぎないので、これを到達点と考えてはあやまりである。彼が何度も語った「自己と自然との力の交渉」▼28としての自然が人との境界をけしゆく調和よりもむしろ対立を強調するそれであること、だからこそ坂本が自然を「向こう」▼29とよんで自己との区別をはっきり自覚していたこと、さらにこの区別によって両者のあいだに生ずる距離の感覚が彼の創作活動に死ぬまでおとろえぬ活力をあたえていたこと、を無視して坂本を語ることはできない。 |
|
|
もし坂本に、自然と一体化した態度をもとめたいなら、「同じものとはちがうものである」という徹底した認識の水準を設定しなければならないが、そのときはすでに「自然」の概念が自然の水位をはなれるときであって、どちらにせよ、人もついに自然の一部にすぎないとする感性の自然主義は否定される。一歩ゆずって人の身体に自然をみたとしても、その身体の運動も軌跡である絵については、 しかしかいた絵は「私」です。「私」そのもので、自然ではありません。▼30 と釘をさすことを忘れないところにいかにも坂本らしい、これは撥無されることのない強靭な意志をみることができる。 |
▼30 坂本「問われるままに」『私の絵 私のこころ』一一八ページ。 |
|
ジャコメッティが「外界」とよんだ存在を、自然と人との二重螺旋構造において、しかもそれぞれが他によって傷つけられることのない全一存在の相をおびている姿でつかまえる-そのために坂本がえらんだ芸術上の仕掛けはやはり「類似」であり「写実」なのであるが、その結果の作品としてのジャコメッティと坂本はなんとおおきくかけはなれていることか、とおどろくよりも、それこそが他ととりかえようのない芸術の存在理由と納得するべきか。さらに、芸術が自然の表現でなく、表現とは自然の等価物としての表現であるという考えにすでに触れたことを思いだしてもよくて、自然を等価交換する流儀がふかくその個人の「質」▼31による以上、芸術家にのぞむ最上のことは、それぞれにわかちあたえられたbon Senseにしたがって自己にであうべく自己の質を認識することであるから、画風のちがいはかえって積極的にみとめるほうがよい。自然は芸術という舞台に千の仮面をつけてあらわれる。 さて音楽でいえばコーダにあたる部分にきたが、ここで再び坂本の論考『存在』をとりあげてみる。彼が『存在』を雑誌『方寸』に発表したのは明治44年、その後昭和30年に改訂されている。この二種のテクストを比較してみると、大同小異で思考の根本はかわっていない。ただここで小異に着目してみると興味ぶかい事実があらわれる。二箇所の加筆された部分なのだが、ひとつは存在と無の反排中律的連関をのべたあとの、 一口に云へば自然の力の有を認める故に、之は恐ろしい事だがその無が匂ふ事である。さうして現有の姿が実に確実となって来る。 なる文であり、もうひとつは生の表層をこえたところで出会う「大きな世界に大きな自分を発見した喜び」をさらにいいかえて、そこに美の範疇をこえる契機をみとめるかのごとく、 之は良心と言ってもいいのかも知れぬ という言葉なのである。 まず前者についていうなら、この考えの傍証というべき発言が『美術手帖』昭和40年3月号の「インタビュー明治」にみられる。そこで坂本は自然を認識するしかないかが宗教的価値の基準ともなると語り、それに対してインタヴュアーが自然とは人をとりまく世界の全体とか質問したのに、一転して、 そんなものではない。とにかく、自然があるか、ないか、本当のことはだれもまだわからない。 と答えているのが思いおこされる。かつて坂本がヨーロッパ留学の感想を要約して、フランスには自然がないと語ったことがあったが、もちろんその場合の自然はフランスと日本との自然の比較として差別相でみられた自然にすぎず、これに対していまもんだいにしている自然が、絶対の自然、すなわち「自然」の概念そのものであるということをみわけるのはそう難しいことではないだろう。そうだとして、ではここで坂本が自然を否定し無とみなすどころか、むしろ逆に自然を全的に肯定するけはいを示していることは言葉の勢いから明らかである以上、自然はないというぶっそうな断定に託して、より高められた自然の認識とともに、さらに語られるはずの、ここではまだ暗示にとどまっている言葉を捜してみるとどうなるか。 すると思考はドミナントヘの曲線を描いて、加筆された文の後者、なんなら「良心」の説といってもよいその言葉にむかう。つまり、自然を自然に生きる動物にくらべて、なまじこざかしい知恵をもったために自然を生きることができなくなったことに由来する、人間の自然に対する愛憎のドラマを、あたかもすでに終ったかのごとくやさしくみかえす眼がかんじられる。もちろんそれは現に生きつつある坂本にとっては「仮構」 の眼であり、それゆえうまれる一種の諦観がつきまとうはずであるが、それ以外のどこに「良心」の説がうまれるだろうか、とむしろ反間するほうがよい。 |
▼31 坂本「画の質」『坂本繁二郎文集』一〇二─一〇八ページ。 |
|
自然を生きることが不可能と「知る」ことは、そのときかえって知る=認識する存在としての人を、それそのものとして、月の「円成」を認めるおなじてつきで、全一の存在としてみつめることの可能性を「知る」ことだ。満月のシリーズはそれを感じさせる。昭和42年作の『櫨の月』など、そのきたな美しいとでもいうしかない色彩といい、ある一点をめがけて大きく湾曲して飛びつづける鳥の群が透体脱落する底の樹木の動きと、そのエネルギーを吸収して静止する月とが均衡する形態、平面でしかも無限の奥行をもつといいたくなるその空間性といい、一見忘れがたい印象をのこす。失明にちかい人の眼に世界はこんなふうにみえるのだろうかという一種の感動を否定しないし、坂本の作品を評して白内障の画家の眼にうつった世界にすぎないと語った人の言葉の一面の事実はうけいれても、そういう判断をこえて、心の深い部分でこれをリアルな自然の相として承認するなにかがうごくことは確かなので、それを一人一人の主観の枠をこえた共同の領域が存在することを予告するものと性急にいいつのりたくなる風さえある。 自然が自然を描いてしまったような、なにかしらとおい悠久をただよわせながら、一方どんな細部にも人の刻印がうたれているこの坂本の作品の不思議なレアリテ。みればみるほど澄明になってゆくそれから、絵画をこえてなにごとかが声低く語られはじめる。坂本繁二郎の良心の説。デカルトが自然を定義してその到達点を「徳」においたことの真の意味をいまぼくは漠然と考えている。 |
|
(ひがししゅんろう 学芸員)